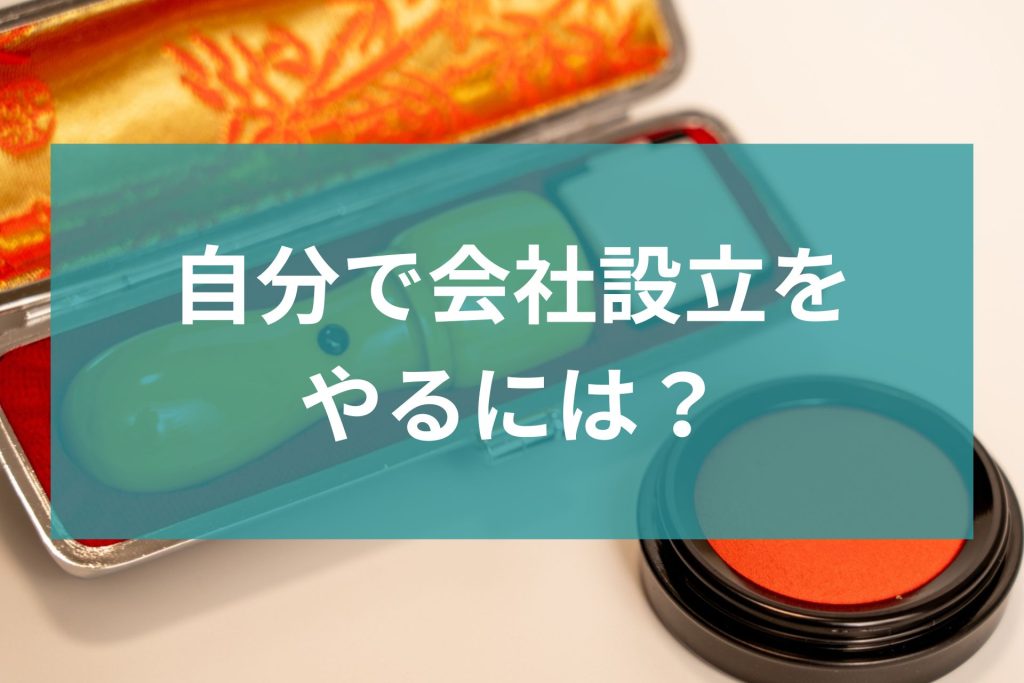
個人でやっていた事業の拡大や独立などによって
「法人化しよう」
「これから自分で会社を設立して事業を行いたい」
「1人で作る場合はいくらでできるの?」
等と思っている人もいるのではないでしょうか。
しかし、実際に会社設立をするまでの流れや必要となる費用について詳しく理解している人はそう多くはありません。今回は、会社設立を自分でやってみようと考えている方に向けてポイントとなる費用や流れを詳しく解説していきます。

関連記事:【費用を抑えたい方必見】横浜で会社設立をするなら税理士事務所へ相談!
関連記事:【会社設立】方法や手続きの流れを解説
解説することのできる会社の種類とは
一言で「会社」と言っても種類がいくつかあるのはご存じでしょうか。
会社の設立に当たって、現在設立することのできる会社は4種類あります。
その種類は、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社となります。
どれかを選ぶことになりますから、まずはそれぞれの特徴を理解しておきましょう。
 株式会社について
株式会社について
株式会社とは、株主から資金調達を行って、株主とは別の経営者が事業を運営してそこで得られた利益を出資者に配分する形態の会社です。株主は配当という形で報酬を受け取ることが可能です。
株式会社では、経営者を株主が株主総会にて選出します。また上場することも可能です。
注意点としては、出資金の比率によって権限も変わりますので事前に調べて失敗しないようにしたいですね。
 合同会社について
合同会社について
合同会社は株主が社員のみで構成されており、利益配分なども経営者間で自由に設定することが可能です。つまり出資者と役員が同じということです。
例として、Apple Japanやアマゾン、グーグルなども合同会社という形態です。
設立費用なども株式会社に比べると安くすむことも特徴と言えるでしょう。
関連記事:【設立の流れ】合同会社に向いている業種は?手順やメリットを解説
 合資会社について
合資会社について
合資会社は会社の債務に対して出資額まで責任を負う「有限責任社員」と会社の債務に対して無制限に責任を負う「無限責任社員」の両方で構成されている会社です。
「無限責任社員」が原則として経営を行い、「有限責任社員」は経営は行いません。
 合名会社について
合名会社について
合名会社は、会社の債務に対して無制限に責任を負う「無限責任社員」で構成されている会社のことです。簡単にいうと個人事業主が何人か集まって構成されているようなイメージを持っていただくと分かりやすいかと思います。
以上が会社の種類となります。
数で圧倒的なのは一番聞き馴染みのある「株式会社」で、将来的に多くの人を雇い、株式を通して資金調達を広く行いたいと考えている場合はおすすめです。
また最近急増しているのが「合同会社」です。設立費用の安さや利益配分の自由さなどから人気になってきています。この先、自分で会社の設立を行うのであればどちらかにすることがおすすめです。それぞれの特徴やメリット、デメリットを知って、自分の事業にベストな選択を行いましょう。
【株式会社】設立の流れ|まとめ
今回は、会社形態の中で一番のシェアを誇る株式会社の設立までの流れをご紹介していきます。
会社設立の手続きにおいて必要な書類
以下、手続きにおいて必要となる書類についてまとめます。
|
登記申請書 |
会社を設立することを法務局に申請するための書類 |
|
登録免許税納付用台紙 |
登録免許税分の収入印紙を貼り付けた用紙のこと。※登録免許税は資本金の額によって算出。(株式会社の場合は資本金の額×0.7%または150,000円のどちらか高い方) |
|
定款 |
会社の基本的なルールなどが記載されている書類 |
|
発起人の決定書 |
定款で本店所在地を詳細まで記載していない場合などに必要 |
|
資本金払込証明書 |
資本金の払込があったことを証明する書面 |
|
取締役の就任承諾書 |
設立時に取締役に就任することを承諾したということを証明する書類 |
|
取締役の印鑑証明書 |
設立時に取締役に就任することを承諾したということを証明する書類 |
|
印鑑届出書 |
法人実印の届出をするために必要となる書類 |
|
登記すべき事項を記載した書面、保存したデータ(CD-R) |
登記申請用紙を法務局の窓口にて入手して、登記すべき事項を記載して添付します。 |
それぞれ漏れのないように必ず事前に準備を行っておきましょう。
会社設立の流れ|7ステップ
ではいよいよ会社設立までの流れをご紹介します。
全体の流れを把握しておくことは重要ですので頭に入れておきましょう。
①会社概要の決定
まずは会社の基本的な事項を決定します。
その内容としては、発起人、会社名(商号)、所在地、印鑑作成、資本金、事業目的などです。
所在地は、始めは自分の家でも良いですが、最近ではシェアオフィスやレンタルオフィスも増えてきていますので検討しても良いでしょう。
また、資本金の金額は1円からでも設定は可能ですが、今後の事業を円滑に進めていく上では、資金繰りに心配せず事業を行っていける3ヶ月分ほどを目安に準備・対策することが相場となっています。決め方は起業する業種や計画によって様々です。
②印鑑などの作成
一般的には会社設立時に必要な「実印」と取引口座開設のための「銀行印」、会社運営上必要となる「角印(社印)」が必要となります。余裕をもって事前に印鑑登録を済ませておきましょう。
③定款を作成する
定款って何?と思う方も多いかもしれませんが、この定款の作成が設立の手続きの中で最も時間を要すると言っても過言ではありません。
先程もお伝えしたように定款は会社の基本的なルールをまとめたものです。
記載する内容としては、会社名、事業目的、本店所在地、出資財源金または最低額、発起人の氏名及び住所、発行可能株式総数などです。事業目的などが曖昧だと今後金融機関からの融資を受ける際にも影響が出る可能性がありますので、明確にしておきましょう。
この他、事業内容によって追加で記載していく形になります。
④定款の認証を受ける
定款を作成し終えたら、公証役場で定款を認証します。定款の認証は、本店所在地の都道府県内で、認証を行う公証人がいる所定の公証役場で行われます。提出方法としては直接役場へ持参するか、定款のデータをメール送信して電子認証を受けるかのどちらかを選択することができます。提出した書類に不備があったり、書類が不足したりすると手間が増えてしまうので事前の確認をしっかり行いましょう。
合同会社の場合は、定款の認証は必要ありません。
⑤資本金の払込を行う
続いて資本金の払込を行います。
先程、上記でもお伝えしましたが、資本金とは会社の事業を円滑にスタートさせるための資金となります。主に運転資金や設備投資のためのものです。額に関してはしっかり検討しておきましょう。資本金の額によって税金・税務の面でも変わりますので注意しましょう。
自分名義の銀行口座に自分名義で振り込みをします。通帳の必要部分をコピーし、振り込み証明書を作成してコピーと一緒に綴じます。この時振り込み証明書の継ぎ目に会社代表印を押印することを忘れないようにしましょう。
タイミングとしては、会社を設立後、法人名義の銀行口座を開設して最初に振り込んだ資本金をこの法人口座に移すという流れになります。
⑥会社代表者による設立登記申請・完了
ここまで完了したら、法務局に登記の申請を行います。
先程紹介した「手続きにおいて必要となる書類」を揃えて、登記申請書及び添付書類を定められた順番に綴じて製本を行います。
そして、法務局の窓口に直接提出、郵送、インターネットにて提出のどれかの方法で提出を行います。
提出後はおおよそ1週間で審査が終了して登記が完了します。
⑦官公庁などへの各種届出
会社の設立登記が完了した後は、税務署、労働基準監督署、地方公共団体、公共職業安定所、社会保険事務所への届出を行います。
それぞれの場所でどのような手続きを行うのかは以下の通りです。
・税務署
法人税に関する手続きは管轄の税務署で行います。提出する書類は、「法人設立届出書」や「給与支払事務所等の開設届出書」、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」「青色申告の承認申請書」、「適格請求書発行事業者の登録申請書」などです。会社形態にかかわらず、同じ書類を提出します。
・労働基準監督署
従業員を雇う場合には、労働保険に関する手続きを管轄の労働基準監督署で行います。労働保険とは、通勤途中や仕事中にけが・病気・障害・死亡などの災害に見舞われたときに国が保証を行う制度です。労働基準監督署へ提出する書類は、「保険関係成立届」や「概算保険料申告書」などがあります。
・地方自治体(都道府県・市区町村)
税金に関する手続きがあるため、都道府県税事務所へ「法人設立届出書」を提出します。この手続きは法人住民税や法人事業税をを納めるために必要です。市区町村は、自治体によって提出の要否が異なるので、事前に届出の要否や手続きの流れなどを問い合わせてください。
・公共職業安定所(ハローワーク)
公共職業安定所(ハローワーク)では、雇用保険に関する手続きを行います。労働保険と同様に従業員を雇う場合には届出が必要です。雇用保険は、従業員が育児や介護などで休業するときに、安定した生活を送るために必要な給付が行われる制度です。
必要な書類は「雇用保険適用事務所設置届」や「雇用保険被保険者資格取得届」です。添付書類として、労務関係の帳簿等(労働者名簿・賃金台帳・就業規則)を提出する必要があります。
・年金事務所
法人は従業員の有無にかかわらず、社会保険への加入が義務付けられています。そのため、会社設立後5日以内に年金事務所へ届出を出さなければなりません。「健康保険・厚生年金保険新規適用届」「被保険者資格取得届」「被扶養者(異動)届」の書類が必要となります。法人でない事業者が健康保険・厚生年金保険の適用事業所として加入したい場合は、「健康保険・厚生年金保険 任意適用申請書・同意書」の提出も必要です。
会社設立にかかる費用
説明してきた会社設立の流れの中で必要になる費用を改めてまとめます。
概算費用:合計で約22万円程度。
内訳は以下です。
・登録免許税
資本金の額×0.7%または15万円のどちらか高い方
(大抵の場合15万円であることが多いです)
・会社の実印作成費用 数千円〜2万円
・定款認証手数料 3~5万円(資本金などの額に応じて異なります)
・定款の収入印紙代 4万円(電子定款の場合は、不要)
・定款の謄本請求手数料 約2千円(こちらは1部250円、必要部数によって異なります)
流れとおおよそのかかる費用なども事前に知っておくことでよりスムーズに設立の手続きを行っていきましょう。
会社設立は自分で行う?依頼する?
会社設立の流れや費用について理解できたところで、手続きを自分で行うのか、専門家に依頼するのかといった悩みが出てくると思います。そこで今回は、自分で行うときのメリット・デメリットを解説します。
自分で行うメリット
自分で手続きを行うメリットとして「費用が抑えられる」と「会社設立の仕組みに関する知識や経験を得られる」という2点が挙げられます。
なぜこの2点がメリットの要素になるのか詳しくお話します。
 費用が抑えられる
費用が抑えられる
前述したように会社設立にかかる費用はおおよそ22万程度ですが、専門家に依頼するとなると、報酬として5万円から20万円程度の費用を支払う必要があります。自分で手続きを行うと専門家に支払う報酬が不要になるので、金銭的な負担が軽減されます。
創業したばかりだと、会社設立だけでなく、会社の設備資金(社用車・オフィスの備品・HP作成費用)や運転資金(人件費・オフィスの賃料・材料の仕入れ代金)などがあるため、資金を確保するためにどこにお金をかけるのか線引きが必要です。
専門家に対する5万円から20万円程度の報酬を「こんなにかかるなら自分でやったほうが良い」と考えるのか、「この費用でほかに時間やお金が割けるなら外注しよう」と考えるのかは、人それぞれです。
実際に潤沢な資金を前もって用意できない場合は、事業開始後にショートしないように余計な支出などは抑えたほうがいいでしょう。
そのため、「会社設立後に利益がすぐに見込めない」「自己資金は少なく、資本金も融資頼り」という方にとっては、費用を抑えることがメリットといえます。
 会社設立の仕組みに関する知識や経験を得られる
会社設立の仕組みに関する知識や経験を得られる
会社設立の仕組みに関する知識や経験を得られるのもメリットの1つといえます。会社設立の手続きを行うことは人生で何回もあることではありません。自分の手で手続きを行うことで、設立の流れのほかに税金や会社法などの知識を得ることができ、事業開始後に生かすことも可能です。
他人からの言葉で聞くよりも、実際に行うことで理解をより深めることができるので、新しく事業を立ち上げたい方や将来的には複数の会社を設立したいと考えている方には、メリットとなり得る要素です。
自分で行うデメリット
メリットがある一方で、デメリットもあります。メリットとデメリットのどちらも把握したうえでどのような方法で手続きを行うか検討しましょう。
 難易度が高く、手間と時間がかかる
難易度が高く、手間と時間がかかる
会社設立には会社法や税金などの専門性が高い部分が大きくかかわっているため、難易度が高くなり、素人が行うには手間と時間がかかります。定款を作成するにも細かいルールがあり、知識がない状態で作成すると余計な費用が掛かったり、その後の会社経営に支障が出る恐れがあります。
さらに事業を開始するための事前準備と並行して行うとなると、手続きの負担が大きくなり、会社の設立時期が大幅に遅れる可能性もあります。以上のことから、会社設立を自分で行うことは難易度が高く、手間と時間がかかるデメリットだといえるでしょう。
 書類作成のミスが起きる
書類作成のミスが起きる
会社設立の手続きには、さまざまな書類を準備しなければなりませんが、自分で行うと書類の作成ミスが起こる恐れがあります。定款を作成するには、事業目的を記載しなければならず、その事業目的も適切な文言で記載しなければなりません。
知識がなければ、作成後に不備がないか確認のために読み返しても、ミスに気付くことができないため、書類を受理してもらえない可能性もあります。小さなミスを繰り返すことで精神的な疲労にもつながり、さらにミスをしてしまうといった負の連鎖になりかねません。
会社設立の流れを見て、「思ったよりも簡単そう」「事業準備の片手間でもできる」と感じた方もいるかもしれませんが、想像よりも負担が大きく、準備する書類も膨大です。ミスをして改めて作成しなおす時間を考えると、会社設立は自分でやったほうがお得といえるでしょうか?
自分で会社設立を行うときに注意すべきこと
会社設立の手続きを自分ですべて行うと決めた方は、これから紹介する注意すべきポイントを抑えておきましょう。
注意すべきことは以下の2点です。

・会社設立後に行うべきことを整理しておく
定款や登記申請書類は、オンラインでも受付を行っているので自分で手続きを行う方はオンラインで提出してください。オンラインで行うことで、「窓口に足を運んで書類を提出する」といった行為をカットすることで、時間的にも精神的にもゆとりができます。ゆとりができることで、ミスが減り、手続き自体もスムーズに行うことが可能になります。
また、会社設立後に行うことを整理しておくことで、段取りよく手続きが行えます。会社設立後も税務署や労働基準監督署などへ提出しなければならない書類もあるため、一息つく時間もありません。事前に行うべきことを順序立てて整理しておくと、期限を経過することなく、すべての手続きを滞りなく終えることができます。
会社設立をミスなく終えるためには、事前の準備や時間の有効活用がとても重要です。もし、1人でやり切ってみたい方は、参考にしてください。
手続きを代行できる専門家とは
会社設立の手続きを代行してもらうために専門家に依頼する場合は、代行してほしい内容によって依頼する専門家が異なります。専門家がどのような業務を代行できるのか紹介するので、自分自身は何を依頼したいのか考えながらご覧ください。
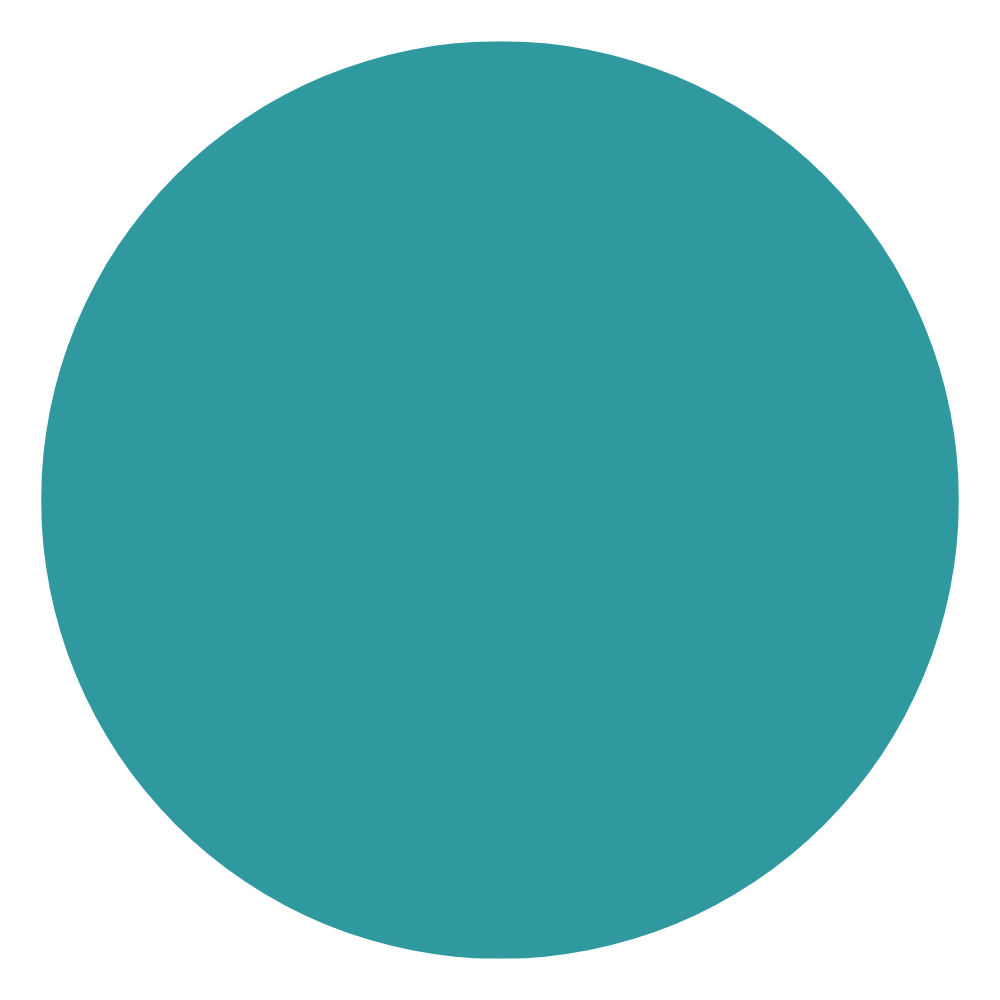 司法書士
司法書士
司法書士は設立登記に関する専門家です。司法書士が代行できる業務内容は以下の通りです。
・登記書類の作成
・定款認証の代理申請
・法務局への提出代行
特に、会社設立時に法務局への登記を代行できるのは司法書士だけとなっているので、上記の業務を代行したい方は司法書士への依頼を検討しましょう。
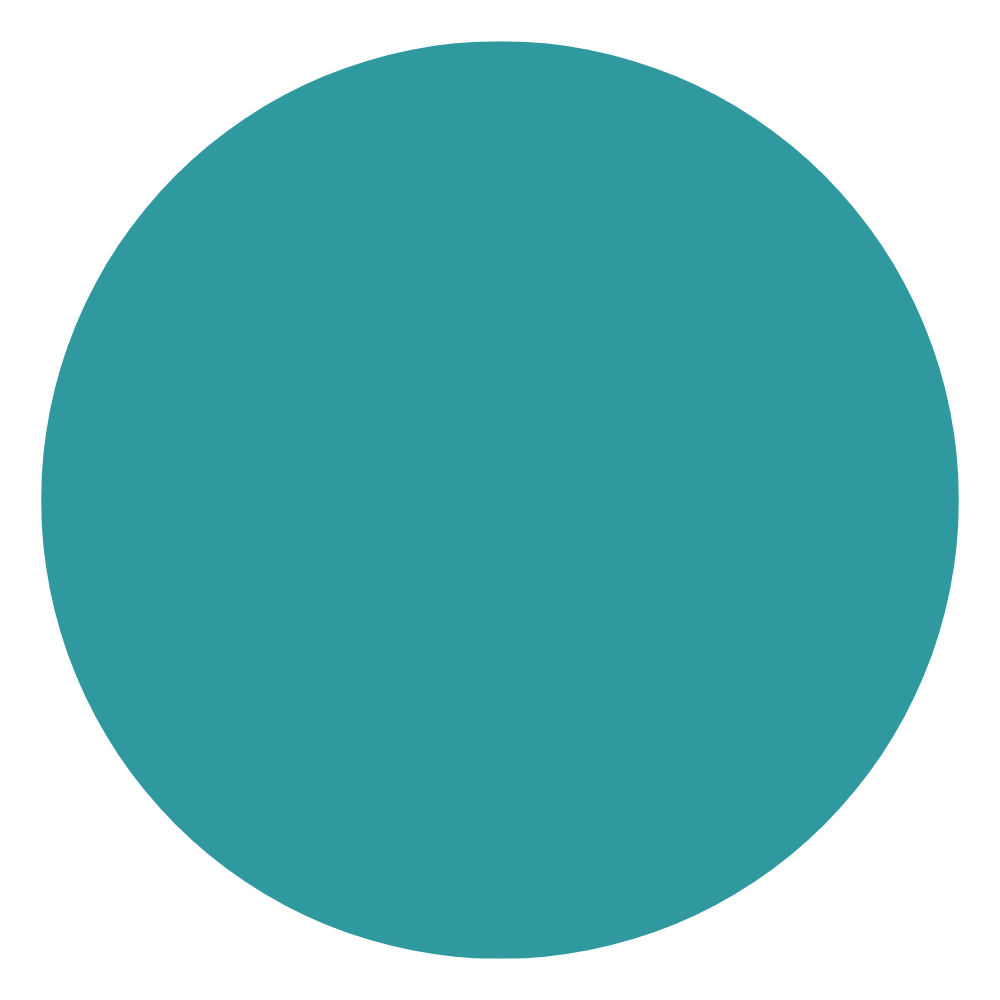 行政書士
行政書士
行政書士は、行政へ提出する書類作成の専門家です。行政書士が行える代行業務は次の通りです。
・定款認証の代理申請
・許認可が必要な業種の申請書類作成や提出代行
設立登記について代行することができませんが、定款の作成と認証は司法書士を同じく代行をすることができます。
許認可に関する手続きの代行ができるので、建設業や飲食業、運送業など許可が必要な業種の場合は、依頼することができます。
関連記事:【会社設立】建設業で法人化をするには?必要な許可や注意点を徹底解説
関連記事:【必見】運送業許可の要件│重要な4つの要件について解説
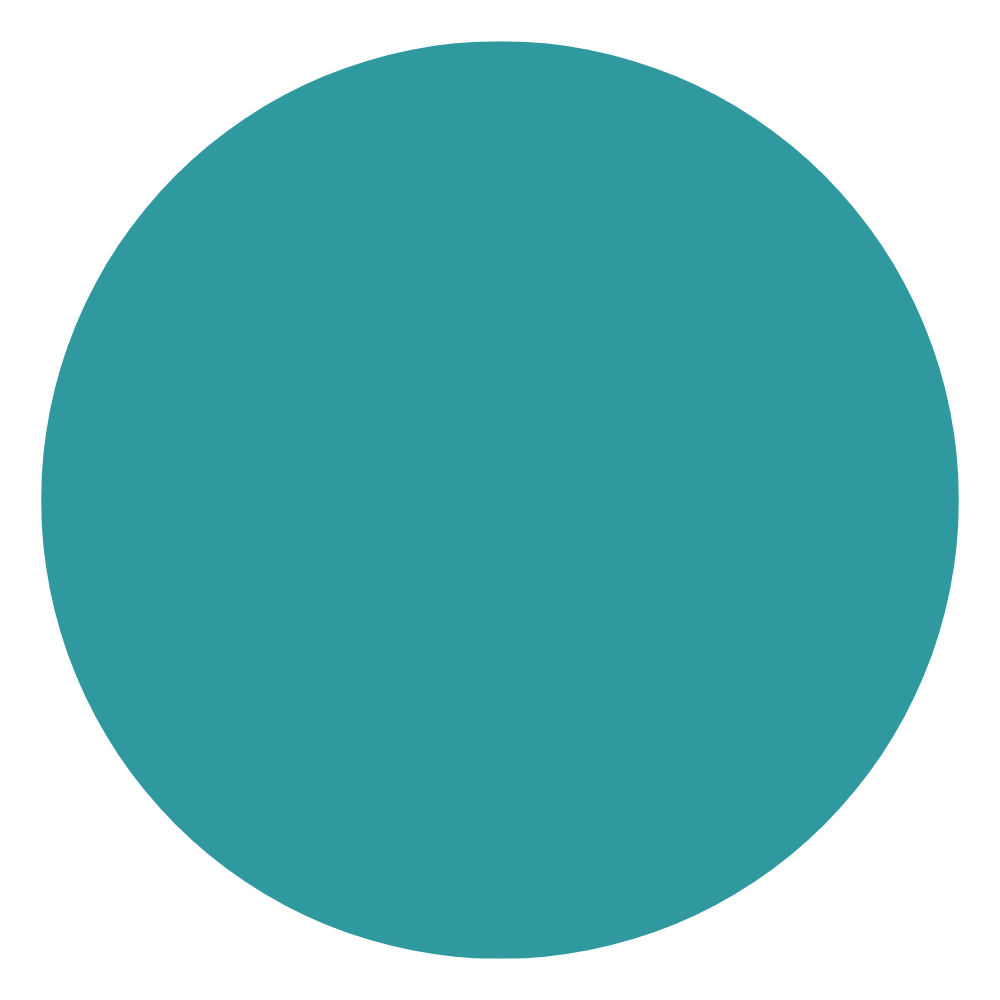 社会保険労務士
社会保険労務士
社会保険労務士はその名の通り、労務や社会保険手続きの専門家です。健康保険・厚生年金保険の手続きや労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)への届出を行うことができます。そのほかにも就業規則の作成や整備、従業員を雇用した際の雇用契約書の作成なども行っています。
そのため、会社設立と同時に従業員の雇用を検討している法人にとっては頼りになる存在です。
関連記事:【教えて!】社会保険の加入条件・手続きについて解説
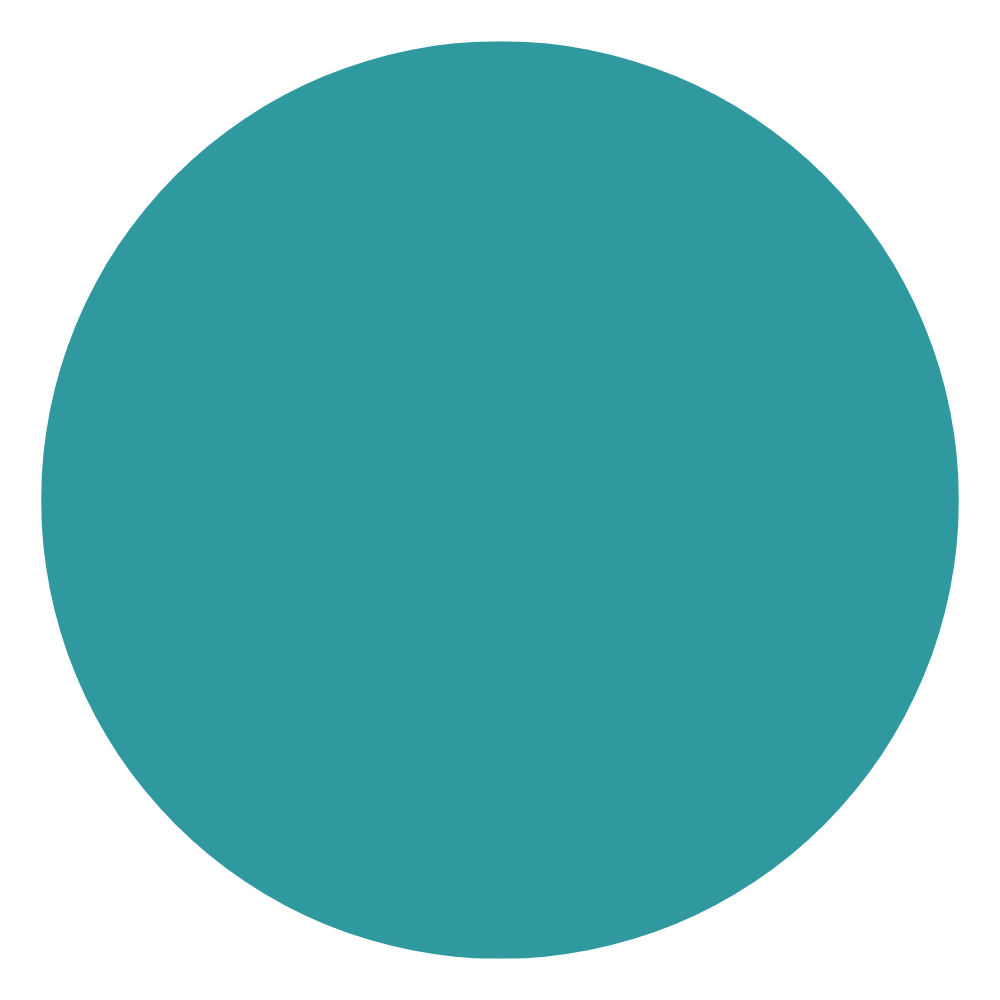 税理士
税理士
税理士は税務の専門家です。設立登記の代行などは行えませんが、書類作成のサポートや設立後の開業届・青色申告承認申請書などの税務署への提出代行、節税のアドバイスを行うことができます。
税金に関しては永続的にかかるものなので、できる限り負担を軽減したい部分だと思います。顧問契約を行い、会社設立だけでなく、補助金や助成金、決算期の税務処理などを任せることができるため、日常的な税務のアドバイスを求めることが可能です。
上記のようにそれぞれの手続きに特化した専門家がいるため、「自分で手続きをするのは難しい」と感じている方は、活用して代行依頼しましょう。また、専門家によっては設立後も業務を代行したり、アドバイスをもらうことも可能なので、必要に応じて顧問契約も検討しましょう。
毎月3社限定|0円で設立サポートします
今回は、会社の種類や設立の流れや費用についてまとめました。
事前に全体的な流れを理解しておくことで、いざ設立する際もバタバタせずに済むようにしたいですね。
とはいえ、ご覧いただいても分かるように会社設立をするには用意、書類作成の対応など多くの手間がかかります。漏れがなく、より円滑に準備を進めていくためには専門家のアドバイスを受けるという方法もおすすめです。
当事務所でも会社設立に関して、毎月3社限定で手数料0円で代行をさせていただきます。会社の設立をお考えの方、ぜひお気軽にご相談くださいね。
ご連絡お待ちしております!
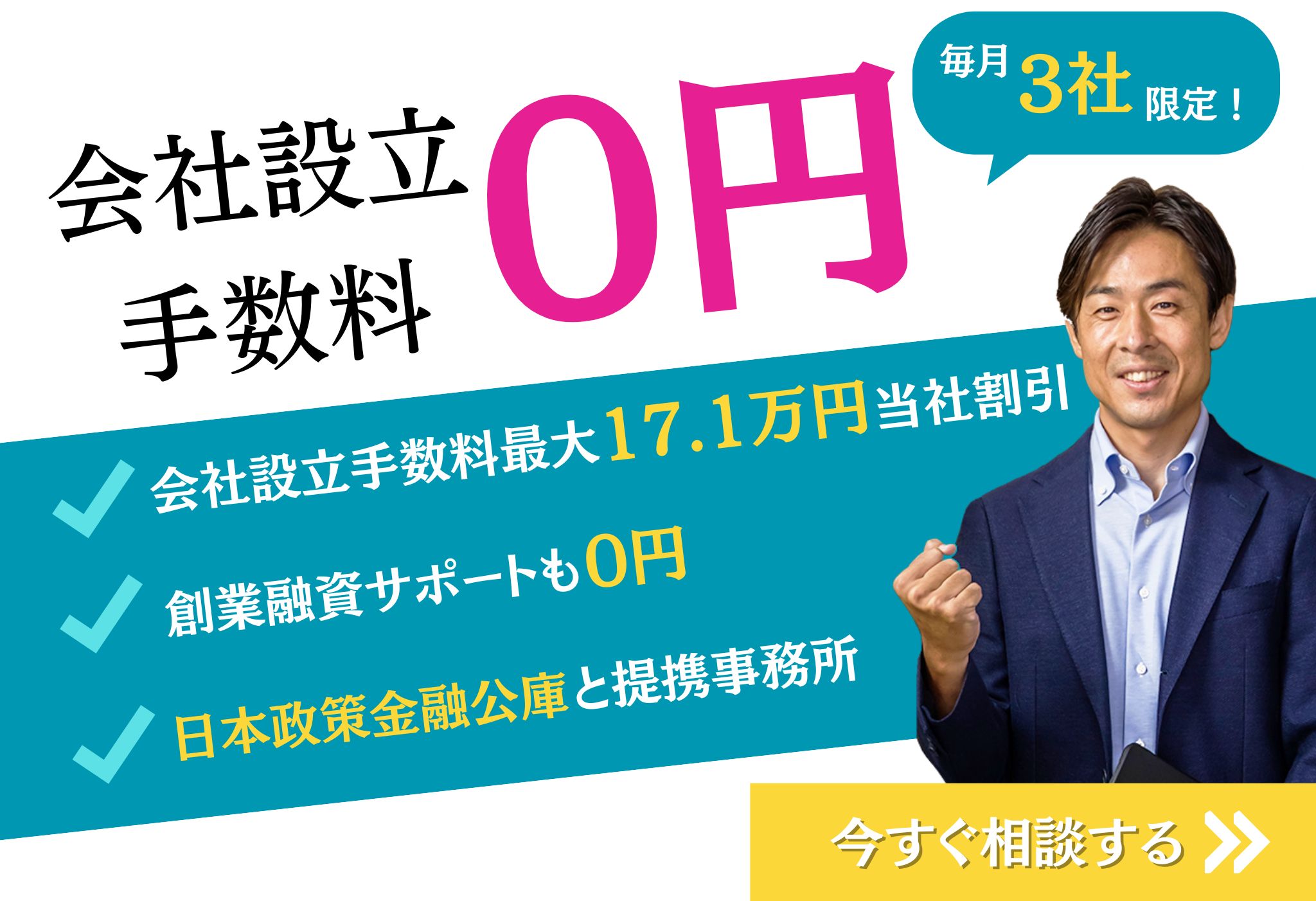
関連記事:【まとめ】会社設立に必要なことリスト
関連記事:会社設立における節税メリットとは?
関連記事:飲食店開業の費用はいくら?流れと資金調達方法について‼︎
関連記事:不動産会社設立の流れとポイントを解説!
関連記事:会社設立が相続税対策に有効?メリットとデメリットを解説
関連記事:横浜市で会社設立をするには?創業融資や補助金・助成金制度を紹介
関連記事:合同会社は代表社員2名で設立できる?会社設立の流れと注意点について
関連記事:会社設立時の持ち株比率と権利について解説



