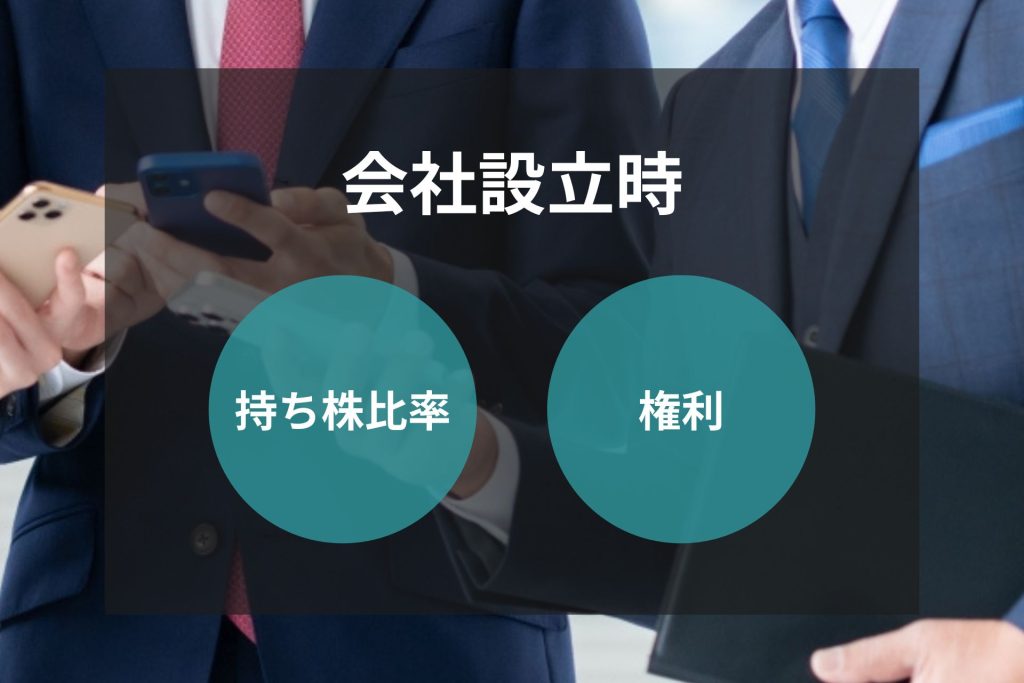
会社設立時、または設立後の様々な疑問点をご紹介していきたいと思います。
今回の記事は「持ち株比率」についてです。
持ち株比率は、企業が発行した株式の総数に対して、株主が保有する株式の割合のことです。
自分で株式会社を立ち上げた際に、創業メンバーの中で株式を持ち合うことは一般的に行われています。一言で株式を持ち合うといってもどれくらいの割合が適切なのでしょうか。
「持ち株についてあまり考えなかったせいで、創業メンバーと揉めてしまい後悔している。。」という声も少なくありません。
そこで、持ち株比率によって保有できる権利や株式を分散させるメリットやデメリット、そして注意点を説明していきます!利や株式を分散させるメリットやデメリット、そして注意点を説明していきます!

持ち株比率について
はじめに、そもそもなぜ持ち株の比率を重視しなければならないかですが、株式会社においては会社の意思決定は株主総会で行います。そこでの議決権は保有する持ち株比率によって与えられるのです。つまり、持ち株比率によって会社経営にどのくらい関与できるかが決まってくるため、特にはじめの創業メンバー間で決める際にはしっかりと検討していくことが重要です。さらに、持ち株比率は、議決の他、配当にも影響してきます。
持ち株比率とは?
持ち株比率とは、企業が発行した株式総数に対して、自身(株主)が保有する株式数の割合を指します。企業全体の株式を株主がどのくらい保有しているのかという指標になります。また、持ち株比率によって株主の呼び方や行使できる権利が異なります。株式の中には、1株のみで行使できる「単独株主権」や一定数量以上の株式で行使できる「少数株主権」などがあります。
持ち株比率は以下のシンプルな計算で求めることができます。

例えば、会社が発行した株式総数が1,000株だとして、そのうちの100株を自分が保有している場合は、持ち株比率は次のように算出することができます。
持ち株比率=(100株÷1,000株)×100=10%
保有している株式が少ない場合でも、会社が発行している株式総数が少なければ、相対的に持ち株比率は高くなります。この数字が高いと、企業への影響力が強くなります。
ただし、創業者が資金調達を目的として株式を大量に発行し、出資者や共同経営者の持ち株比率が高くなると、ほかの株主や自身の持ち株比率は下がるため、影響力が弱まります。
このような状況になると、自分の会社にも関わらず、経営方針を決定することができなくなる恐れがあります。これから経営者になろうとしている方は、このようなトラブルを防ぐために、持ち株比率には注意しましょう。
株主の権利を知ろう
株主にはさまざまな権利があるとお伝えしましたが、実際にどのような権利があるのかを知っている方は少ないでしょう。そこで株主の権利について紹介します。
株主の権利とは、以下の3つを指します。
・株主総会の議決権
株主総会に参加した際に、挙げられた議案に対して賛否の投票ができる権利を指します。原則として1単元株につき1つの議決権が与えられるため、株式を多く保有している人ほど会社への影響力は大きいです。
どうしても株式を多く保有している人の考えが企業の経営や活動を決めてしまいますが、株式を保有する人全員に議決権は与えられています。自分の意見を事業へ反映できるので、所持している権利は使ったほうが良いでしょう。
・利益配当請求権
株式を保有し、株主になることで配当金を受け取る権利を得ることができます。余剰金配当請求権や配当請求権といわれることもあります。
長期的にみると株価は企業の成長と密接に関係しており、企業の価値が上がると株価も上昇します。そのため、長期投資をする際は、この利益配当請求権が重要になります。
・残余財産分配請求権
残余財産分配請求権とは、企業が解散する際に行使される権利です。企業が解散や清算手続きを行う場合、残った財産はまず負債に充てられます。負債に充てても残った財産は、株主の持分割合に応じて財産の分配を請求できる権利です。
紹介したように株主にはさまざまな権利が与えられます。会社の設立を検討している方や経営者の方は、株主の権利を提供する義務があることを覚えておきましょう。
保有できる権利について
まず、株の割合ごとにどのような権利があるのかをご紹介します。多ければその分できる範囲も広がりそうなざっくりとしたイメージを持っている方も多いのではないでしょうか。
しっかりと理解を深めていきましょう。
|
1株以上を保有 |
議事録の閲覧や株主代表訴訟を起こす権利があります。 |
|
1%以上を保有 |
株主総会での議案を提出できる権利が発生します。また、総会の検査薬を選任する請求を出す権利も生じます。(会社法303条2項) ただし、定款の定めがない限り、6か月以上の保有が必要です。 |
| 3%以上を保有 |
株主総会の招集や、会社の帳簿などの経営資料を閲覧する権利、役員を解任させる請求ができる権利が発生します。(会社法297条1項、会社法433条1項) 1%以上保有と同様に、定款の定めがない限り、6か月以上の保有が必要です。 |
| 10%以上を保有 |
訴えにより、会社の解散を裁判所に対して請求できる権利が発生します。 |
| 1/4以上を保有 |
重要事項の特別決議を単独で阻止できる権利が発生します。 ・定款変更 ・監査役解任 ・自己株式の取得 ・募集株式の募集事項の決定 ・事業譲渡 ・合併・会社分割など組織再編などを阻止することが可能 |
| 1/3以上を保有 |
定款の変更や監査役の解任など重要事項の特別決議を単独で否決できる権利が発生します。 |
| 1/2以上を保有 |
普通決議を単独で可決する権利が発生します。(会社法309条1項) 取締役の選任や解任をはじめとして、会社の意思決定のほとんどを自ら行うことができます。 |
| 2/3以上を保有 |
自己株式の取得に関する事項の決定、募集株式の募集事項の決定、事業譲渡、合併や会社分割といった組織変更の決定などの際に株主総会の特別決議を単独で可決する権利が発生します。(会社法309条2項) つまり会社経営における重要事項のほとんどを単独で可決することが出来るということになります。 |
| 90%を保有 |
対象となる会社の承認を得るなどの一定の手続きを経て、対象会社及び特別支配株主以外のすべての株主に対して、対象会社の株式を特別支配株主へ売り渡すよう請求する権利が発生します。(スクイーズアウト) |
| 100%保有 |
すべての事柄において、自分の意思で決定することが可能です。 |
上記をみてみると、持ち株の割合によって行使できる権利が細かく分かれていることが分かりますね!このように、株式比率に応じた権利が会社法によって定められています。まずは、これを踏まえて創業メンバー間の持ち株の割合を検討しましょう。
持ち株比率や議決権比率、出資比率の違い
持ち株比率のほかに混同しやすい言葉として、議決権比率と出資比率の2つがあります。それぞれの意味は以下の通りです。
・持ち株比率
企業の株式を誰が何割保有しているのかを示す数字です。通常であれば、持ち株比率は出資比率の比率と同じになることがほとんどですが、起業の際に出資額に対して割り当てる株式の数を異なる割合にすることもできます。
・議決権比率
株主が持っている議決権を行使できる割合を意味しています。持ち株比率との違いは、計算に用いる株式の種類が異なる点です。どの程度の議決権を保有しているかによって、行使できる権利が異なるため、会社への影響力の指標として重要な比率です。
・出資比率
誰が何割出資しているのかという比率を指します。例えば、起業をする際の出資金が1,000万円だとすると、そのうちAさんが500万円、Bさんが300万円、Cさんが200万円を出資したとします。このような場合の出資比率は、Aさんは50%、Bさんは30%、Cさんは20%という割合になります。
ここで覚えてほしいのは、株式には議決権を持つ「普通株」と議決権を持たない「無議決権株」があることです。議決権を持たない代わりに、普通株よりも高い配当が与えられる配当優先株式などがあります。そのため、持ち株比率と議決権比率の割合が必ず一致するとは言えないので、注意が必要です。
議決権比率は以下の計算式によって求めることができます。

例えば、発行済み株式数が1,000株あり、総数のうち普通株式が700株だとした場合、普通株を100株と無議決権株を20株保有する場合の持ち株比率と議決権比率を計算してみます。持ち株比率と議決権比率がどのような変化があるのか確認してみましょう。

(120÷1,000)×100=1.2%
議決権比率(%)=(自分の保有議決権数÷行使できる議決権の合計数)×100
(100÷700)×100=約1.43%
発行済株式数のうち、普通株式と無議決権株式の数が異なると上記のように、持ち株比率と議決権比率の数字は異なります。持ち株比率の高い株主であっても、株式の大半が無議決権の場合は、ほかの株主と比較して企業の議決権が少ないため企業への影響力は小さくなります。
持ち株比率による名称の違い
株主は持ち株比率によって名称が異なります。株主に馴染みがない方でも「大株主」などは聞いたことがあるのではないでしょうか。厳密に定義されているものとそうでないものがあるので、事前に確認して使いましょう。
・大株主
大株主は明確な定義は定められていませんが、株主の中で企業の株式の持ち株比率が高い(保有している株式が多い)株主を指す言葉として用いられます。
・主要株主
主要株主とは、企業の議決権のある発行済株式の100分の10以上を保有している株主のことです。この定義は金融商品取引法で定められています。
・筆頭株主
筆頭株主とは、企業の議決権のある発行済株式を最も多く保有している株主を表す言葉です。
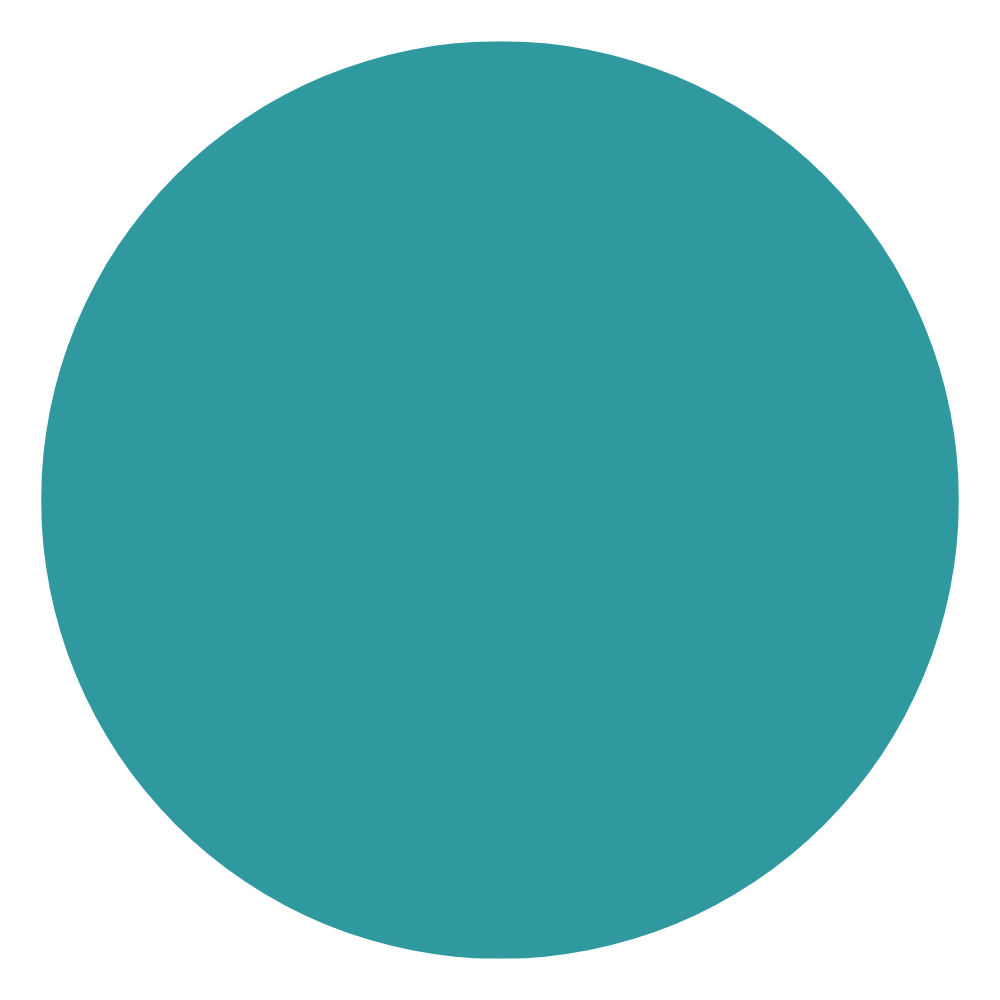 株式を分散させるメリット
株式を分散させるメリット
次に、創業メンバー間で株式を分散させて持つことのメリットをご紹介していきます。
それは、「メンバー間で会社を運営していくにあたっての線引きがはっきりしている」ということでしょう。持ち株比率によってメンバーごとにどれだけの権利を保有しているのかを周知することができるので、意思決定する際にもスムーズにいきやすいというメリットはあるでしょう。もし、全員が平等に同じ持ち株保有率であるならば、当然のことながら保有できる権利も同じとなり、メンバー全員が同じ方向を向いて仕事がしやすくなるのではないでしょうか。
しかし、メンバー全員が常に同じ考えという事はありません。最終的な意思決定は代表者であるべきです。この後にも記載しますが、誰か1人の代表者が過半数の株式を持つと良いでしょう。
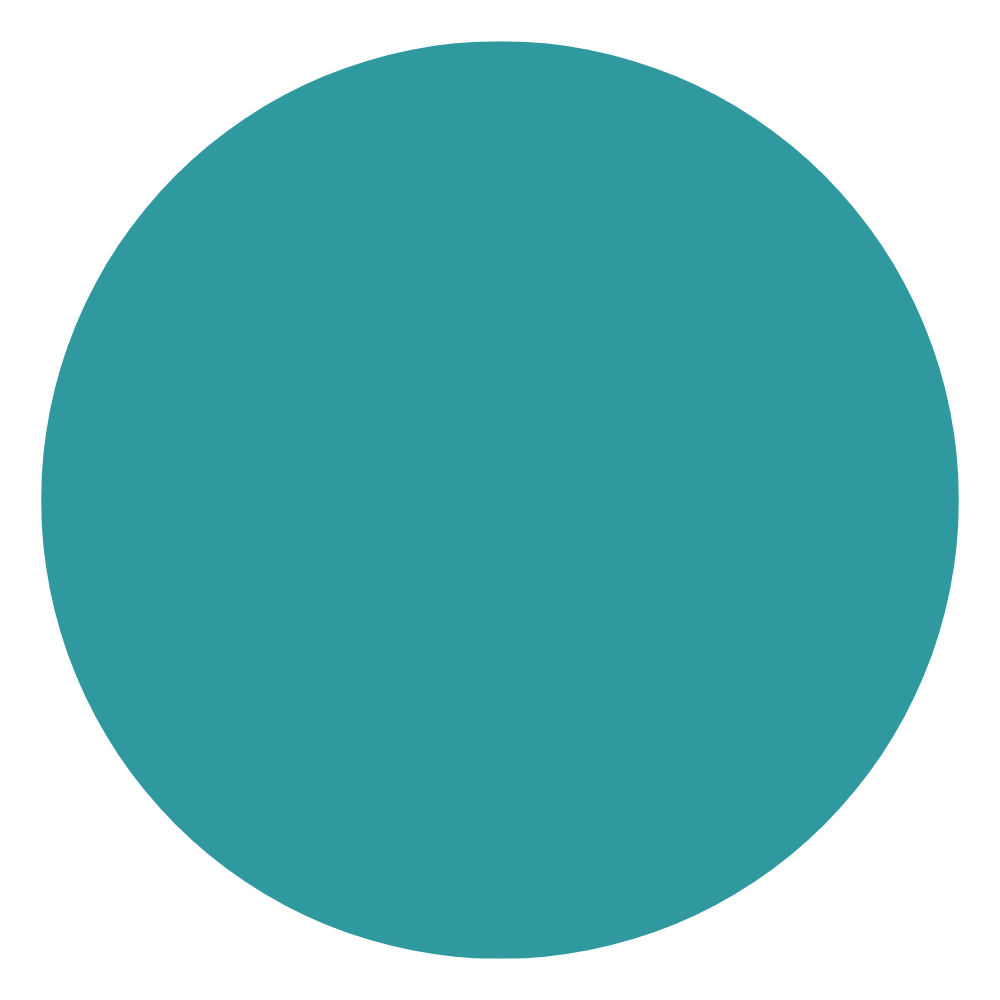 持ち株を均一にするのは避ける
持ち株を均一にするのは避ける
先程メンバー間で持ち株比率を均一にした場合のメリットをご紹介しましたが、ひとつ注意しておくべきことは権利が平等だからという理由だけで持ち株を均一にシェアすることは避けておくべきです。持ち株比率を均一にするということはメンバー間で同等の権利を行使できるという面もありますが、同時に意思決定の軸となる人物をはっきり決めないまま事業が開始されるということでもあります。実際の経営権は誰が持つのかはハッキリ決めておく必要があるでしょう。
創業の段階ですべきこと
会社を設立する際に、事前に持ち株比率についてしっかりと考えておく必要があります。ただ、企業が発行する株式や持ち株比率について理解している方は多くないでしょう。
そのため、創業の段階でやるべきことを紹介するので、事前に準備を行いましょう。
会社の代表者を1人に絞って明確に決めておこう
持ち株比率について検討する際に、明確に決めておくべき事柄として「代表者が誰なのか」ということです。創業メンバーが複数いる場合でも代表となる人物は一人に絞ることを強くおススメします。その場合、その人物の持ち株比率は他のメンバーより多くしてください。
代表者の持ち株比率は最低でも1/2以上
代表者が決まったら、どのくらいの持ち株比率を保有するかということになりますが、ずばり、最低でも1/2以上、2/3以上が理想的な割合と言えるでしょう。
上記で紹介した行使できる権利の上では1/2以上の持ち株比率があれば、取締役などを解任させる権利も持てるので一定の経営権は確保することができます。
逆に、それ以下であれば他の人の意思で代表を解任されてしまう可能性もありますので注意が必要です。
さらに、安心して会社経営を行い、代表者の不利益にならないようにするには会社に関するほとんどの事柄を自ら決定することのできる2/3以上の持ち株比率が理想的です。
持ち株比率に関しての注意点
持ち株比率は一生涯変わらないというわけではありません。会社を経営するにあたって、会社の規模を拡大したり従業員を雇用したりという変化があると、発行する株式数も大きく変更するケースがあります。そのようなケースを含めて、持ち株比率について注意する点を解説していきます。
 出資を受ける際は持ち株比率も見直そう
出資を受ける際は持ち株比率も見直そう
事業を始める、または拡大していこうと考える際に出資を受けて資金調達をすることもあるでしょう。その際は現状の持ち株比率も見直すことをおススメします。なぜならば、出資をうけることによって伴う新株発行により、発行済みの株式の数が増加して、1株あたりの価値が低下してしまう可能性があるからです。
ここで忘れてはいけないのが「経営に対して行使できる権利は、あくまでも全体の株式総数に対する持ち株の比率によって決まる」ということです。資金調達をうければ、その投資家へ新しい株を発行しなければなりません。そうなると、もともと創業時のメンバーが持っている株の数は変わらないので全体に対する比率が変わり、それにより行使できる権利内容も異なってくるという訳なのです。気が付くと代表者が保有する持ち株比率の割合が2/3を切っていたという事態が発生しかねません。そうしたリスクを避けるためにも、資金調達の際には特に慎重に検討していきましょう。
 出資を受ける予定があれば余裕をもって持ち株比率を設定する
出資を受ける予定があれば余裕をもって持ち株比率を設定する
新しく出資を受けたり、株主が増えると創業者や経営者を含む、既存株主の持ち株比率は低下します。経営者のつながりや会社設立の関係があって、事前に出資を受けることがわかっている場合は、余裕を持った持ち株比率を維持できるように設定しましょう。
持ち株比率が67%程度の状態で出資を受けると、持ち株比率が66.7%(2/3)未満になる可能性が高くなります。持ち株比率が低くなると、会社に対する影響力が小さくなってしまうので注意が必要です。
 創業者の持ち株比率を上げる方法を知識として身につけておく
創業者の持ち株比率を上げる方法を知識として身につけておく
新規の出資者や株主の増加に伴い、創業者の持ち株比率が下がる可能性があります。経営の安定化のために、創業者の持ち株比率を上げる場合は、2つの方法があるので知識として身につけておきましょう。
・株式の発行
新しく株式を発行して、その株式を創業者が購入することで持ち株比率を上げることができます。
ただし、新しく株式を発行するには発行する株式の種類や総数を株主総会で決定する必要があるため、他の株主から反対されてしまうと株式の発行自体が否決される可能性があります。必ずしも株式の発行ができるわけではないというのは覚えておきましょう。
・ほかの株主から株式を買い取る
既存の株主から株式を買い取ることで、持ち株比率を上げることができます。株式を買い取るには、購入する費用の負担が必須になります。また、一般的には株式譲渡制限があるため、株主総会や取締役会などの認められた機関・組織からの承認がないと株式を買い取ることができません。
株式を買い取るにも、当事者同士が株式の譲渡に同意していたとしても、ほかの株主からの同意がないと行うことができないため、ハードルが高いです。
上記のような持ち株比率を上げるための方法を知識として身につけておくことで、対応することができますが、前述したように方法も限られているため、持ち株比率を下げないように対応していく必要があります。
 資金調達には「借入」がおススメ
資金調達には「借入」がおススメ
資金が不足する場合、株式保有の観点からみると上記で説明した通り「出資」では保有株式の割合が変わってくるため、出資という形で資金調達するのではなく融資などで借入ができないか検討してみることをおススメします。借入であれば持ち株比率も変わらないのでその点では安心です。一つの選択肢として頭に入れておきましょう。
 株主との信頼関係を築く
株主との信頼関係を築く
株式の発行は、資金調達の手段として利用されることがありますが、会社の意思決定に参画できる権利を得ることができる点がとても重要です。その権利があることで株主は企業にとって最も重視すべきステークホルダー(利害関係者)であると考えられます。
そのため、企業は株主との信頼関係を築くことが大切です。株主との信頼関係が築けていないと、企業の新しい事業や施策などを提案したとしても受け入れてもらえなかったり、一方的に反対される場合があるため、会社の経営自体が困難になります。信頼関係を築くには、日々の積み重ねが大切になるため、日ごろから会社の経営方針を話したり、コミュニケーションをとることが必要です。
信頼関係を構築すると、何か提案をした際に欠けている点についての補完や代替案の提案など、前向きな議論を行うことができ、経営への協力を得ることができます。そのため、日常的に株主とのコミュニケーションをとって、信頼関係の構築に努めましょう。
不安な方はご相談ください
今回は会社設立時の持ち株比率についてご紹介しました。
創業メンバー間で持ち株比率をどうするかによって会社の方向性が大きく変わってくるといっても過言ではありません。最近では友人関係で起業するというようなケースも増えてきています。安易に半分ずつ保有して、後から会社の方向性についてスムーズに決定できないといったことにならないためにもしっかりと持ち株の割合における保有できる権利について理解して、事前にきちんと検討、決定しておきましょう。
とはいえ、なかなか自分たちではどう決めていいか分からない、不安という方もいらっしゃると思います。
当事務所では、会社設立時における持ち株についてのご相談もお受けしています。
会社設立を検討している方、また、より詳しく知りたい、相談したいという方はまずはお気軽にご相談ください。
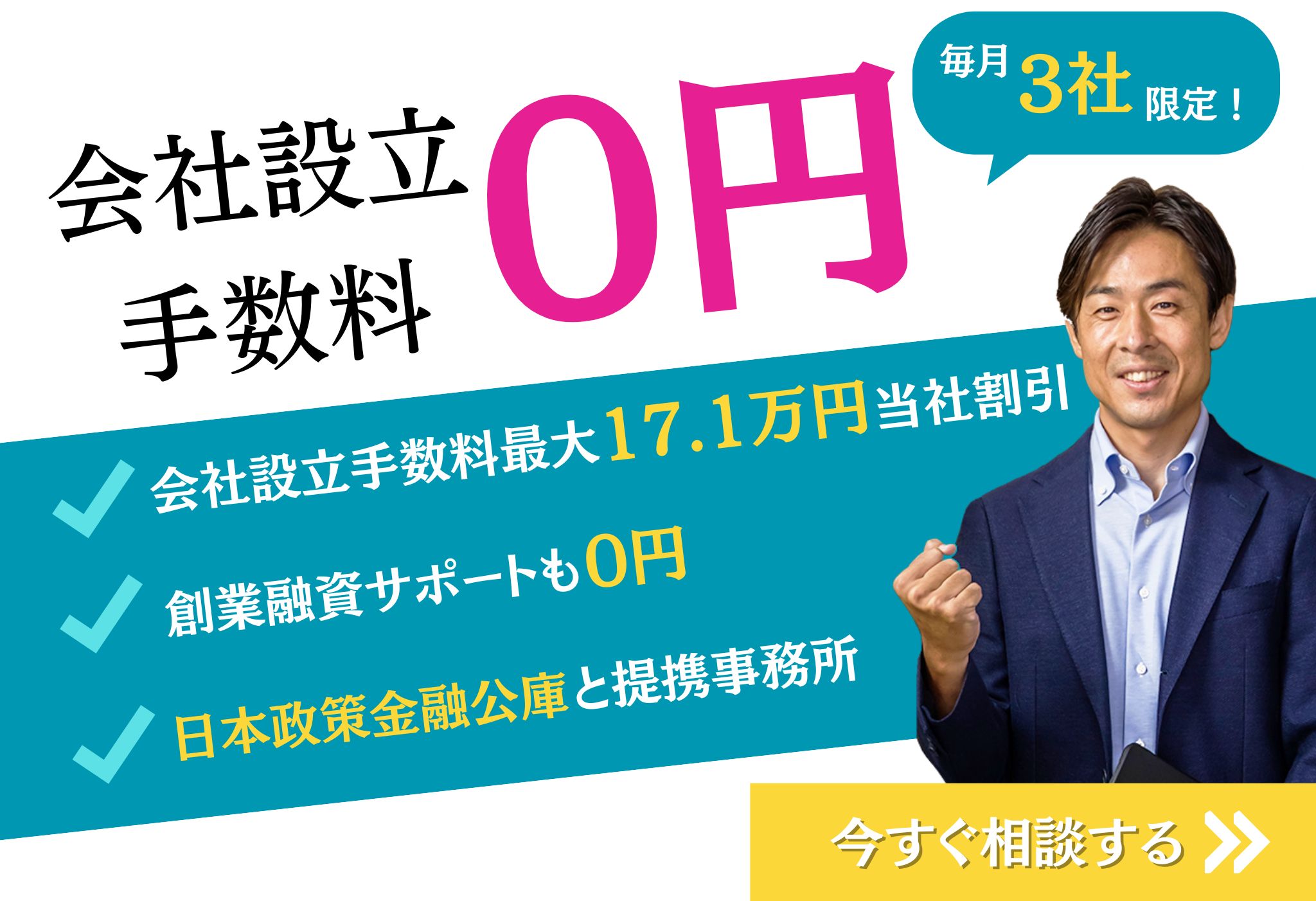
関連記事:会社設立のための資本金はいくら必要?平均額や決め方について解説
関連記事:【知っておきたい】会社設立時、設立後にかかる税金とは?
関連記事:不動産会社設立の流れとポイントを解説!
関連記事:会社設立が相続税対策に有効?メリットとデメリットを解説
関連記事:【最新版】給与計算は税理士と社労士どちらを選択する?相場と選択基準!
関連記事:【最新】有限会社は株式譲渡できるのか?株式譲渡の流れやメリット、注意点を解説
関連記事:横浜市で確定申告を無料相談できるところ



