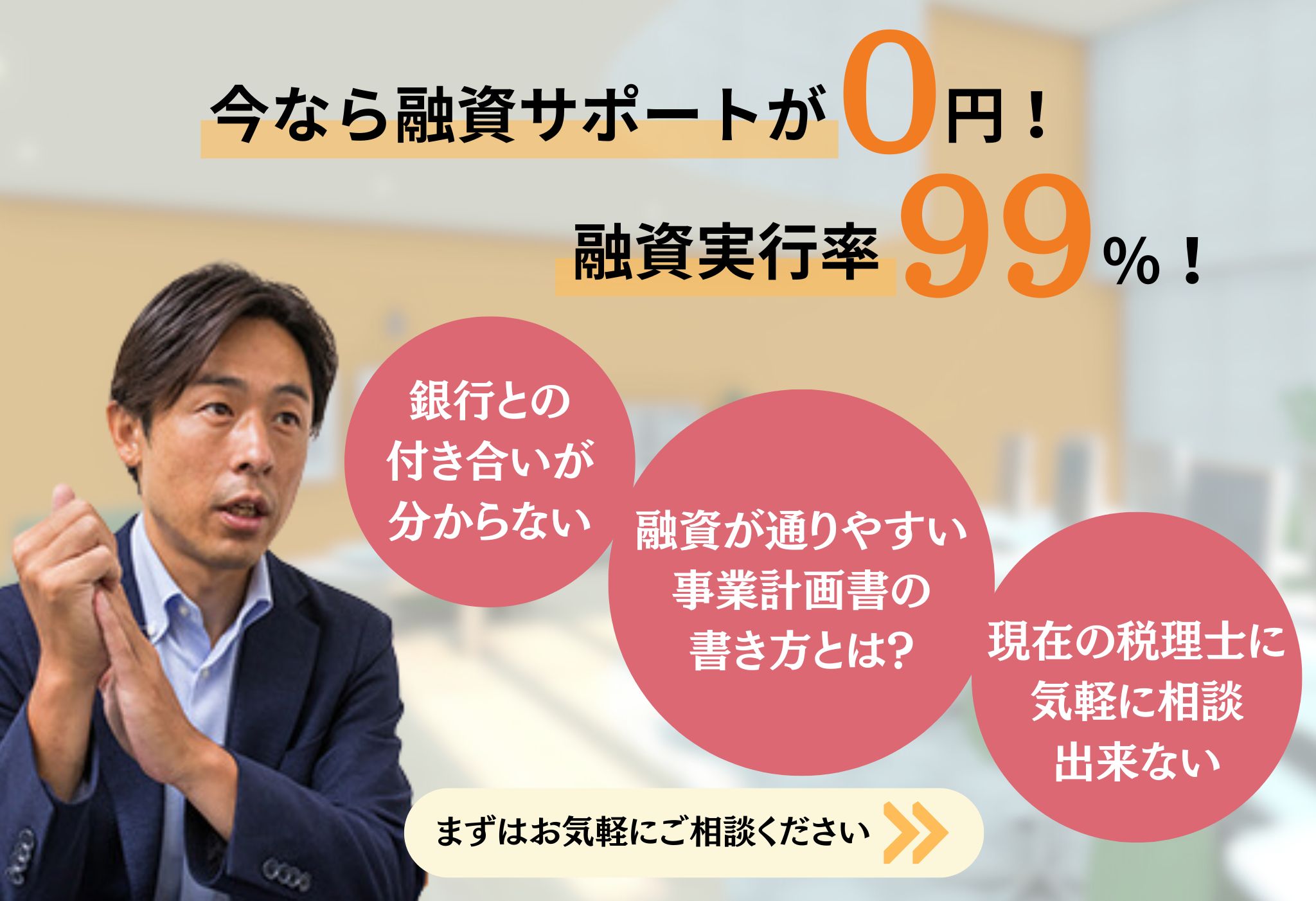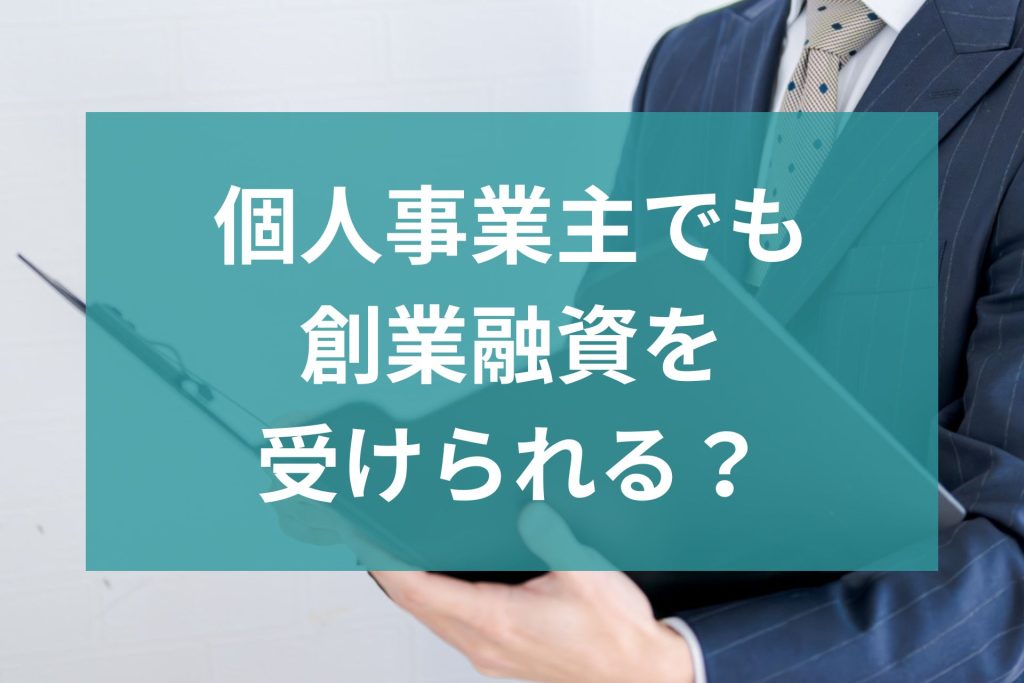
昨今、仕事として、あるいは副業として自分でビジネスを行う「個人事業主」は急速に増えています。
そして、事業をする上で避けては通れない問題が、「資金調達」です。
個人事業主だと融資を受けるのは難しいのでは?
そう思われている方もいらっしゃるでしょう。
結論からお伝えすると、個人なのか法人なのかなど事業形態によっては、融資審査通過の影響を受けるとは言えません。
重視されるのは、「この人にお金を貸して返ってくるのか?」ということです。
今回は、個人事業主でこのようなお悩みを抱える方へ向けて、創業融資について受けることのできる条件や事業者として行うべき対応をご紹介していきます。
実際の融資事例:【新規開業支援】ビーガンスコーン専門店“iro” 横浜市西区伊勢町にオープン!
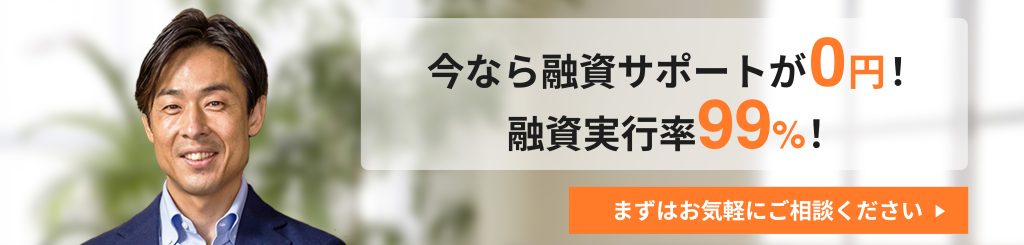
創業融資について理解しよう!
まず、創業融資という言葉について理解をしておきましょう。
創業融資とは、新しくビジネスを始める事業者に必要な資金を融資する制度のことをいいます。
冒頭でも軽く触れましたが、開業にあたっては仕入れや人件費などある程度まとまった資金が必要になります。そんな時に金融機関など外部から資金調達して準備することが多いのです。
関連記事:【創業融資】起業の際に確認すべきこと
創業融資の種類
創業融資が通常の融資とは異なる点としては、必要な資金を借りやすくして創業者を支援するために設けられている制度だということです。創業融資の種類としては以下の2つがあります。
・日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金制度」
・各都道府県、市区町村の「制度融資」
通常、「融資」と聞くと銀行など金融機関から借りるというイメージが多いかと思いますが、金融機関は確実に返済してくれるかという点に重きを置いて審査を行います。そのため、実績の乏しい創業間もない事業者は融資を見送られるケースが多いです。一方で創業融資は、元々の対象者が創業間もない方なので、過去の実績ではなく、会社の将来性や今までの経験値などから計画性を重視しているため、借入れ自体もしやすいというメリットがあります。
さらに、基本的には金利自体も低く設定されているので、その点も利用しやすいポイントになるでしょう。
個人事業主が創業融資を受けるには
では、先程ご紹介した創業融資ごとに利用するための条件を見ていきましょう。
日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金制度」
日本政策金融公庫は金融庁からの出資で運営される、いわば政府金融機関であり、国民生活事業や農林水産事業、創業間もない個人事業主・中小企業などに対して積極的に融資を実施してサポートを行っています。
そんな日本政策金融公庫の融資制度の中の一つが「新規開業・スタートアップ支援資金制度」です。以前は「新創業融資制度」がありましたが、2024年3月に廃止となり、その制度を統合・刷新してつくられたのが、「新規開業・スタートアップ支援資金制度」です。
特徴は以下の通りです。
 メリット
メリット
・創業前、創業直後の事業者が無担保、無保証で利用できる。
・創業してからおおむね7年以内の方も対象となるので、対象者が幅広い(女性や若者、シニア世代など含む)
・一定の要件を満たす方は、基準利率ではなく、特別利率を適用。
・従来の「創業資金の10%以上の自己資金が必要」という要件が撤廃され、自己資金なしで申込可能。
・最大で7,200万円までの借入が可能。
 デメリット
デメリット
・融資の実行までに時間がかかるため、緊急を要する融資には不向き。
・この後紹介する「制度融資」に比べると金利が高めである。
金利は年度ごとに変動しているので、最新の金利はこまめに確認しておきましょう。
「新規開業・スタートアップ支援資金制度」を利用する要件
ではこの制度を利用することのできる要件をご説明します。
・これから新たに事業を始める人、または事業開始後の税務申告を2期終えていない人
これはつまり創業間もない事業者であるということが必要なのですが、今から始めようと考えている皆さんは当てはまっているかと思います。
・事業開始後、おおむね7年以内の方
この対象者に関しては、「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限られているため、創業計画書や事業計画について厳しく審査される可能性があります。
[有利な条件で融資を受けれる方]
・女性、若者、シニアの方で創業をする方
・廃業歴等があり、創業に再チャレンジする方
・中小会計を適用して創業する方
上記に当てはまる方は、基準の利率よりも低い金利で融資を受けられます。そのなかにも、担保の有無や災害貸付(東日本大震災復興特別貸付、令和6年能登半島地震特別貸付等)を利用するか否か、経営者の保証を不要とする融資を利用されるかなどによって、金利は変動します。さらに詳しく知りたいという方は、専門家や日本政策金融公庫の窓口に問い合わせるのが確実です。
各都道府県、市区町村の「制度融資」
続いて「制度融資」についてご紹介します。制度融資は各地方自治体がそれぞれの信用保証協会と金融機関とを連携して運営している創業融資制度のことです。
制度融資の場合は、信用保証協会が連帯保証を行うことで融資を受けやすくします。
特徴は以下の通りです。
 メリット
メリット
・金利が低いこと、地方公共団体からのサポートを多く受けることができる。
・金利に関しては、自治体からの利子補給がついていることも多く、一般的な金融機関より低い金利で借入を行うことが可能。
・自治体がサポートに付いているということで、創業アドバイザーによる創業支援サービスや各種セミナーへの参加などさまざまな公的サービスを受けることが可能。
 デメリット
デメリット
・日本政策金融公庫とは異なり、制度融資では申込者(事業主本人)が保証人となる代表者保証が求められる。
・融資実行時に信用保証協会を利用するため、その利用料を「保証料」という形で支払う必要があるという点。保証料の金額は借入金額や保証期間などによって異なります。
・金利や融資上限額、対象事業者の要件などは、自治体によって異なるため、地域によってはほかの地域よりも不利になる可能性もあります。
・自治体、保証協会、金融機関の3者が融資に関わっているため、手続きは複雑。書類など資料の準備のみならず、融資実行までの期間も長く必要になりますので、もし利用を検討されている場合は、余裕を持って進めていくことをおすすめします。
「制度融資」を利用する要件
この制度融資に関する要件などは、各自治体ごとに異なりますので、細かい申し込みの方法や手続きの流れに関することは各自治体のホームページや問い合わせなどから前もって確認するようにしましょう。
また、「制度融資」は、時間に余裕があってじっくりと準備ができる方や地域の支援機関と相談しながら進めたいという方にはおすすめです。
以上創業融資の種類や特徴をご紹介してきました。
それぞれによって特徴、メリットがあり、自分の事業にはどれが良いのか判断する必要があります。ただ、低金利、無担保、無保証で事業への負荷を抑えられるという点では、個人事業主で利用される場合は日本政策金融公庫の融資をまず最初に検討すると良いでしょう!
融資の申込の流れ|詳しく解説
融資の申し込みは、さまざまな手続きが必要で時間がかかります。事前に手続きの流れを知っておくことで、前もって書類などを準備することも可能になるので、以下の流れを把握しておきましょう。

・申込書類の提出
・担当者との面談
・審査
・融資の開始・返済
 融資相談・申込先の決定
融資相談・申込先の決定
まず最初に融資の相談を信頼できる人にすることがとても重要です。
もちろん金融機関の窓口に相談することも1つの方法ではありますが、それぞれの窓口も会社の利益のために、自社の融資商品を進める可能性が非常に高いため、おすすめはできません。
多くの知識を持っている中小企業診断士や税理士、商工会議所などの専門家であれば、今までの経験や知識から、客観的で的確なアドバイスを得ることができます。
そのアドバイスをもとに、融資の申込先を決定します。目的や条件に応じた融資制度が数多く存在しているので、自身が行っている事業や状況に応じた制度を比較して検討し、信頼できる融資機関へ申し込みましょう。
 申込書類の提出
申込書類の提出
申込が決まったら、申込書類の準備と提出をしなければなりません。融資を申し込む際に必要になる一般的な書類は以下の通りです。
- 創業計画書(事業計画書)
- 資金繰り表
- 直近の決算書
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 許認可証(該当する場合)
手続きを行う機関によっては、さらに必要な書類があるので指示に従い、準備しましょう。また、準備した書類に不足があったり、記載している情報に間違いがあったりすると審査が遅れる可能性があるので、必要に応じて専門家に内容に不備がないか確認してもらったり、作成自体の依頼を検討することも視野に入れておきましょう。
 担当者との面談
担当者との面談
申込をした融資機関によっては、担当者と面談する必要があります。担当者面談を通して、「融資に適した事業者なのか」「どのような返済計画を立てているのか」といったことを把握したいので、ごまかしたりせずにはっきり答えましょう。
また、審査を通過するために、担当者との問答が重要になるので、事前に聞かれる質問などを予測して、回答を準備しておくとよいでしょう。
 審査
審査
必要書類の提出や担当者との面談を終えると、申込先での審査が始まります。申込先によりますが、審査は最低でも1週間程度かかります。審査をしている期間に追加で必要な書類や不備のある書類の提出が求められる場合もあるので、迅速に対応できる体制を整えておきましょう。
 融資の開始・返済
融資の開始・返済
審査が通り、融資が決定した場合は、契約手続きを行い、入金する口座や返済口座などを指定して手続きを行います。その手続きが完了した後に、融資金が入金されます。
融資金が入金されると、返済も開始されるので計画通りに返済を行えるようにしましょう。
融資を受けるときに重要なポイント
融資を受けるときに気を付けるべきことや準備しておくべき重要なポイントを説明します。以下のポイントを踏まえたうえで、融資の申し込みを行うようにしましょう。

・事業に関する経験や実績
・自己資金を準備する
・信用情報
創業計画(事業計画)をしっかりとたてる
融資を申込むうえでとても重要なのが、創業計画(事業計画)をしっかりとたてることです。融資制度に申し込むときに、創業計画書や事業計画書の提出を求められることはよくあります。融資を行う側としては、「融資をした後に返済できる能力があるのか」という点を見定める必要があります。
そのため、創業したばかりの企業の場合は、実績などがない状態なので、取引先などとの関係や売り上げの見通し、資金計画などを見て将来性を判断します。事業計画書は、今までの経営状況などから今後の見通しをある程度予測して、どのようにして安定した事業を継続していくのかといった点を数字やデータとして示すことが重要です。
論理的な根拠をもとに、今後の事業計画を作成することが審査を通過するためのポイントです。
事業に関する経験や実績
創業したばかりで会社としての実績がない場合は、個人としての経験が審査のポイントの1つとなります。これまで個人として経験してきた分野と起業した事業の分野が同じであれば、過去の業務経験や人脈が今の会社につながるので、融資を受けられる可能性が高くなります。
会社員として同じ業種に勤めていた経験や個人事業主としての経験などがあることで、経験の長さや今までの実績から評価が高くなり、審査が通りやすくなります。
もし、別の業種であっても管理職の経験がある方や人脈のある方であれば、取引先や顧客の見込みがあるため、創業融資では有利です。それぞれの良いところをアピールすると印象に残りやすく、貸出を行う対象として安心できる判断材料になり得ます。
自己資金を準備する
事業を継続して行うには、資金が必要不可欠なので、自己資金を準備することが大切です。自己資金とは、個人の口座に保有している預貯金や投資などで得た利益、親などから援助された資金を指します。自己資金は返済能力の指標として扱われるケースが多いので、自己資金を準備しておくと審査が通りやすくなるかもしれません。
また、自己資金の目安は融資総額の2~3割程度準備しておくといいといわれています。自己資金がない場合でも融資を受けることはできるので、「自己資金はないけど、融資を受けるにはどうすればいいの…」と悩んでいる方は、こちらの記事をご覧ください!
信用情報
会社で最も重要なのが信用情報です。過去の信用情報に問題があると、融資を受けられないだけでなく、契約なども解除される可能性があります。
信用情報は、過去のクレジットカードの支払い履歴や家賃の支払い、税金や住宅ローンなどが未納または滞納していないかを確かめています。そのため、過去に料金の未納や滞納をしていると審査が通りづらくなります。そのため、個人の支払いであっても、適切な資金管理が行われていないと、お金にだらしないという風に判断されてしまいます。
また、会社として過去に助成金の不正受給などがあった場合も融資が受けられないので、個人・法人のどちらも注意が必要です。
今なら、融資サポートが0円!
今回は個人事業主の方が創業融資を利用する場合の条件と選択肢をご紹介しました。
どの制度を利用するかによって要件や必要な手続きも異なります。早めの段階から検討し、計画的な手続きと自己資金などの準備を進めていくことが大切です。
しかし、自分1人で調べたり準備するには、かなりの時間と手間がかかってしまうのも事実です。創業前や創業直後は特にその他経営の面でも事業をスムーズにスタートするためにやるべきことが多くあります。そんな時は、融資に関する相談は専門家に依頼して、安心して準備を進めてください!
当事務所では、事業計画書の作成をはじめ、創業融資のサポートに関しても幅広く行っており、実績も多くございます!
今後検討される方、少しでもご不安をお持ちの方、まずはお気軽にご相談ください。
ご連絡お待ちしております!