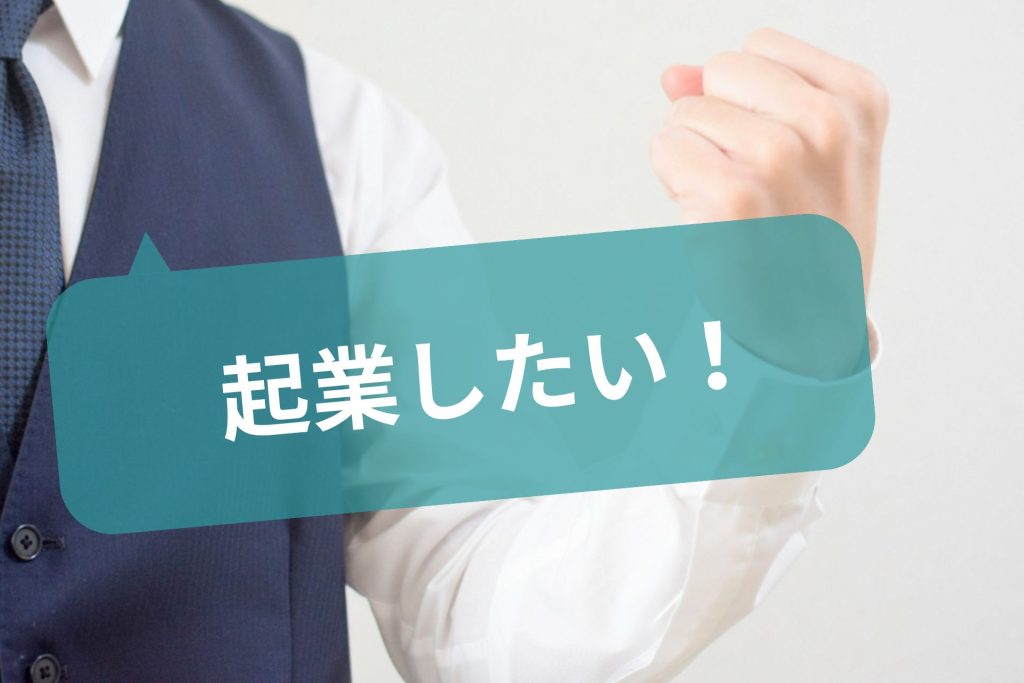
『自分で事業、ビジネスを始めたい!』『開業したい!』と考え、いざ起業するとなったとき、創業時には何かと費用がかかってきます。
そこで多くの人が検討するのが「融資を受ける」ことです。融資の制度には様々あり、自分に合うものを適切に選択し、審査に通らなければなりません。ただ、もし申請する段階で自己資金がない場合、融資は受けられるのでしょうか?
本記事ではこちらの点についてポイントを詳しくご紹介していきます!ぜひ参考にしてください。
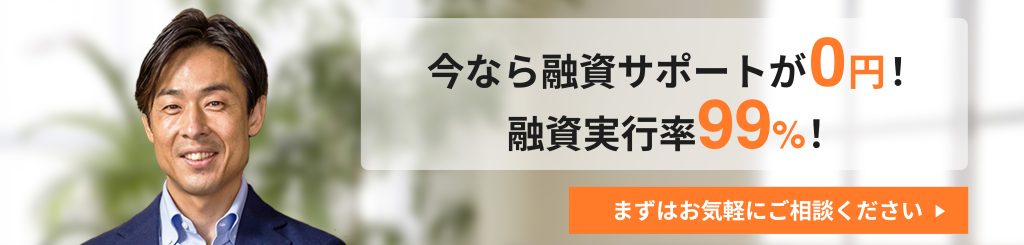
関連記事:【創業融資】起業の際に確認すべきこと
Contents
自己資金と融資の関係性を知ろう
まず、自己資金の有無が融資審査の可否には関係するのかということですが、結論、大いに関係してきます。正直、創業時の融資に積極的な日本政策金融公庫でも、自己資金がない場合融資を受けることが難しいでしょう。
なぜなら、基本的には事業主の計画や自己資金を駆使して行う事業に対して足りない部分を融資するというスタンスで、自己資金の割合でその事業に対する計画性があるかどうかを判断しているからです。自己資金がゼロのケースでは事業に対する計画性もないとみなされかねません。
しかし、実は融資審査で自己資金が免除になる例外もあります。この後詳しくご説明していきますね!
融資を受ける主な4つの先をご紹介
まず初めに、そもそも起業家が借り入れを受ける先としてどのようなものがあり、どのように選択するべきなのでしょうか。融資を行う金融機関の種類は以下の通りとなります。
 日本政策金融公庫(公庫)
日本政策金融公庫(公庫)
政府系金融機関で、簡単に言うと政府が出資し、制作と連動した様々な融資を行う金融機関です。日本政策金融公庫の目的が一般の金融機関が行う金融を補完することであることから、民間の金融機関が積極的には受け入れない創業融資も積極的に行ってくれます。ただ以前にもお伝えしたように融資を受けるには基本的には自己資金が創業資金総額の10分の1以上用意できる方という条件があります。
横浜市では、下記の支店がございます。
関連記事:日本政策金融公庫の創業融資とは?利用時の必要書類を紹介
関連記事:【日本政策金融公庫】創業融資をうける時の手続きの流れを解説
日本政策金融公庫は、これから起業する方や融資の実績がない方に対しても幅広く融資を行う公的機関です。日本政策金融公庫が、起業や新規事業を始めようとしている方を対象とした融資制度を3つ紹介します。
【新規開業資金】
| 利用対象者 | 新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方 | |
| 資金の使い道 | 新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金 | |
| 融資限度額 | 7,200万円(うち運転資金4,800万円) | |
| 返済期間 | 設備資金 | 20年以内(うち据置期間5年以内) |
| 運転資金 | 10年以内(うち据置期間5年以内) | |
| 利率 |
基準利率。ただし、ある下記要件に該当する方は特別利率。 ・女性の方、35歳未満または55歳以上の方 ・外国人起業活動促進事業における特定外国人起業家の方で新たに事業を始める方 ・創業塾や創業セミナーなどを受けて新たに事業を始める方 ・「中小企業の会計に関する基本要領」または「中小企業の会計に関する指針」を適用しているまたは適用する予定の方であって、自ら事業計画書の策定を行い、認定経営革新等支援機関による指導および助言を受けている方 ・地域おこし協力隊の任期を終了した方であって、地域おこし協力隊として活動した地域において新たに事業を始める方 ・Uターン等により地方で新たに事業を始める方 |
|
| 併用できる特例制度 |
経営者保証免除特例制度 創業支援貸付利率特例制度 設備資金貸付利率特例制度 賃上げ貸付利率特例制度 |
|
【新規開業資金(中小企業経営力強化関連)】
| 利用対象者 | 新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方のうち、「中小企業の会計に関する基本要領」または「中小企業の会計に関する指針」を適用しているまたは適用する予定の方であって、自ら事業計画書の策定を行い、中小企業等経営強化法に定める認定経営革新等支援機関による指導および助言を受けている方 | |
| 資金の使い道 | 新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金 | |
| 融資限度額 | 7,200万円(うち運転資金4,800万円) | |
| 返済期間 | 設備資金 | 20年以内(うち据置期間5年以内) |
| 運転資金 | 10年以内(うち据置期間5年以内) | |
| 利率 | 特別利率A | |
| 担保・保証人 | 要相談 | |
| 併用できる特例制度 |
経営者保証免除特例制度 創業支援貸付利率特例制度 設備資金貸付利率特例制度 賃上げ貸付利率特例制度 |
|
参照:日本政策金融公庫「新規開業資金(中小企業経営力強化関連)」
【挑戦支援資本強化特別貸付(資本性ローン)】
| 利用対象者 | 次の1および2を満たす法人または個人企業 | |
| 1 融資制度 |
次の⑴から⑹までのいずれかの融資制度の対象となる方 ⑴新規開業資金 ⑵新事業活動促進資金 ⑶海外展開・事業再編資金 ⑷事業承継・集約・活性化支援資金 ⑸企業再建資金 ⑹ソーシャルビジネス支援資金 |
|
| 2 その他条件 |
次の要件も満たす方 ⑴地域経済活性化にかかる事業を行うこと。 ⑵税務申告を1期以上行っている場合、原則として所得税等を完納していること。 |
|
| 資金の使い道 | 該当する融資制度に定める設備資金および運転資金 | |
| 融資限度額 | 7,200万円(別枠) | |
| 返済期間 | 5年1か月以上20年以内 | |
| 利率 | 融資後1年ごとに直近の実績に応じて、返済期間ごとに2区分の利率が適用される。 | |
| そのほか |
・本制度による債務については、金融機関の資産査定上、自己資本とみなすことができる。 ・本制度による債務については、法的倒産手続きの開始決定が裁判所によってなされた場合、すべての債務に償還順位が劣後します。 |
|
| 融資条件 |
・利用の際には公庫に事業計画書を提出する。 ・関西まで、四半期ごとの経営状況の報告等を含む特約を結ぶ。 |
|
参照:日本政策金融公庫「挑戦支援資本強化特別貸付(資本性ローン)」
新規開業資金と新規開業資金(中小企業経営力強化関連)の制度は、どちらも「認定経営革新等支援機関による指導および助言を受けている方」を対象としているのが特徴です。このような条件を挙げている意図として、自己資金がない方は特に専門的なサポートが必要という点がある。また、あわせて健全で安定的な経営を行うために、専門家を頼ることの重要性を暗に示しているだろう。当事務所も税理士と社労士が在籍しており、専門的なサポートが可能なので、困った際はご相談ください。
 信用金庫、信用組合
信用金庫、信用組合
信用金庫、信用組合の主な取引先は比較的規模の小さい中小企業や個人事業主などです。もともと資金力が弱い会社を対象としています。信用金庫の目的は、利用者や会員同士の互助であり、地域住民の方や事業を営んでいる方に向けて金融サービスを提供しています。
信用組合も同様に特定の地域を対象として金融サービスを提供しています。信用金庫と異なる点は、預金の受け入れを原則組合員を対象としているところです。信用金庫と信用組合のどちらも地域密着型の金融機関となり、創業時や初めて融資を受ける方も利用しやすいというメリットがあります。
横浜市にある信用金庫と信用組合は、以下の通りです。
信用金庫:横浜信用金庫、かながわ信用金庫、城南信用金庫、湘南信用金庫、川崎信用金庫、芝信用金庫、さわやか信用金庫、世田谷信用金庫
信用組合:神奈川県医師信用組合、神奈川県歯科医師信用組合、横浜幸銀信用組合、小田原第一信用組合、相愛信用組合、東浴信用組合、東京証券信用組合、共立信用組合、ハナ信用組合
 地方銀行
地方銀行
地方銀行の主な取引先は中小企業で、リスクなども含め相談に乗ってもらうことができます。信用保証協会の保証がついていることを条件として、自己資金がない場合でも受けられる創業融資があります。自己資金がないという条件があるので、審査もかなり厳しく設定されているため、妥当性と将来性のある事業計画書を綿密に作りこむ必要があります。
横浜市で代表的な地方銀行は横浜銀行が挙げられます。
 都市銀行(メガバンク)
都市銀行(メガバンク)
メガバンクの主な取引先は大企業のため、創業間もない企業や一般の中小企業の融資は難しい現状があります。
関連記事:【税理士が教える!】銀行融資は法人の○○を見ている!
関連記事:なぜ税理士に相談した方がいい?融資のサポートを受けるメリット
上記の点も踏まえ、一般的に融資先としてまず考えやすいのが日本政策金融公庫の融資でしょう。銀行に比べ低金利で、創業時の融資審査のハードルも低めです。創業の資金を借りる場合は「新規開業資金」という制度があります。以前は「新創業融資」という制度がありましたが、令和6年3月31日に取り扱いが終了となり、新しく「新規開業資金」という制度が始まりました。この新規開業資金では、新たに事業を始める方が7,200万円(うち運転資金4,800万円)を限度とした融資を受けることが可能です。もし日本政策金融公庫が難しかった場合は、地方自治体・信用保証協会・金融機関が一体となって提供する制度である「制度融資」を検討してみるのも良いかと思います。融資制度にもいくつか種類がありますので事前に確認しておくことをおすすめします。
融資を受ける際に必要な書類とは
新規開業資金などの融資を受けるにあたって、審査を行うための書類作成が必要になります。具体的にはどのような書類が必要なのか紹介していきます。

・履歴事項全部証明書または登記簿謄本(法人の場合)
・運転免許証またはパスポート
・許認可証(飲食店などの許可や届け出が必要な事業を営んでいる方)
・設備資金の見積書 ※設備資金を申し込む場合
・不動産の登記簿謄本または登記事項証明書(担保を希望の場合)
・生活衛生関係の事業を営む方は、都道府県知事の「推薦書」または生活衛生同業組合の「振興事業に係る資金証明書」
・日本公庫電子契約サービス利用申込書
・送金先口座の預金通帳の写し
上記が必要書類になりますが、該当しない書類に関してはもちろん準備する必要はありません。自分が始めようとしている事業に該当する書類の漏れがないか事前に確認しておきましょう。特に許認可が必要な事業に関しては、許認可が下りるまでに時間がかかるので、各種手続きを行う際には、手順を確認してスムーズに行えるようにしましょう。
また、申し込みを行う場合は、インターネット上で行うことが可能となっており、申し込みフォームに必要事項を入力し、必要書類を添付します。
自分が準備するべき書類などがわからない場合は、当事務所へご連絡いただければ、お話を聞いたうえで判断させていただきます。
審査を通過するためのポイント
融資の申請に必要な書類について解説しましたが、審査を通過するためにはどのような対応が必要になるのかご存知でしょうか?厳しい審査を通過するには、提出書類の完成度や内容の充実度がとても重要です。具体的にはどのような点が必要になるのか解説していきます。
創業計画書の妥当性や明確性
融資を申請する際に「創業計画書」の提出が必要になる旨は先述した通りです。審査を通過するためには、その創業計画書の妥当性や明確性が重要です。創業計画書とは、事業を始める際に事業目的や事業内容などを説明する書類を指します。創業計画書は事業計画書を含むことが多く、創業の動機や必要な資金と調達方法、事業の見通しなどを記載する必要があります。
創業計画書で大切なのは、資金計画や収益計画、市場の分析を行い、事業内容や事業目的を実現することができるのかという妥当性です。あまりにも無理な計画を立てると計画性などがないと判断されてしまいます。
そのため、自分の事業を実現するために具体的かつ明確に説得力のある書類を作成することが重要になります。自分自身の目線から読むだけでなく、第三者にも読んでもらい、説得力のある書類になっているのか確認してもらうようにしましょう。
会社の財務状況を説明できる
事業の将来性を把握するとともに、会社の財務状況について説明できることがとても重要です。これまでの確定申告や決算書について自分の言葉で説明できるようにしておきましょう。もちろん持続的に安定的な売上があることは会社として理想ではありますが、世間の経営状況などによって市場の状況も異なるため、現実的に難しいです。
現実的に難しい点も含めて、将来的な財務リスクや課題を洗い出すことが会社を経営する上でとても大切なことです。また、現在の収益や借入の状況を明らかにして、借入に至った経緯などを把握しておきましょう。過去の経緯なども踏まえて、今後の事業計画をどのようにしていくかを伝えることで、将来の返済能力をアピールしましょう。
自己資金はどのくらい必要なのか?
では具体的にはどのくらいの額が必要になるのかお伝えしていきます。日本政策金融公庫から融資を受ける場合、必要となる自己資金は創業資金の総額によるため、申し込み者ごとに異なります。基本としては、創業時に必要な資金総額から自己資金を差し引いた額を融資で借りるという形になります。
具体的な金額としては、創業資金総額の3割を目標に貯めましょう。
例えば1,500万円の創業資金総額を予定している場合は、その3割の450万円が貯めるべき自己資金額ということになりますね。
ただし、融資を実際に受けることのできる金額は自己資金額だけで判断されるのではなく、事業計画書の内容や面談など総合的に判断されるためあくまで目安と考えておきましょう。
開業資金を融資制度以外で準備できる方法
融資制度を利用せずに開業資金を準備するにはどうすればよいのでしょうか。自己資金なしでも開業するためにその方法を紹介します。
助成金・補助金制度
国や地方自治体が交付している補助金や助成金制度を活用しましょう。補助金と助成金は返済義務がないものなので、自己資金がなくても問題ありません。補助金と助成金にはどのような違いがあるのかという点は覚えておいたほうが良いかもしれません。違いについては以下の表のとおりです。
| 補助金 | 助成金 | |
| 交付する機関 | 主に経済産業省、地方自治体 | 主に厚生労働省、地方自治体 |
| 交付する目的 | 産業の育成や施策を推し進めること | 雇用や労働環境の改善 |
| 受給条件 | 受給条件を満たしたうえで審査に追加する必要がある | 条件を満たしていれば支給される可能性が高い |
| 交付される金額 | 金額が大きい(数百万~数億円まで) | 金額が小さい(数十万円程度) |
| 対象範囲 | 幅広い事業を対象とするものが多い | 雇用関係を対象とするものが多い |
| 受給しやすさ | 予算が設定されている場合が多く、受給できない可能性がある | 基準を満たせば受給できる可能性が高い |
| 申請期間 | 1か月など短い傾向にある | 随時または長期の傾向にある |
| 専門家 | 主にコンサルティング会社や中小企業診断士、税理士など | 主に社会保険労務士や情勢書士など |
補助金や助成金を申請する場合は、審査が行われるため、書類の準備が必要になります。また、財源に限りがあるため、金額なども定められています。そのため、会社が行う事業についてどのような計画を立てているのかがわかる事業計画書などを提出する場合があり、厳しく審査されます。
事業を行うにあたって、数年後などを見据えた事業計画書を作成するのも良いかもしれません。
クラウドファンディング
クラウドファンディングとは、インターネット上で不特定多数の人から資金を集める方法です。近年、新しい資金調達の方法として活用する企業や事業者が増加しています。
会社の事業目的や事業内容などをクラウドファンディングサイトに掲載することで、その内容に共感・賛同した人が気軽に支援できる仕組みとなっており、比較的簡単に資金調達を始めることができます。
ただし、出資するメリットを提示できていなければ、まとまった金額を集めることは困難になります。クラウドファンディングは、不特定多数の出資を求めることができますが、目標額に対して、確実に達成することができるという確約はできません。そのため、綿密な計画を立てたうえで準備を行い、該当サイトへ掲載したほうが効果的です。
家族や親族から借りる
家族や親族から借りた場合は、借入金として自己資金にはなりません。あくまで一つの手段として利用しましょう。
[その他]開業資金がかからない事業を選択する
動画編集やプログラマー、翻訳などパソコンさえあればできる事業を選択するのも自己資金がなくても開業できる方法の一つです。もし、開業資金がかからない事業で開業を検討している場合は、まず個人事業主として開業して、ある程度まとまった資金ができたら法人として会社を設立するという流れのほうが適切でしょう。
自己資金なしで起業する際の注意点
自己資金なしで開業を検討している方は、自己資金なしで開業する際の注意点があるのでしっかり覚えておきましょう。
融資の審査が通りづらい
お金を借りるということは必ず返済しなければなりません。金融機関からの融資を行う際に、返済能力や信用力などを審査するために、保有資産や実績などさまざまな視点から判断します。そのため、自己資金がないと返済能力がないと判断されてしまい、審査が通りづらくなるので、注意が必要です。
融資額は希望通りになる可能性が低い
融資の審査が通ったとしても融資額は自己資金額によって変動するため、最初に希望した融資額ではなく、少ない金額での融資になる可能性がとても高いです。融資は返済することが前提となっているため、自己資金がないと返済能力が低いと判断される可能性が高く、融資金額も低くなってしまいます。
融資額は減額することはできますが、増額することは原則できないため、提示された金額が上限という認識でいたほうが良いでしょう。
金利が高くなる
金利は、融資額や返済期間などさまざまな観点から設定されるされるため、金利が高くなる可能性があります。自己資金がないということから、融資額や返済期間を算出するため、金利は最大値で設定されることもあらかじめ覚悟しておきましょう。
自己資金が免除になる例外も!
創業融資には自己資金は不可欠とされていますが、前述した日本政策金融公庫の新創業融資の自己資金要件には例外があり、自己資金がなくても融資を受けられる可能性があります。
その例外とは「現在勤めている企業と同じ業種の事業を始める人」「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める人」です。
前者はこれから挑戦する事業で実績があるかどうかです。
後者が分かりづらいかと思いますが、ここでの「特定創業支援事業」とは国が新規創業を支援するために始めた事業です。国が認定した地方自体が起業する人を支援するもので、詳細は自治体ごとに異なりますが、自治体が経営や財務、人材育成に関するセミナーや個別相談などを実施し、それを受けた人は申請すると証明書をもらえます。そしてこの証明書があれば、自己資金がなくとも日本政策金融公庫の新創業融資に申し込む資格があるということになります。興味がある方は是非詳しく調べてみてくださいね!
ただこの特例があるから、はなから自己資金はなくても良いというわけではありませんので、このような要件もあるということを知識として持ちながら、用意できる分はしっかりと貯めておきましょう!
自己資金にできるものできないもの
自分では自己資金と認識しているものでなくても、自己資金に該当する可能性があるので、自己資金にできるものとできないものの違いを解説します。
 自己資金と認められるもの
自己資金と認められるもの
自己資金とはそもそも自分で貯めたお金だとイメージする人も多いかと思いますが、融資申請する際の自己資金とは「預貯金通帳で確認することのできる、出所の確かな現金」です。
自己資金と認められるもので一番一般的なものが現金預金(貯金)です。ただ、手元に貯金がない場合でもその他認められる傾向にあるものがあります。具体的には資本金、退職金、相続金、生命保険の解約金、不動産などの資産を売却した資金、みなし自己資金、第三者割当増資、資産を売却した資金などです。
みなし自己資金:すでに事業を始めていて設備などに資金を投じている場合の金額のことです。
第三者割当増資:すでに株式会社を運営している場合の方法で、新しく会社の株式を発行しその発行した株式を第三者に引き受けてもらうことでの資金調達のことです。注意点としては生命保険や学資保険などの解約返戻金や投資信託や不動産など資産を売却したお金ですが、これらはすぐに使えない可能性もあるため、事前にしっかりと確認しておきましょう。
 認められない可能性のあるもの
認められない可能性のあるもの
反対に自己資金とは認められない傾向にあるものは「出所のわからないお金」です。具体例として挙げると、返済義務のあるお金などです。見てわかる通り、出所が不明のお金やカードローンなどの返済義務のあるお金は認められない可能性が高いです。親からの資金援助は原則として借り入れ扱いになるため、その場合は口座振込にしておきましょう。そのようにすると親から自己資金を援助してもらったことを証明でき出所不明金とはならないためです。
自己資金なしで創業融資を受ける場合の注意点
自己資金なしで創業融資を受ける場合は、自己資金がある場合と比較して異なる注意点があります。前項で記述した「融資額が希望額通りになる可能性は少ない」「金利が高い」という点も同様ですが、その他にも注意する点があるので、把握した上で対策しましょう。
一時的な見せ金は違法になる可能性がある
見せ金とは、相当する資金があるかのように見せかけるお金のことです。融資を受けるために一時的にお金を借りて、自己資金があるかのように金融機関に提示を行い、審査が終了した後にお金を返済する行為を指します。
日本政策金融公庫は、6か月程度の入出金が記帳されている通帳の原本の提示を求めることがあるため、急に大金の入出金があると不審に思われます。多額の資金移動を短い期間の中で行われていると、そのお金の出どころや入金された経緯を追及される可能性があります。日本政策金融公庫は、これまでに多くの融資を行ってきており、さまざまな顧客の審査を行っているため、帳簿や決算書との整合性が取れず、結局はばれてしまいます。自分では問題ないと考えていても、不審な資金移動と感じる人のほうが多いでしょう。
さらに見せ金は、法律に違反する可能性が高く、刑事告訴される可能性があるため、見せ金は行わないようにしましょう。
関連記事:【会社設立】資本金の見せ金はやっていいの?徹底解説‼︎
返済計画を立てないと返済できなくなる
自己資金なしで、創業融資を受ける場合は、開業後の運転資金などを借入金からまかなうようになるため、事業を開始した後の売り上げからすべて返済を行わなければなりません。返済する計画を立てておかないと、会社を経営するにも支障が出てしまう可能性があります。さらに返済するのは借入金だけでなく、利息も併せて返済していく必要があります。
自己資金がないと金利が高くなる傾向にあるため、利息も高くなるでしょう。返済金額だけでなく、月々支払う家賃や税金などの費用も考慮して、毎月の支出を計算する必要があります。当然ながら月によって売上が変動する可能性も含めて返済計画を立てることが重要です。早く返済をしようという思いから、無理な返済計画を立ててしまうと会社全体に悪影響を及ぼす可能性があるため、私たち専門家と相談したうえで適切な返済計画を立てましょう。
【まとめ】自己資金がない方でも方法はある
今回は自己資金と創業融資の関係についてお伝えしてきました。起業にあたっての資金調達として、創業融資を検討している場合、融資金額を左右することになる自己資金の準備はみなさん大きなハードルとなることでしょう。「どのくらいの額を目標とすべきなのか」まずは創業資金がどのくらい必要なのかを確認し、おおよその目標額を決めて計画的に準備しましょう。
とはいっても、起業したいけど手元に貯金がないという人もいるかと思います。当事務所では創業融資についてもしっかりとサポートさせていただいております。説明したように自己資金となるものは、個人の貯金だけではありません。
「自分の場合はどうなのだろう?」
「日本政策金融公庫の融資制度は受けられるのだろうか?」
「事業計画書などの提出する資料を確認してほしい」
融資で失敗しないか不安に思う方、そもそも何から始めればよいのか分からないといった方でもまず一度お気軽にご相談ください!
実際の融資事例:【新規開業支援】ビーガンスコーン専門店“iro” 横浜市西区伊勢町にオープン!
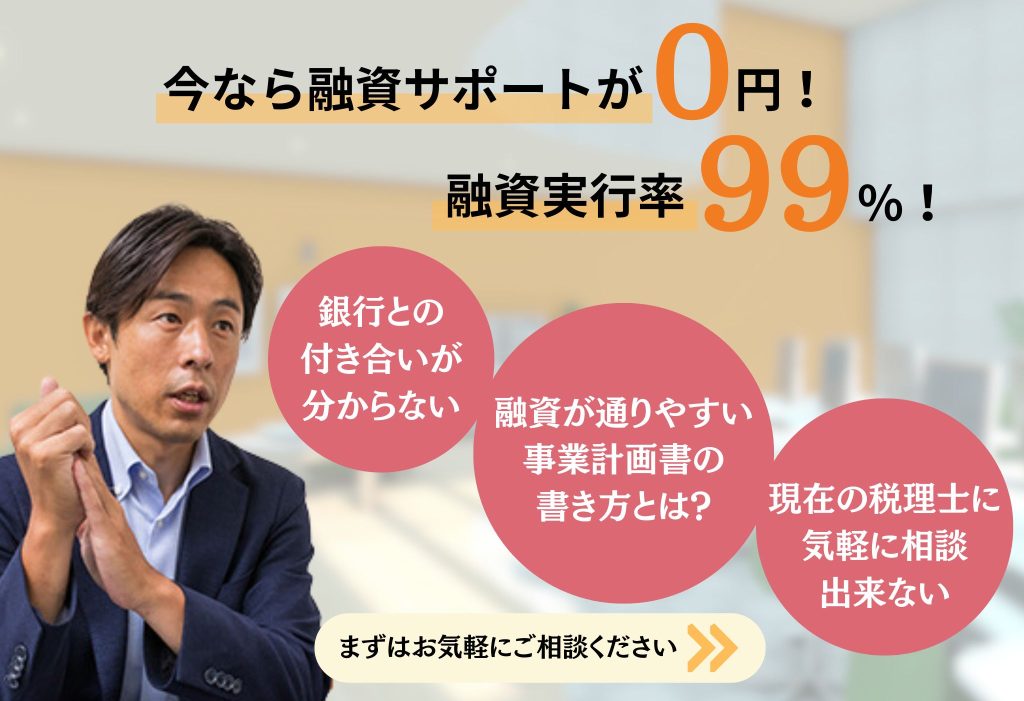
関連記事:個人事業主でも創業融資を受けられる?
関連記事:飲食店開業の費用はいくら?流れと資金調達方法について‼︎



