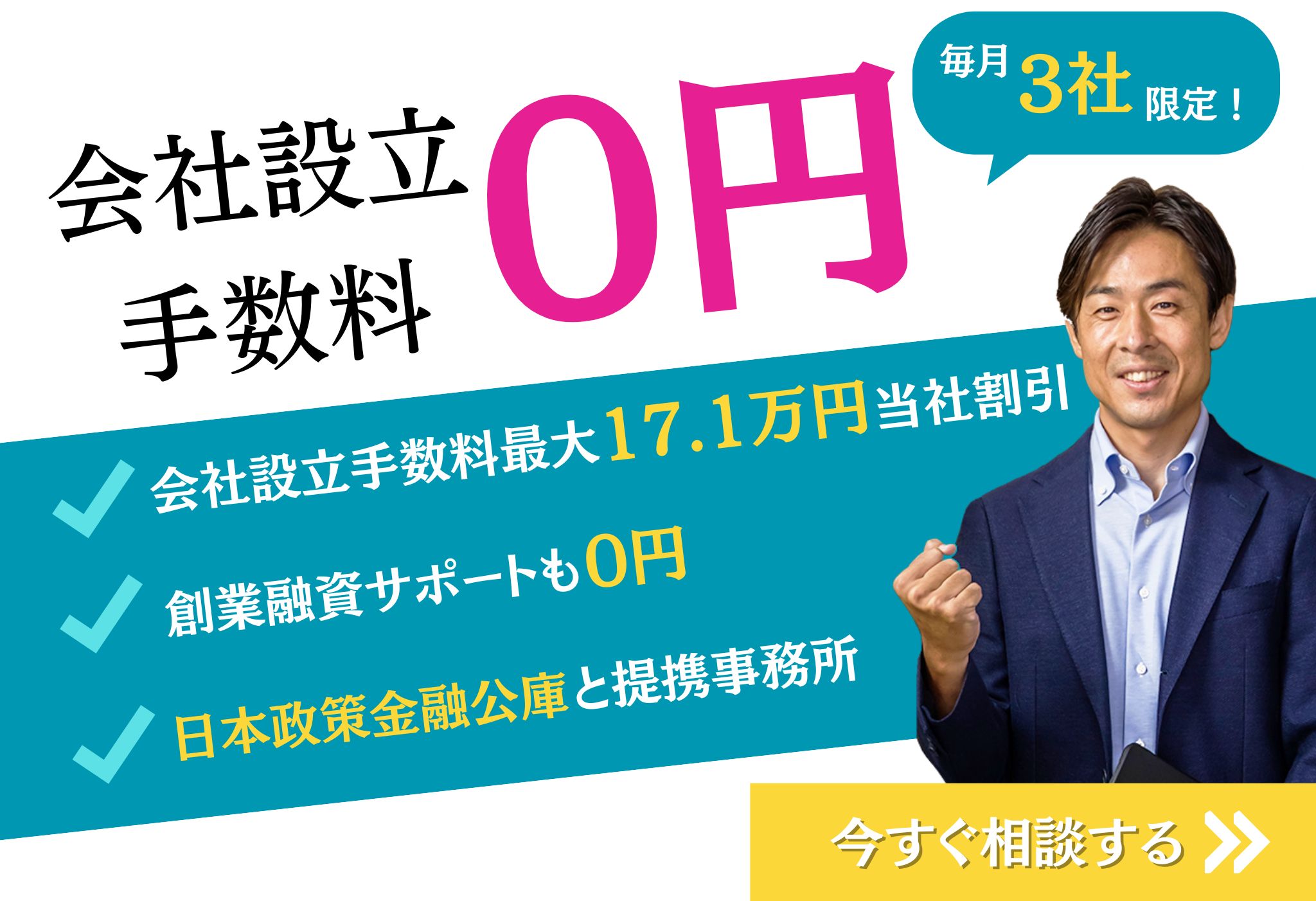トラック運送業を始めたいと検討している方は、事前に運送業の要件について確認しておく必要があります。この要件を抑えていないと、会社の運営や運送業の許可が不可能になるので、注意しましょう。
ただ、検討している方の中には、
「専門用語だらけでわかりづらい・・・」
「法律を見ると難しく書かれているから理解が難しい」
と感じる方も少なくないでしょう。
本記事では、専門用語などを使わずに、運送業を運営するための要件や手続きについて分かりやすく解説します。これから手続きを開始する方には必見の情報も記載しているので、是非最後までご覧ください。
関連記事:【横浜で会社設立】流れや方法とは?メリットや必要書類について

Contents
貨物自動車運送事業の種類
運送業を始める場合は、運送業許可が必要になります。運送業許可が必要になるのは、大きく分けて以下の3種類があります。
| 一般貨物自動車運送事業 |
荷物をトラックや自動車などを使用して有償で運送する事業(緑ナンバー) |
| 特定貨物自動車運送事業 |
特定の荷主の荷物のみを有償で運送する事業 |
| 貨物軽自動車運送事業 |
軽自動車やバイクなどを使用して有償で荷物を運送する事業(黒ナンバー) |
私たちの生活でよく利用されているのが、一般貨物自動車運送事業です。この一般貨物自動車運送事業はほかの2つと比較して、満たすべき要件が多く、手続きが完了するまでに多くの時間を要します。そのため、本記事では「一般貨物自動車運送事業」に焦点を当てて、運送業許可や手続きについて解説します。
運送業許可とは何か?
運送業許可というのは、一般貨物自動車運送事業を行うのに必要な許可で、有償で継続的な運送を行う場合に取得する必要があります。
したがって、社外の人から依頼を受け、有償で定期的に荷物を運送したいという要望に応える場合は、運送業許可を得なければ事業を行うことはできません。自家用車による運送や無償で行う運送については、許可は不要になります。
運送業許可の4つの要件
運送業許可(一般貨物自動車運送事業)の取得には、大きく分けて4つの要件を満たさなければなりません。
その4つの要件とは「資金」「人」「施設」「車庫」です。この要件の中で1つでも欠けてしまうと、運送業許可を取得できないので、事前に準備をすることが大切です。
具体的には、どのような準備をするべきかひとつひとつ確認しましょう。
①資金
運送業を始めるには、一定の資金が必要です。会社を設立するための費用はもちろんのこと、人件費や車両購入費、燃料費、修繕費、油脂費、備品費等の費用を6か月分から12か月分を調達しなければなりません。このほかにも建物費や土地費、保険料、税金などもあるため、これらを合算した金額以上の資金を確保していないと要件がクリアできません。
自己資金の目安は1,500万円〜2,500万円です。金額に開きがあるのは、事業者によって車両購入費や建物費、駐車場の賃料などが異なるためです。
また、運送業許可を取得するためには、開業以降の6か月の間に必要とされている資金が常時確保されていることも条件となります。そのため、会社設立時に必要な資金と運営に必要な資金を分けて準備しておく必要があります。会社を設立する前には、資金調達の方法などを確認しておいたほうが良いでしょう。
②人
人に関する要件とは、運送業に携わる申請者や人員や資格について定められているものです。具体的な要件は以下の通りです。

・役員法令試験へ合格していること
・最低限の人員を確保していること
・有資格者が配置されていること
それぞれの要件について分かりやすく説明します。
欠格事由に該当していないこと
欠格事由とは、運送業許可を取得する際に不適格と判断される事由を指しており、具体的には以下のような事由が挙げられます。
・一般/特定貨物自動車運送事業の許可取り消しを受け、その取り消しを受けた日から5年経過していない
・申請者と密接な関係者(親会社・子会社等)が一般/特定貨物自動車運送事業の許可取り消しから5年経過していない
・一般/特定貨物自動車運送事業の許可取り消しの処分をする日または処分をしないと決定した日までに自主廃業した場合、その届出した日から5年経過していない
・営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者または成年後見人である場合、その法定代理人が上記に該当する
役員法令試験へ合格していること
運送業許可を取得するには、役員法令試験へ合格することが必須とされています。役員法令試験とは、事故の発生を予防して運送の安全性を確保するために、適切な事業運営を行うための法令知識が備わっているかの確認を目的とした試験です。
法人の場合は、役員のうち1人が受験する必要がありますが、個人事業主は事業主本人が受験します。試験を受けるタイミングですが、許可申請を行った後に試験実施の通知が届き、通知に従って試験を受けることになります。そのため、事前に受かってから会社を設立するわけではないので流れを間違えないようにしましょう。
試験自体は、1回目が不合格だとしても2回目を受けることが可能です。ただ、2回目も不合格となった場合は、許可申請が却下処分となり、改めて申請をするとなると2か月後ろ倒しになってしまいます。1回目と2回目の受験者は違う人でも構わないため、もし1回目を受けて合格が難しいと感じた場合は、ほかの人にバトンタッチすることも視野に入れてみてください。
最低限の人員を確保していること
運送業は許可を取得するために、5台の車両が必要になり、最低でも5名のドライバーが必要です。また、ドライバーと合わせて資格保有者も営業所ごとに必要になるため、営業所には最低でも6名の従業員が確保されていなければなりません。
有資格者が配置されていること
前述したように、営業所には「運行管理者」と「整備管理者」の資格を有した従業員の配置が必須です。「運行管理者」とは運転者の指導監督や点呼、安全運行の指示を行うなどの役割を担うスペシャリストです。
運行管理者の業務は営業所が保有する車両によって変動するため、車両台数あたりの運行管理者数が以下の一覧のように定められています。
| 保有車両数 | 運行管理者数 |
| ~29両 | 1名以上 |
| 30~59両 | 2名以上 |
| 60~89両 | 3名以上 |
また、整備管理者は「自動車整備士技能検定の1級/2級/3級のいずれかに合格している者」、「2年以上の実務経験を有し、かつ地方運輸局長が行う研修を修了した者」に該当していなければなりません。
③施設
施設というのは、営業所や休憩施設などを指しており、運送事業を円滑に運営するためには必須の要件になっています。許可を得るためには、以下の項目を満たさなければなりません。

・休憩室や睡眠施設があること
この2つについてどのような施設であれば問題ないのか解説します。
営業所があること
営業所は、都市計画法や建築基準法、農地法に抵触しないような建物であることが定められています。そのほかにも、建物や土地の使用権原を有しているか証明できることや営業所としてPC・事務机・キャビネットなどがおける程度の現実的な広さがあることが挙げられます。
一方で、都市計画法で言われている
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域(一定の条件を満たす)
- 第一種住居地域(一定の条件を満たす)
には原則、営業所を設置することができません。
また、建築基準法に違反している建物は営業所として認められないので、建物自体が違反でないか等を確認する必要があります。
休憩室や睡眠施設があること
許可を取るためには、休憩室や睡眠施設の設置が必要です。建物としての条件は営業所と同様ですが、営業所または車庫(駐車場)に併設することが定められています。
スペースなどの問題で、営業所に併設できず、車庫に休憩室を設置する場合は、営業所から直線距離で10㎞以内に納めなければなりません。これは地域によって異なるので、専門家に確認してみましょう。
休憩室は広さなどの定義がなく、テーブルやいす、ソファーなどが設置されていれば良いですが、睡眠施設の場合は、1人当たり2.5㎡の広さを確保する必要があります。休憩室や睡眠施設は運転者の休息に必要不可欠なものなので、パーテーションなどで区切るなどの工夫をしましょう。
④車庫(駐車場)
運送業として、当然ながら車庫が必要になります。前述したように、原則車庫は営業所に併設しなければなりませんが、土地などの都合上により不可能なケースがあります。そういった場合は、直線距離で10㎞以内の位置に設置します。
車庫の条件は営業所と同様ですが、その条件に加えて交通安全上の条件もあります。

・車庫の出入口が道路の曲がり角や横断歩道から5m以内にない
・車庫の出入口が交差点の角にない
・保有している車両がすべて収容できる
保有する車両の種類や台数によって異なりますが、大型トラックなどを収容する場合は車庫(駐車場)の規模などを慎重に検討したうえで判断しなければなりません。
運送業許可の申請は計画的に!
本記事では、運送業許可を取得するための要件について解説しましたが、ご理解いただけたでしょうか?
「貨物を運ぶだけだから簡単な事業なのでは?」と考えてしまう方も中にはいます。ただ、ご覧いただいたように、人の要件や施設の要件などを満たしていなければ、運送業許可を取得することはできません。要件の内容も建築や道路交通に関するさまざまな法律が絡んでくるため、初めての個人だけでは、全容を把握することがなかなか難しいです。
そのため、運送業許可を申請する際は専門家へ1度相談されてから手続きを進めたほうがよろしいでしょう。なかなか時間が取れない方や手続きのすべてを依頼したい場合は、当事務所へお気軽にご相談ください!