
個人の方が起業をして会社設立をしようと考えたとき、会社設立には「資本金」が必要となります。
なんとなくある程度は必要そうなイメージはあるけれど、具体的にどのくらい必要になってくるのだろう、、、
そうお悩みの方も多いのではないでしょうか?
本記事では、会社設立時に必要な資本金について、平均額や金額の決め方のポイントとなる点を詳しくお話していきます!
関連記事:【費用を抑えたい方必見】横浜で会社設立なら税理士事務所へ!

Contents
そもそも、資本金ってなんだっけ?
まず、そもそもの話なのですが、資本金とはどのようなものなのでしょうか。簡潔にいうと資本金とは『そのビジネスを行うための元手』です。法人を設立するにあたっての運転資金や、株主や投資家から調達した資金等も資本金に分類されます。ただ、株式上場を目指すケースのようなかなり有望な事業や有名なスタートアップでない限り、創業時にいきなり出資を受けるのは難しいため、創業者が無理のない範囲で自己資金を投じる場合がほとんどです。
かつては会社の設立について株式会社なら1,000万円以上、有限会社なら300万円以上の資本金が必要という決まりがありましたが、2006年の法改正によって最低資本金制度がなくなり、新会社法の施工後は資本金1円から会社を設立することができるようになりました。
資本金から分かることとは?
ビジネスの元手となる資本金ですが、実は、法務局へ行って登記事項証明書を発行してもらうことで、社外の人でも知ることができます。資本金から得られる情報はどのようなものがあるのか理解したうえで、資本金額を設定しましょう。
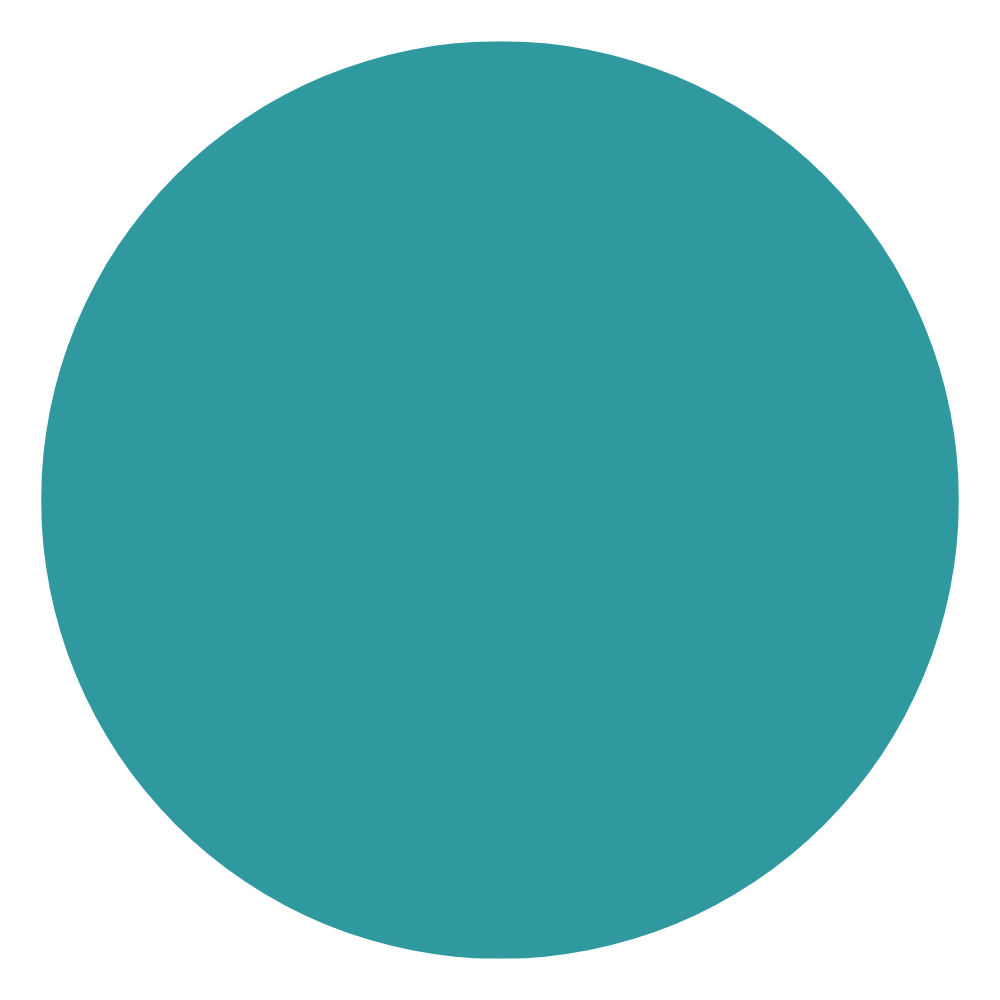 会社の規模や対外的な信用度をを表す
会社の規模や対外的な信用度をを表す
他社と取引を行うときや銀行からの融資を受ける際に、会社の規模や信用度を表す目安としてみられるのが資本金額です。もちろん、資本金額だけで会社を評価することはできませんが、資本金額と会社の規模に比例する傾向にあります。そのため、資本金額が大きければ安定した経営を行っている企業だと取引先や銀行、顧客からの信用を得られやすくなります。
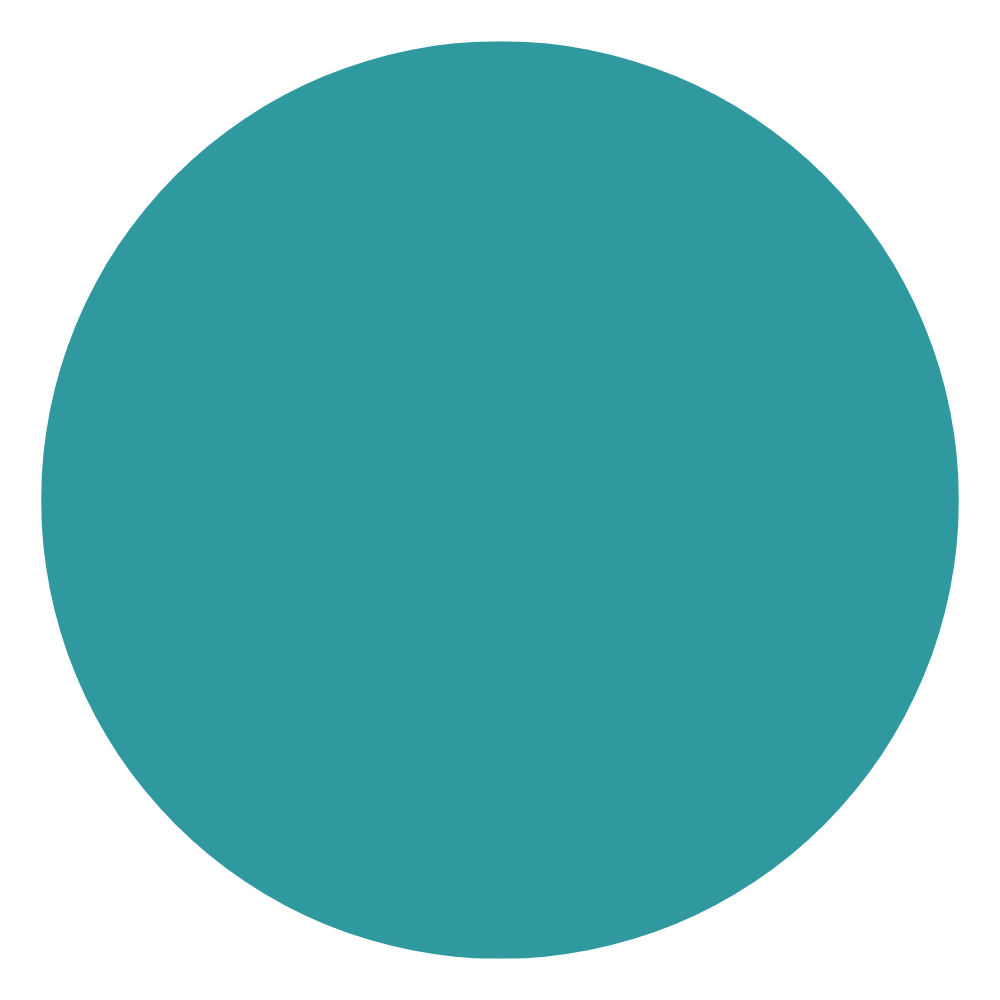 許認可を受ける基準になる
許認可を受ける基準になる
事業内容によっては、所轄官庁などから許認可を受ける必要があります。許認可を受けるためには、事業内容に応じて一定の資本金額が定められているので注意が必要です。
例えば、貨物利用運送事業の場合は300万円以上、一般建設業の場合は500万円以上、一般労働者派遣事業の場合は2,000万円以上×事業所数など、一部の業種では必要な資本金額が定められています。資本金額が一定の金額に達していない場合は、会社設立自体を行うことは可能ですが、該当している事業を始めることはできません。
許認可申請が必要になるタイミングで増資を行うこともできますが、事前に事業について許認可が必要かどうか確認するようにしましょう。
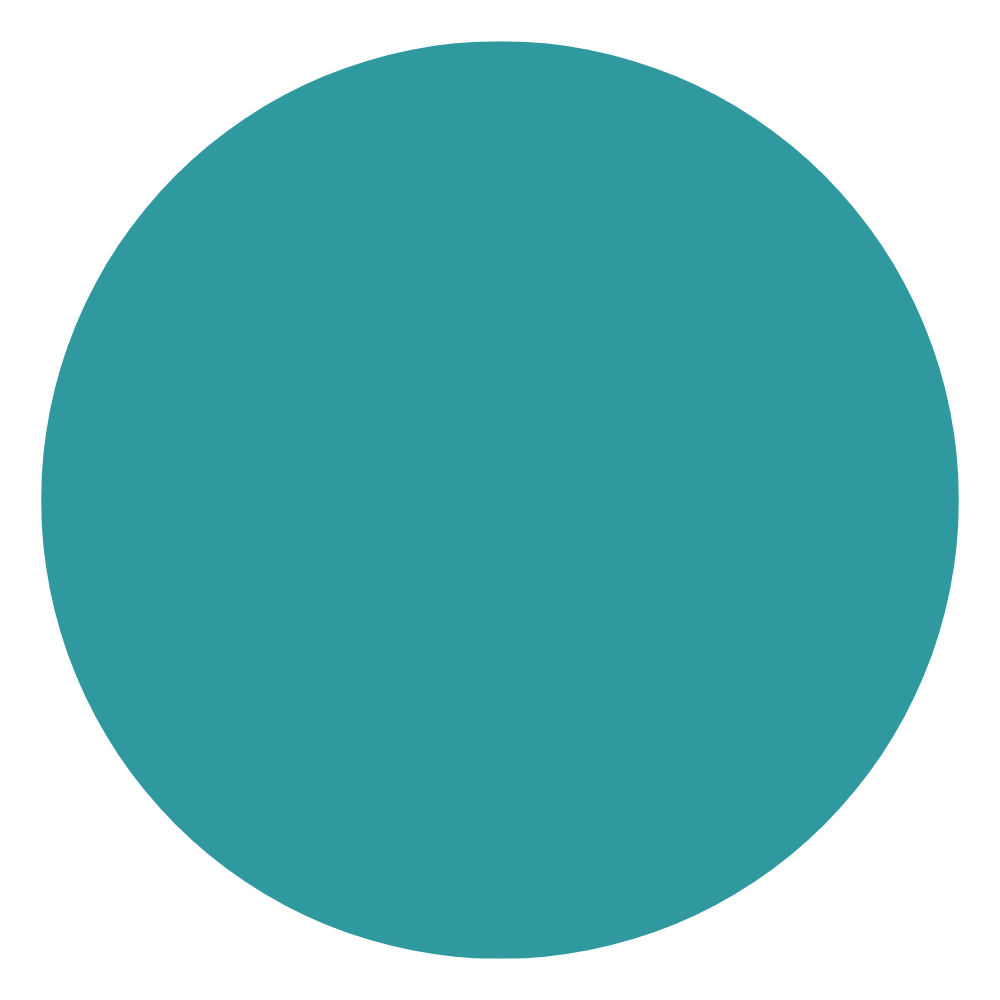 税金に影響を与える
税金に影響を与える
ある程度の金額が必要ということがわかりましたが、「資本金額が大きければ大きいほどいいんでしょう?」というイメージを持つのはやめておいたほうがいいかもしれません。
資本金額が大きいと会社の規模や対外的な信用を表すことができる一方で、納める税金額が多くなってしまう可能性があります。資本金額と関連のある税金について解説していきます。
消費税
消費税に関しては、資本金額が1,000万円以下に設定した場合は原則会社設立後の2期目までは納税義務が免除されます。1,000万円以上に設定すると設立した初年度から課税事業者に該当することになります。
ただし、インボイス制度の開始に伴い適格請求書発行事業者登録を行った場合は、課税事業者となるため納税義務は免除されません。そのため、会社設立後の売上見込みが1,000万円以下で消費税の負担を軽減したい方は、資本金を1,000未満に設定したほうがいいでしょう。
法人税
法人税は会社の利益だけでなく、資本金によっても税率が変動します。資本金額の基準は国税庁が定めており、資本金の基準額が1億円と大きいため、会社設立当初は課税所得部分の800万円のラインを気にしておけば良いでしょう。
| 資本金1億円以下の普通法人 | 年800万円以下の部分 | 15% |
| 年800万円超の部分 | 23.2% | |
| 上記以外の普通法人 | 課税所得額によらず一律 | 23.2% |
基本的には、節税目的で資本金額を1億円以下に設定することが多いです。事業内容によっても金額を設定する必要があるため、税理士に相談しながら決めることをおすすめします。
住民税
法人住民税は、均等割と法人税割がありますが、均等割は赤字だったとしても必ず支払わなければいけません。資本金額によって課税額が変動しますが、資本金額が1,000万円以下の場合は、最低納税金額の7万円で済みます。
よって、境となっている資本金額1,000万円と合わせて、地方住民税について検討したほうがいいでしょう。
登録免許税
登録免許税は会社設立の際に必要な費用となり、資本金額によって納税金額が変わってくるため、資本金額を設定する際に十分な検討が必要です。また、会社の形態によっても金額が変動するので、以下の表を参考にしてください。

[合同会社]60,000円 または 資本金額×0.7%上記どちらか高い金額を納税
資本金の平均額はいくらなの?
先述の通り、資本金は1円からでも会社を設立できるようにはなりましたが、資本金は事業開始後利益が出るまでの運転資金となるため、あまりに少ないと事業に支障をきたす恐れがあります。そのため、一般的には営業開始から3カ月利益が出なくても事業を問題なく継続できる額が目安とされていて、その平均額は300万円となっています。
ただ、こちらはあくまで平均なので、自分の事業内容などによってもさまざまです。資本金は返済の義務がない自己資金となり、いわば会社の規模や体力といっても過言ではありません。また金融機関からの融資を受ける際や、新しい取引先と取引を始める際なども資本金の金額は大きく影響してきます。しっかりと今後も見据えた上で資本金の額を決定し、準備を進めておきましょう。
| 資本金額 | 企業数 |
| 300万円未満 | 200,501 |
| 300~500万円未満 | 578,882 |
| 500~1,000万円未満 | 253,148 |
| 1,000~3,000万円未満 | 555,646 |
| 3,000~5,000万円未満 | 72,933 |
| 5000万~1億円未満 | 52,126 |
| 1~3億円未満 | 17,674 |
| 3~10億円未満 | 7,337 |
| 10~50億円未満 | 3,600 |
| 50億円以上 | 2,319 |
参照:総務省・経済産業省 経済センサス‐活動調査 令和3年経済センサス‐活動調査 速報集計 企業等に関する集計
上記の表では、300~500万円未満の資本金額で設定している企業が1番多いようです。その次は1,000~3,000万円未満です。上記を参考にしつつ、事業内容や事業計画をみながら当事務所の税理士と相談しながら決めていきましょう。
資本金額の額を決める5つのポイント
では続いて、資本金の額はどのように決めるべきなのでしょうか。やみくもに額を決めたところで後から足りないということになってしまうと本末転倒です。決める際にポイントとなる点をご紹介していきたいと思います。
 会社設立時や運転資金に必要な金額はいくらなのか
会社設立時や運転資金に必要な金額はいくらなのか
事業の業種などによってはそもそも開業するまでにかなりの金額がかかることもあります。また会社設立となると、登記するための費用のほかに事業を継続するための運転資金もかかってきます。
会社設立時の出費ではざっと以下が考えられます。
オフィスや店舗の賃貸費用、電話やインターネットなどの通信費、店舗や事務所においておくための備品、パソコンなどのOA機器、ホームページやパンフレットなどの広告費です。
運転資金としてかかる出費は、従業員を雇用するための人件費や賃料、水道光熱費、材料や商品の仕入れに関する費用などが考えられます。
業界や本社、支店の立地によっても異なりますが、初期費用や多くの経費が必要になる会社は資本金が高い傾向にあります。事前に会社設立などに必要な資金を計算したり、シミュレーションで把握しておくと、おおよそいくらくらいかかるのかを考慮して資本金を用意できるのではないでしょうか。
 許認可に必要な資本金ラインはいくらか
許認可に必要な資本金ラインはいくらか
業種によっては許認可を得ないと営業をスタートできない場合があります。この許認可によっては資本金が一つの審査基準となっているケースもあります。例えば旅行業は3,000万円以上、建設業は500万円以上が基準となっています。
業種によって条件や違いがある点に注意しましょう。
 融資希望額はいくらなのか
融資希望額はいくらなのか
金融機関から融資を受けたい場合、資本金が少なすぎると融資を断られてしまう可能性もあります。資本金は融資を受ける際の融資額の基準にもなりますのでしっかりと準備しておきましょう。注意点としては、融資を受けて借りたお金は資本金にすることはできませんので間違えないようにしてくださいね。
 取引先の企業の資本金はいくらなのか
取引先の企業の資本金はいくらなのか
多くの企業は新しく取引を始める場合、その企業の信用度をチェックするものです。その信用度に大きく関わってくるのが資本金です。特に創業して間もない企業の場合は、「発注してもきちんと納品はしてくれるのだろうか」「納品したらきちんとお金は払ってくれるのだろうか」などと不安に思われがちです。そう思われないためにも、事前に取引をしたい企業の資本金を調べて、大体の相場感をつかんでおくことが重要です。
 税金面では資本金1,000万円未満に設定しておくとお得
税金面では資本金1,000万円未満に設定しておくとお得
今までは資本金の額は会社の体力(信用)ともいえるので少なすぎてはいけないとお伝えしてきましたが、税金の観点からいうと、多ければ多いだけよいという訳でもありません。
一般的に、税金納付の観点から考えると資本金は1,000万円未満に設定しておくとお得になります。理由としては、法人税の均等割が1,000万円以上は18万円になるところが、1,000万円以下の場合は7万円のままという形になります。もしも1,000万円にしようと考えている人は、特段のこだわりがなければ999万円にしておいた方が節税にはなりますね。
資本金を集める方法4選!!
今までの話からある一定額は資本金が必要なことはお分かりいただいたかと思います。では具体的にどのような方法で集めるのでしょうか。
一番多いのは起業する本人の貯蓄です。起業をする人はある日突然起業を思い立ちすぐに実行する人はなかなかいません。個人事業主として事業を行う流れを経験してどのような会社にしていくのかじっくり考え、その過程の中で資本金はいくら必要なのか考えるケースが多いです。手元にまとまった資金がないのであれば、会社を設立しようとしている時期から逆算して計画的に資金を貯めるようにしていきましょう。創業時は、補助金や助成金制度などを活用することも可能なので、知識として身に着けておくと今後の経営において活用できるので、知っておいて損はないでしょう。
また、銀行での融資審査の際などは資本金=起業する本人の熱意とも捉えられますので尚更です。それでもどうしても目標額に届かない場合は以下の資金調達の方法もあります。
家族や親せき、友人からの出資
周りの方で資産がある方にとって、こちらは自分で貯蓄して貯める以外に多いケースです。
生命保険を解約する
解約返戻金がある生命保険の場合、解約することでの返戻金を自己資金に充てることが出来ます。金額などをまずは保険会社に確認してみてもよいでしょう。ただし、解約すると何かあった時の保証が失われるリスクがあるので、慎重に検討したほうが良いでしょう。
株式や不動産などを売却する
所有している株式などの有価証券や、不動産を売却することで利益を資金とします。ただ有価証券はタイミングによって損が出てしまうこと、不動産は買い手がつくまで期間を要する場合がほとんどですので注意が必要となります。
個人投資家からの出資
過去の実績などで経営者への信頼が高ければ可能です。ただこれは実績や人脈が必要になるため創業時にはなかなか難しいのも現状かと思います。
上記のような方法をご紹介はしましたが、最初にお伝えしたように一番の近道はやはり「貯蓄」かと思います。起業する前に会社に勤めたり、副業をしたりなどをして資本金を貯めるケースが一般的です。そのためには早めの目標額設定がカギとなりますね!
創業後、資本金を増資する方法
会社設立後に資本金を増やしたい場合がありますが、上記で解説した資本金を集める方法のほかに、新株を発行して資本金を増やす「増資」という手段があります。増資の方法として以下3種類あります。
・公募増資
公募増資は、一般投資家などの不特定多数の投資家に対して新しい株式を発行し、出資を得ることによって資金調達を行う方法です。ただし、公募増資は株式公開済みの企業(上場企業)のみが行える手段になるので、どの企業でも行えるわけではありません。
・株主割当増資
株主割当増資とは、すべての既存株主に対して、その持分比率に応じて新株を引き受ける権利を与えることで出資を募る方法です。既存の株主に対して行われるため、株主構成や持ち分割合が変化しずらいというメリットがある一方で、必ずしも応じてもらえる保証はありません。
・第三者割当増資
第三者割当増資は、親会社などの特定の第三者を出資者として発行した新株を引き受ける権利を与えて、その対価として出資を得ることで資金調達を行う方法です。
増資するメリット
増資をすることによって得られるメリットは「財務基盤の強化」「会社の信用度の向上」「会社の支援者の増加」などが挙げられます。詳しい内容については以下の通りです。
 財務基盤の強化
財務基盤の強化
増資することで、純資産が増加し自己資本比率も高まるため、財務基盤の強化が見込まれます。また、資本金が多くなることによって事業に関する設備などを充実させることができ、資金の循環がスムーズになります。
 会社の信用度の向上
会社の信用度の向上
前述したように、資本金は会社の規模や対外的な信用度を表します。そのため、資本金が増加することで、会社の規模拡大や社外からの信用を得やすくなります。信用度の向上があることで、取引先や顧客の拡大などが見込まれるため、さらなる企業の発展が期待できます。
 会社の支援者の増加
会社の支援者の増加
増資は新株を発行して投資者からの出資を募る方法です。その増資がきっかけとなり会社の支援者の増加につながります。
増資するデメリット
資本金が増えることで注意しなければならない点があります。それは「既存の株主が不利益を被る可能性がある」「税務上の優遇措置が受けられなくなる」の2点です。詳しくは以下の通りです。
 既存の株主が不利益を被る可能性がある
既存の株主が不利益を被る可能性がある
増資をすることで発行済株式が増加し、1株に対する利益が下がるため、既存の株主に不利益が生じる可能性があります。また、持株比率にも影響があり、第三者に対して増資を行うと経営者の持株比率が低下します。経営者の持株比率が低下することで、経営者ではない第三者の意思によって代表取締役の解任を行うことができる可能性が出てきます。
 税務上の優遇措置が受けられなくなる
税務上の優遇措置が受けられなくなる
増資することで、資本金額による法人税や消費税などの優遇措置が受けられなくなる可能性があります。資本金の増加と税務上の優遇措置のどちらを重視するのか、よく検討したうえで判断する必要があります。
資本金と資本準備金の違いとは?
会社設立の際に準備している資本金と混じってしまうのが「資本準備金」です。一見、何が違うのかわからない方が多いでしょう。会社設立の際に間違わないようにしっかりと覚えておく必要があります。
「資本準備金」とは、将来的な赤字の補填や損失などに備えるお金です。資本金と資本準備金は、株主から出資受けたお金という点では同じですが、資本金に含まれていない残額のことを「資本準備金」として定めています。また、資本金は登記簿謄本に記載されますが、資本準備金は記載されることがないので、社外に把握されることがありません。
会社法において資本準備金は、払い込まれた資本金のうち2分の1を超えない金額までなら計上することができます。資本金だけでなく、資本準備金として計上する理由は以下の2つです。
・取り崩しが資本金よりも簡単
資本金を取り崩す場合は、その都度株主総会を開き、登記手続きを行わなければならないため、とても手間がかかります。一方で、資本準備金は登記が不要になるため、株主総会などで取り崩しを決定することができ、簡単に手続きをすることができます。
・資本金額を抑え、税務上の優遇措置を受けられる
資本金額によっては、法人税や消費税といった税金に関する優遇措置を受けることができますが、一定の金額を超えてしまうと受けられなくなってしまいます。そのような事態を防ぐために、資本準備金を活用して資本金が一定の金額を超えないようにすることが可能になります。
設立後の運転資金も考えて準備しよう
今回は、会社設立に不可欠な資本金についてまとめてみました。事業開始後の3カ月分と聞くと最初は漠然としているかもしれません。その場合は、まずは平均額の300万円を念頭に置いたうえで、自分の始めようとしている事業はおおよそいくらくらいが妥当なのか調べることをおススメします。
弊社は神奈川県横浜市を中心に会社設立に関しての全般的なサポートや代行をさせていただいています。もちろん資本金のご相談についてもお任せください!
会社の設立を検討されている方、何から進めていけばよいのか不安な方、まずはお気軽にご相談ください。お待ちしています!
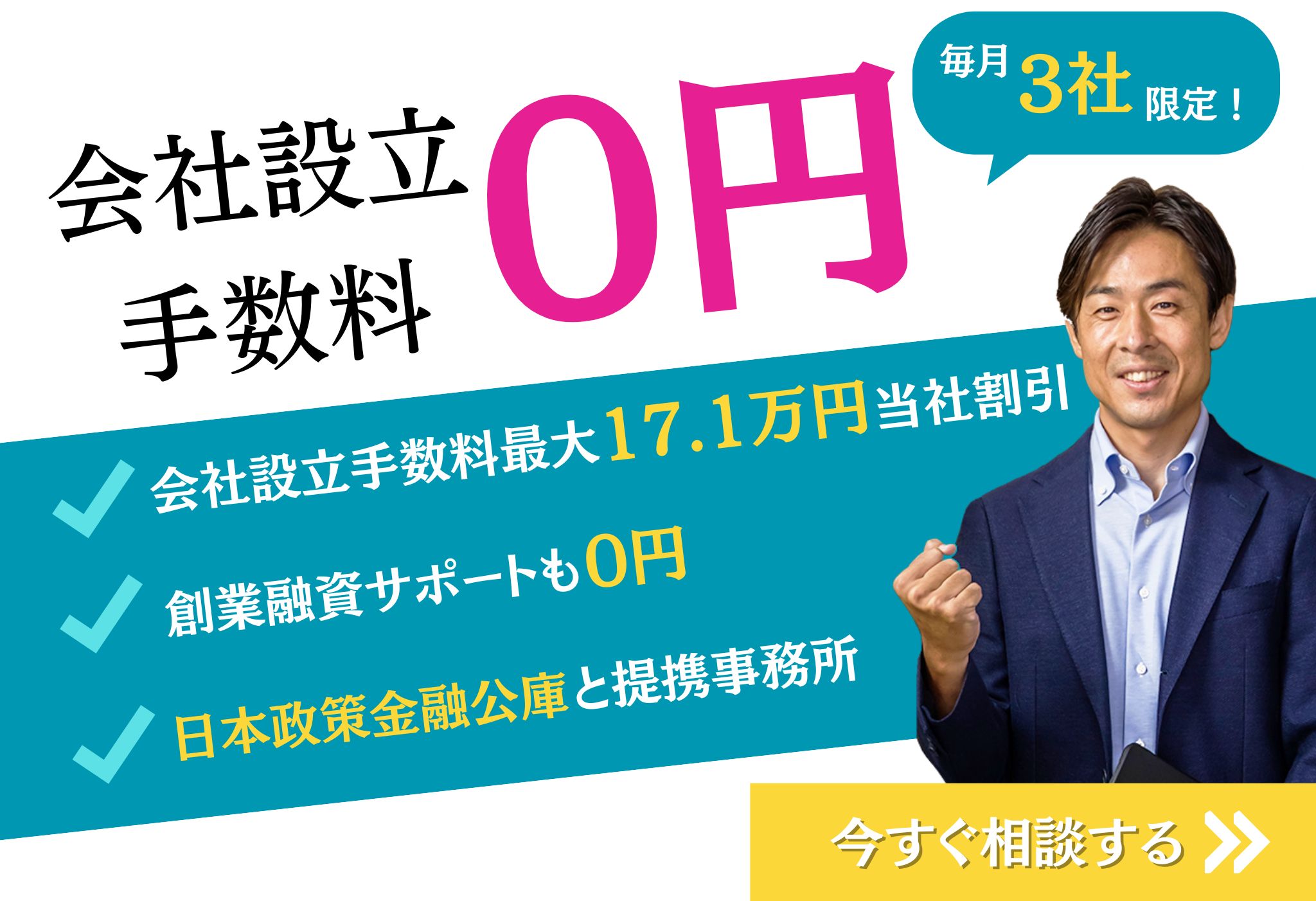
関連記事:会社設立時の持ち株比率と権利について解説
関連記事:【知っておきたい】会社設立時、設立後にかかる税金とは?
関連記事:【会社設立】方法や手続きの流れを解説
関連記事:会社設立のメリットは?個人事業主と法人どちらが良いの?
関連記事:【副業サラリーマン必見!】会社設立のメリットとデメリット
関連記事:会社設立のスケジュールはどのくらい?分かりやすく解説‼︎
関連記事:不動産会社設立の流れとポイントを解説!



