
個人事業主で赤字になった場合でも、確定申告をすることがおすすめです。
赤字でも確定申告をすることで、様々な恩恵を受けられます。
しかし、初めて確定申告を行う方は、このような疑問があるのではないでしょうか。
・具体的にどのようなメリットがあるのか
・赤字の場合、確定申告は必要なのか
・赤字になった場合の確定申告のやり方がわからない
本記事では、赤字になった場合に、確定申告をするメリットと確定申告の方法や流れについて解説します。ぜひ最後まで読んでください。
関連記事:【横浜市で確定申告に強い税理士】確定申告が必要な方や流れについて解説
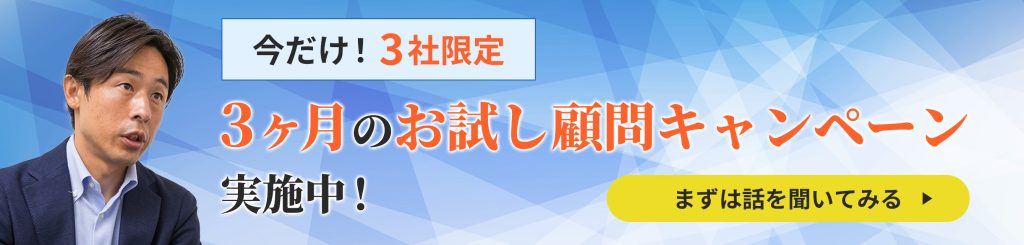
関連記事:個人事業主が経費にできるものは?判断基準や法人との違い
Contents
個人事業主の確定申告とは?
個人事業主の確定申告とは、1月1日から12月31日の1年間で事業によって得られた利益(所得)に対して、所得税を計算して申告をする手続きのことです。
法人で利益(所得)が発生した際に法人税を納めるのと同様に、個人事業主も一定以上の利益(所得)が発生した場合は、所得税を納める必要があります。
そのため、個人事業主として開業したら、売上と経費の帳簿付けをして集計することが必要です。
集計が終われば、確定申告書類を作成して納税額を計算したのちに、税務署へ提出します。
赤字の場合、確定申告は必要なのか?
結論から言えば、赤字になった場合は確定申告の必要はありません。
所得税の計算は、事業で得た利益(所得)から計算されます。
利益が(所得)が0円の場合、納税をする必要がある所得税が発生しなくなります。
そのため、赤字の場合、確定申告をしなくても、ペナルティを課せられるといったことはありません。
しかし、赤字になった場合でも、確定申告をした方がいいケースがあります。
また、赤字になった場合に、確定申告をしなかった際のデメリットもあります。
そのため、赤字の場合に、確定申告するメリットと確定申告をしない場合のデメリットについて確認しておきましょう。
赤字の場合に確定申告をする3つのメリット
はじめに、赤字の場合に確定申告をする3つのメリットについて解説します。
- 赤字の繰越しと繰戻しができる
- 損益通算が可能
- 還付が受けられる可能性がある
それぞれ、赤字であっても恩恵を受けられる制度なので、確認していきましょう。
赤字の繰越しと繰戻しができる
赤字の繰越しについて、事業で赤字になった場合、次の年から3年間利益から差し引くことができます。損益通算の結果残った赤字についても、3年間損益通算が可能です。
なお、繰越しをするためには2つの要件を満たす必要があります。
- 赤字が出た年に青色申告書を提出していること
- その後も連続して確定申告をしていること
開業当初は利益がでていなくても、確定申告をすることで将来利益が出た際に手元のお金が残りやすくなるのでおすすめです。
赤字の繰戻しについて、事業になった場合、前年の黒字と相殺できる制度です。
こちらは前年に青色申告書を提出しておくことが必要です。
繰戻し還付は一度、黒字になって納税した税金を還付することになります。そのため、税務署からの問い合わせや税務調査が入ることもあります。
翌年以降の黒字化が困難といった状況以外では、繰越しを選択するほうがいいでしょう。
繰越しも繰戻しも青色申告書を提出する必要があるので、注意が必要です。
参考リンク:国税庁「所得税/青色申告制度」
損益通算が可能
事業で赤字になった場合、確定申告をすることでほかの所得の黒字額と損益通算ができます。
通算とは、黒字になっている所得と赤字になっている所得を合算して計算できる制度です。
例えば、会社に勤めながら副業で個人事業をやっていた場合、事業所得と給与所得の2種類を受け取ることになります。
確定申告をすれば、給与所得から事業所得の赤字分を引いて所得を計算することができます。
給与所得が減少すれば、納めるべき納税額も少なくなるので、還付が受けられる可能性があるでしょう。
還付が受けられる可能性がある
赤字の場合、確定申告をすると、還付を受けられることがあります。
報酬によっては、支払者が代わりに報酬から源泉徴収を行い、納税することが必要です。
例えば、司法書士や社会保険労務士などの特定の資格を持っている方への報酬・原稿料・講演料などがあります。
事業が赤字になった場合、本来であれば、所得税は発生することはありません。
しかし、報酬を受け取る側から見れば、所得税を先払いしていることになります。
確定申告をすることで、前払いしていた分の所得税の還付を受けることができます。
また、期中に予定納税していた場合にも、還付が受けられることがあります。
確定申告をすることで、赤字であるにもかかわらず還付を受けられるのは、大きなメリットです。
関連記事:【必見】確定申告した還付金の受け取り方法は?計算方法や注意点を解説
赤字の場合に確定申告をしなかったら?
赤字の場合に確定申告をしなくても、ペナルティは課せられません。
しかし、確定申告をしないことによるデメリットも存在します。
知らないと損をすることになるので、事前に知っておくといいでしょう。
所得の証明ができない
確定申告をしなかった場合、確定申告書類がないため、客観的に所得を証明することができません。そのため、融資や住宅ローンの審査が通らなくなるケースも出てきます。
赤字の場合でも、確定申告をすることで、所得を証明することができます。
申告の際に控えを添付していれば、受付印を押してもらい確定申告の書類の控えを取得でき、様々な場面で根拠資料として使うことが可能です。
例え赤字であったとしても、確定申告をして手元に所得を証明できる書類を残しておくことがおすすめです。
国民健康保険料に影響が出る
国民健康保険料について、所得が一定以下の場合、減額を受けることができます。
しかし、国民健康保険料の減額措置を受けるためには、所得税の確定申告をする必要があります。
確定申告をしていないと、国民健康保険料の算定に影響が出てくるので注意が必要です。
また、国民健康保険の加入者は住民税の申告が必要になります。
確定申告をしていれば問題はありませんが、確定申告をしていなかった場合、住民税の申告のみを行うことが必要です。
非課税証明書がもらえない
赤字で確定申告をすると住民税が非課税になる可能性があり、非課税証明が受け取れることがあります。
非課税証明書とは、地方自治体が発行している住民税が非課税であることを証明する書類です。
住民税は、所得税の確定申告をもとに計算されるので、確定申告をしていないと非課税証明書がもらえないことがあります。
非課税証明書を受け取ることで、各種公共サービスの減額といったメリットが受けられます。
また、住民税の申告をすることもできますが、確定申告をすれば、住民税の申告をする必要はありません。
ほかのメリットも受けられるので、赤字であっても確定申告をするほうがおすすめです。
個人事業主は青色申告がおすすめ
確定申告には青色申告と白色申告がありますが、赤字で確定申告をする場合は、青色申告をすることがおすすめです。
青色申告を選択すると、赤字の繰越しと繰戻しをすることができます。
青色申告をするためには、事前に青色申告承認申請書が必要になりますが、その前に開業届を提出しなければなりません。
また、青色申告は赤字の場合だけではなく、黒字の場合でも所得控除や税額控除などのメリットがあります。
青色申告は、白色申告と違い複式帳簿で記入する必要があり、簿記の知識が必要です。
しかし、青色申告は節税につながる恩恵を受けることができるので、少し手間がかかっても青色申告がおすすめです。
赤字の場合に確定申告をするデメリット
赤字で確定申告をするデメリットは、主に2つです。
- 手間がかかる
- 税務調査が入る可能性がある
デメリットについて正しく理解をしていないと、かえって時間がかかったり、ペナルティが課せられたりすることがあります。ここでしっかり頭に入れておきましょう。
手間がかかる
赤字の場合に確定申告をするデメリットは、手間がかかるという点です。
赤字であれば、確定申告をする必要はありませんが、メリットを受けるためには確定申告書類を作成する必要があります。
また、赤字で確定申告をする場合は青色申告をすることで、メリットを受けやすくなります。青色申告をする際には、前もって青色申告承認申請書の提出が必要です。
青色申告の場合、複式帳簿付けをしなければならないため、簿記に関する知識が必要になります。
そのため、日々の経理業務が増えるといった手間がかかります。
赤字で確定申告をする場合には、確定申告表第一表や二表のほかに第四表が必要です。
日々の業務が増えるだけではなく、申告する書類が増えるので時間と手間がかかると言えるでしょう。
税務調査が入る場合がある
法人だけではなく、個人事業主も税務調査の対象になることがあります。
税務調査とは、納税を適切に行っているかを、税務署の調査官が訪問して調査することです。法律では過去5年分をさかのぼって調査ができます。一般的に3年と言われていますが、申告ミスなどがあった場合は過去5年にさかのぼります。
また、不正や隠ぺいの疑いがある場合は、最長で7年分の税務調査が行われます。
場合によっては、過少申告加算税や不納付加算税などのペナルティが加算されることがあるでしょう。
自分が税務調査の対象ではなかったとしても、取引先に税務調査が入った場合に無申告であることが知られる可能性もあります。
税務調査が入る可能性も想定し、書類は大事に保管するといいでしょう。
赤字の場合の確定申告書の作成手順
ここでは、赤字の場合の確定申告書の作成手順について解説します。
赤字の場合、必要書類は確定申告書の第一表と第二表のほか、第四表(損失申告用)です。
確定申告は難しいと感じる方も多くいるので、事前に知っておくことで、スムーズに申告することができます。
事前準備
確定申告をするためには、必要書類をそろえておく必要があります。
赤字の場合、確定申告書の第一表と第二表、第四表(損失申告用)が必要なので、事前にそろえておきましょう。
また、事業主の場合には、収支内訳書(青色申告の場合は青色申告決算書)がという書類が必要になります。
この書類を正確に作成するためには、日々の帳簿への記帳が大切です。
いつ、何に、いくら使ったのかを把握しておけば、スムーズに作成することができます。
また、経費計上はレシートや領収書をもとに記入されますが、購入したものが経費になるかは事業に関連するか否かで決まります。
もし、経費にできるか不安な場合は、税理士に相談してみるといいでしょう。
確定申告第四表(一)
確定申告第四表(一)に申告する年度と、申告書の前に確定と記入します。
次に、現在の住所または居所事業所等の欄と氏名、フリガナの欄を記入しましょう。
確定申告第一表の所得金額等の欄の⑴~⑹までを合計して、Aの経常所得(申告書 第一表の⑴から⑹までの計+⑽の合計額)に記入します。事業が赤字だった場合、マイナスになるので、赤字となる金額の前に△を記入しましょう。
例えば、200万円の赤字だった場合、
△2,000,000円と記入します。
そのほかの所得がある場合は、B~Fの欄に記入します。
損益通算を行う場合は、損益通算の結果を損益通算の欄に記入しましょう。
出典:確定申告書等の様式・手引き等(令和4年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁、申告表第一表・第二表【令和4年分以降用】、記載例
確定申告第四表(二)
はじめに、確定申告第四表(二)でも確定申告第四表(一)と同様に、申告する年度と確定の文字を記入します。
青色申告書の損失金額の欄に、確定申告第四表(一)の経常所得の金額を記入します。
その後、繰越しに関する申告内容を記載します。
事業の内容と赤字の内容によって、必要書類と記入内容が変わってくるので、必要な書類を事前に準備をして正確な情報を記入しましょう。
また、確定申告第四表(二)は、繰越損失がない場合は記入が不要です。
出典:確定申告書等の様式・手引き等(令和4年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁、申告表第一表・第二表【令和4年分以降用】、記載例
困ったときは税理士や税務署に相談
確定申告で困ったことがあれば、専門家に相談することがおすすめです。
事業の内容によって確定申告で必要な書類のほか、仕訳や勘定科目が異なるので、個人で正しく記入することが難しいと感じている方も多くいらっしゃいます。
記入ミスや記入漏れを防ぐためにも、事前に税理士や税務署に相談をして、必要な書類や記入場所について事前に確認をしておきましょう。
お試し顧問キャンペーン実施中!
個人事業主で赤字になった場合でも、確定申告をしたほうがいいでしょう。
赤字の場合、利益(所得)が発生しないので、確定申告をする必要はありませんが、確定申告をすることで、様々なメリットを受けることができます。
しかし、確定申告を自分でやると、難しいと感じる方も多いと思います。
また、青色申告の場合、簿記の知識も必要になり、白色申告と比べるとハードルが高くなってきます。
当事務所では、今回解説させて頂いた確定申告のご依頼も対応しております。また、現在は3か月間のお試し顧問契約キャンペーンを実施しております!お気軽にご利用ください。
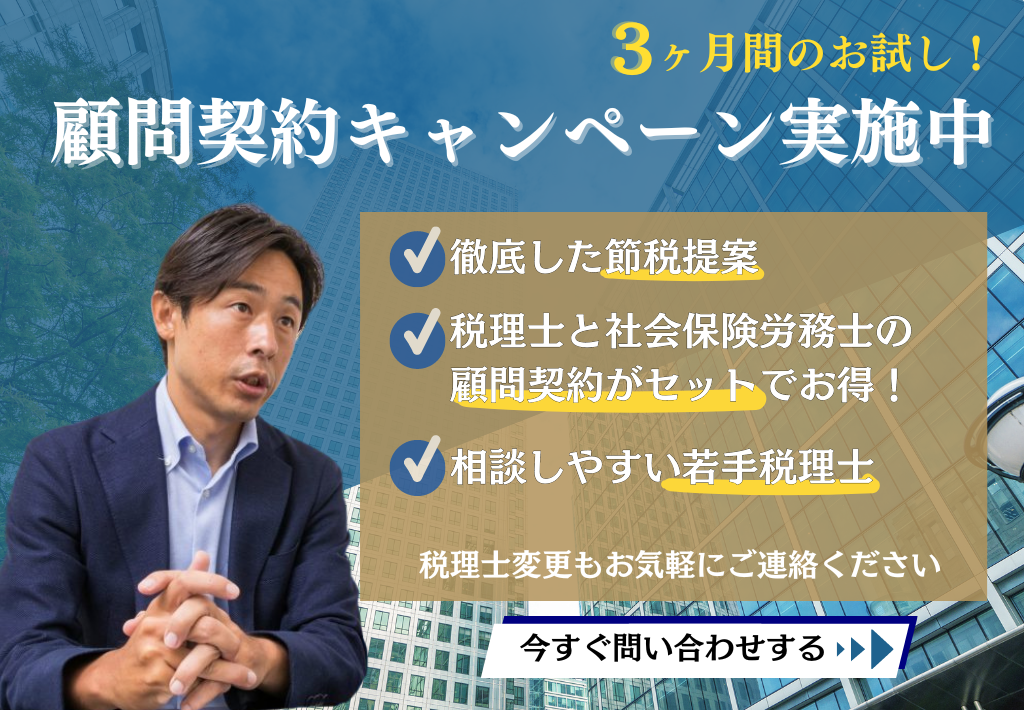
関連記事:税理士と社会保険労務士(社労士)の業務の違い|どちらに依頼すべき?
関連記事:社労士の独占業務とは?どんな時に依頼するのか詳しく解説‼︎
関連記事:個人事業主が毎月やるべき経理業務とは?行う理由についても理解しよう



