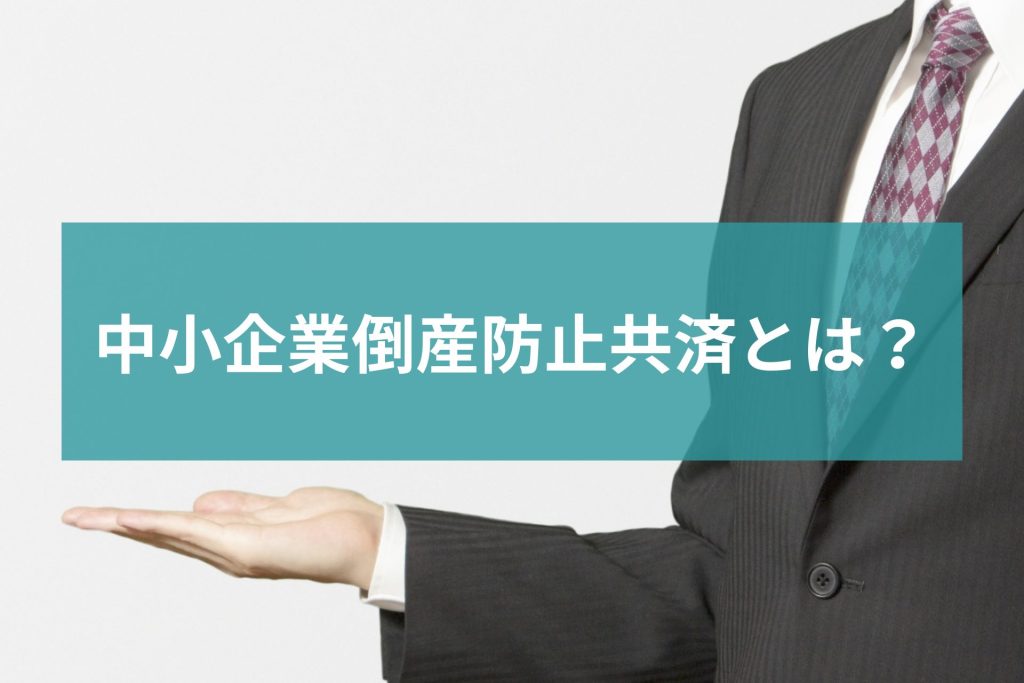
中小企業倒産防止共済(通称:経営セーフティ共済)とは、取引先が倒産したことにより経営難に陥ったり、倒産連鎖が起きないように中小企業などを支援する制度です。
取引先が倒産した際に売掛金などが回収できないと、経営に大きなダメージを負うことになります。特に個人事業主や中小企業は、1つの取引先が売り上げに直結する場合があるため、売掛金が回収できないケースに耐えられる資金力がないと連鎖的に倒産する危険性もあります。
このようなリスクに備えるための制度が、中小企業倒産防止共済です。制度の仕組みを理解していれば、何かあったときも慌てずに対処することができます。
これから起業をする方や加入を検討されている方は、制度の概要やメリット・デメリットなどを解説しているので、是非参考にしてください。
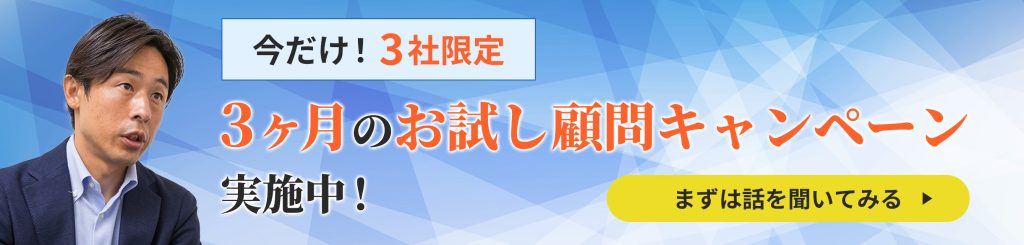
Contents
中小企業倒産防止共済とはどんな制度?
中小企業倒産防止共済とは、取引先の倒産によって売掛金などが回収できない場合に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための支援制度です。「経営セーフティ共済」とも呼ばれています。
独立行政法人中小企業基盤整備機構により、中小企業倒産防止共済法に基づいて運営されており、1978年に創設されました。
中小企業などは、大規模な企業と比較して「取引先の数が少ない」「取引先の経営状況や財務状況を把握することが難しい」というケースが多く、取引先が倒産した場合の被害が経営に大きな影響を与えます。取引先の倒産をきっかけとして、経営の継続が困難となり、連鎖倒産してしまうことも珍しくありません。
倒産連鎖を防ぐことを目的として制度が創設され、中小企業間の相互扶助のもと成り立っています。また、名称が似ている制度で「小規模企業共済」がありますが、こちらは小規模企業の経営者や個人事業主のために創設された積み立てによる退職金制度です。
どちらも独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営していますが、制度自体が異なるため、それぞれの加入条件を満たしていれば同時加入も可能です。
制度の概要
取引先の倒産理由によって、制度が利用できるのかが判断されます。どのような理由で借り入れの可否が決まるのかは以下の通りです。
[借り入れが可能な取引先の倒産]
- 法的整理
- 取引停止処分
- でんさいネットの取引停止処分
- 私的整理
- 災害による不渡り
- 災害によるでんさいの支払不能
- 特定非常災害による支払不能
[借り入れが不可な取引先の倒産]
- 夜逃げ
経営悪化や法的な処分、災害によって影響を受けた場合には、共済金借り入れの対象となります。多くの企業が借入金の対象となる可能性が高いです。
一方で、もし取引先が夜逃げによる倒産になった場合は、共済金を借り入れることができないので、可能であれば、取引先の財務状況は把握しておきましょう。
また、加入するに際して掛け金の月額や納付方法を決める必要があります。掛金や納付方法などは以下の表のとおりです。
| 掛金月額 | 5,000~200,000円までの範囲 (5,000円単位) |
| 納付方法 | 口座振替(希望によって前納も可能) |
| 口座振替日 | 毎月27日(土・日・祝の場合は、翌営業日) |
| 積立限度額 | 8,000,000円まで |
掛金月額は、5,000円単位で変えることができ、加入時に設定します。掛金は加入した後に変更することも可能なので、経営状況によって増額・減額の手続きを行いましょう。
掛金総額が掛金月額の40倍に達している場合は、掛金の払込を止めることができます。どのような場合に手続きを行えばよいかわからないときは、税理士などの専門家に相談を検討しましょう。
中小企業倒産防止共済の加入条件
加入できるのは、1年以上継続して事業活動をしている中小企業などです。中小企業の範囲は、企業や個人事業、組合です。中小企業は業種や資本金などによって、加入の可否が異なるので確認しましょう。
[中小企業の加入要件]
| 業種 | 資本金額または出資金の総額 | 常時使用する従業員数 |
| 製造業、建設業、運輸業、その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
| ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
個人事業主は、上記の表と同じ加入要件となるので、「業種」と「常時使用する従業員数」が該当していれば問題ありません。
加入ができないケース
加入要件を満たしている中小企業だったとしても、中小企業倒産防止共済への加入は認められないケースがあります。加入できないケースは以下の事例が挙げられます。

・事業に係る経理内容が不明
・中小機構から返還請求を受けた共済金、一時貸付金、早期償還手当金、解約手当金の返還を怠っている
・納付すべき所得税(法人税)を滞納している
・掛金を12ヶ月以上滞納したため中小機構により共済契約を解除され、解除された日から12ヶ月経過していない
・不正行為により共済金もしくは一時貸付金の貸付、または解約手当金の支給を受け、また受けようとした日から12ヶ月経過していない
・現在、共済契約者となっている
また、会社や組合の形態によっては、加入できない場合があります。具体的には以下の通りです。
[会社]
| 加入できる会社形態 | 株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、合同会社士業法人(弁護士法人、監査法人、税理士法人など) |
| 加入できない会社形態 | 医療法人、農業組合法人、NPO法人、外国法人 |
[組合]
| 加入できる組合形態 | 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、商工組合 |
| 加入できない組合形態 | 森林組合、農業協同組合 |
加入手続きを行う前に自身の会社が加入条件を満たしているのか確認を行いましょう。
中小企業倒産防止共済に加入するメリットとデメリット
どの制度にもメリットとデメリットがあり、どちらも理解したうえで利用する必要があります。メリット・デメリットについて解説していくので、自社に合っているのかを確認してください。
加入のメリット
中小企業倒産防止共済は、取引先が倒産したことで売掛債権が回収できず、さらに倒産してしまうといった倒産連鎖を防止するための制度となっており、取引先が多くない個人事業主や中小企業にとってメリットが大きいです。
「取引先が倒産する可能性は低いから大丈夫」と思っていても、社会の流れは変化し、取引先の財務状況には問題がないと断言できるわけではありません。また、倒産防止のほかにも資金繰りという面で活用できる場合もあります。
加入には、以下の5つのメリットがあるので、それぞれについて詳細を解説します。
2.節税効果が高い
3.掛金の増額・減額が可能
4.解約手当金が受け取れる
5.一時貸付金の利用が可能
 取引先の倒産後にすぐ借り入れできる
取引先の倒産後にすぐ借り入れできる
取引先が倒産したときは、担保や保証人も必要なく、事業者との取引が確認でき次第、スムーズに借り入れを受けることができます。
借り入れできる金額は、「実際の損害額」と「納付済掛金の10倍の金額」のいずれか小さい額と定められています。
例えば、2,000万円の売掛債権が回収できず、すでに100万円の掛金を納付していた場合は、1,000万円(2,000万円>100万円×10倍=1,000万円)の借り入れが可能です。ただし、上限額は8,000万円と決められており、かつ、夜逃げなどによる倒産は、共済金の対象外となるので注意しましょう。
 節税効果が高い
節税効果が高い
掛金は損金または必要経費として計上できるため、節税対策として活用が可能です。
万が一に備えて、資金を保有するのは大切ですが、保有している資金額が大きくなると課税される金額も大きくなります。課税される金額が大きくなってしまうと会社にとっては対策が出来にくくなってしまいます。
そのため、中小企業倒産防止共済を活用して、万が一に備えられるように準備をしつつ、掛金を損金や必要経費に算入して節税対策を行うことで、特に黒字額が大きい年度では大きなメリットになります。
ただし、個人事業主の場合は必要経費として算入できるのは事業所得だけであり、不動産所得には算入できません。
 掛金の変更が可能
掛金の変更が可能
掛金は毎月5,000円から200,000円の範囲で自由に金額を設定することができます。掛金は800万円が上限となっているので、毎月200,000円を納付している場合は、40か月掛け続けることができます。
また、加入後に金額の変更を行えるため、経営状況や年度の売り上げによって金額を増額、減額することができるのもメリットの1つです。
 解約手当金が受け取れる
解約手当金が受け取れる
中小企業倒産防止共済を自己都合で解約する場合であっても、解約手当金が受け取れます。今まで納付した掛金の金額や加入していた期間によって変動しますが、上限額まで掛金を納付している場合は、掛金全額が解約手当金として戻ってくる仕組みです。
ただし、12か月以内の解約は掛け捨てになるので、加入するタイミングは検討しましょう。
解約事由(解約の種類)と解約手当金の支給率は以下の通りです。
[解約事由]
| 解約事由 | 解約の種類 |
| 契約者の任意解約 | 任意解約 ‐契約者が任意で行う解約 |
| 個人事業主の死亡 | みなし解約 ‐契約者の死亡、解散、分割(会社の事業をすべて承継させるものに限る) |
| 会社等法人の解散 | |
| 事業譲渡 | |
| 会社等法人の分割 | |
| 契約者に対する機構解除 | 機構解約 ‐契約者が12か月以上の掛金を滞納したときなど中小機構が行う解約 |
[解約手当金の支給率]
| 掛金を納付した月数 | 任意解約 | みなし解約 | 機構解約 |
| 1か月~11か月 | 0% | 0% | 0% |
| 12か月~23か月 | 80% | 85% | 75% |
| 24か月~29か月 | 85% | 90% | 80% |
| 30か月~35か月 | 90% | 95% | 85% |
| 36か月~39か月 | 95% | 100% | 90% |
| 40か月~ | 100% | 100% | 95% |
 一時貸付金の借り入れが可能
一時貸付金の借り入れが可能
中小企業倒産防止共済に加入していると、取引先が倒産したとき以外でも資金が必要になったときに一時貸付金の借り入れが可能です。
事業を運営していると、突発的に資金が必要になる場面があります。ただ簡単に資金調達をすることができない場面で活用できるのが、一時貸付金です。納付期間に応じて最大で解約手当金の95%相当を借り入れることができます。
一時貸付金を借り入れできるのは、掛金を12か月以上納付していることが条件となっているので、誰でも利用できるわけではありません。
加入のデメリット
倒産を防止するための対策として非常に優秀な反面、手取りを増やしたい場合や退職金の原資作りには向いていません。
そのほかに4つのデメリットが挙げられるので、加入は慎重に進めましょう。
2.12か月未満は掛け捨てになる
3.40か月未満だと元本割れをする
4.解約手当金は課税される
次項でデメリットについて詳しく解説します。
 事業年数が1年未満だと加入できない
事業年数が1年未満だと加入できない
中小企業倒産防止共済は「1年以上事業を継続している」ことを加入条件として定めています。事業を開始したばかりのころは、資金が十分でない可能性が高く、取引先との関係性も安定しているわけではありません。そのような時期だからこそ、万が一に備えるために制度を利用したいところではありますが、起業をして1年未満の事業者は加入できません。
たとえ、多額の資金を保有していたとしても、事業継続が1年未満であれば加入できないので、起業したばかりの資金繰り対策として利用できないので注意しましょう。
 12か月未満は掛け捨てになる
12か月未満は掛け捨てになる
前述したように、納付月数が12か月未満で解約する場合は掛け捨てになります。
解約事由を問わず、加入から11か月と12か月だと大きな違いがあるので、解約をするタイミングには注意しましょう。
 40か月未満だと元本割れをする
40か月未満だと元本割れをする
メリットでも解説したように、共済を解約すると解約手当金を受け取ることができます。注意すべきは、40か月以上納付していないと100%の返戻を受けることができず、元本割れをしてしまう点です。
一定期間納付していないと、積立金の総額が元本割れしてしまうので、加入の際には40か月以上掛金を納めることを前提として、手続きを行うのが望ましいでしょう。
 解約手当金は課税される
解約手当金は課税される
掛金が損金や必要経費として算入できる反面、解約手当金は益金(法人)、雑収入(個人事業主)として扱われるため、課税対象になります。
納付期間が長くなると比例して解約手当金も多くなるため、税負担が大きくなります。そのため、解約のタイミングなどを事前に検討したうえで加入をしましょう。
中小企業倒産防止共済に加入する際の注意点
中小企業倒産防止共済は、時代の変化に伴い、改正が行われる場合があります。そのため、加入する前や加入した後も制度の改正について適度にチェックする必要があります。
2024年3月に所得税法等の一部を改正する法律が成立したことによって、中小企業倒産防止共済の内容も変化しました。
所得税法等の一部が改正されたことで、掛金の税法上の取り扱いについて規定している租税特別措置法が改正されました。改正により、2024年10月1日以降に共済契約を解除して、再度共済契約を締結した場合、解除した日から2年経過するまでの間は、掛金を損金または必要経費として算入できません。
安易に解約手続きを行ってしまうと、掛金として算入できない期間が2年あるため、節税対策ができなくなることは把握しておきましょう。
中小企業倒産防止共済の活用方法
本記事では、中小企業倒産防止共済のメリットやデメリットについて解説しましたが、大切なのは解約のタイミングです。
掛金は損金や必要経費として算入できる一方で、解約する際には、解約手当金全額が課税対象となります。上限額の800万円を掛金として、経費計上できたとしても解約をすると800万円全額が雑収入となり、課税されることになります。
経費計上できるとしても、解約すると税金負担があるというのは歯がゆく感じる方が多いのではないでしょうか。節税をするには、解約するタイミングなどが重要になるので、業績が好調のときと不調のときに、どのような対応をすればよいのか例を挙げて説明します。
[業績が好調なとき]
会社役員の退職金を支払うタイミングで解約して相殺すれば、節税になります。会社役員の退職金は経費計上できるため役員が退職するタイミングに合わせて、中小企業倒産防止共済を解約すると解約手当金の課税部分と相殺できます。
[業績が不調のとき]
納付済の掛金総額よりも赤字や繰越欠損金が大きい場合は、解約手当金と相殺できます。会社の経営が難航しているときに中小企業倒産防止共済を活用すると、資金繰り対策としておすすめです。
タイミングを見極めつつ、会社の経営状況や財務状況に応じて共済を解約したり、掛金を増額して節税対策を行ったりすると節税効果が高まるので、臨機応変に対応することが重要です。
中小企業倒産防止共済の手続きはお任せ!
今回は、中小企業倒産防止共済の概要やメリット・デメリットなどについて紹介しました。個人事業主や中小企業など取引の規模があまり大きくない場合は、倒産防止のために加入しておくことをおすすめしますが、会社にとってのメリットとデメリットを把握したうえで申込しましょう。
また、会社の経営状況に応じて解約すべきかどうかなどの判断も重要になります。事業を運営していると、なかなか節税対策について検討する機会は多くないでしょう。
ただ、会社を発展させるためには節税対策は必要不可欠です。中小企業倒産防止共済を含め、節税対策について何をすればよいかわからない方は、当事務所へご相談ください!
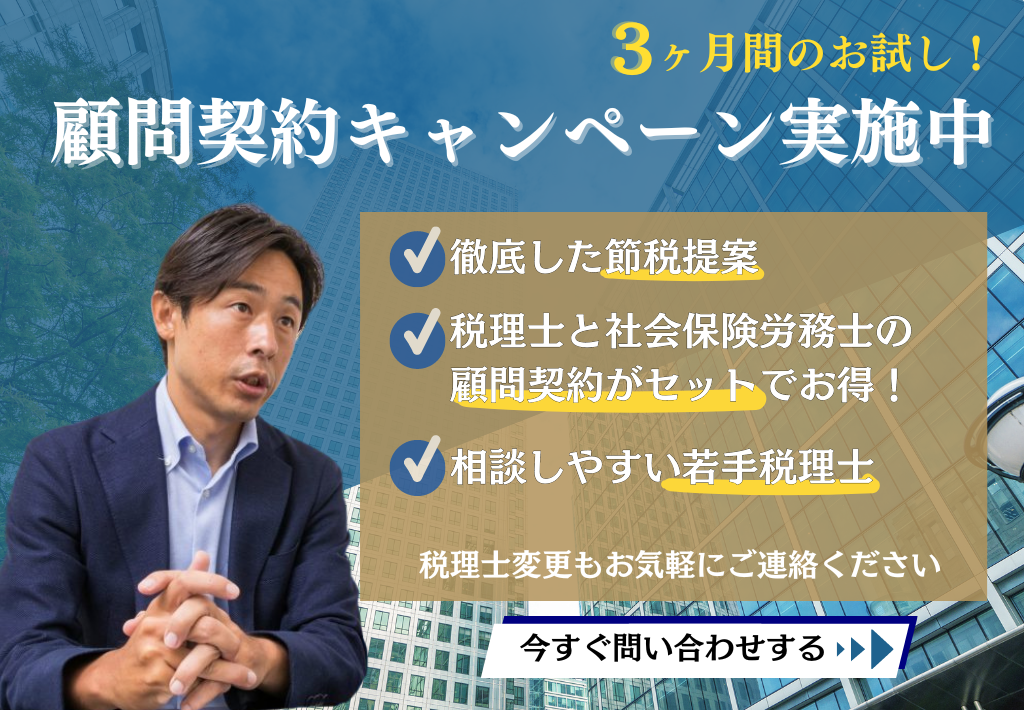
関連記事:法人の利益が出過ぎた際の節税対策は?注意点について解説



