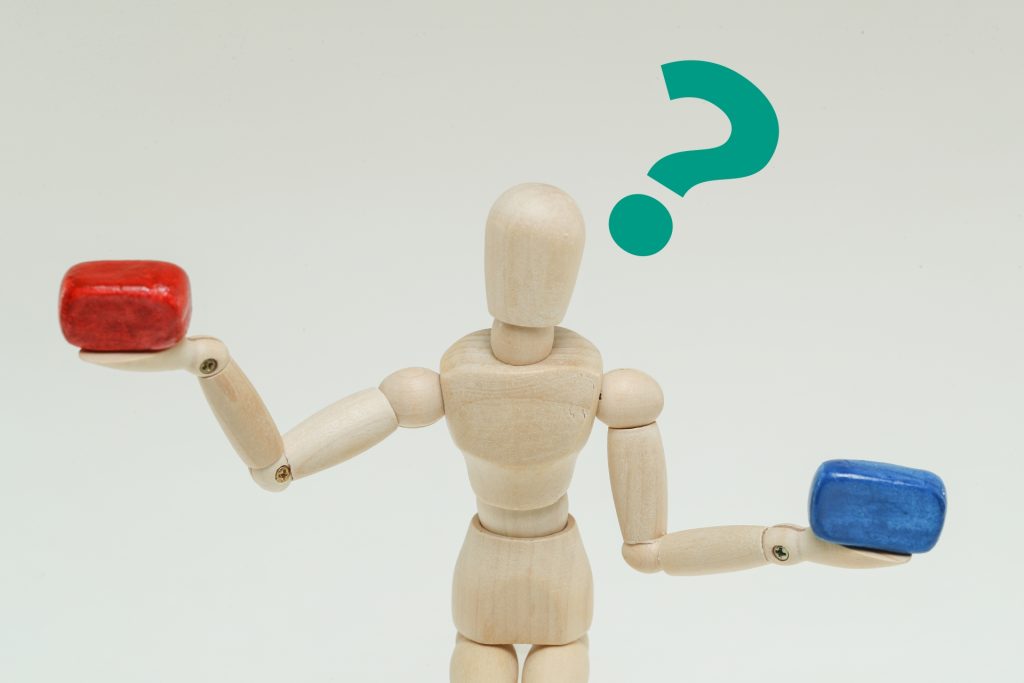
会社経営をされている方やこれから独立・起業を検討している方であれば、
税金のことで質問したい!
年末調整って何から手を付ければいいの…?
労務管理について教えてほしい。
社会保険の手続きに必要な書類が知りたい!
そんな悩みを持たれたことがある人も多くいるのではないでしょうか。
また、そんな時、「税理士と社会保険労務士のどっちに聞けばいいの?」という疑問も出てきます。
これらの悩みを解決してくれる専門家である「税理士」や「社労士」との関わりは無くてはならないものとなるでしょう。一般的に多くの会社では、顧問税理士や顧問社労士などを雇っており、諸手続きや書類作成などを委託している場合があります。
しかし、「税理士」や「社労士」について聞いたことはあるけれど、実際には具体的にこの2つの違いについてしっかりと理解している人は少ないように感じます。今回は「税理士」と「社労士」についての違いやライセンスの特徴を、どちらの資格も有している横浜市の松原税理士・社会保険労務士事務所がお伝えしていきます。
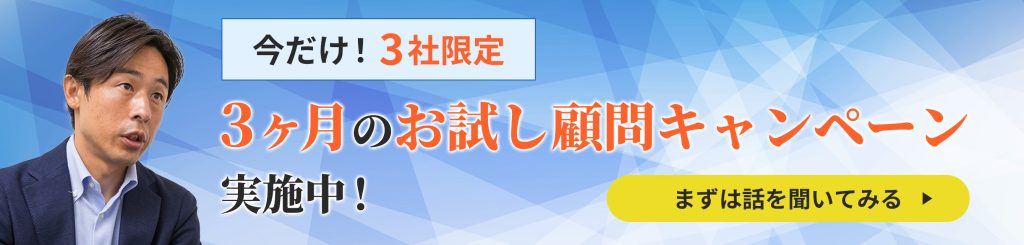
Contents
税理士の業務について詳しく解説
税理士はその名の通り、いわば「税金のプロ」です。税理士法というものがあり、そこには税理士のみが行うことのできる独占業務として以下の3点が定められています。

・税務書類の作成
・税務相談
独占業務とは、資格所有者のみが行える業務のことを指しており、資格所有者以外が業務に携わることが法律によって禁止されています。
税理士ができる業務は独占業務のほかに、税務業務に付随する会計業務やそのほかの業務などがあります。
会計業務は、「会計帳簿への記帳」や「財務諸表の作成」などあり、独占業務のほかに併せて依頼される経営者の方が多くいます。そのほかの業務は、税理士個人の能力や経験によって異なりますが、「経営コンサルティング」「相続・事業継承」「M&A」があります。そのほかの業務も依頼したい場合は、事前に可能な業務なのかを確認する必要があります。
まずは、税理士の独占業務であるそれぞれの内容について詳しく見ていきましょう。
 税務代理
税務代理
税務とは、税務署に税金を申告して納付することや、税務署から調査や処分を万が一受けた場合に主張や陳述を行うことをいいます。本来ならば、これは納税する本人が行わなければなりませんが、これを税理士であれば代理で行うことが出来ます。具体的な業務内容は、確定申告や青色申告の承認申請、場合によっては税務調査が行われるときの立ち合い、税務署の更生や決定に不服があるときの申し立てなど包括的な手続きを行います。
近年では、税金の申告はパソコンを利用して電子申告することも可能です。
もし、税理士でない人が本人の代わりに電子申告を行ってしまうと税務の代理にあたってしまうため、この税理士法に違反したことになり、2年以下の懲役または100万円以下の罰金が課されます。
最近では、税理士を語って詐欺をする人もいるため、注意が必要です。ともあれ本来ならば自分で調べて行わなければならない税金の申告や納付を税理士に頼むことができるのは、時間的コスト削減には大きく繋がり、事業に集中することができますね!
 税務署類の作成
税務署類の作成
税務書類とは、税務署に税金を申告する際に作成する書類や、事業者が事業年度ごとに作成する経営状態・財務状況をまとめた書類のことです。その書類作成も税理士の独占業務の1つとなっています。具体的な書類は、以下のようなものが該当します。
・貸借対照表
・キャッシュフロー計算書
・所得税・法人税・消費税申告書
・決算書
・源泉徴収票
この書類作成も専門的な知識が必要になるため、慣れていない場合は難易度が高く、税理士に依頼することをおすすめします。専門家に依頼することで、時間的コストの削減や書類作成ミスなどのリスクを大幅に減少させることができます。
 税務相談
税務相談
税務相談とは、税務署への税金の申告、および税務署から調査や処分を受けたときの主張や陳述などの税務について、対策や対応などの相談に応じることです。
具体的には、納税額の計算方法や納税のための手続き方法、節税効果の算出、税務署への主張や陳述の仕方などです。会社の経営について、税金や経費などお金に関する問題解決は必要不可欠です。税額を低くするためにはどのように対策をすればいいか、経費計上できるものはどんなものなのかといった悩みや対応について、専門的な視点からアドバイスをすることができるため、積極的に活用しましょう。
税務に関する書類や手続きに関して、もし間違った方法で行ってしまうと会社経営自体に影響を及ぼしかねません。信頼できる顧問税理士に早めに相談して計画的に納税などについても進めておきましょう。
また、先述したようにこれらに付随する会計業務(会社の税務書類の作成、会計帳簿の記帳代行など)や財務分析なども行っています。独占業務以外で税理士が行うことが多い仕事を具体的に挙げてみます。
・コンサルティング業務
作成した決算書をもとに、税務申告や節税対策などの経営に関するアドバイスを企業に対して行います。
・M&Aなどの組織再編税務
昨今、M&Aは大企業だけでなく、中小企業のM&Aも増えてきています。企業の合併や買収が行われると業務内容や財務状況が変化するため、事前に税務や財務のリスクを調査して、問題点を洗い出すことができます。また、税務や会計などさまざまな面での手続きが必要になるため、経営者に代わってその手続きを行うことが可能です。
最近では、横浜市も中小企業の事業承継を積極的に支援しており、今後も活発化していくことでしょう。
(公財)横浜企業経営支援財団(IDEC横浜)|事業承継相談窓口
・国際税務
近年では事業拡大に伴い、海外進出を行う中小企業も珍しくはありません。そういった国際税務も行います。
・起業支援
起業の際の各種手続きや書類の作成を行い、起業支援制度などを活用した資金繰りについてのアドバイスや手続きも行っています。
・相続や事業承継
前任者から事業を相続する場合や後継者に事業を継承する場合は相続税や贈与税が関係するため、税金に関するアドバイスや手続きを行います。
会社経営において正確な納税や、適切な節税を行うことは会社を長く経営していくにおいてとても重要であることは言うまでもありません。
信頼のおける「税金のプロ」は経営者にとってなくてはならない存在といえるでしょう。
社会保険労務士の独占業務について
次に社労士についてご紹介します。社労士はいわば「人事や労務管理の専門家」といえます。税理士と同様に社会保険労務士も社会保険労務士法で以下のような独占業務が認められています。

・労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成
それぞれについて詳しく内容を見ていきましょう!
労働社会保険諸法令に基づく申請書類作成、手続代行
社労士の申請書類作成・手続き代行とは、労働及び社会保険に関する法令に基づいて行政機関に対する申請書、届出書、審査請求書、再審査請求書などを作成して、提出の手続きを代行することです。
具体的には、労働保険(労災保険、雇用保険)の申告、社会保険(健康保険、厚生年金、介護保険)の算定基礎届、月額変更届、助成金などの申請が挙げられます。
従業員を雇用する場合、雇用保険や社会保険の手続きを行わなければなりません。企業によっては社会保険などの専門知識がなかったり、労務に関する人手が足りなかったりする場合は、社内だけで書類作成や手続きを行うことがなかなか難しく、ミスが多発したり、時間がかかるリスクもあります。そういった問題やリスクを防ぐために、労働社会保険関連の手続きは社会保険労務士が行っています。
労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成
帳簿書類の作成について具体的な内容としては、労働者名簿の作成、賃金台帳の作成、就業規則の作成や変更などです。
会社は就業規則や賃金規程、労働者名簿などの帳簿をそなえておかなければなりませんが、起業や独立に伴い、初めから書類や帳簿を一気に作成することは困難な場合が多くあります。また、法の改正に伴い、これらの内容も改定しなければならないこともあり、法律に詳しくないとなかなか思うように作業も進みません。そこで社会保険労務士に依頼することでこういった「帳簿書類等の作成」を行ってもらうことができるのです。
その他、人事労務に関する相談や指導、アドバイスなども行います。雇用や人材育成、人事、賃金、労働時間などの人事・労務管理に関するコンサルタント業務にも携わっています。
社会保険労務士の独占業務は無償であれば税理士や弁護士なども兼任して行うことも可能ですが、場合によっては業務範囲の問題で違反になってしまうことがあります。
年末調整は税理士?社会保険労務士?
ここまで、それぞれの業務内容について述べてきましたが、それぞれの業務範囲を正しく理解しておかないと、場合によっては業務範囲の問題で違反となり、対応できないことがあります。
どういうことかというと、社会保険労務士の独占業務は無償であれば税理士や弁護士も兼任して行うことも出来ますが、税理士が代行できる範囲は「租税債務の確定に必要な事務の範囲内」までとなっています。
つまり、税理士は労働および社会保険料の計算はできますが、届出をすることが出来ません。税理士が届出を行うと違反行為になるのです。
逆に社会保険労務士が年末調整を行うことは違反行為にあたるので給与計算はできても年末調整は行うことはできません。
このようにどこからどこまで対応してもらえるのか理解しておくことがとても大切です。対応可能な範囲を理解していないと、違反になり、予定していた日数以上の時間を要するリスクが生まれるため、注意が必要です。
さらに具体的なケースとして「給与計算」を比較してみましょう。給与計算に関する業務でそれぞれどちらが何を行うことができるのか紹介します。

算定基礎届の提出/労働保険の申告/月額変更届の提出→社会保険労務士のみ可能
年末調整→税理士のみ可能(源泉徴収票などの作成)
上記のように、「給与計算」と一言でいってもそれぞれの項目で税理士、社会保険労務士どちらも携わることになるため、依頼する側も注意が必要です。
もし、できる業務について判別の仕方が不安、別々の事務所などに依頼するのが面倒という人は、税理士事務所と社労士事務所が提携していたり、税理士と社労士のダブルライセンスを持つ先生がいたりする事務所を選ぶと依頼先が1か所で済むのでおススメです。
関連記事:【最新版】給与計算は税理士と社労士どちらを選択する?相場と選択基準!
それぞれのダブルライセンスのメリット
今回紹介した税理士と社労士は、専門性の高い資格の中でもとても相性の良い資格です。なぜ相性がいいのか、メリットを含めて解説していきます。
 業務の親和性が高い
業務の親和性が高い
税理士と社労士の業務は主に税務と労務になりますが、この2つは密接に関係しているため親和性がとても高いです。
従業員を雇うと給与や交通費の支払いなどの税務・会計周りと、社会保険や労働保険といった手続きや書類作成が必要になります。中小企業になると税務と労務についてまとめて相談をしたいと考えている方が多いですが、税務・会計については税理士、労務・人事業務については社労士の独占業務になるため、資格を保有していないと対応ができません。
労務と税務は取り扱う業務が近く、関わる場面が多いため、ダブルライセンスを保有していると行える業務の幅が広がります。また、クライアントから見ると、税理士と社労士をそれぞれ別の事務所で探す手間も省くことができ、時間や労力の削減にもつながります。
 包括的なサポートが受けられる
包括的なサポートが受けられる
企業における成功の要素は、ヒト・モノ・カネの3つと言われています。3つのうちのカネとヒトのスペシャリストが税理士と社労士であり、商品やサービスなどのモノに関することを除いて、包括的なサポートを受けることができます。
会社を経営するには、商品やサービスの売上も大切ですが、会社の骨組みとなる労務や税務の基盤が整備されていないと、会社として成立することが困難になります。そのため、労務と税務のどちらの業務も行えることで、会社の基盤や骨組みを盤石にし、会社にとって非常に信頼できる存在になります。
 経費削減につながる
経費削減につながる
先述したように、ダブルライセンスを保有している税理士・社労士に依頼をすることで別の事務所で探す手間が省けます。さらに、税務と労務の2つの業務を1人に依頼することができるので、経費削減につながることもポイントです。
顧問税理士や顧問社労士を雇うことを検討している場合は、毎月の顧問費用が発生することを覚えておきましょう。別の事務所へそれぞれ依頼することになると、当然ながら毎月の出費が多くなります。ダブルライセンスを保有している税理士・社労士が在籍している事務所へ依頼することによって、支払い対象が1箇所のみとなるため、毎月の負担が軽減されるため、経営者にとって大きなメリットになります。
 税務・労務以外にも依頼できる場合がある
税務・労務以外にも依頼できる場合がある
ダブルライセンスを保有していることで「税務問題」と「労務問題」を取り扱うことが可能です。どちらも会社を継続していくにあたって必ず直面する問題になるといえるため、必要不可欠な存在といえます。
ダブルライセンスにより、2つの問題を1人に任せることができ、人件費の削減と見知らぬ人へ任せるうえでのリスヘッジにもなり得るため、さまざまな面でメリットがあります。
また、個人差はありますが、税務業務や労務業務のほかに、コンサルティング業務や相続・事業承継などの相談や手続きなどが可能になる場合もあります。会社によって依頼したい内容は異なるかと思いますが、税務や労務以外に依頼したい業務がある場合は、事前に依頼できる業務について確認しましょう。さらに依頼できる業務の幅が増加するので、企業にとって負担軽減が期待できます。
当事務所がワンストップで対応します
今回は会社を経営する上でのいわば「パートナー」である「税理士」と「社労士」について紹介してまいりました。どちらの分野も専門性が高く、企業にとって重宝する存在ですが、それぞれの独占業務も細分化されており、しっかりとした区分があります。
様々なトラブルを未然に防止し、それぞれの専門性をしっかり生かして自分自身の会社経営に携わってもらうためにも違いを理解して適切に依頼しましょう。
とはいっても細かい業務範囲を明確に把握するのは中々難しいですよね…….。
当事務所では、横浜市を中心に税理士業務と社労士業務のどちらもワンストップで対応させていただいておりますので、とてもお得です。会社経営に関すること、税金に関すること、労務に関することなど様々なお悩みをお気軽にご相談ください。
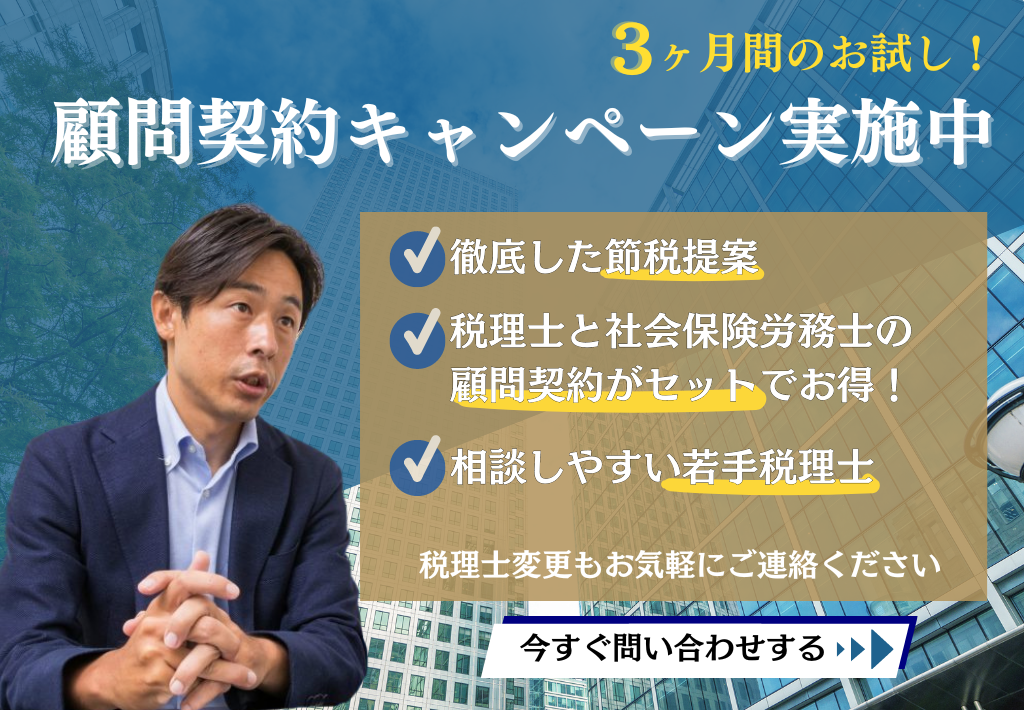
関連記事:給与計算は誰に依頼すべき?税理士・社労士に依頼する違いを解説
関連記事:税務調査への対応はどうするべき?税理士への依頼費用も解説
関連記事:横浜市で確定申告を無料相談できるところ



