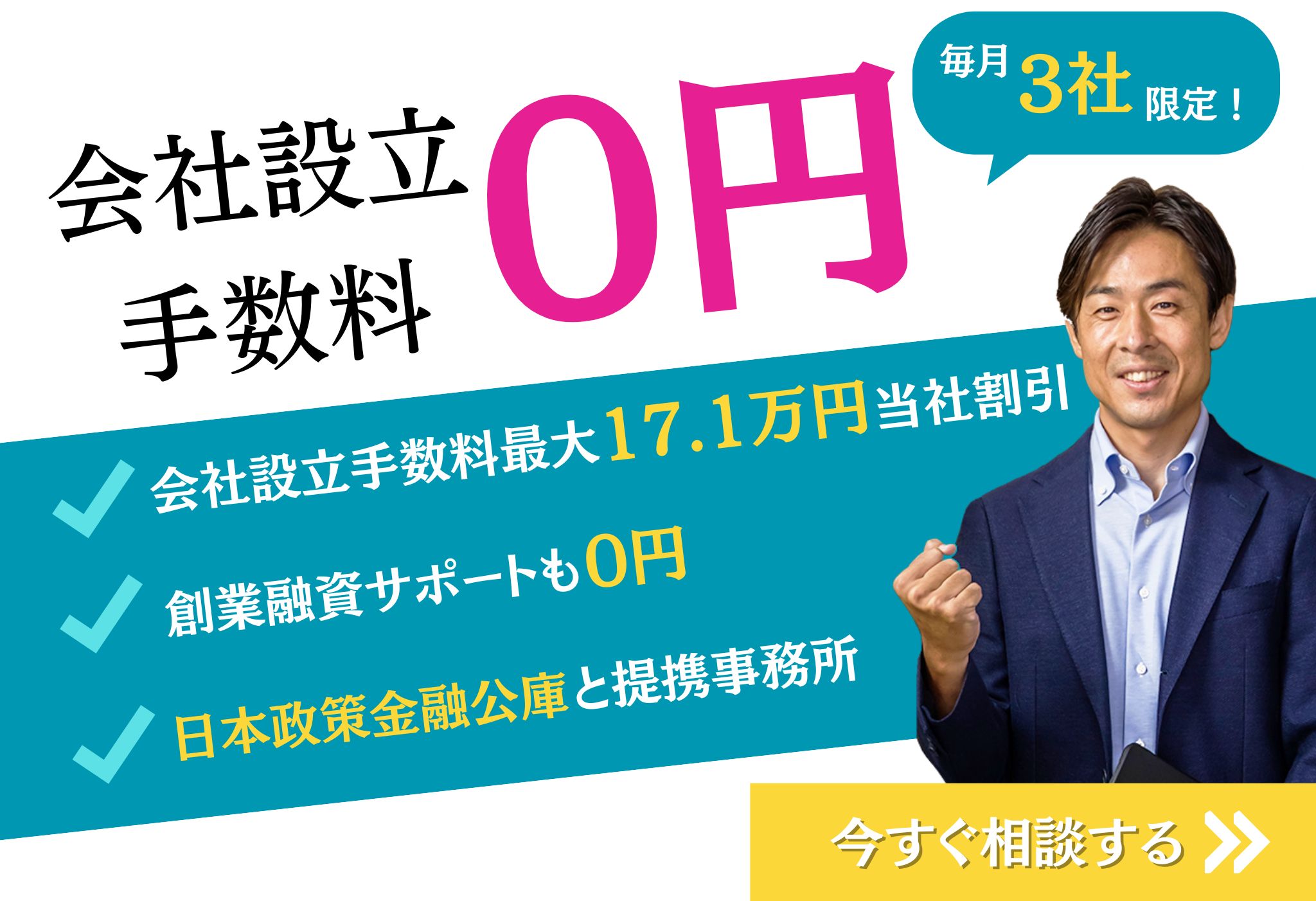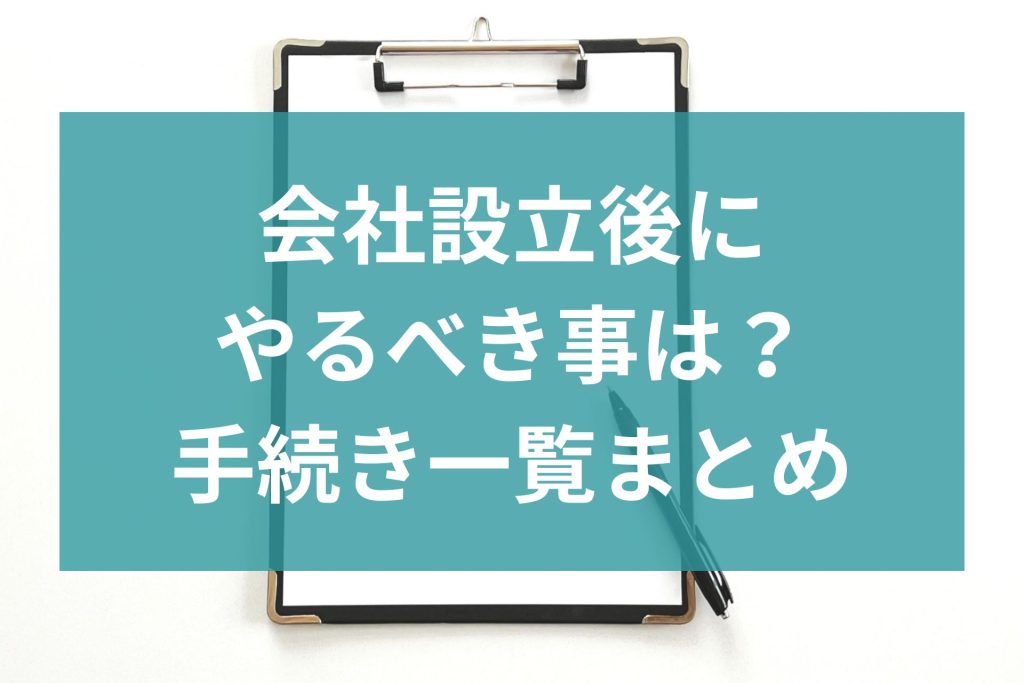
無事、会社設立ができて一安心!
しかし、会社設立後でも事業を始めるまでにやらなければならない手続きは多々あります。
「会社設立はできたけど、その後は何をすればいいか知りたい!」
本記事ではそんな方に向けて、会社設立後の手続き関係について詳細を解説していきます!少しでも流れをイメージしていただけたら幸いです。

関連記事:【知っておきたい】会社設立時、設立後にかかる税金とは?
Contents
会社設立後の手続き
冒頭でもお伝えしたように会社設立後でも必要な手続きがあります。この手続きは会社設立のための手続きと切り離して考えるのではなく、設立のための一連の流れとして把握しておきましょう!また、会社形態に関わらず、合同会社でも株式会社でも同じような流れですので参考にしてください。
会社設立後の手続きには、具体的に「税務関係」「社会保険関係」「労働保険関係」等がございます。期限が短いものや提出先も様々ですので、漏れのないように準備していきましょう。
では早速、会社設立後に行わなければならない手続きを紹介します。
【会社設立後の手続き一覧】
|
提出先 |
手続き |
任意・必須 |
期限 |
| 税務署 |
必須 |
設立から2カ月以内 |
|
|
消費税課税事業者届出書 |
必要に応じて |
すみやかに |
|
|
給与支払事務所等の開設届出書 |
必要に応じて |
給与支払いを行う事務所などの開設から1カ月以内 |
|
|
任意 |
期間の定めなし |
||
|
任意 |
設立から3カ月を経過した日の前日、第1期の事業年度終了日の前日のいずれか早い日 |
||
|
都道府県税事務所 |
法人設立届出書 |
必須 |
設立後おおむね1カ月以内 |
|
市町村役場 |
法人設立届出書 |
必須(※東京都23区は不要) |
設立後おおむね1カ月以内 |
|
年金事務所 |
必須 |
加入する日から5日以内 |
|
|
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 |
必要に応じて |
加入する日から5日以内 |
|
|
健康保険被扶養者(異動)届 |
必要に応じて |
加入する日から5日以内 |
|
|
労働基準監督署 |
時間外労働及び休日労働に関する協定届 |
必要に応じて |
時間外労働させる前まで |
|
労働保険保険関係成立届 |
必要に応じて |
従業員を雇った日の翌日から10日以内 |
|
|
労働保険概算保険料申告書 |
必要に応じて |
従業員を雇用するようになった場合、50日以内 |
|
|
就業規則(変更)届 |
必要に応じて |
常時10人以上の従業員を雇っている場合、すみやかに |
|
|
適用事業報告書 |
必要に応じて |
従業員を雇い入れた時に遅滞なく提出(従業員が同居の親族だけの場合は不要) |
|
| ハローワーク |
雇用保険適用事業所設置届 |
必要に応じて |
適用事務所になった場合、その日の翌日から10日以内 |
|
雇用保険被保険者資格届 |
必要に応じて |
従業員を雇った日の翌日から10日以内 |
 事前に準備しておくべきもの
事前に準備しておくべきもの
設立後の手続きを行う前に、準備しておくべきものを把握しておくことが大切です。会社設立前後はさまざまな手続きが必要になるので、時間や手間がかかりがちですが、事前に必要なものを準備しておくだけでスムーズに行えます。
会社設立の手続き完了後は、法務局で登記簿謄本(履歴事項全部証明書)と印鑑証明書を取得しましょう。特に登記簿謄本は、都道府県税事務所や市町村役場など複数の窓口で提出を求められるケースがあるので、2~4部ほど発行しておくことをお勧めします。
また、印鑑証明書は法人の銀行口座開設や賃貸契約、創業融資の申請を行うときに必要です。ただし、金融機関によっては、発行日から3か月以内のものでないと受付してもらえない場合があるので、発行と手続きのタイミングはできる限り合わせたほうがよいでしょう。
 税務関連の手続き
税務関連の手続き
会社を設立するとそれに伴い、様々な税金がかかることになります。会社設立後は必要書類を会社の所在地を管轄する税務署に提出します。どこの税務署が管轄なのかは国税庁のサイトから調べられます。
提出する書類は以下です。
法人設立届出書
設立から2ヶ月以内に提出してください。この書類には、法人番号を記載しなければなりません。法人番号とは、設立登記後に国税庁から郵送される「法人番号通知書」にて確認しましょう。
・国税庁:法人設立届出書
・国税庁:新しく法人の設立登記をされた方へ
消費税課税事業者届出書
会社を展開していく上で、消費税関係の届出書の提出も必要です。その中でも「消費税課税事業者届出書」は、基準期間等の課税売上が1,000万円を超えた時、すみやかに提出しなければなりません。
消費税に関係する届出書は「消費税課税事業者届出書」だけでなく、「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」や「消費税簡易課税制度選択届出書」、「適格請求書発行事業者の登録申請手続」、「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」などがあるので、法人によって必要な届出や手続きが異なります。先述した届出書が必要な条件は以下の通りです。
| 手続きや申告内容 | 条件 |
| 消費税課税事業者届出書 | 基準期間内の課税売上が1,000万円超 |
| 消費税の新設法人に該当する旨の届出書 | 消費税の新設法人に該当することになった場合 |
| 消費税簡易課税制度選択届出書 | 簡易課税制度を選択しようとするとき |
| 適格請求書発行事業者の登録申請手続 | 適格請求書発行事業者の登録を受けようとしている場合 |
| 任意の中間申告書を提出する旨の届出書 | 任意の中間申告制度を適用しようとするとき |
どのような事業を行うとしても、消費税は必ずかかわってくるので自社がどこまで該当するのかを確認しながら手続きを行ったり、届出書の提出を行ったりする必要があります。
インボイス制度が導入されたことで、基準期間内の課税売上が1,000万円に達していなくても、取引先との関係性のために課税事業者になるケースも少なくありません。
消費税に関する手続きは、タイミングを間違うと確定申告に大きく影響を及ぼす恐れがあるので、専門家に相談しながら手続きの要否などを確認しながら進めましょう。
関連記事:【保存版】インボイス制度の申請方法・手順について分かりやすく解説
給与支払事務所等の開設届出書
給与支払いがある場合、事務所などの開設後1ケ月以内に提出してください。もし、1人社長の場合でも自分自身に役員報酬を支払う場合には提出が必要となります。
提出期限は会社の設立後1か月以内とされていますが、期限を超過して提出しても罰則などはありません。ただし、届出を忘れてしまうと所得税の納付書を発行してもらえないため、結果的に追尾課税になってしまいます。また、期限までに届出を提出して所得税の納付書の発行ができたとしても、納付期限を過ぎてからの納付には不納付加算税というペナルティが課せられます。
仮に設立した時点では無くても、将来的に支払う可能性のある場合には初めに提出しておくことをおすすめします。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
こちらの書類は任意です。期限の定めはありません。この申請書は、常時雇用する従業員が10人未満の事業者が対象となっており、給与などから源泉徴収した所得税の納付を年2回にまとめて納付することが認められます。この制度は「納期の特例」と呼ばれており、常時雇用する従業員が10人以上になると条件を満たせずに、原則通り、支払月の翌月10日に納付します。
納期の特例の適用を受けたい場合は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を適用を受けたい月の前月までに税務署へ提出しなければなりません。この月から適用したいと明確に決まっている方は、申請書の提出するタイミングに気を付けましょう。
青色申告の承認申請書
こちらの書類は任意です。会社設立後3ヶ月を経過した日の前日、第1期の事業年度終了日の前日のいずれか早い日に提出しましょう。青色申告は白色申告よりも節税効果が高いため、節税対策を徹底したい意向の方にはおすすめです。また、法人の場合は、赤字繰越の期間が最長10年とされているので、さらに税制優遇が受けられます。ただし、注意が必要なのは、その税制優遇を受けるには条件をクリアしなければなりません。赤字繰越の制度を適用するには、期限内に確定申告を行い、毎期継続して申告書に記載することが条件となっているので、忘れずに行いましょう。
上記のように税制優遇を受けるためには、青色申告の承認申請書の提出が必須です。青色申告を設立の1期目から受けたい場合には、最初の段階で一緒に提出しておくようにしましょう。
国税庁:青色申告の承認申請書
また、都道府県税事務所及び市町村役場に設立後おおむね1ヶ月以内に法人設立届出書をそれぞれ提出します。こちらは法人住民税、法人事業税に関する手続きとなります。税務署への手続きとは異なり、非営利型の一般社団法人であってもこの届出書の提出は必要となります。期限など厳密には各自治体によっても異なるため、それぞれのホームページなどで確認をしてみて下さい!
 社会保険関係の手続き
社会保険関係の手続き
会社を設立すると健康保険や厚生年金保険といった社会保険に加入するため、そのための手続き等も必要になります。もし仮に1人社長であった場合にも、社会保険へは原則加入する義務があります。
年金事務所へ以下の書類を提出します。
健康保険・厚生年金保険新規適用届
加入する日から5日以内に提出してください。「健康保険・厚生年金保険新規適用届」は社会保険に加入すべき事業者が提出すべき届出です。事業所としての申請になるため、登記事項証明書や法人番号指定通知書などの書類が必要になります。法人番号指定通知書が手元にない場合や紛失してしまった場合は、国税庁の法人番号公表サイトで法人名や所在地などから検索することが可能なので、その画面を印刷して提出しましょう。
日本年金機構:健康保険・厚生年金保険新規適用届
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
加入する日から5日以内に提出してください。
従業員が仮に年金受給者であったとしても、加入条件を満たしている場合には届出をする必要があります。また、60歳以上の方が退職後1日の間もなく再雇用された場合、公民健康保険組合に引き続き加入し一定の要件に該当する場合などは別途添付の書類が必要となりますので事前に確認しておきましょう。
健康保険被扶養者(異動)届
被保険者に扶養する者がいる場合、すみやかに提出しましょう。
また、被扶養者の追加、削除、氏名変更などがあった場合も事実が発生してから被保険者が事業主を経由して申請が必要となる書類です。戸籍謄本及び年収130万円未満を証明する書類の添付が必須となります。また、被保険者と別居している被扶養者や、被保険者と内縁関係の被扶養者の場合は別途添付書類が必要となります。
日本年金機構:被扶養者(異動)届
国民年金第3号被保険者資格取得届
被保険者に被扶養配偶者がいる場合、すみやかに提出しましょう。
 労働保険関係の手続き
労働保険関係の手続き
従業員を雇うとなった場合には労災保険と雇用保険の加入手続きが必要となります。労働基準監督署とハローワークそれぞれに提出するものがあります。
労働基準監督署に提出するもの
時間外労働及び休日労働に関する協定届
従業員に時間外労働させる場合、時間外労働をさせる前までに提出しましょう。
労働保険関係成立届
従業員を雇用する場合、10日以内に提出してください。
ダウンロードは不可のため、管轄する労働基準監督署かハローワークから郵送してもらうか取りに行くなどして入手する必要があります。
厚生労働省:保険関係成立届 記入見本
労働保険概算保険料申告書
従業員を雇用するようになった場合、50日以内に提出してください。
従業員を雇用した場合、その年度分の労働保険料として申告・納付する必要があります。年度の末日までに労働者に支払う総額賃金の見込み額に保険料率を乗じて得た額が概算保険料となります。ただ、賃金総額は年度末にならないと確定しないので、翌年度の納付時に確定した賃金総額に基づいて保険料を確定し、過不足分を清算するという流れになります。
厚生労働省:概算保険料申告書 記入見本
就業規則(変更)届
従業員が10名以上になって、新たに就業規則を作成した場合に提出します。会社を設立した段階で従業員が10名以上の場合には併せて提出しておくことをおすすめします。
東京労働局:就業規則(変更)届
適用事業報告
従業員を雇用する場合、雇用してから速やかに提出してください。
ハローワークに提出するもの
雇用保険適用事業所設置届
雇用保険に加入する従業員を使用するようになった場合、10日以内に提出ください。
ハローワーク インターネットサービス:雇用保険適用事業所設置届
雇用保険被保険者資格取得届
雇用保険に加入する従業員を使用するようになった場合、翌月10日までに提出してください。
ハローワーク インターネットサービス:雇用保険 被保険者資格取得届
以上がそれぞれの書類と提出先となります。
ご覧いただいてもわかる通り、各種書類も多く、提出先も様々となります。
漏れのないように事前にしっかりと作成、準備することが必要となります。
 法人口座を開設する
法人口座を開設する
また、このタイミングで行っておいた方が良いのが法人口座を開設することです。
法人口座とは、個人で使用する口座とは異なり、金融機関の口座名義が会社名になっています。法人口座の開設自体は任意であり、個人口座を使用して事業の取引を行っても法的には問題はありません。しかし、税務処理を正しく行うためには法人口座の方が望ましいと言えるでしょう。また、社会的信用度の面から見ても、融資の際など法人口座の方が有利です。
会社を設立した段階で、併せて法人口座も早めに開設しておくことを推奨しています。
その他必要な手続きや準備すべきもの
会社を設立して税務署や年金事務所、労働基準監督署などへの必要な手続きを済ませた後は、それぞれの会社で必要な手続きを行います。この手続きに関しては任意なので、会社の方針を確認して必要であれば、手続きしましょう。
許認可申請の手続き
行う事業によっては、許認可が必要になるものがあります。
例えば、飲食業や建設業、運送業、介護事業などが挙げられますが、この他にも許認可が必要な業種はあります。業種によって申請先も異なり、都道府県や保健所、運輸局などへ申請が必要です。
許認可申請を怠ると、営業停止や刑事罰などのペナルティが課せられ、社会的な信用失墜にもつながるので、自社の事業について許認可が必要かどうかは事前に確認しましょう。
関連記事:【会社設立】建設業で法人化をするには?必要な許可や注意点を徹底解説
会社の電話番号やドメインの取得
法人として運営を行うには、問い合わせの電話番号や取引先とやり取りをするためのメールアドレスを取得することをおすすめします。
メールアドレスに関しては、フリーメールのドメインも使用できますが、社会的信用に欠けるため、会社独自のドメインを取得したほうが良いでしょう。また、会社のホームページなども作成する予定があれば、あわせて独自のドメインを取得しておくと信用は向上します。
法人のクレジットカードを作成する
会社設立時に法人用のクレジットカードを作成しておくと、経費の管理がしやすくなります。会社の設備や備品などを購入する際にクレジットカード決済をすれば、個人の支払いと法人の支払いを分けて管理できます。
クレジットカードだと過去の利用履歴が確認できるため、明細を確認したい場合でも柔軟に対応が可能です。
備品の準備やパンフレットなどの作成
オフィスで作業するための机やいすの準備、外部へアピールするためのパンフレットの作成などを行います。
従業員に貸与するためのパソコンや携帯電話の準備やコピー機など、細部に至るまでさまざまな備品の準備が必要です。準備するものや必要な個数などを事前にピックアップしておくとかかる費用も把握しやすいです。
また、会社の事業内容や提供する商品・サービスについて説明するためのパンフレットなどの作成も必要であれば行います。営業活動で必要になるものであれば、デザインなども検討を重ねる必要があります。
会計環境の整備
会計環境を整備するために会計ソフトの導入を検討しましょう。会計処理は煩雑な作業が多いため、作業の負担軽減には会計ソフトを導入して、作業の効率化を図ることも大切です。
特に青色申告の場合は、複式簿記での記録が必須のため、より複雑な作業が必要になります。
会計ソフトにもそれぞれの特徴や機能の違いがあるため、複数のソフトを比較して、自社に合ったソフトを選択しましょう。
わからないことは専門家に相談!
今回は、会社設立において、主に会社設立後の手続き等をご紹介しました。
会社設立は登記までだと思われがちですが、設立後の手続きまでしっかりと行うことがその後の事業を安心してスムーズに行うためには必要です。期日まで時間が短いものも多く、「混乱する」「作成自体が不安」といった場合には1人で溜め込まず、税理士や社労士など専門家にご相談ください!
当事務所でも会社設立後の会計業務についても対応しております!現在は無料にて相談お受けしておりますのでお気軽にご連絡ください。