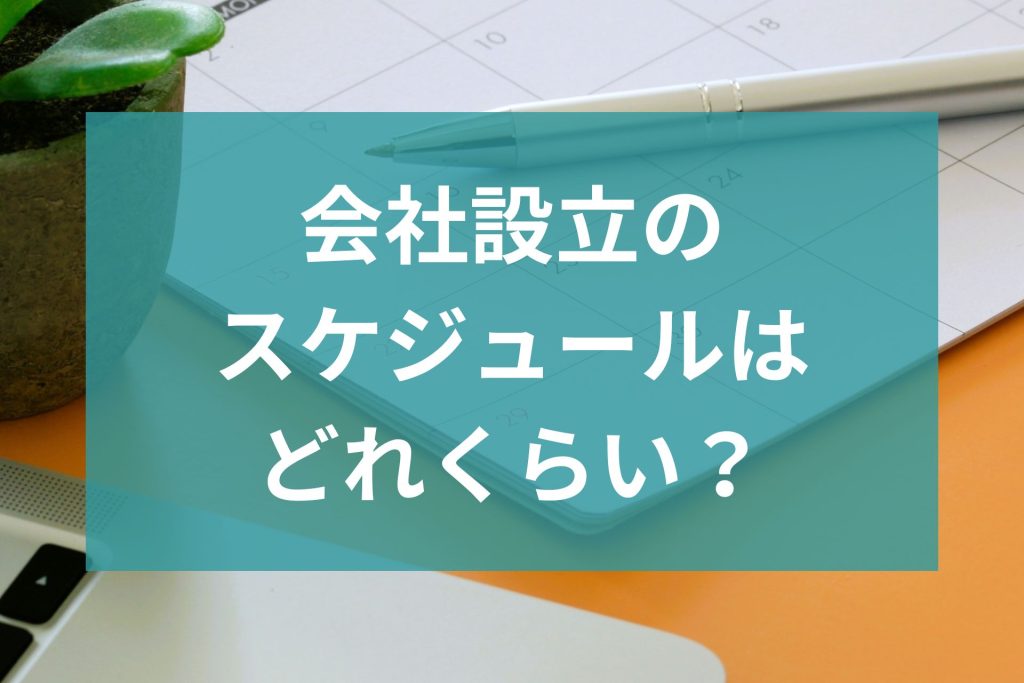
今回は、会社を設立する際の具体的なスケジュールをご紹介していきます!
自分で会社を設立したいけど、最短のスケジュールはどのくらいだろう。
流れがイマイチ分からなくて動きづらい。
まずは全体的なスケジュール感を知っておきたい。
こんなお悩みを持っている人はいませんか?
一言に「会社を設立しよう!」と思っても、全体の流れやスケジュール等の知識がないとそのための準備も始めにくいかと思います。
そんな方のために、この記事では会社設立におけるスケジュールや注意すべきことをご説明していきます。

関連記事:自分で会社を設立するには?費用や流れを詳しく解説‼︎
関連記事:【設立の流れ】合同会社に向いている業種は?手順やメリットを解説
関連記事:【まとめ】会社設立に必要なことリスト
Contents
会社設立の流れ:5Step
会社設立までにかかる日数としては、トータルでおおよそ1ヶ月程度になります。
まずは、全体的な流れや対応を大まかにご紹介していきますね。
①会社の概要を決める
実際の手続きを行う前に、決定しておくべき項目があります。
・会社名
株式会社の場合は前株か後株かなどその他にも名前をつける際のルールがいくつか存在します。例えば、ー(ハイフン)や&(アンド)、’(アポストロフィ)といった記号はアルファベットや数字の区切りとして使用することはできますが、商号の先頭や末尾に使用することはできません。ただし、.(ピリオド)は例外として末尾に使用できます。また、商号が既に存在している会社名と類似している場合は、商標権侵害で訴訟される恐れがあるので、事前に確認しておくことが重要です。商号を決めるにも多くのルールがあるので、検討する際にはしっかり確認しましょう。
・会社所在地
基本、自宅の住所でも問題はありませんが、法人口座を開設する審査のことを考えると会社専用の事務所をもっておくことをおすすめします。
最近では、本店の場所をシェアオフィスやレンタルオフィス、バーチャルオフィスなどにすることも多いですね。ただし、本店所在地は会社のブランドや信用に影響を及ぼす可能性があるので、長期的な利用を目的として慎重に検討する必要があります。
・事業の目的
事業目的は、後ほど紹介する定款に記載しなければなりません。会社を設立するにあたって何を事業とするのか「具体的」に記載します。また、もし後から事業目的を追加・変更となると手続きが煩雑化するため、今後、事業拡大などを考えている場合は始めのうちに記載しておくのが良いかと思います。
・資本金
資本金の額をいくらにするのかも事前に検討しておきましょう。基本的には1円からでも可能ですが、事業を初めて軌道に乗るまでは、売上が見込めなくても数ヶ月は事業が行えるくらいは用意しておくのがベターです。必要な具体的な金額は業種によっても様々ですので、事前に自分でリサーチしておくか、専門家などに相談して設定するのが良いかと思います。
・事業年度
法人の場合は、事業年度つまり会社の決算時期を自分で設定することができます。1年以内であれば特に指定されていないため、自由に決められます。
業種にもよりますが、自由に決められるので、会社の繁忙期となる時期を避けるのが今後のためにもおすすめです。
・株式譲渡の有無
株式譲渡の有無とは、株式を公開するかまたは非公開にするかを選択するということです。
設立したばかりの小さな会社などは、面識のない人が株主になることを避けるために譲渡制限をつけるのが一般的です。
・役員構成
現在、会社法が施行されてからは、設立する本人1人だけでも設立することが可能となっています。
以上が事前に検討しておくべき項目です。
これらを最初に決めておくと、会社設立の手続きもスムーズになりますので早めに検討しておくことがポイントです。
②法人用の実印の作成
会社設立には、印鑑証明書に登録する会社の印鑑(実印)が必要になってきます。
届け出や契約など、印鑑も用途に応じていくつか種類があります。
・代表者印(会社実印)
代表者印は、印鑑届出書を法務局に提出して登録します。これが会社の印鑑証明用の印鑑となります。
・銀行印
銀行印は、会社の銀行口座を開設する際に必要となる印鑑です。
・角印
角印とは請求書などに押印される際に最も使用される印鑑です。角印を作成せず、代表者印を使用しても問題ありませんが、リスクを考えると分けておいた方が無難かと思います。
・ゴム印
会社のゴム印とは事務作業をする上で効率化を考えて作成されるスタンプのことです。
引用:印鑑作成_アスクル
③定款を作成する
会社の定款とは、会社の事業目的や資本金など会社のルールが記載されたものとなります。
作成にかかる時間は、内容によっても様々ですが「おおよそ数時間」です。
【絶対的記載事項】
次の項目は必ず記載しなければなりません。
・事業の目的
・会社の名称
・会社の本社所在地
・資本金
・発起人の氏名と住所
見ていただくとわかる通り、①の内容とほとんどかぶっていますので、事前に検討しておくと作成もスムーズです。
【相対的記載事項】
これは「法的には記載しなくても問題ないものの、記載がないとその事項について効力が認められないもの」です。
変態設立事項(会社法28条)
設立時取締役及び取締役選任についての累積投票廃除(会社法89条、342条)
株主名簿管理人(会社法123条)
譲渡制限株式の指定買取人の指定を株主総会(取締役会設置会社にあっては取締役会)以外の者の権限とする定め(会社法140条5項)
相続人等に対する売渡請求(会社法174条)
単元株式数(会社法188条1項)
株券発行(会社法214条)
株主総会、取締役会及び監査役会招集通知期間短縮(会社法299条1項、368条1項、376条2項、392条1項)
取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人及び委員会の設置(会社法326条2項)
取締役、会計参与、監査役、執行役及び会計監査人の責任免除(会社法426条)
社外取締役、会計参与、社外監査役及び会計監査人の責任限定契約(会社法427条)
取締役会設置会社における中間配当の定め(会社法454条5項)
日本公証人連合会「定款認証」
【任意的記載事項】
任意的記載事項とは、上記の絶対的記載事項と相対的記載事項には該当せず、かつ違法性のない内容を記載する項目のことです。
具体的には以下の項目となります。
・株主総会の開催規定
・役員報酬に関する事項
・配当金に関する事項
定款の作成が完了したら、公証役場にて認証をうける必要があります。
必要な時間は「おおよそ30分〜1時間」です。
作成した定款のほかに実印、身分証明書など必要書類がありますので、漏れのないように用意しておきましょう。
④出資金を払い込む
定款の認証まで受けたら、個人の名義の口座から資本金を払い込みます。
資本金の払い込みが完了したら、登記申請を行うときに必要な払込証明書を作成します。払込証明書に記載が必要な項目は以下の通りです。

・払込をした日付
・会社名
・会社の所在地
・代表取締役の氏名
・設立時発行株式数(株式会社のみ)
また、払込証明書には添付する書類や作り方があります。その手順についても紹介します。
ⅰ表紙となる証明部分を作成する
上記の必要な記載項目を表紙に記載して、表紙となる証明書部分を作成します。用紙のサイズはA4が一般的であり、片面のみに収まるように文面や文字を調整して作成しましょう。
ⅱ払い込んだ通帳をコピーする
通帳の表紙・裏表紙のコピー(開いた状態で表と裏を同時にコピーも可)と資本金が振り込まれたことがわかるページのコピーが必要です。振り込みをすると振り込みをした相手の名前と金額が印字されるため、マーカーなどを引いて分かりやすくするとより良いでしょう。
⑤登記申請書類を作成し、法務局へ申請する
登記に必要な申請書類を作成して、法務局へ提出します。法務省の登記・供託オンライン申請システムの「登記ねっと」からオンラインで法人登記をすることもできるので、法務局へ行く時間がない方は、ぜひ活用してください。
特に不備がない場合には「7日〜10日程度」で登記が完了します。
登記申請書は、こちらの法務局のサイトからダウンロードすることが可能です。漏れのないように必要事項を記載していきましょう。その他必要な書類がいくつかありますので、こちらについても事前に確認しておきましょう。

・登記申請書
・定款
・代表取締役の就任承諾書
・取締役の就任承諾書
・監査役の就任承諾書
・発起人の決定書
・資本金の払込証明書
・印鑑届出書
・登録免許税納付用台紙
・登記すべき事項を記録した書面、もしくは保存したCDーR
また、会社の設立年月日は登録申請を行った日付(法務局で受付してもらった日付)になるので、思い入れのある日付にしたい場合は不備のないように書類を準備することが大切です。
設立後にすべきこと
登記が完了すると「会社設立」ということになりますが、実際に取引を開始するには他にもいくつか行うべきことがあります。
・印鑑証明書の取得
会社設立の手続きを行う段階で、実印の作成と同時に実印を登録しておくと印鑑証明書の取得がスムーズです。
印鑑証明書は法人の銀行口座開設の際に必要な書類になる場合がほとんどなので、口座開設前に準備しておくと良いでしょう。ただし、印鑑証明書は発行した年月日から6か月以内が有効期限とされているため、日付を開けて口座開設する場合には注意が必要です。
・会社の銀行口座の開設
取引を行うには法人口座が必要になります。現在はマネーロンダリングの観点から、口座開設を行う際のハードルが高くなっており、必要書類の作成や審査などの期間も含めると「おおよそ2週間〜1ヶ月程度」は見ておいた方か良いかもしれません。

・会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
・会社の実印
・会社の印鑑証明書
・代表者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
・営業許可証(必要な業種のみ)
また、基本的には上記のように必要書類の準備が必要ですが、金融機関や会社が行う業種によって書類が増減する可能性もあるので、金融機関窓口や専門家に相談しながら進めたほうがスムーズです。
・税金に関する手続き
個人と同様に法人にも、法人住民税や法人住民税、消費税などを納めなければなりません。そのため、法人として会社を設立したことを知らせるための「法人設立の届出」を会社の所在地を管轄している税務署・地方自治体・県税事務所へ提出する必要があります。
税務署へ手続きを行う際には、「青色申告承認申請書」や「消費税に関する各種届出」、「適格請求書発行事業者の登録申請書」などの手続きも併せて行うと手間が省けます。専門家に相談しながら、まとめて行える手続きは一度で済ませてしまいましょう。
・社会保険の手続き
会社設立後には、年金事務所や労働基準監督署、ハローワークなどで各種保険に関する手続きを行います。保険に関する手続きを行わないと法律に違反する恐れがあるので、忘れずに手続きしましょう。
年金事務所には、「健康保険・厚生年金保険新規適用届」「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」「健康保険被扶養者異動届」を提出します。この届出は、代表者1人の場合でも必ず行わなければならないので、注意しましょう。
また、従業員を雇う場合には労災保険と雇用保険への加入が必要です。労災保険の手続きは労働基準監督署、雇用保険の手続きはハローワークで行います。それぞれ手続きを行う場所が異なるので、申請書類と申請場所は事前に確認しましょう。
| 場所 | 必要書類 |
| 会社の所在地を管轄している労働基準監督署 | ・労働保険関係成立届 ・労働保険概算保険料申告書 ・適用事業報告書 |
| 会社の所在地を管轄しているハローワーク | ・雇用保険被保険者資格取得届 ・雇用保険適用事業所設置届 |
・営業許可の申請手続き
業種によって事業を行うために許認可が必要になるケースがあるため、申請手続きの準備をしましょう。許認可が必要な業種は以下の通りです。
| サービス業 | ・飲食店業 ・喫茶店営業 ・一般旅行業・代理店業 ・国内旅行業・代理店業 ・旅館業 ・政府登録旅館 ・政府登録ホテル ・美容業 ・理容所 ・病院 ・診療所 ・動物病院 ・産業廃棄物処理業 ・一般労働者派遣事業 ・特定労働者派遣事業 ・質屋営業 ・風俗営業 |
| 建設業 | ・建設業 ・電気工事業 |
| 製造業 | ・食品製造業 ・食肉処理業 ・食肉製品製造業 ・乳製品製造業 ・菓子製造業 ・医薬品等製造業 |
| 物品販売業 | ・酒類販売業 ・たばこ小売販売業 ・米穀販売業 ・食肉販売業 ・魚介類販売業 ・生菓子販売業 ・アイスクリーム類販売業 ・薬局 ・動物取扱業 ・古物営業 |
| 不動産業 | ・宅地建物取引業 |
許認可を申請する窓口は、都道府県や税務署、保健所などがあり、業種によって申請先が異なります。さらに一定の基準を満たしていれば許認可を取得できる場合もありますが、試験や審査を通過しないと許認可が取得できず、事業を始められない可能性もあります。そのようなリスクを避けるためにも、事前に事業に関する必要書類などを準備しておくことが重要です。
会社設立を迷っている方へ
これまで会社を設立するための流れを書いていきましたが、
「会社設立したいなとは思うけど一歩が踏み出せない・・」
そう思っている方もいると思います。
そんな方へ会社を設立するメリットもお伝えしておきますね。
・節税対策の面でメリットが大きい
・社会的な信用度が大きい
・決算月を自分で自由に決めることができる
自分で事業を始めようとするとき、個人事業主として開業をするのか、または会社を設立して起業するかのどちらかを選ぶことになりますが、法人の場合は主に上記のようなメリットが挙げられます。
会社設立を急ぐとトラブルの原因に!
これから会社設立をしようとする人の中には、仕事の都合上や補助金・助成金制度の兼ね合いで出来るだけ早く手続きを終わらせたい方もいるかもしれません。
実際、会社を設立するには3〜4日が最短とされています。手続きを急ぐあまり、書面の内容に目を通し切れていないケースもあり、事業を始めた後にトラブルが発生する可能性があります。
どのようなトラブルがあるのかを紹介します。
 定款の抜け漏れ
定款の抜け漏れ
定款は会社の根本規則をまとめた書類で、「会社の憲法」と呼ばれることもあります。会社を設立するためには必須の書類ですが、この定款に抜け漏れがあるとさまざまな問題が起こるリスクがあります。
特に合同会社で設立する場合は、株式会社のように公証人による定款の認証は不要のため、設立後にトラブルが起こる可能性が大きくなりやすいです。合同会社の特徴は、出資者と経営者が同一で、出資額にかかわらず、社員全員が平等な議決権を持っていることです。意思決定が迅速で、経営の自由度が高いところが魅力的ですが、定款の抜け漏れがあると以下のようなトラブルが発生します。
・権利の譲渡や事業承継については社員全員の同意が必要になるので、スムーズに行えない
・会社の解散したときの財産分与の割合をどうするか
・社員の追加・退出についてどのように処理を行うのか
上記のようなトラブルが発生してしまうと、正常な経営ができなくなってしまうほか、相続や合併などに関する抜け漏れがあると最悪の場合、強制的に会社を解散させられてしまう可能性もあります。
そのため、意思決定や事業承継、相続、社員の権利などについて定款に記載しておく必要があります。例えば、意見が対立してしまいまとまらないときのために、「過半数の同意」があれば実行するなどの文言を記載すると、まとまらないときでも決着をつけることができます。
 資本金が不足している
資本金が不足している
資本金は1円以上であればいくらで設定しても問題ありませんが、深く考えずに設定してしまうと資本金が不足して、債務超過に陥る恐れがあります。
資本金は会社の運転資金なので、新しい設備や事業拡大をする際にまとまった資金が必要なときに使うケースがあります。その資金が不足していると、事業を続けることが困難になったり、会社の信用や評価が低くなったり、銀行から融資を受けられないという可能性があります。
業種によっては、一定額以上の資本金が会社設立の条件となる場合があるので、自分の業種は当てはまるのか確認しておきましょう。
[一定額以上の資本金が条件となる業種]
・旅行業:3,000万円以上
・人材派遣業:2,000万円以上
・一般建設業:500万円以上
・特定建設業:2,000万円以上 純資産の合計が4,000万円以上
上記のように一定の金額を設定するのは、事業の安定性や継続性を担保するためです。上記以外の業種は金額に定めはありませんが、300〜500万円が平均の金額とされています。設立後に資本金を変更することも可能ですが、登記の変更だけでなく、税務署や都道府県税事務所への手続きが必要になるため、時間と手間がかかります。会社設立の時点で専門家に相談してみると助言してもらえるかもしれません。
 決算月を短く設定した
決算月を短く設定した
法人は決算月を自由に決めることができますが、決算月を会社設立後すぐに設定してしまうと事業を開始して間もなく決算申告料が発生してしまいます。
そのため、会社を設立する時期や業種の繁忙月などを加味したうえで適切な決算月を設定することが望ましいです。一般的には、3月を決算月に設定している企業が多いので参考にしてください。
スムーズに会社設立をするために
スムーズに会社設立をするには、書類に不備がないことなどがとても重要になります。なるべく早く会社設立をしたい方は、これから紹介する要点を抑えておきましょう。
 発起人の実印と印鑑登録を済ませておく
発起人の実印と印鑑登録を済ませておく
発起人が実印を持っていない・印鑑登録をしていない場合も多いので、最短で終わらせられるようにするには、前もって発起人全員の実印と印鑑登録を済ませておきましょう。
実印を持っていないと、実印を購入して市町村の役所窓口で手続きを行う必要があるため、早くても1日〜2日くらいの時間がかかります。印鑑自体も100均のものでも問題ないですが、安全面から考えると専門店などから購入したほうが心配ないかもしれません。
 資本金を用意しておく
資本金を用意しておく
会社の信用度を上げるという意味でも資本金は事前に用意しておく必要があります。発起人のうちの1人がお金を用意できていなかったり、お金の借りられる目途が立っていなかったりすると会社設立自体も後ろ倒しになってしまいます。
お金は数日間のうちに用意できるものではないので、会社設立後の事業計画に基づいてどのくらいの資本金が必要になるかをシミュレーションしてじっくりと準備すると会社設立もスムーズに行うことができます。もし今すぐにでも会社を設立しなければならないという場合は、資本金を少なめに設定するという選択肢もあります。ただ、資本金を少なく設定することで、前述したように資本金が不足したり、法人の銀行口座が作りづらくなるというデメリットもあることは認識しておきましょう。
 専門家に依頼する
専門家に依頼する
コスト削減のために会社設立を自力で行おうとする方も多いですが、専門知識や複雑な手続きが必要になるので、専門家に依頼するとスムーズに安心して任せることができます。
会社設立は、定款や登記申請書、就任承諾書など多くの書類の作成が必要です。定款については会社の根本規則にかかわる重要な書類なので、知識がない素人の方が作成するのはなかなか厳しいです。もし作成できたとしても、書類が不足していたり、内容に不備があったりすると差し戻されるため、再度書類の精査や内容の見直しなどをしなくてはなりません。
また、手続きを行う場所は市町村の役所窓口や税務署、都道府県税事務所など多くの場所に行く必要もあるため、時間がない方は特に専門家に依頼することをおすすめします。
会社設立は計画的に!
今回は、会社設立における流れとスケジュールについてご紹介してまいりました。
副業としてビジネスをする方も多くなり、それが軌道に乗ってくると自ずと今後どうしようか考える場面が出てくるかと思います。
本記事でご覧いただいた流れを頭に入れておけば、準備に置いてバタバタすることも少なくなるはずです。経営する上では、やるべきことが山積みです。少しでもスムーズに事業が開始できるように準備は前もって計画的に進めるようにしましょう!
当事務所は、会社設立に関するサポートも幅広く行っています。何から始めたら良いのか分からないといった方でもまずはお気軽にご相談ください!お待ちしております。
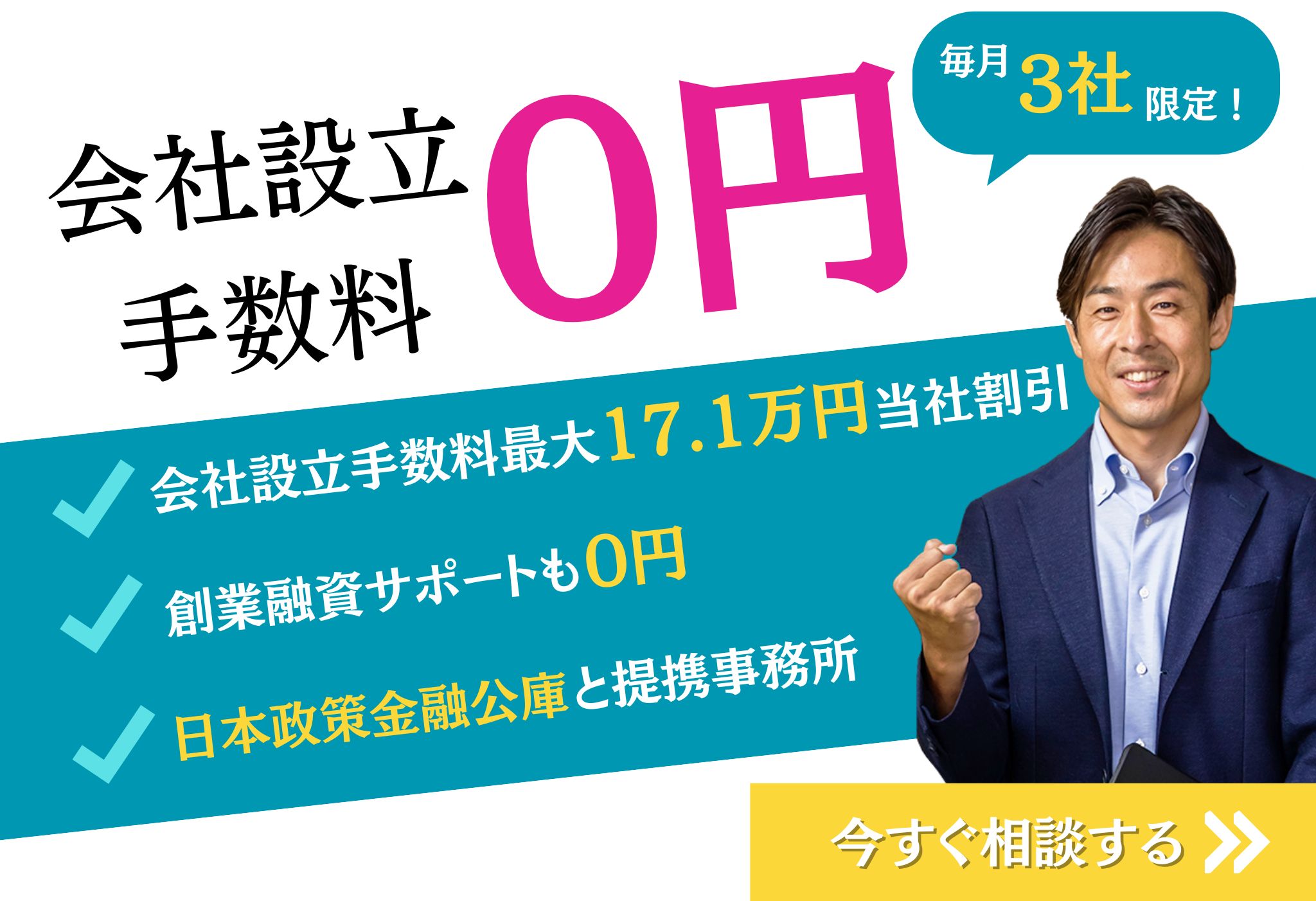
関連記事:【会社設立】方法や手続きの流れを解説
関連記事:不動産会社設立の流れとポイントを解説!
関連記事:会社設立が相続税対策に有効?メリットとデメリットを解説



