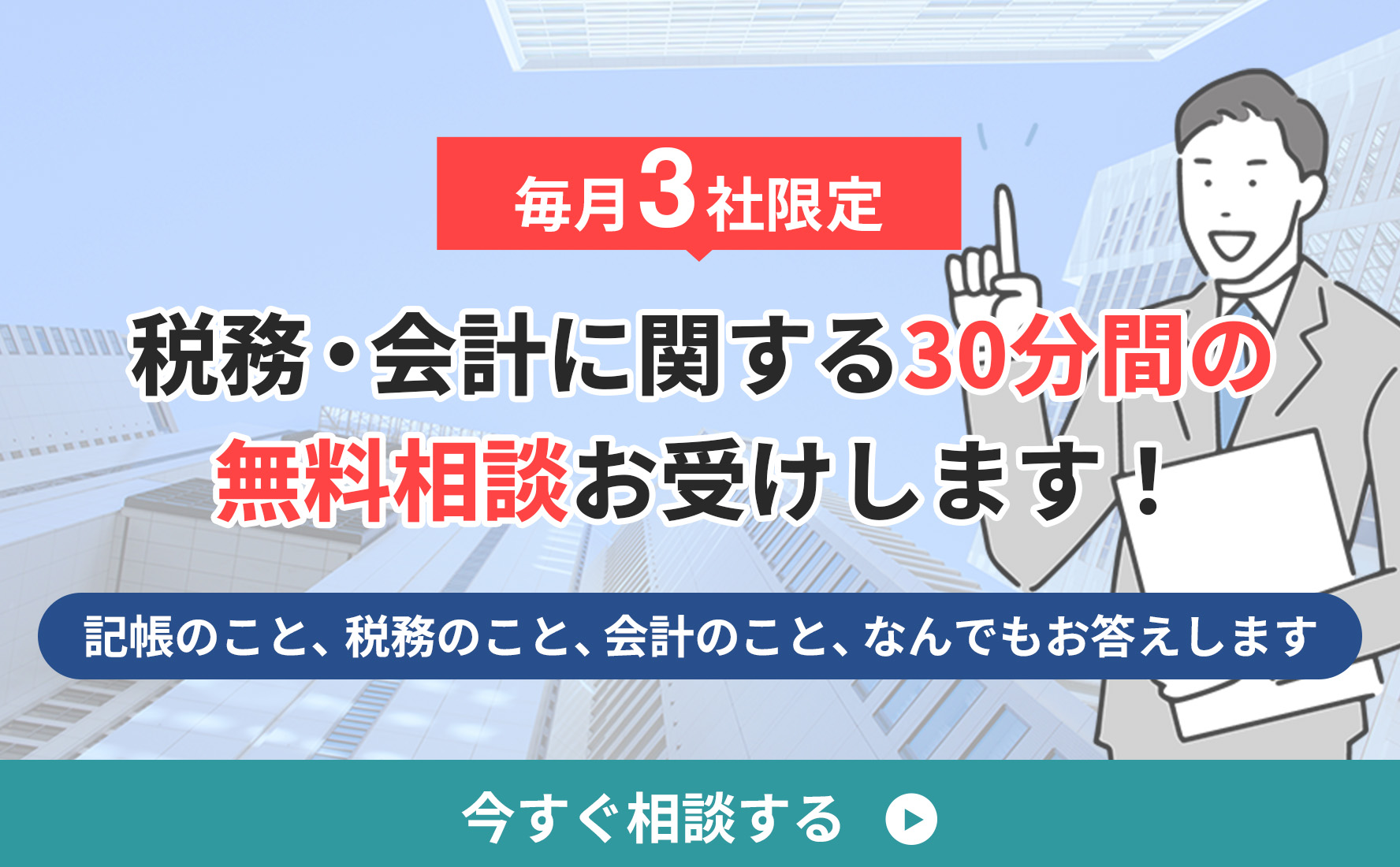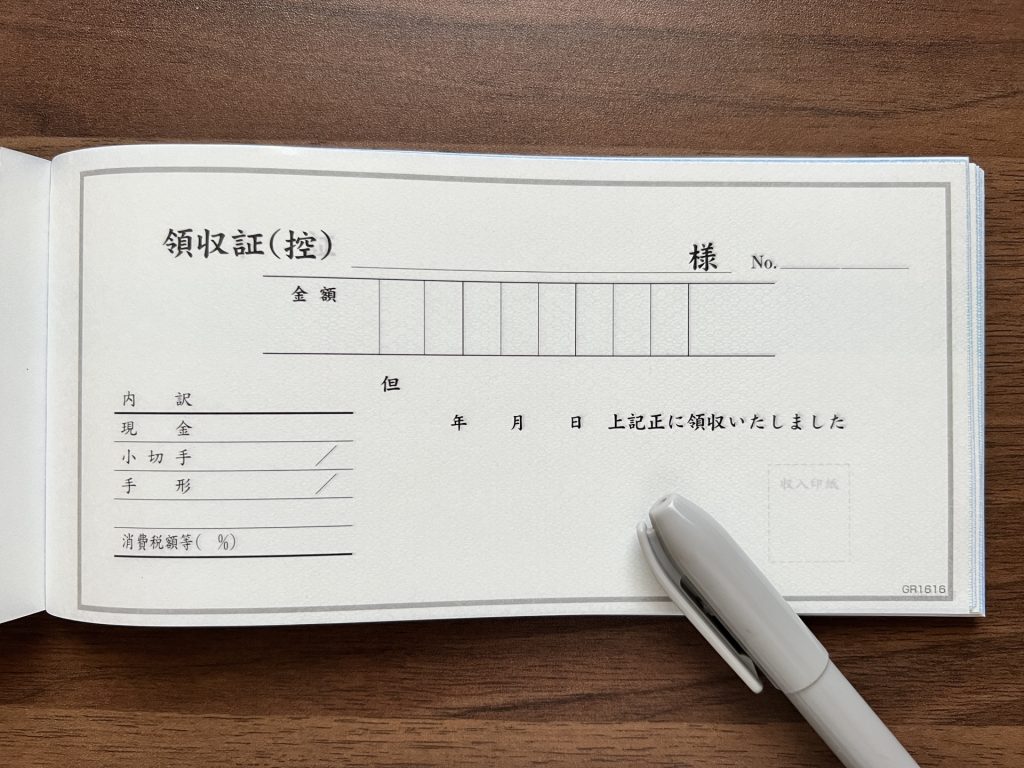
毎年、確定申告で頭を悩ませている個人事業主の方は多いのではないでしょうか。
個人事業主が節税を考えるにあたって、「どの支払いが経費として判断できるの?」「経費の上限はあるの?」といった疑問がある方が出てくるはずです。
「経費」という言葉は聞くけれどあまり馴染みがない方がほとんどでしょう。
本記事では、経費に計上できるもの・できないものや経費の上限、経費にできる判断基準について詳細を解説していくので、是非参考にしてください。

Contents
経費とは事業を行う上で必要な費用のこと
経費とは、所得を得るために必要な事業運営に関する支出のことを指します。実際に国税庁が示している経費として計上できる基準は以下の通りです。
事業所得、不動産所得および雑所得の金額を計算するうえで、必要経費として算入できる金額は、次の金額です。
(2)その年に応じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
経費として一般的に計上できるのは、事業に関する支出のため、自身のプライベートに関する支出は経費計上することはできません。
個人事業主などの場合は、自宅やフリースペースで仕事をすることが多いため、事業に関する支出とプライベートに関する支出を明確に分けることが難しいと感じる方が多いのではないでしょうか。
事業費用に関する経費計上は、節税効果にも影響するため、これから事業を始める初心者の方は正しい知識を身につけて適正な申請を行いましょう。
関連記事:個人事業主が毎月やるべき経理業務とは?行う理由についても理解しよう
経費計上のメリット・デメリット!
個人事業主は、企業とは異なり、資金調達から営業、総務、経理などの全てに関する知識が必須になります。その中でも、経費に関しては、自身の生計にも影響が大きいため、メリット・デメリットをしっかり理解したうえで申請を行いましょう。

メリット
個人事業主が経費計上するメリットは、「税金の納付金額を抑えることができる点」です。
事業主は、売上から経費を差し引いた所得金額によって、支払う税金の金額が決められます。事業の利益が増加していくと、比例して税金が高くなります。経費計上を行うことで、納税金額が少なくなるため、手取りの金額が多くなります。

デメリット
経費を計上をすることで、「事務負担の増加」が発生するデメリットがあります。経費を申請する際に、支払った金額や勘定項目を証拠となる書類と相違がないように整理して管理するのは、とても負担がかかるためデメリットと言えるでしょう。現在はデータで管理している場合もありますが、経費計上をしていいかチェックを行う必要があるため、データ上でもチェックしやすい体制を調える必要があります。
また、「税務調査の可能性」が考えられます。経費計上の際に正しい申請が行われていない場合、脱税行為が疑われ、税務署からの調査が入る可能性があります。帳簿に正しく記載して、証拠等も合わせて適切な管理を行いましょう。
また、経費を過剰に申請してしまうと黒字収支で締められなくなり、銀行から融資できる金額が減少するので、注意が必要です。
【一覧】経費計上できるものを紹介
経費は勘定科目に分けて、年間を通して帳簿などに記載して管理を行い、確定申告を行います。勘定科目とは、経費の取引内容を分かりやすくするために設定された項目のことです。
経費として計上できる勘定科目と具体例は以下の一覧の通りです。
|
勘定科目 |
概要 | 具体例 |
|
租税公課 |
税金や公的な負担金 | 個人事業税、事業利用の固定資産税、自動車税、登録免許税、印紙税 |
|
荷造運賃 |
荷物の運賃や梱包費用 | 運送料や段ボールやガムテープなどの梱包資材代 |
|
水道光熱費 |
電気代・ガス代・水道代 | 電気代、ガス代、水道代、灯油代 |
|
旅費交通費 |
移動費用、宿泊費用 | 交通費、宿泊費、コインパーキング代 |
|
通信費 |
郵便代、電話料金インターネット料金 | 切手代やはがき代、電話料金、インターネットの使用料 |
|
広告宣伝費 |
事業や商品に関する広告費用 | Webサイトなどの広告掲載料、ポスターやチラシ、カタログなどの印刷費 |
|
接待交際費 |
取引先への接待や贈答品にかかる費用 | 取引先への接待にかかる飲食代(外食)や贈答品代、慶弔費 |
|
損害保険料 |
事故や火災などの損害保険料 | 事務所の火災保険料や事業用の自動車の保険料、自賠責保険料 |
|
修繕費 |
物件や機械などの修理代 | 店舗や機械、設備などの修理代 |
|
消耗品費 |
取得価額が10万円未満か使用可能期間(法定耐用年数)が1年未満の消耗品 |
文房具や伝票、名刺、デスク、10万円未満のパソコンなど |
|
減価償却費 |
10万円以上かつ1年以上使用可能な固定資産を法定耐用年数に従って分割して計上する費用 |
建物や自動車、コピー機、デスク、オフィスチェア |
|
福利厚生費 |
医療、保険などのための費用 |
従業員の健康診断や慰安旅行にかかる費用、慶弔費 |
|
給料賃金 |
従業員への給与 | 従業員に支払う給与や手当、賞与 |
|
外注工費 |
外部に委託した支出費用 | 外部に業務を発注した際にかかる費用 |
|
支払利息 |
借り入れの支払利息 | 借入金の利息や手形の割引料 |
|
地代家賃 |
事務所やオフィスなどの家賃や使用料 | 建物の家賃や礼金、駐車場代 |
|
貸倒損失 |
取引先の倒産などによって回収不能になった損害金額 |
未回収の売掛金や貸付金、未収入金 |
|
雑費 |
ほかの経費にあてはまらないもの |
事業に関する書籍代、制服などのクリーニング代、年会費などの上記のいずれにも該当しない費用 |
上記勘定科目に沿って、帳簿に記載することが一般的です。
しかし、勘定科目は法律などで厳密に定められているわけではないため、事業内容によって必要な勘定科目を自由に追加することが可能です。
勘定科目を追加することで、取引内容によって勘定科目を分けることで、管理がしやすくなります。
一方で、勘定科目を増やし過ぎてしまうと、どの勘定科目にどのような経費が該当するかわからなくなってしまうため、闇雲に増やすことはおすすめしません。
「計上は毎年決まった勘定科目で行わなければいけない」という決まりがあるため、当初に決めた勘定科目と別の項目に入れることはできません。
そのため、起業をしたのちに勘定科目を追加するときは、取引内容や経費計上できる費用を明確にしたうえで科目ごとに分類しましょう。
関連記事:青色申告で経費にできる項目は?勘定科目で認められる内容について
経費にできないものを知っておこう
事業に関しての支出は経費として計上することができるので、個人事業主としては少しでも経費計上を行い、節税効果を高めたいところです。
しかし、原則として事業に関係のないプライベートでの購入品は経費として計上することはできません。
経費として計上できない例をいくつか挙げてみましょう。
・個人事業主個人の税金・資産
経費にできるものとして、租税公課を挙げましたが、個人事業主自身の所得税や住民税は経費計上することができません。所得税や住民税などは個人に課せられる税金になるため、事業に関する費用として認められません。誤って計上しないようにしっかり覚えておきましょう。
また、事業主個人が所有している10万円以上のパソコンなどは経費ではなく、固定資産として計上されます。その上、固定資産は耐用年数に応じて減価償却費として計上されるので、金額が大きいものや耐用年数に関しては事前に税理士に相談して、検討しましょう。
・個人の福利厚生費
従業員の福利厚生費は経費として計上することができますが、個人事業主自身の医療費や健康診断、人間ドッグなどの福利厚生費は、計上することができません。従業員の福利厚生費が経費計上できるからと言って、誤って計上してしまわないように注意が必要です。
・家族や親族に対する支払い
事業主と生計をともにしている家族や親族は、家計が同一と認識されるため、給与の支払いをしていても経費として計上することができません。
・私的な飲食代や買い物
私生活における飲食代や書籍代、衣服の購入代、交通費など明らかに事業とは関係ないものは経費として扱うことができません。
出張に行った際の会食や交通費などは経費として扱うことができますが、プライベートとの線引きが必要です。
私的な出費を経費計上してしまうと、ペナルティが課せられる等の税務上のトラブルが発生するため、注意が必要です。
経費として判断が難しいものは税理士に確認!
個人事業主の出費の中では、支払い内容ではなく、状況によって経費になるもの・ならないものがあります。
経費にできるかどうかは「事業を行う上で発生する費用であるか」「個人に関する支出ではないか」という点に着目して判断するようにしましょう。また、税務調査が行われた際に後ろめたい気持ちにならず、経費として計上した正当な理由を伝えることができるかという点も重要な判断材料になります。
経費として判断が難しいものに関しては、いい加減な申告をするのではなく、専門家に相談して判断を仰ぎましょう。
関連記事:腕時計は経費で買える?購入した場合の計上方法や注意点
関連記事:犬や猫などペットの購入・飼育費用は経費として計上できる?条件や注意点を解説
経費計上に必要なものを把握しよう
事業を行っている中で発生した支出を経費として計上する時には、経費計上できることを証明するための証拠となる書類が必要です。
明確に経費として証明できない内容に関しては経費として申告することができません。申告できない内容のものを誤って申告してしまった場合は、税務署から注意される可能性があるため、正確に記載しましょう。証拠書類として一般的なのは、領収書やレシートが挙げられます。
そのため、事業を経営する場合は、領収書やレシートを受け取り、保管するよう習慣づけましょう。
証拠書類に必要な項目
証拠書類として使用するためには以下の項目の記載が必要です。項目が埋められているかしっかりと確認するように心がけましょう。
・支払った金額
・但し書き(具体的な支出内容)
・支払いを受けた人の名前や会社名・所在地
・支払った日付
領収書以外で証拠書類となるもの
領収書を紛失した場合や慶弔など領収書が発行できない場合は、ほかの証拠書類で申告することが可能です。ネットで商品を購入することやチケットを予約する機会が増えているため、証拠となる書類は是非覚えておきましょう。
証拠となる書類の具体例は以下の通りです。
・クレジットカードの利用明細書
・ATMの振込明細や通帳の記録
・交通系ICカードの利用履歴
・インターネット通販の購入メールのプリントアウト
・祝儀袋や不祝儀袋の表書きのコピー
クレジットを活用した際に利用明細書などがメールで届くので、その利用明細書が領収書の代わりになります。また、取引先や仕入れ先に対して振り込みをした場合は、振り込みをした通帳の記録や請求書、納品書を一緒に管理しておくことで、証拠として申告することができます。
事業の支出とプライベートの支出の区別をつけるために、個人のクレジットカードと法人カードで分けて購入する方法もあるので、検討してみてください。
取引先へ移動する際に利用する交通系ICカードの場合は、利用履歴を印刷すれば交通費として申告することができます。交通系ICカードはプライベートでも利用する機会が多いため、仕事用と私用にそれぞれ分けておくと、分別する手間がなく申告手続きを行うことが可能です。
また、証拠書類は、確定申告が終わった後も保存期間が最長で7年と定められています。そのため、税務調査があった場合に、提出できるように年度ごとに保管しておくと、手間なく分かりやすいでしょう。
電子取引した場合の保存方法

請求書や納品書などもメールを使ってやり取りをする機会が増えてきたように感じます。そのきっかけは、2022年1月に「改正電子帳簿保存法」が施行されたことです。
「改正電子帳簿保存法」とは、請求書や領収書を電子データとして受け取った場合は、そのまま電子データとして保存しなければいけないという改正法です。この改正法は全ての事業者を対象としており、2024年1月1日以後の取引からは完全義務化となっています。
領収書や請求書、レシートなどを電子保存する場合は、そのまま保存するだけではなく、不正を未然に防ぐために、改変や削除をしないようなシステムを利用したり、適切な理由なく訂正や削除ができないように事務規定を作成するなど、電子データ保存の要件に則った保存や運用を行う必要があります。
しかし、全ての領収書などを電子データとして保存する必要はなく、最初から紙で受け取った場合は、2024年1月以降も書類として保存しても問題ありません。
紙の書類を電子データとして保存したいときは、一定の要件を満たすことで、電子保存を行えば、紙の領収書などの原本は破棄をすることが可能です。電子保存でまとめたい場合は、電子帳簿保存法のスキャナ保存の要件に沿った対応が必要になるので、電子保存にする際は、事前に確認を行い、不備がないようにしましょう。
法人と異なる「家事按分」という考え方
個人事業主は、自宅で仕事ができたり、勤務時間の拘束がない点がメリットです。一方で、仕事とプライベートの境目が曖昧になってしまい、経費計上の判断が難しいのがデメリットになります。
そこで個人事業主の方に覚えておいてほしい考え方が「家事按分」です。
自宅で仕事をしているため、仕事とプライベートのどちらでも使用する自宅兼事務所の家賃や光熱費などは一定の比率で区分して、経費として計上することが「家事按分」です。
家事按分は、法律などで明確に定められているわけではないので、税務署に説明を求められたときのために、家事按分の明確な根拠を説明できるようにすることが大切です。
家事按分できる費用
家事按分として認められるのは、事業に関わる費用として合理的に説明できる場合のみであり、具体的には以下の費用が該当します。
・家賃
自宅兼事務所として使用している家の家賃を家事按分する場合は、「住居の1部屋を仕事用として使用している」「ダイニングやリビングの一角を仕切って仕事用に割り当てている」という明確な事実が必要になります。
事業として使用している部屋や場所の範囲によって、経費計上できる金額が計算できます。
具体例
自宅の面積が100平方メートルだった場合、仕事で使用する面積を30平方メートルと仮定すると、按分率は30%となります。
家賃が月20万とすると、以下のような計算になり、経費計上ができる金額は6万円になります。
また、賃貸だけでなく、持ち家も経費計上できます。
持ち家の場合は、家賃ではなく、建物自体の減価償却費や住宅ローンの金利、固定資産税、火災保険などが対象です。住宅ローンの金利は、事業用の家事按分が2分の1を超えると、住宅ローンの控除適用外になるので、注意が必要です。
関連記事:個人事業主が知っておくべき家賃の経費計上方法と按分割合の決め方
・水道光熱費
水道光熱費も家賃同様、事業として使用する面積または業務時間で按分するのが一般的です。
行う事業によって異なりますが、わかりやすいのは電気代です。
業務上、常にパソコンを使用する場合は、1日8時間使用すると電気代の3分の1を経費として計上することができます。
ガスや水道に関しては、飲食業などの業務で多用する場合以外は、家事按分としては該当しないのが一般的です。
・通信費
携帯電話の料金やインターネット回線の契約料金などは、事業を経営するうえで必要不可欠であると言えます。
経費計上をしやすくするために、業務用とプライベート用に分けて、携帯などを使用することが理想ですが、法人などではなく、個人事業主になるとそこまで手間をかけるのは難しいと考える方が多いでしょう。
明確に分けることが難しい場合は、通話履歴や使用時間から、就業時間の使用時間とプライベートでの使用時間を比較して家事按分の割合を出す必要があります。
・自動車関係の費用
地域によっては、車での移動が必要になります。こちらも通信費同様、事業用とプライベート用を分けて所有するのが理想ですが、車の場合は金額などを考えても小規模事業者が多い個人事業主にとっては、現実的ではないことが分かります。
プライベートと業務での走行距離を計算して、家事按分の割合を決めましょう。
自動車関係の経費として、自動車の購入代金やガソリン代、車検代、自動車税、駐車場代などが挙げられます。
ガソリン代や駐車場代は、出先のガソリンスタンドやコインパーキングで発行されるレシートが証拠となるので、忘れずに保管しましょう。
自動車の購入代金は、ほかの代金と比較して金額が大きくなるため、資産計上を行い、減価償却で家事按分するのが一般的です。
関連記事:法人の経費で車を購入する方法!計上方法やポイントを解説
経費の上限は定められていません!
経費の上限額があるのか疑問に思う方も多いでしょう。結論から言うと、個人事業主の経費の上限は定められていません。
事業を経営するうえで必要なものに関しては、経費計上を行うことができます。ただし、上限がないからといって、必要以上の経費の申告は行わないようにしましょう。
節税効果を高めるポイント2つについて
個人事業主の最大のメリットは、節税効果の恩恵を受けることができるという点です。経費計上を行うことによって、所得金額を抑えることができ、税金の負担が軽減されます。
さらに節税効果を高めるポイントが、2つあります。
1つ目は「青色申告を行うこと」、2つ目は「税理士へ相談する」ことです。詳しい内容については、それぞれ解説していきます。
青色申告を行う
確定申告の際に、青色申告控除を行うことで節税効果を高めることができます。
確定申告は青色申告のほかに白色申告がありますが、この2つがどのように異なるのかを併せて説明していく。
①事前申請
青色申告は、3月15日までに所轄の税務署へ「青色申告承認申請書」と「開業届」の提出が必要になります。この書類を提出しないと、青色申告を行うことができません。
白色申告は必要な事前申請はないので、所轄の税務署へ届出を出さない場合は、自動的に白色申告になるので、青色申告で考えている人は提出する期限などに注意しましょう。
②帳簿の記帳方法の違い
白色申告は青色申告と比較して簡易的な申請になるため、1つの取引に応じて1つの記録を行うといった記帳方法になり、とても簡易的です。
青色申告は複雑になっており、65万円の特別控除を受ける場合は、複数簿記形式での記帳が必要になります。主な帳簿としては、「仕訳帳」と「元勘定元帳」を作成し、事業内容や取引状況に応じて、「売掛帳」や「買掛帳」といった簡易的な帳簿の作成も必要になる場合もあります。
③提出書類の違い
白色申告は、確定申告書と収支内訳書のみが提出書類になりますが、青色申告はその他にも提出すべき書類があります。
青色申告は、青色申告決算書や貸借対照表、損益計算書などの提出が必要になり、保存帳票なども多くなります。そのため、管理する手間が多くなりますが、その分節税効果があります。
④税制上の優遇措置の違い
白色申告は、基本的に税制上のメリットはありません。一方で、青色申告は最大65万円の控除を受けることができます。
控除を受ける場合は、複数簿記形式で記帳を行い、青色申告決算書や貸借対照表、損益計算書などを確定申告書に添付して期限内に提出することで55万円の青色申告控除を受けることができます。それに加えて、e-Taxなどの電子申告を行う場合または、優良な電子帳簿保存を行っている場合は、65万円の控除を受けることができるため、日々の経費や領収書などの管理などが重要になります。
そのほかにも青色申告専従者給与を必要経費にすることも可能です。配偶者や家族を従業員として働かせ、給与を支払う場合は、一般的には必要経費として処理を行うことができませんが、青色申告を行うことで、経費計上を行うことができます。
ただし、事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄の税務署に提出が必要になるので、忘れずに手続きを行いましょう。
インボイス制度とは
2023年10月からインボイス制度が施行されましたが、実際に内容を理解している人は少ないのではないでしょうか。
インボイス制度が導入された背景には、消費税の軽減税率の導入により、消費税率の正確な把握が困難になったことが挙げられます。
そのため、事業者が正しい消費税を収めるために適格請求書(インボイス)の発行を義務付けたのが、インボイス制度です。
インボイス制度に対応するにあたって、取引先が免税事業者か、課税事業者か把握することが重要です。適格請求書の発行ができるのは課税事業者のみなので、注意してください。
また、適格請求書を発行するには、適格請求書発行事業者として所轄の税務署へ登録を行う必要があります。webサイトのe-Taxまたは郵送での申請が可能となり、審査後に、登録通知書が送付されるか、希望によりデータで受け取ることができます。登録通知書は紛失しないように保管するか、紛失しないためにデータで受け取ることも検討しましょう。
インボイス制度の導入から、請求書や納品書などを紙ではなく、PDFなどのデータでやり取りを行うことが増えているようです。また、会計ソフトに関してもインボイス制度に適したバージョンに更新することが必要になります。2023年以前から使用している場合は、更新されているか確認を行いましょう。
関連記事:【2023年10月開始】インボイス制度とは?すべき対応を分かりやすく解説
関連記事:インボイス制度によって開業2年間の消費税免除はどう変わる?
曖昧なことは必ず税理士へ相談をする
事業を行っていく中で、特例なケースや一般的ではないため判断が難しい費用に関しては、知識がないとその場で決断することは出来ないでしょう。そのため、専門家の税理士に相談するようにしましょう。
自分の知識だけでは思いつかない節税方法や経営上の税金に関するアドバイスをしてくれるため、将来的な知識を身につけることができます。
税理士へ依頼する料金に関しても、経費計上することができます。料金は発生しますが、相談することで、自分自身の知識を増やすことができ、事業の節税に関して学ぶことができるため、長期的に考えると節税効果が期待できます。
ペナルティが課せられる場合もある?
税務署が行う税務調査は、事業の売り上げと管理している帳簿や証拠となる領収書やレシートなどの提出が求められます。
その際に、証拠となる資料が不適切であったり、意図的に所得を少なく申告したり、経費を過剰に申請を行ったりした場合は、ペナルティが課せられます。
本来支払うべき金額より、少ない金額で確定申告を行った場合は、「過少申告加算税」という税金が課せられます。「過少申告加算税」とは、本来納付すべき金額と過少に申告した差額を納める際に10%に相当する金額が加算されることです。そのため、実際に支払うべき金額よりも負担が大きくなるため、経費計上は正しく適切な状態で行いましょう。
自主的に修正を行った場合は、上記のようなペナルティが課されることはありませんが、
延滞税が発生してしまうため、分かり次第早めに対応した方が良いです。
また、経費計上を架空のもので申請を行ったり、証拠書類を隠ぺいや偽造を行った場合は、「重加算税」が課せられます。重加算税は、過少申告加算税・不納付加算税に代えて35%、無申告加算税に代えて40%の税率で課されることになります。
この問題が発覚するのは基本的に税務調査の時なので、修正申告や更正処分が行われますが、違反をしていないとはっきり言える場合は、再調査の請求や申し立てを行うことができます。
ただ、再調査の請求や申し立てができる期限は限られているため、迅速な対応が必要になります。
関連記事:個人事業主はいくらから税務調査の対象?
日々の会計業務をサポートします!
個人事業主の経費計上ができるもの・できないものなどを解説しましたが、法人とは異なるため、「家事按分」の考え方は覚えておいた方がいいでしょう。また、経費に関しては正しく行うことが大切になるので、適切な判断を行えるように知識を得ることも重要です。
事業を行っていく中で、支払いが多くなり、経費として計上できるか判断が難しい場面が出てきます。その時は、なんとなくで経費計上せず、分からないことは必ず顧問税理士に都度確認するようにしましょう。
当事務所では、横浜市を中心に個人事業主、中小企業を対象に税務全般のサポートを行っております。
今なら3ヶ月お試し顧問キャンペーンを実施しておりますので、気になる方はご相談だけでも大丈夫なので、下記フォームよりご連絡ください!
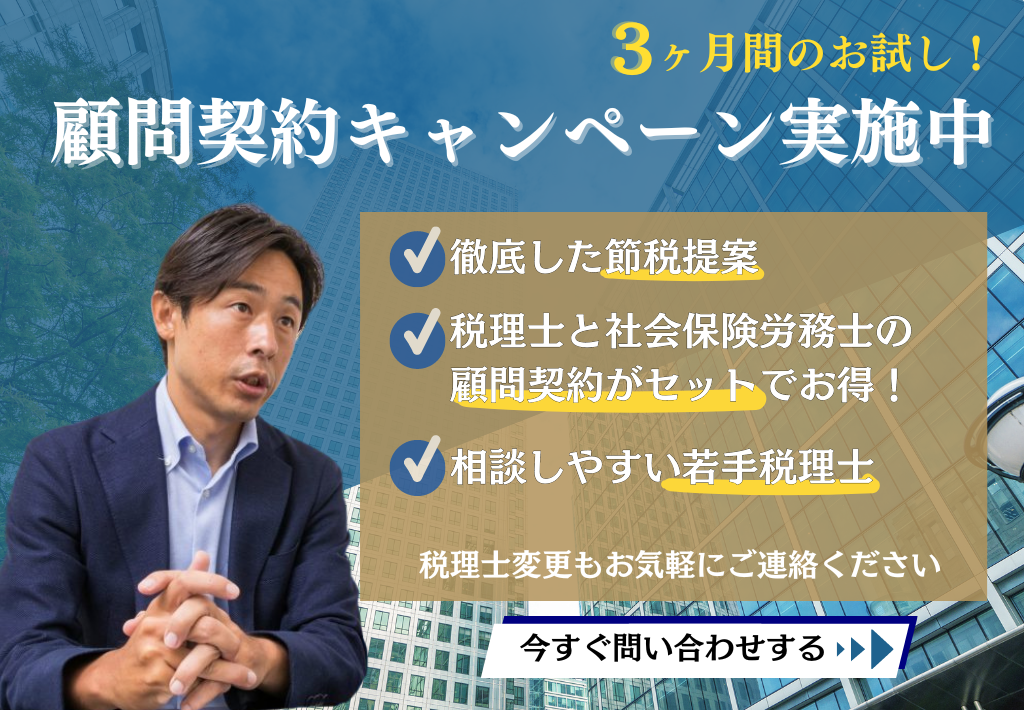
関連記事:決算申告後に経費計上漏れが発生?修正方法や注意点を解説
関連記事:個人のクレジットカードで経費立替は可能?仕訳方法や注意点を解説