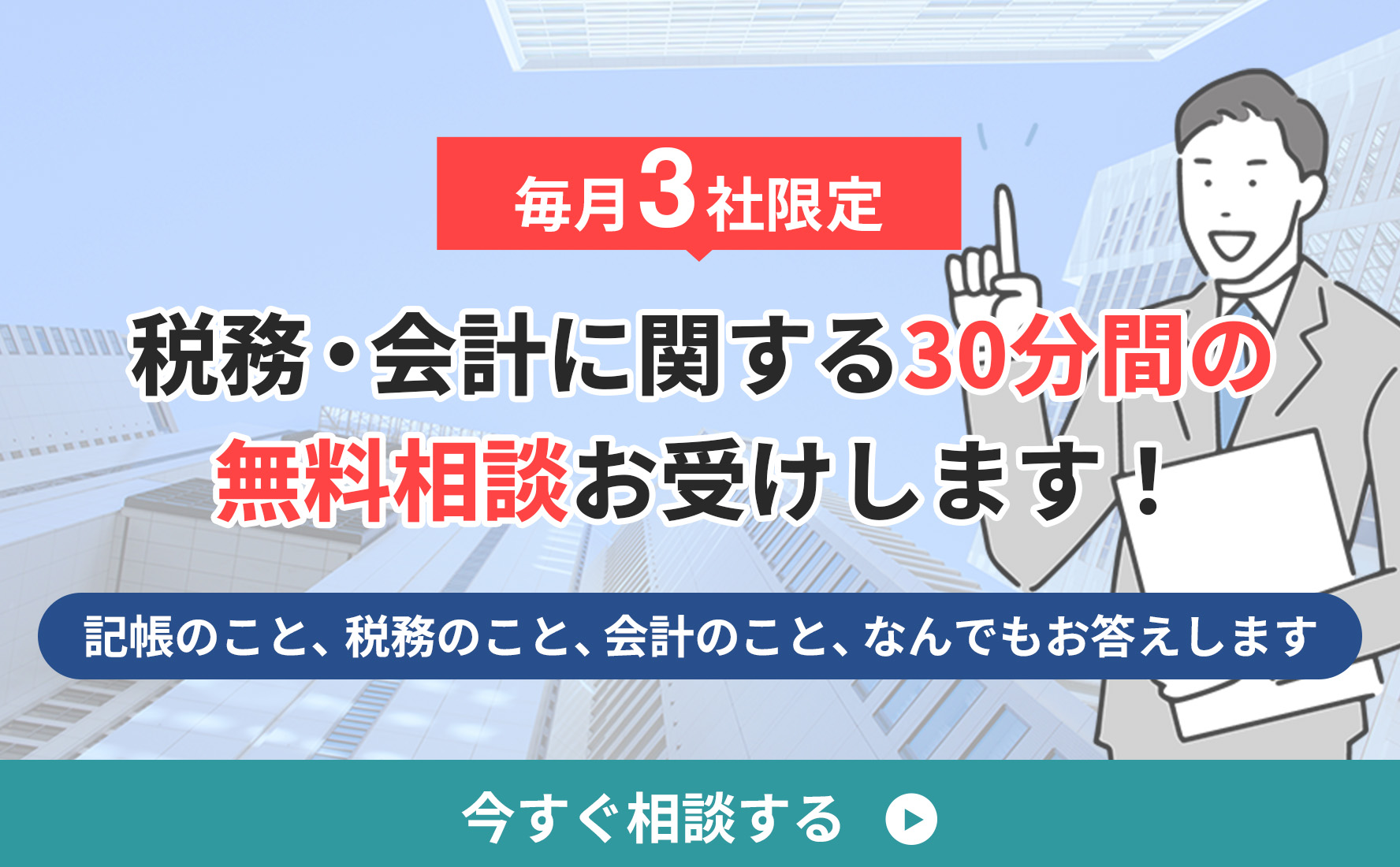新たに事業を始める場合や個人事業主から法人成りする場合、開業してから2年間は消費税の支払いを免除されます。しかし、2023年10月からスタートしたインボイス制度がこの消費税免除の仕組みにどんな影響を与えるのかを理解しておく必要があるでしょう。
そこで開業してからの消費税免除の仕組みや、法人化したばかりの事業者が課税事業者としてインボイス制度に登録すべきかどうかを判断するためのポイントについて解説します。

Contents
インボイス制度と消費税免除について
まずはインボイス制度の概要と、開業2年間の消費税免除について解説していきます。
インボイス制度とは?
インボイス制度は正式には「適格請求書等保存方式」といい、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除方式です。インボイスに登録すると適格請求書(インボイス)が発行できるようになり、発注者と受注者が適格請求書を保存することで、消費税の仕入税額控除が適用されます。言い換えると適格請求書がない場合、仕入税額控除は受けられません。
仕入税額控除とは、商品などの仕入時に支払った消費税から売上時に受け取った消費税を差し引いて計算することで、消費税が二重に課税されるのを防ぐための制度です。
原則、2023年10月からスタートしたインボイス制度で仕入税額控除の対象となるのは、受注者から発行された適格請求書がある取引に限られます。適格請求書を発行できるのは「適格請求書発行事業者」として税務署に登録された事業者だけです。
インボイス制度によって適格請求書発行事業者に登録できるのは消費税の課税事業者のみであり、免税事業者が登録する場合には、課税売上が1,000万円以下であっても、消費税の課税事業者として登録される必要があります。ですから、インボイス制度に登録して課税事業者に登録されると消費税免除のメリットを失うことになります。
関連記事:【2023年10月開始】インボイス制度とは?すべき対応を分かりやすく解説
開業2年間の消費税免除について
消費税の課税基準は「2年前の売上高」を基準として発生します。新規事業者の場合、開業2年間は前年度と2年前の売上が存在しないので免税事業者となります。消費税の免除を受けるためには資本金が1,000万円未満であるという条件があるため、これから創業を考えているのであれば資本金を設定する際の参考にすると良いでしょう。
また、資本金が1,000万円以下でも課税売上が1,000万円を超えた場合や、給与等の支払額が1,000万円を超えると消費税の免除対象から外れます。開業1年目の業績が良かった場合、開業2年目も引き続き免税の適用を受けるためには、社員の雇用によって発生する給与支払額を抑えるために業務委託を活用するなどの工夫が必要です。
個人事業主が法人成りするメリットはどう変わる?
個人事業主から法人成りすると、法人は別の法的実体として扱われるので、事業を続けながら開業しても新規開業と同じように2年間は消費税が発生しません。また、個人事業主としての免除の特例期間と開業2年間の免除を組み合わせることで、4年間は免税事業者として消費税の支払いを免除されます。
インボイスに登録すべきかどうかはビジネスモデルや取引先の状況によって異なりますので、税理士などの専門家の意見も踏まえて決定すると良いでしょう。
関連記事:【徹底解説】会社設立して消費税が免除となる条件とは?
インボイス制度に登録すべき?
開業2年以内の事業者はインボイス制度に登録した方が良いのでしょうか。ここでは、インボイス制度に登録せずに消費税免除を選択した場合のメリットとデメリットについて解説していきましょう。
開業2年はインボイスに登録しないことで消費税免除になる
【メリット】
適格請求書を発行できるインボイスに登録しない最大のメリットは消費税を納税しなくてもよいことです。消費税率は通常8%または10%であり、多くの業種で10%が適用されます。例えば、税込110万円の取引をした場合、そのうち10万円は消費税として納税する必要がありますが、免税事業者のままでいれば、110万円がそのまま自社のものとなります。この10%の違いは、特に小規模事業者にとっては経済的に大きなメリットとなるでしょう。
2点目のメリットとして会計処理が簡単であることが挙げられます。免税事業者は適格請求書を作成する必要がないため、請求書に8%と10%の消費税を区分し記載する手間がかかりません。適格請求書を発行する課税事業者は、毎回この複雑な処理を行わなければなりません。しかし、免税事業者は一つの様式の請求書で済むため、日常業務において複雑な処理に追われることはありません。
インボイス登録をしないと取引先を失う可能性がある
【デメリット】
インボイスに登録しないデメリットは主に2点挙げられます。
1点目は、取引先が減る可能性があること、そして2点目は取引先から値下げを求められる可能性がある点です。なぜこのようなデメリットが発生するかを理解しておくことは、インボイス登録をするかどうかの判断材料になりますので、詳しく解説していきます。
まず、「取引先が減少する可能性がある」という点についてです。
2023年10月にインボイス制度が導入されたことで、適格請求書発行事業者との取引だけが消費税の仕入税額控除の対象として認められるようになりました。つまり、仕入税額控除を適用するためにはインボイスに登録する必要があるのです。そのため、インボイス登録をしていないと取引先に対して適格請求書を発行できないため、取引先は仕入税額控除ができませんのでインボイス登録していない免税事業者と取引する金銭的なデメリットが発生します。
提供している製品などが他社でも代替可能で、適格請求書を発行できる事業者があれば、そちらと取引するために取引を打ち切られる可能性があります。
また、免税事業者であることを理由に取引先から値下げを求められる可能性もあります。先ほど解説した通り、免税事業者であることは、取引先にとっては「取引において仕入税額控除ができない」ということを意味します。従って取引先の収益が低下します。そのため、取引先は本来であれば控除できたはずの消費税額をあらかじめ支払い金額から差し引いて取引を継続する可能性があります。取引を失わなかったとしても、免税事業者であることが理由で値下げを要求される可能性が考えられます。
開業2年以内の事業者のインボイス対策
開業2年以内の事業者にとって、インボイス登録するかどうかは業種や取引先などによって判断が分かれるのですが、インボイスの登録が必要な場合に備えてインボイスの影響を軽減できる方法を紹介していきます。

簡易課税者に登録してインボイスの影響を軽減する
簡易課税制度は、消費税の申告時に使用される計算方法で、この制度を利用するには「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出する必要があります。
簡易課税制度は中小事業者の仕入税額控除計算を簡略化し、事務処理にかかる業務負担と費用を軽減するために設けられた制度で、インボイスに登録した場合の「本則課税」に比べると簡単に税額が算出できます。また取引先に適格請求書を発行できるので、取引先を失うリスクや値下げのリスクを軽減できます。
インボイスに登録して2割特例を活用する
「2割特例」とは税負担を「売上税額×20%」に軽減できる特例措置です。この特例の適用期間は2023年10月1日から2026年9月30日までで、この期間内に免税事業者が新たにインボイスに登録して課税事業者になり、2年前に発生した売上が1,000万円以下である場合に適用される制度です。
2割特例の期間終了時または、2割特例の対象期間中に対象事業者でなくなった場合は、次の課税期間から簡易課税制度を選択できるので、先に紹介した簡易課税者としてインボイス登録で発生する複雑な納税計算などの手間を避けることができます。
毎月3社限定|会社設立0円サポート!
松原税理士事務所では、インボイス登録によって企業会計がどう変わるのか、納税額を抑える方法があるのかなど、税に関する様々な相談やアドバイスが可能です。適切に納税額を抑えたい場合にはぜひご相談ください。
また当事務所では、毎月3社限定で会社設立を0円でサポートしております!インボイス制度に関連して法人成りを考えている個人事業主や、これから創業を考えている方もお気軽にご連絡ください。
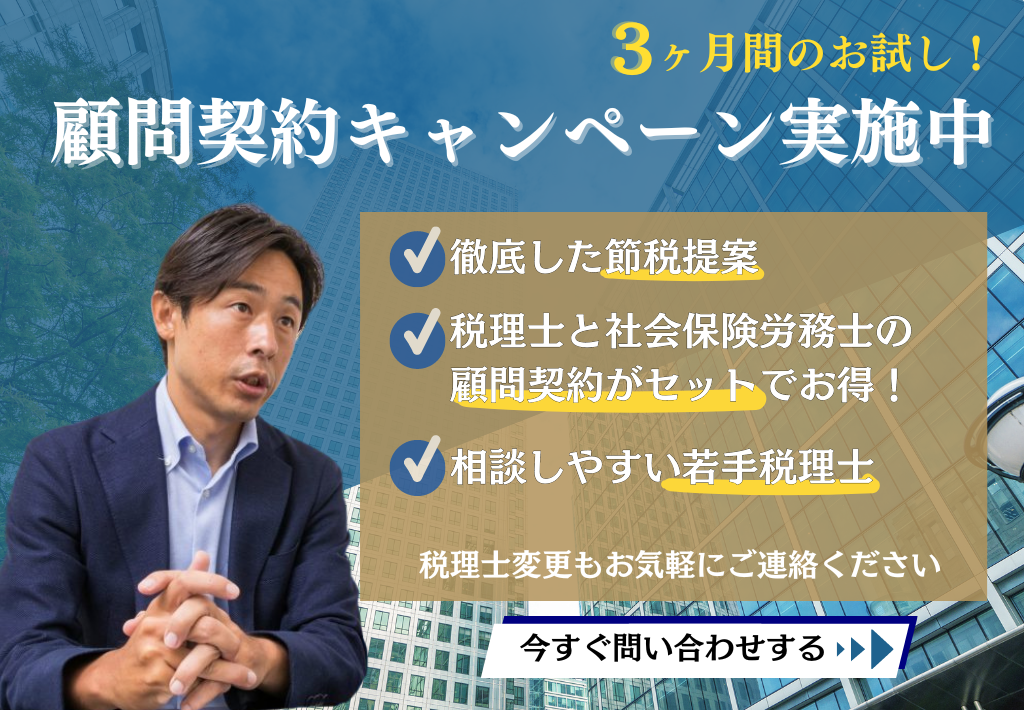
関連記事:【インボイス制度】やらないとどうなる?状況に応じて解説!