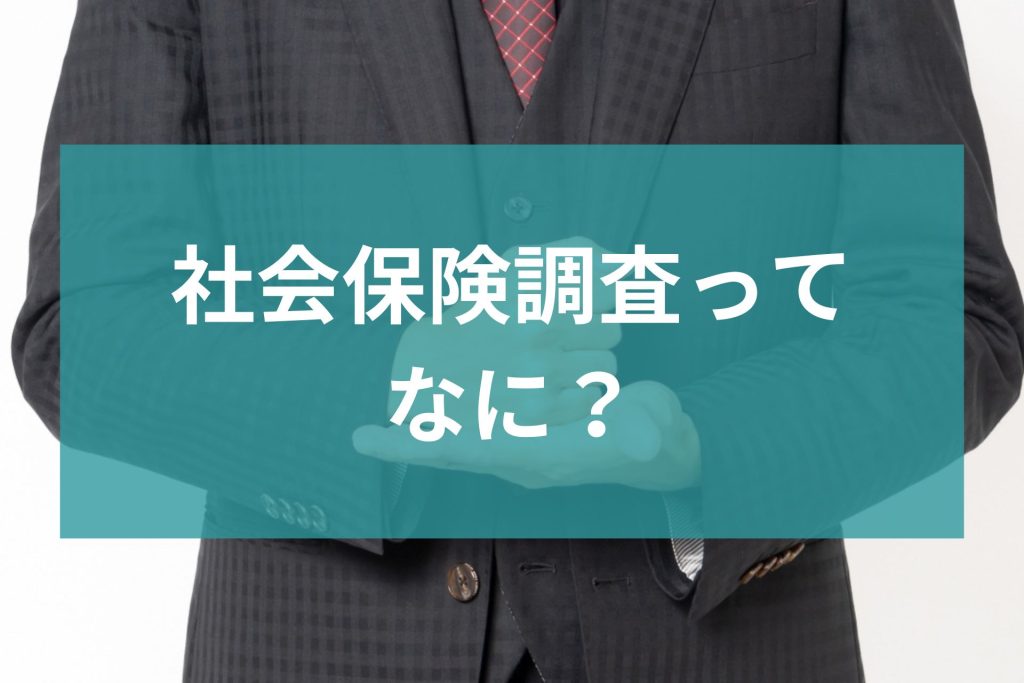
社会保険とは、一定の条件を満たしている人の加入が義務付けられている健康保険や厚生年金などの公的保険を指します。多くの法人は、基本的に健康保険や厚生年金などを給与から天引きしています。
この社会保険について、年金事務所からの調査が入ることはご存知でしょうか?
企業の社会保険に関する届出や帳簿などについて、年金事務所(日本年金機構)が調査をするケースがあります。いきなり調査に関する連絡が来て、企業の経営者や担当者の方は戸惑いや驚きがあるかもしれません。さらに社会保険調査は、2022年の社会保険適用が拡大されて以降、調査の厳しさが年々増しています。
そこで、今回は社会保険調査に関して、調査が厳しいといわれている理由や調査目的について詳しく解説します。
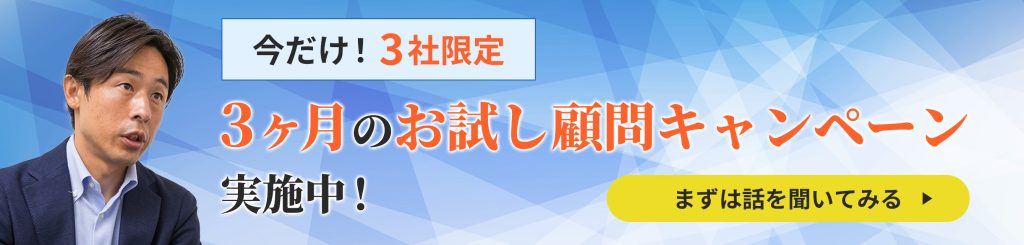
Contents
社会保険調査の目的
社会保険調査の目的を把握しておけば、適切な準備や対策が可能になります。調査に臨むうえで、基本的な内容は必ず理解しておきましょう。
社会保険調査の目的は、多岐にわたりますが主に以下の4つです。
・保険料の適切な徴収を確認するため
個人によって保険料の額は異なるため、適切な算出方法で保険料を算定して、納付を行っているのかを確認することが目的です。不正や手続きの漏れがあった場合は、罰則が科される可能性があります。
・労働条件の差異を確認するため
労働契約書の労働条件と実態の労働状況に差異がないか調査で確認を行います。書類に虚偽の記載があったり、書面と実態の不一致があったりすると即是正対象となります。
・労働者の権利を保護するため
社会保険は、将来年金を受け取るための公的保険という一面を持っているため、納付状況を確認して、労働者の権利が守られているかを確認します。
・制度の運営改善のため
社会保険調査を通して、社会保険に関する制度の運営状況全体を確認するために行っています。厳しい審査基準をもとに、データ収集や分析を行うことで、より良い制度への改善に努めます。
健康保険や厚生年金は、ある一定の条件を満たしている従業員すべてを会社が加入させなければなりません。また、給与から天引きされる社会保険料は、給与金額に応じて計算されるため、金額が異なります。適切な届出や計算が行われていなかった場合、会社と従業員の双方に大きな影響を与えてしまうので、取り扱いには注意が必要です。
社会保険調査は厳しい?
以前は税務署の調査ほど厳しいものではありませんでしたが、2022年の社会保険適用の拡大に伴い、「社会保険調査は厳しい」と言われることが多くなりました。
社会保険適用の拡大とは、少子高齢化による人手不足や非正規雇用の増加を背景に、社会保障の不足を補うため、短時間労働者の加入要件を緩和して実施された施策です。2022年平均の正規職員・従業員数は3,597万人で前年より1万人増加した一方で、非正規職員・従業員数は2,101万人で前年より26万人増加しました。加えて、役員を除く雇用されている労働者の非正規の職員・従業員の割合は、36.9%となっており、4割を占めています。
そのため、非正規雇用者は正規雇用者に比べて、社会保険に加入しずらく、保証も十分でない点から不公平な扱いが問題視されていました。そこで社会保険適用の拡大が施行されたわけですが、パートやアルバイトの加入漏れが相次いでいることや過少申告の取り締まり、追加徴収などにより事業主と従業員の双方に影響を及ぼす点から、調査が厳しいといわれています。
調査の対象となる法人
調査の対象となる事業所は、社会保険の加入が強制となる株式会社や合同会社などの法人事業所、常時5人以上を雇用している従業員がいる個人事業所(一部の業種を除く)です。また、社会保険の加入が任意となっている任意適用事業所に対しても調査を行います。会社の規模などにかかわらず、すべての適用事業者が調査対象になることは覚えておきましょう。
調査が行われるタイミング
「すべての適用事業者が対象になることはわかったけど、調査が行われるタイミングっていつ?」と疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
調査が行われるタイミングは、大きく分けて3つあります。そのタイミングに合わせて、事前に対策ができていると指摘や罰則などを受ける必要がないので、しっかり把握しておきましょう。
社会保険に新規加入したとき
法人が社会保険に新規加入したとき、新規適用されてからおおよそ半年から1年の間に調査が入るケースがあります。社会保険に関する手続きを始めて行うため、不慣れな部分も多く、不備や漏れなどがないか確認するために、新規加入のタイミングで調査を行います。
そのため、新規加入の手続きに不安を抱えている方は、専門家への相談を1度検討してみましょう。
定期的に実施されるとき
社会保険に加入してから、3~5年に1度のペースで行う定期調査もあります。特に毎年7月の算定基礎届を提出する時期に合わせて行うことが多いです。
この定期調査では、社会保険の資格取得や資格喪失に関する手続き漏れ、標準報酬月額が適切かといった点を厳しく調査します。新規加入時の調査と比べて、法令順守をしているかという確認の意味合いが強いです。そこで、経営者や人事・労務を担当している皆さまにとっては、社会保険の状況や資格に関する手続き、金額の差異などを確認することがとても重要です。日ごろから確認や適切な保管を行っていれば問題ないので、定期調査に伴って、社会保険に関する書類の確認や実態の改善などの対策を行いましょう。
社会保険に未加入の事業者に対する加入を促すとき
社会保険の適用対象になっているにもかかわらず、加入手続きを行っていない適用事業所に対して調査を行い、加入勧奨や手続き状況の確認を行います。株式会社や合同会社などの法人は、正社員もしくはフルタイムで誰か1人でも雇用していれば強制加入の対象となります。
社会保険調査に至るまでに、法人の登記情報から法人として会社が設立しており、かつ社会保険の手続きを行っていない会社を特定します。調査を経て、社会保険に加入していない事実が発覚すると、強制加入が命じられます。未加入だった期間の社会保険料は、その期間の最大2年分をさかのぼって納付しなければなりません。また、年金事務所からの加入勧奨を無視するなどの悪質なケースだと罰則が科される可能性があります。
流れとしては、「行政指導→強制加入→保険料の徴収」となりますが、どのタイミングでも対応をしないでいると、最終的には罰則という重いペナルティを受けなければなりません。手続きを忘れてしまったり、適切な対応ができていなかったりする場合は、人間として少なからずあるでしょう。ただし、年金事務所の指導が入った時点で指導に沿って手続きを行うことが重要なので、指導を無視することといった行為はやめてください。
社会保険調査の指摘されるポイント
社会保険調査は企業に対して年金事務所が厳しくチェックをすることで、社会保険が正しく運営され、労働者の権利を守ることなどにつながる非常に大切な取り組みです。
調査の内容は厳しいだけでなく、細部に至るまで徹底的に調べられるため、人事や労務の担当者にとっては、大きなプレッシャーになります。事前に指摘されやすいポイントを抑えておくと対策を講じることもできるので、以下3つのポイントをしっかり把握して対策をしましょう。

・加入時期が適切であるか
・賞与の支払届出の提出確認
加入漏れの有無
社会保険の加入漏れについては、会社と従業員の双方に影響を及ぼすため、厳しい追及は避けられない可能性があります。
社会保険の加入手続きは、会社に入社した新入社員やフルタイム勤務の従業員がいる場合、5日以内に年金事務所へ資格取得届を提出しなければなりません。新しく入った人だけではなく、パートとして勤務していた従業員が正社員の労働時間の3/4働いていると、その従業員も社会保険の加入対象になります。
虚偽の申告をしたとしても、出勤簿や賃金台帳などの書類情報をもとに加入漏れの有無を厳しく確認されるので、確実に指摘される事項といっても過言ではありません。加入漏れが発生していた場合は、未加入だった期間を最大2年分さかのぼって保険料を一括で納付しなければならず、大きな負担が発生します。
加入時期が適切であるか
社会保険に加入する条件に該当する方は、原則入社日が加入資格を取得した日になります。社会保険調査では、取得した日付と実際に働き始めた日付に相違がなく、適切に手続きが行われているかを確認します。「試用期間は社会保険に加入しなくても大丈夫!」という考え方や取り扱いはないので、手続きが行われているか見落としのないようにしましょう。
また、パートやアルバイトの従業員は、社会保険加入の条件を満たした日が資格取得日になるので、十分に留意する必要があります。基本的には、勤務時間が正社員の3/4以上になると加入対象になるケースが多いですが、ほかの勤務条件や勤務先の会社規模によって3/4未満でも加入対象になる場合があるので、専門家に相談したほうが確実です。
賞与の支払届出の提出確認
賃金台帳などを確認して賞与が支払われている場合、賞与の支払届出が提出されていないと指摘を受けます。賞与の支払届出が提出されていないと、加入資格と同様に最大2年分さかのぼって賞与の支払届出を提出して、社会保険料を一括で納付することになります。
指摘を受けないための対策
前述したように、社会保険調査は細かいところまで厳しく確認を行うため、指摘を受けないのは不可能に近いです。しかし、前もって対策を行っていれば、指摘を少なくしてペナルティを免れることができます。
・書面の作成や保管を正しく行う
・社内での対応が難しく専門的な知識が必要なものは、外部委託する
日常的に賃金台帳や出勤簿、社会保険関係の書類の作成や保管は正確に行いましょう。また、労務関係の担当者だけでは対応できないものについては、外部へ委託する方法も検討することをおすすめします。年金事務所は社会保険調査を通じて、企業が法令を順守しているのかという状況を厳しく判断します。そのため、常に厳しい書類作成や管理体制を整えることが事前の対策としてとても効果的です。
社会保険に関する相談は社労士へ!
今回は社会保険調査が厳しいといわれている理由や目的、指摘されるポイントについて解説しました。社会保険に関する加入資格の取得や保険料を適切に徴収しているかといった点を年金事務所は厳しくチェックしているので、日々の書類作成や保管についても適切な運営を行いましょう。
社会保険に関して、「どのように手続きをすればいいかわからない」「計算方法はこれで合ってる?」といった不安や悩みを抱えている方は、専門家への依頼をご検討ください。当事務所は社労士と税理士がどちらも在籍しており、社会保険や税金関連のご相談を受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください!
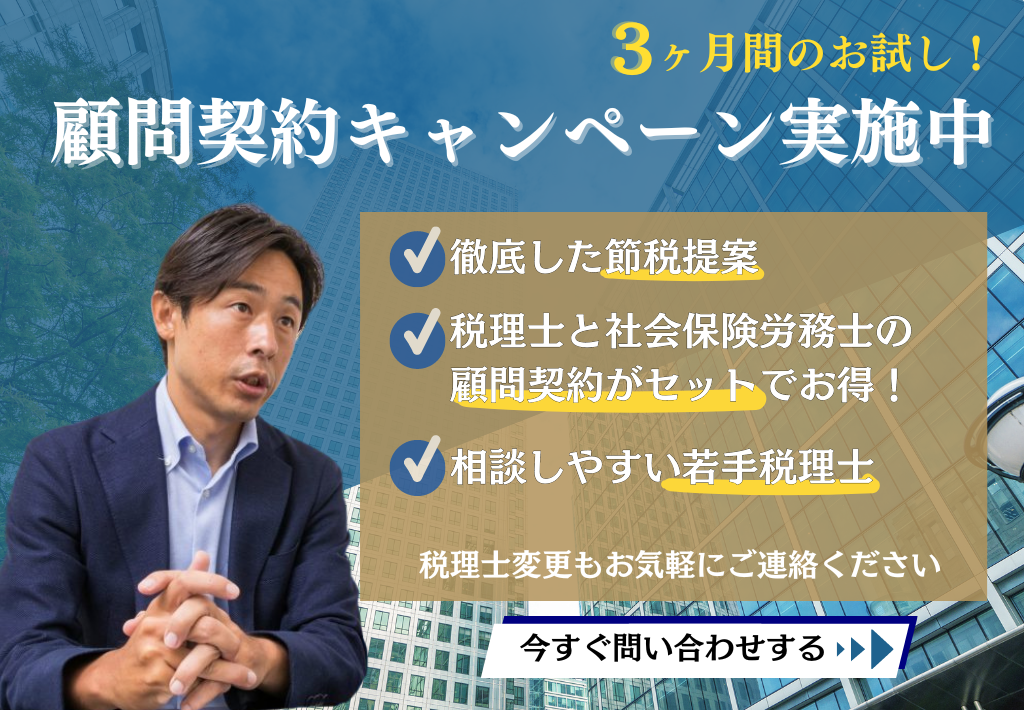
関連記事:【103万円の壁】引き上げはいつから?メリットや企業・従業員への影響、会社が対応すべきポイント



