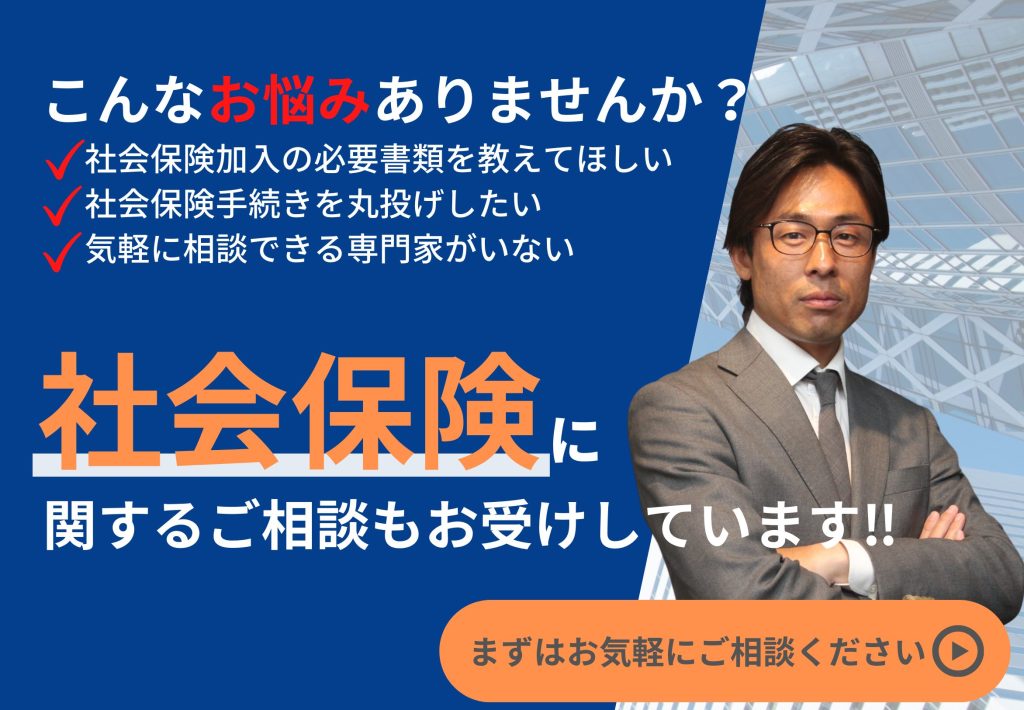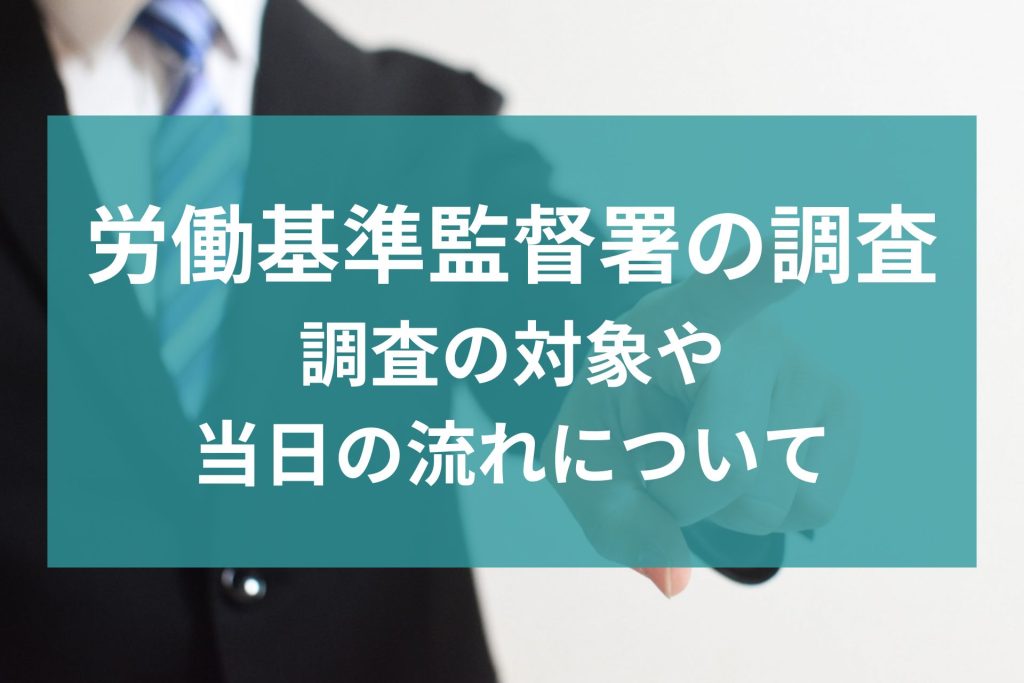
近年、働き方の多様性が広がっていますが、個人の働き方などが変わっても、労働に関する多くのトラブルは後を絶ちません。
「法定労働時間を超えても残業代が支払われない」「時間外労働の上限を超えている」
近年では、上記のような事例から精神的に追い詰められ、精神疾患にかかる労働者が増えており、最悪自殺を図るケースがあります。労働者へ身体的・精神的苦痛を与えないように労働環境を整備するのが、法人としての責務です。
しかし、社内の問題を公にしたくないから、問題がなかったように改ざんをする方がいるのも事実です。したがって、労働基準監督署の調査が抜き打ちもしくは定期的に行われるケースがあります。調査を行うにあたって、労働基準監督署はどのような目的をもって調査を行うのか、どのような対策を行えばいいのかといった点が判断できず、戸惑う方も多いでしょう。
そんな方のため、本記事では労働基準監督署の調査について、目的や調査の種類、指摘されやすい点について具体的に解説します。
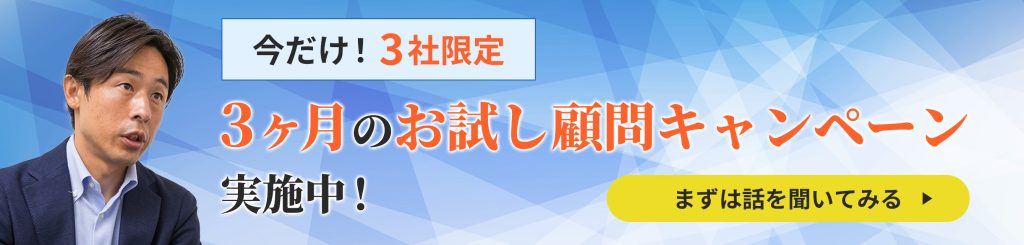
Contents
労働基準監督署の調査目的・役割とは?
労働基準監督署の調査目的は、「労働者の雇用・賃金・安全・健康を確保すること」です。従業員の労働環境などが適切であるかを確認するために、企業が労働基準法や労働安全衛生法、最低賃金法といった労働関係の法令を順守しているかを監督しています。
また、労働基準監督署は厚生労働省の出先機関として全国に配置されており、労働者からの相談を受け付けてアドバイスを行ったり、不当な扱いを受けた場合の申告先としての役割を担っています。
さらに労働者だけでなく、企業にとっても役立つ機関といえます。会社を運営しているといっても、労働に関する法令をすべて把握している訳ではないので、社内の就業規則や労使協定などを作成する際に労働基準監督署からアドバイスが受けられます。法令に関することだけではなく、労働に関する従業員とのトラブルについても相談を受け付けているので、頼れる機関として把握しておきましょう。
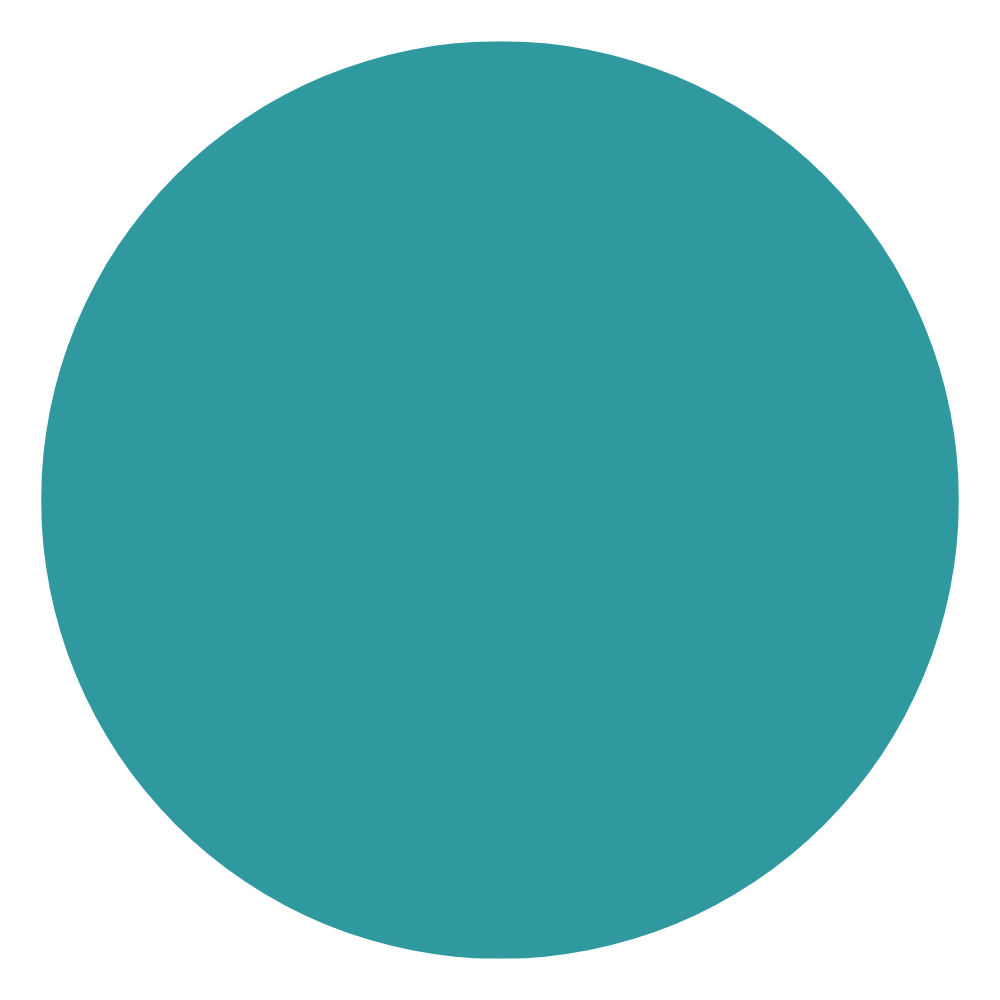 調査の種類
調査の種類
労働基準監督署が行う調査には3種類あり、各調査が実施されるタイミングが異なります。以下の3つの調査について詳しく解説します。

・定期監督
・災害時監督
申告監督
申告監督とは、会社の法令違反に関する申告が労働者からあった場合に行われる調査です。労働者と会社の間で、不当解雇や残業代の不払いなどのトラブルが起こると、相談に至るケースが多いです。申告監督は、労働者保護の観点から、労働者からの申告であることを明らかにしないケースと、申告をした人物を明らかにして呼び出すケースがあります。
定期監督
定期監督は調査の中で最も一般的な調査であり、監督計画に基づいて任意の調査対象を選出し、調査を行います。
監督計画は最新の行政課題を反映しているため、行政課題に沿った事業所が選定されます。例えば、長時間労働が課題として挙げられると、長時間労働が発生しやすい事業所を調査対象として選出するという流れです。そのため、行政課題の情報は、随時確認しておくと事前の対策を講じることができます。
災害時監督
災害時監督は文字通り、一定規模以上の労働災害が発生したときに行われる調査です。企業が提出する「労働者死病傷病報告」などをもとに、法令違反を疑われている企業を選択して労働環境等に問題なかったのかを調査します。
また、労働災害の原因究明や発生した時の状況を確認して、法令違反の有無について調査し、再発を防ぐ対策を講じるために、指示や指導を行います。
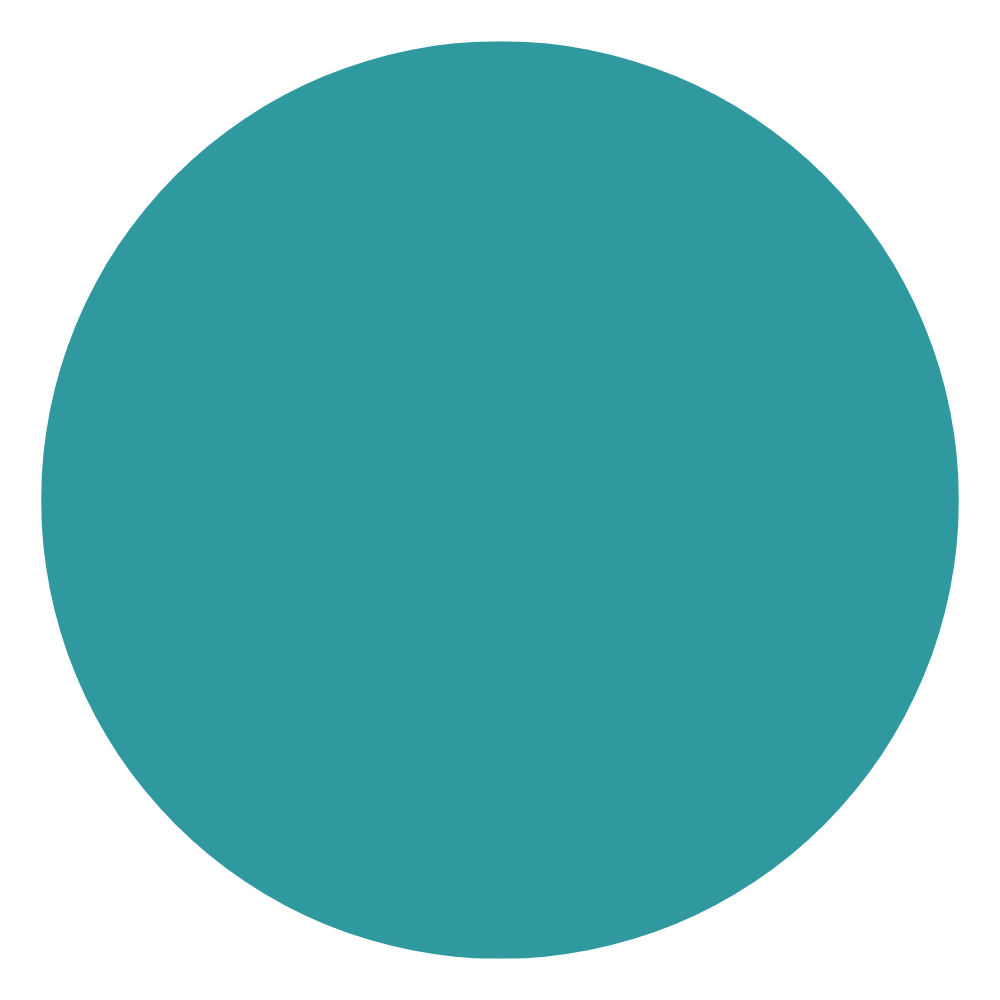 労働基準監督官の権限
労働基準監督官の権限
実際に調査を行う労働基準監督官は、会社の法令違反がないかを強制的に調査(臨検)できる権限を有しています。労働基準関連の法令に関する質疑応答や書類の提出に応じないと、罰則が科されるリスクもあるほど強力な権限なので、原則、会社は調査を拒否することができません。
労働基準監督官は、労働基準法などの法令違反が判明した場合は、刑事訴訟法に規定されている司法警察官としての職務も担っています。
そのため、調査(臨検)によって、法令違反が判明した場合は司法警察官として逮捕・送検することも可能です。このように労働基準監督官は強い権限を持っているので、調査が行われるときは指示に従いましょう。
調査の流れ|詳しく解説
労働基準監督署の立ち入り調査の流れは、おおまかに分けて以下の通りです。

②必要書類の準備・事前調査
③労働基準監督官の立ち入り調査
④是正勧告書・指導票・使用停止等命令書の交付
⑤報告書の提出
書面や電話連絡などでの予告(予告がない場合もある)
立ち入り調査が行われる前に、書面や電話などで予告される場合とされない場合があります。あらかじめ、必要書類の準備が必要な場合や出席者に指定がある場合は、事前に通知されることが多いです。
一方で、予告することで書類の改ざんや破棄、不正の隠蔽の恐れがあるケースだと予告なしで立ち入り調査が行われます。また、書類の保管状態や書類作成・届出などの日常的な状態を調査したい場合も、予告なしの抜き打ち立ち入り調査が実施されます。
前述したように、調査を拒否することは原則できません。ただし、当日担当者が不在で対応が難しいといった正当な理由がある場合は、日時の変更に応じてもらえることがあります。もし仮に調査を正当な理由なく拒否、妨害または書類の改ざん、隠蔽などが行われると、法律に基づいて30万円以下の罰金刑が課されてしまうので注意が必要です。
必要書類の準備・事前調査
調査対象の規模によって一部異なりますが、調査の際に必要な各種書類はおおむね以下の一覧の通りです。
・出勤簿
・賃金台帳
・就業規則
・賃金規程、そのほか諸規定
・タイムカード、もしくは従業員の労働時間がわかる書類
・時間外・休日労働に関する協定届
・有給休暇管理表
・雇用契約書
・健康診断結果
・安全衛生管理体制に関する書類
提出書類について、従業員ごとに必要な書類は作成されているのか、保存期間が守られているかなどを確認します。なお、1年分の書類を求められるケースが多いですが、書類によって求められる期間が異なるので、労働基準監督官の指示に従って準備します。
また、立ち入り調査の前に事前調査が行われる場合があります。事前調査といっても、会社に関する基本的な情報のヒアリングなので、この時点で違反になることはあまりありません。事前調査は主に定期監督のときに行われ、書面で回答する必要があります。調査項目は以下の項目が挙げられます。
・男女別従業員数
・18歳未満の従業員数
・外国人従業員数と在留資格の種類
・パート・アルバイトの従業員数
・障害のある従業員数と仕事内容
・給与が最も少ない従業員の給与額
定期的に従業員数などの労務管理を行っていれば、あまり時間をかけずに提出できます。立ち入り調査当日までには提出しておくべきですが、「当日までに間に合わない」「自分では手に負えない」と感じる方は、社労士などの専門家に頼ることも1つの方法です。
労働基準監督官の立ち入り調査
当日の調査は、労働基準監督官が2名派遣され(1名の場合もある)、次のような流れで調査が行われます。
・帳簿や労働関係書類の確認
・事業主や責任者への聞き込み(書類に関する不明点等の確認)
・事業所内での立ち入り調査と労働者への聞き込み(実態の把握)
・口頭での指示や改善指導
調査内容は、管轄の労働基準監督署や業種によって異なりますが、基本的な労働条件や労働環境、労働時間、休日の有無、給与の実態について調査することが多いです。まず最初に書面を確認することで、作成日や管理状態に問題がないかを確認し、責任者や従業員にヒアリングすることで、記録と実態に乖離がないかをチェックします。
立ち入り調査では、適切な労働環境を提供しているかを確認するだけでなく、必要な手続きを行っているのかという点もチェックされています。
是正勧告書・指導票・使用停止等命令書の交付
立ち入り調査が終了すると、口頭でも今後の指示や指導を行いますが、問題点が重大だった場合は書面での指導が行われます。交付される可能性がある書面は「是正勧告書」「指導票」「使用停止等命令書」の3種類です。交付される理由や法的拘束力は次の通りです。
・是正勧告書
調査によって、労働関係の法令違反が発覚した場合に、企業に対して違反状態の是正を求める書面です。
・指導票
法令違反などの事実はないものの、改善することが望ましい事項や法令違反の可能性がある事項について、改善を促すことを目的とした書面です。
・使用停止等命令書
労働者の安全や健康に危険が及ぶ恐れがある状況を是正するために、施設や設備の使用停止や変更を命じる行政処分を通知する書面です。この書面はほかの書面よりも緊急性が高く、法的拘束力を持っています。
報告書の提出
是正勧告書や指導票を交付された場合は、指示されたとおりに問題点を解決したことを報告する必要があります。報告書の書式は決められていないため、「指摘された違反内容」「是正内容」「是正完了日」を記載した後、「会社名」「住所」「代表者の氏名」を記入して押印すれば提出できます。
改善期日があるので、期日に間に合うように対策を講じて、報告書に記載します。
調査のときに指摘されやすいポイント
調査のときに指摘されやすいポイントは、次の表のとおりです。
| 労働時間 | ・36協定の締結と届出を行っているか ・法定労働時間を超えていないか ・時間外労働や休日出勤の実態(法令を超えていないか) ・シフト管理が適切か |
| 労働条件 | ・労働契約書を締結しているか ・労働契約書の内容は労働基準法を遵守しているか ・就業規則の作成、届出を行っているか ・就業規則が従業員に周知されているか |
| 年次有給休暇 | ・有給休暇の取得状況 ・有給休暇の取得記録 ・取得日数が法令を下回っていないか |
| 賃金 | ・最低賃金が確保されているか ・賃金台帳の有無や内容 ・割増賃金の計算方法は間違っていないか ・残業代の支払い状況 |
| 健康診断 | ・毎年決まった時期に健康診断を受けているか ・健康診断の結果が報告されているか |
| 安全衛生管理 | ・衛生管理者の選任状況 ・産業医の選任状況 ・安全衛生委員会の設置状況 ・長時間労働している従業員と面接を行っているか |
労働基準監督署の調査では、労働時間や労働条件に関する書面の内容を確認するほか、年次有給休暇の取得状況や割増賃金の計算方法に誤りがないか、衛生管理者・産業医の選任状況などについても確認します。書面の日付や内容などの細かいところまで調べて、指摘をするので、企業にとって見落としがちなところも指導される可能性が高いです。
再度、労働関係の書類や法令を確認して、労働基準法通りに労働環境が提供できているか確認しましょう。
調査をどのようにして乗り切るか
労働基準監督署の調査は、先述したように定期的に行われることもありますが、頻度は高くありません。そのため、労働基準監督署から調査の連絡が入ったときに「法令について知識がないから、どんな対応をすればいいかわからない」「法律違反をしていないか不安だ」と感じる方が多いです。
もし、労働基準監督署の調査が決定して、労務管理などに不安を抱えている方は次の2点を抑えておきましょう。
 不備のある書類の改善
不備のある書類の改善
調査の際に提出が求められる書類は、日常的に適切な作成や保管をしていなければなりません。しかし、見落としていたり、ミスがあったりすることもあるので、労働基準監督官の指摘を受けるケースは少なくありません。
そこで調査のために提出する書類に不備がないか、不備があった場合に改善することが大切です。調査の実施前に不備のある書類の改善に向き合う姿勢が重要なので、もし時間が足りない場合は、労働基準監督署へ実施日の変更を依頼しましょう。
労働基準監督署の目的は、「労働者の雇用・賃金・安全・健康を確保すること」なので、不備を突き詰めて、罰則を与えることではありません。不備があった場合は、是正勧告書や指導票の提出が求められるので、適切に対応すれば問題ありません。
 専門家へ相談・立ち合いを依頼する
専門家へ相談・立ち合いを依頼する
調査が行われると決まったときに、専門家への相談を行うとどのように対応すればいいかアドバイスをもらうことができます。また、調査の立ち合いも可能で、会社の経営状況などを勘案して、監査項目について労働基準監督官へ交渉をしてくれる場合があるため、心強い存在といえます。
専門知識があることで、書類の改善に関するアドバイスや労務管理について教えてくれるので、不安を抱えている方にも寄り添ってくれます。ただ、いきなり専門家に依頼するのはハードルが高いという方は、調査の有無を問わず、日常的に労務などについて相談できる専門家へ相談できる体制を整えておくことをおすすめします。
調査が入ったら、すぐ相談!
今回は労働基準監督署の調査について、目的や調査の流れ、指摘されやすいポイントについて解説しました。公的機関の調査となると、不安や緊張でどうすればいいかわからなくなるかもしれません。そんな時は、誠心誠意対応する姿勢を見せることが大切です。専門的な知識がなくても、指摘された箇所に対して改善する対応が重要です。
もし事前の書類に関する準備や当日の対応に対する不安を解消したい場合は、専門家への依頼をおすすめします。書面の不備や修正方法、当日の監査項目に関する交渉などサポートを行ってくれます。調査の相談だけではなく、労働環境などの悩みについてもアドバイスが可能なので、会社に合った専門家を選ぶと安心です。
当事務所は社労士や税理士が在籍しており、労務関係の悩みだけでなく、税務関連の手続きについても受け付けているので、専門家への相談を検討している方はお気軽にお問い合わせください!