
最近、テレビで取り上げられることが多い「103万円の壁」ですが、実際に内容を把握している方はどのくらいいるでしょうか?
「103万円の壁」以外にも「〇〇の壁」という言葉は多く、税金や社会保険料に関する年収のことを表現しています。支払う税金や社会保険料の金額によって、給与所得が変動するので、特にアルバイトやパートをしている方にとって重要な問題です。
本記事では、主に「103万円の壁」がいつから引き上げられるのか、従業員や企業への影響、企業がすべき対応について解説します。
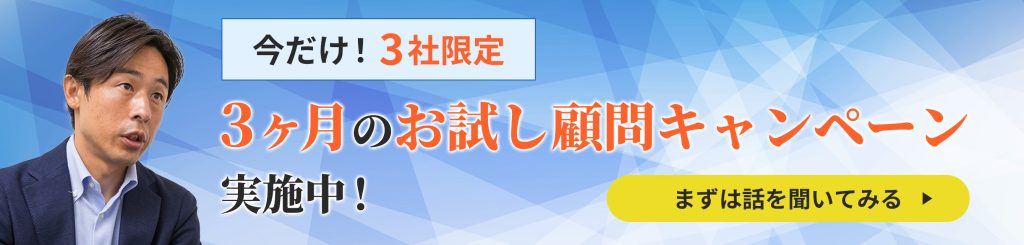
Contents
103万円の壁とは?詳しく解説
まず「103万円の壁」というのは、所得税の支払いが発生する境界線を指しています。年収が103万円以下であれば、所得税はかかりません。103万円という金額には給与所得者の控除が関係しています。
給与所得者とは、会社員やパート、アルバイトなどの会社に雇われて働いている人全員を指します。給与所得者に課せられている所得税は、次のような計算で算出されます。

②給与所得ー(基礎控除+所得控除)=課税所得
③課税所得×税率ー控除額=所得税額
給与所得控除の金額は、給与収入の金額によって変動しますが、最低控除額は55万円と決められています。また、基礎控除は合計所得金額(課税前)に応じて決められており、合計所得金額が2,400万円以下の場合は、48万円となります。この給与所得控除の55万円と基礎控除の48万円と合わせると103万円になり、ここまでは所得税がかからないので「103万円の壁」といわれています。
さらに、配偶者控除を受ける条件の中に「配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入で103万円以下)」であることが挙げられています。所得税の境界線になっていることに加えて、配偶者控除の恩恵が受けられないと世帯全体の手取りが減る可能性があるため、「103万円の壁」といわれています。
106万円の壁
「106万円の壁」という言葉もありますが、これは以下の条件をすべて満たしている場合は、社会保険料の負担が発生する境界線を指しています。社会保険料は、健康保険や厚生年金、雇用保険、労災保険といった生活の安全を支えるための財源として使われています。

・所定労働時間が週20時間以上
・月額賃金が8.8万円以上(残業代や交通費は除く)
・2か月を超える雇用見込みがある
・学生ではない
106万円の壁を超えると、今まで負担していなかった社会保険料を支払わなくてはいけません。社会保険料の支払いが発生すると、手取りの収入が減ってしまいます。
一方で、社会保険料を負担することで、将来受け取れる年金額が増えたり、健康保険の給付が手厚くなったりするメリットもあります。そのため、「106万円の壁」も撤廃する予定で議論が進められています。
130万円の壁
「130万の壁」を超えると、親や配偶者の扶養から外れ、社会保険への加入が義務付けられます。「106万円の壁」と似ていますが、親や配偶者の社会保険の扶養から外れるので、国民健康保険や国民年金の負担が発生します。よって、収入が増えることよりも社会保険料などの負担が増加する恐れがあります。
そのため、「106万円の壁」よりも「130万円の壁」のほうがより意識されやすいです。
いつから引き上げられるのか
2025年3月4日に行われた衆議院の本会議にて、年収の壁であった103万円から最大160万円に引き上げる予算案が通過しました。令和7年度の年末調整から適用され、金額が103万円から160万円に引き上げられます。
そのため、令和7年度の年末調整から「所得控除と基礎控除の拡大」と「特定親族特別控除の創設」が実施されます。具体的な内容は以下の通りです。
所得控除と基礎控除の拡大
令和7年度の年末調整から、所得控除と基礎控除の金額は表の通りに拡大します。
| 2024年(現行) | 2025年(改正後) | |
| 所得控除 | 55万円 | 65万円 |
| 基礎控除 | 48万円 | 95万円 |
| 非課税金額(給与収入) | 103万円 | 160万円 |
特定親族特別控除の創設
「所得控除と基礎控除の拡大」とともに「特定親族特別控除」が新たに創設されます。「特定親族特別控除」とは、19歳以上23歳未満の子供を扶養している従業員に対して、これまでの特定扶養親族よりもさらに控除の範囲を広げた制度です。
今までは、大学生の子どもがアルバイトしていても年収を103万円までに納めなければ、親に対する控除がなくなるため、就業をセーブせざるを得ない状況でした。
税制改正に加えて、123万円超の年収を対象とした「特定親族特別控除」が創設されたことにより、188万円までは控除が緩やかに減る仕組みになります。この制度が整備されることで、アルバイトの就業調整が不要になり、親の税負担が軽減されます。
なぜ103万円から引き上げるのか
前述したように、従来は103万円まで所得税がかかりませんでした。しかし、近年ニュースでも話題になったように、「103万円の壁」があるため、パートやアルバイトは働き控えが多くなり、社会問題として取り上げられる機会が増加しました。
103万円の壁が問題視されるようになった背景には、2つの要因が挙げられます。
働き控えによる人手不足
少し触れましたが、働き控えによる人手不足が近年顕著になってきていることが103万円から引き上げる要因のひとつです。
11月や12月になると、年末セールや仕事納めなどがあり、どこの企業も忙しくなる時期ですが、103万円を超えないようにシフトを減らすパートやアルバイトが多いのが課題でした。会社としても「働いてもらいたい」、従業員も「働きたい」と思いつつも、年収の壁に阻まれていました。
この年収の壁が引き上げられることで、会社と従業員双方の悩みを解決することができます。
生活水準の向上
そもそも「年収103万円」という金額が設定されたのは、1995(平成7)年に行われた税制改正によるものなので、約30年は変わっていないということになります。そのため、現在は物価も当時より高くなっており、年収の壁がいつまでも同じだと生活のコストとのバランスがとれていないことが問題となっています。
さらに、基礎控除は「最低限の生活費には税金をかけない」という考え方に基づいて設けられています。最近は、嗜好品だけでなく、食料品や日用品、ガソリン代などの値上がりが多く、納税者の「健康で文化的な最低限度の生活」が難しくなっています。そのため、これらの生活コストの上昇に伴い、基礎控除の見直しが重要視されています。
引き上げによる従業員への影響
年収が引き上げられる分、労働制限が緩和され、今後年収が増えることで手取りが少なくなる心配をせずに働けるようになります。特にパートやアルバイトで、親や配偶者の扶養に入っている従業員にとっては、収入増加や就業調整のストレス軽減、経験が増えて自身のスキルアップにもつながるので、働く意欲の向上にもつながります。
企業への影響についても解説
会社にとっても、働き控えによる人手不足が解消されるほか、離職率の低下や人材の早期戦力化などのメリットが挙げられます。
また、会社は従業員が社会保険に加入すると、基本的に保険料を半分支払わなければなりませんが、新たに社会保険に加入するパートやアルバイト従業員に対して、最大で1人当たり50万円の助成金を受け取れる制度があります。そのため、企業負担も軽減され、従業員にとっても働きやすい環境を整備することができます。
会社の人事や労務が行うべき対応
税制が改正されることで、企業も事前に対応を考えて準備しておかなければなりません。どのような対応が必要になるのかは大きく分けて以下の3つあります。それぞれ詳しく解説していきます。

・計算方法の確認
・年末調整の記入方法の案内
 従業員への法改正の周知
従業員への法改正の周知
年末調整や源泉徴収などに関する税制改正があったことを前もって社内に周知しておく必要があります。年末になると年末調整に関する問い合わせが社内で多くなるため、混乱を避けるためにも、従業員全員に要点を抑えて伝えておきましょう。
国税庁のホームページにも記載されているように扶養の範囲が拡大しているので、扶養する人数が変わる場合は、扶養控除等(異動)申告書や健康保険・厚生年金保険被扶養者(異動)届なども提出する必要があります。
さらに「特定親族特別控除」の対象となる19歳以上23歳未満の子どもを持つ従業員は、年末調整までに子どもの年収を把握しておくよう社内で促しておきましょう。
 計算方法の確認
計算方法の確認
国税庁から公表される資料などをチェックして、年末調整や源泉徴収票にかかわる計算方法を把握しておきましょう。所得控除や基礎控除などの金額を把握しておき、不備がないように注意します。
さらに新しく創設された「特定親族特別控除」については、対象者となる19歳以上23歳未満の子どもがいる従業員をピックアップして、計算方法を確認しておくととてもスムーズに処理を進めることができます。
 年末調整の記入方法の案内
年末調整の記入方法の案内
「特定親族特別控除」に該当する19歳以上23歳未満の子どもを持つ従業員は、年間の所得を詳しく把握しておく必要があります。
紙で申告する企業の場合は、紙面に記入するのは所得になるので、従業員が記入した金額が「収入」なのか「所得」なのかしっかり確認しましょう。従業員が多い企業では、外部のツールなどを利用して、収入や扶養状況、年齢などを入力して所得を自動的に計算できる体制を整えています。ケースに応じて、外部ツールを活用して管理しやすい体制を整備すると、税改正などがあった際に対応しやすくなります。
その他の壁には注意が必要
税制改正によって、所得税の壁は103万円から160万円に引き上げられましたが、社会保険の壁は現状維持なので注意が必要です。
社会保険には106万円と130万円の壁があるため、所得税の壁が160万円になったからといって、社会保険のことを考えると意識するべきは160万円という数字だけではありません。年収106万円(月収88,000円)以上になると社会保険料の負担が義務となります。少子高齢化などの問題によって、年々社会保険料は増加傾向にあるので負担が大きくなる可能性が高いです。家庭にもよりますが、「収入は扶養の範囲内に納めたい」という考えもあるので、企業は雇用しているパートやアルバイトとよく相談して勤務調整を行いましょう。
税制改正についてご相談ください
今回は「103万円の壁」の引き上げについて、従業員や企業の視点から解説しました。所得税が課せられる金額が103万円から160万円に引き上げられて、働き控えや人手不足による問題が解決されて働きやすい環境が整えられました。
企業はその変更に伴って、社内への通知や計算方法の確認などを行う必要があるので、人事や労務は行うべきことが盛りだくさんです。税制が改正されるとさまざまなところに影響を及ぼすので、対応するべき人への負担はとても大きいです。
税務について分からない点や依頼したい業務がある場合は、お気軽に当事務所へご相談ください!
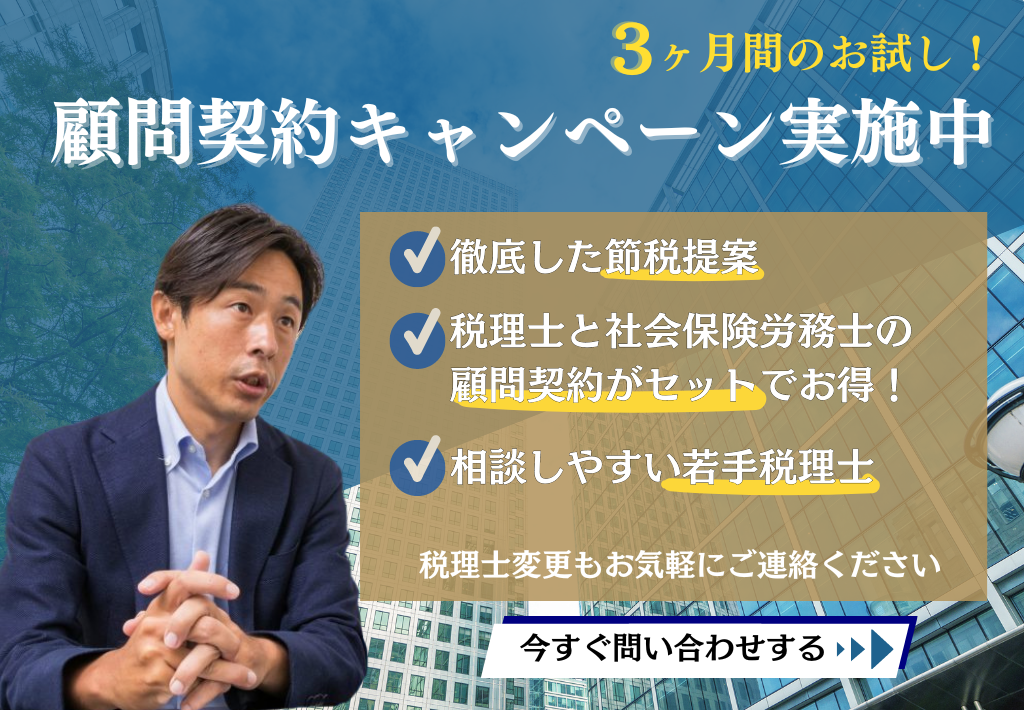
関連記事:【教えて!】社会保険の加入条件・手続きについて解説
関連記事:税理士と社会保険労務士の業務の違い|ダブルライセンスのメリットとは



