
新しく会社を始めるとなったとき、営利法人を設立するなら合同会社か株式会社のどちらかを選択することが多いです。
「初期費用を抑えたい」という理由のほか、「自由度の高い経営がしたい」「人が主体となる事業がしたい」などの理由で合同会社を選択する人もいるでしょう。
合同会社は代表社員が1名いれば設立できますが、代表社員2名(複数)でも可能です。その場合には会社内部の社員同士の関係性や業務内容、取引先との関係性を十分に考慮しなければいけません。合同会社を選択するなら、まずはその特徴や性質を理解する必要があります。
本記事では、合同会社を代表者2名(複数)で設立する場合のメリットやデメリット、注意点についても解説していきます。
関連記事:合同会社の役員報酬はどのように決める?決め方や注意点を解説
関連記事:トラブルに注意!共同経営のメリットとデメリットについて解説

Contents
合同会社とは?
そもそも合同会社とはどういうものなのでしょうか。
ここでは、合同会社と株式会社の違いや、設立に必要な人数や期間・費用をふまえて解説していきます。
合同会社は新しい会社形態
現在、日本で新たに設立できる会社形態は合同会社、株式会社、合名会社、合資会社の4つで、合同会社は「出資者=会社の経営者」の持分会社です。
合同会社は、有限会社の代わりとなる比較的新しい会社形態で、2006年5月1日の会社法改正でアメリカのLLC(Limited Liability Company)をモデルに導入されました。
合同会社では出資者が会社の決定権を持ち、会社の経営に携わることが可能です。なお、合同会社の社員とは出資者のことを指します。
関連記事:設立の流れ|合同会社に向いている業種は?手順やメリットを解説
株式会社と合同会社の違い
株式会社と合同会社では異なることがいくつかあり、ここでは8つの項目に分けて簡単に解説していきます。
①会社の所有者と経営者の関係
株式会社は、株を発行することによって資金を集め、その資金をもとに経営するので、基本的には出資者(株主)と法人の経営者の役割は切り離されています。しかし、設立者が出資者だった場合など出資者と経営者は同一人物の場合もあります。
ただし、あくまでも会社の所有者は株主です。経営者以外の人が多くの株を保有している場合、経営のトップであろうと思い通りに経営を行うことはできません。
これは「意見を述べる権利は株式の保有数に応じて付与される」という仕組みで、保有している株が多い人ほど、経営方針などを決定する決議への影響力が大きくなります。
一方で、合同会社は「出資した人が経営も行う」という仕組みで、所有と経営が一致しています。出資者(社員)が会社の経営者であり、出資金額に関わらず同等の代表権と業務執行権をもっているため、迅速な意思決定や自由度の高い会社経営が可能です。
②意思決定の方法
株式会社では、会社に関する重要な意思決定を行なう際、必ず「株主総会」を開催し、決議をとらなければいけません。株主の人数が多いほど、場所の確保やスケジュールの調整に時間がかかるため、その分意思決定にかかる時間も増えていきます。
合同会社では、社員(出資者)全員が同意すれば正式な決定事項となるため、迅速な意思決定が可能です。あらかじめ限られた社員の人数にしておけば、調整もスムーズに行えるため、株式会社と比較してもより早い意思決定が可能になります。
③設立時の手続きと費用
会社設立時の手続きでの違いは定款の認証が必要か否かです。株式会社の場合は公証役場で定款の認証の手続きを行なわなければいけません。この手続きに3万2千円の費用がかかります。
合同会社の場合は定款の認証を行う必要がありませんので、その分費用が安く済みます。
④決算公告の義務
株式会社は、1年に1度株主や債権者などに向けて会社の決算状況を公開する「決算公告」を行なう義務がありますが、合同会社には決算公告をする義務はありません。
※しかし、多くの株式会社が決算公告をしていないのが実態です。
引用:株式会社東京商工リサーチ「官報で決算公告、株式会社のわずか1.8%」
⑤役員の任期更新の必要性
株式会社の場合、役員の任期は通常2年、最長10年(非公開会社の場合)までと決まっています。期間ごとに更新が必要で、法務局への登記申請には1万円がかかりますが、もし手続きを怠った場合、100万円以下の罰金を支払うことになりかねません。
合同会社の場合は任期自体がないため、更新が不要です。
⑥利益配分のやり方
株式会社の場合、原則として保有している株(出資額)の数に応じて利益の配当が受けられます。つまり多く株を保有している人がより多くの利益を得られるのです。
合同会社の場合は、定款で自由に利益配分を定めることが可能です。そのため出資額に関わらず利益の配当が受けられます。ただし、各社員から不満が出ないように適切な設定にすることが求められます。
⑦資金調達の方法
株式会社は幅広い資金調達が可能です。株式の発行や株式市場への上場もできるため、上場時の利益を狙う投資家や企業、金融機関から多額の出資を受けられる可能性があります。
しかし合同会社は株式の発行ができないため、多額の出資を集めるには向かず、大規模な会社経営には向きません。
⑧代表者の役職名
株式会社では、業務執行の意思決定をする役職者のことを「取締役」といい、その中から選ばれた一人が会社の社長となるため、「代表取締役」という名称になります。
合同会社では、出資を行ない業務執行の権利を有する人を「社員」と呼び、その代表者のことを「代表社員」と呼びます。
また、合同会社の代表社員は登記上「代表者」と定められていますが、肩書についての決まりはありません。社長やCEOや最高経営責任者など自由に決められます。ただし「代表取締役」は会社法で株式会社のみ使用が可能なため、使用しないよう注意してください。
合同会社の設立に必要な人数や期間、費用
・合同会社は1人から起業ができます。
・期間は一般的に、最短2週間程度で起業可能です。しかし、これは事前準備や法人の実印、必要書類などを、不備なく揃えて円滑に申請できた場合に限ります。会社の起業を焦り、準備を怠ると、起業後に問題が発生することがあるため注意しましょう。
・合同会社の設立自体にかかる費用は約10万円です。
登録免許税〈6万円〉
収入印紙代〈4万円〉
定款の謄本手数料〈約2千円〉
・資本金とは、合同会社の設立時に出資した金額のことを指します。資本金には下限がないため、最低1円でも可能です。また、お金ではなく現物で出資することもでき、例えば自動車、パソコンなどの電化製品、オフィス家具、有価証券・債権などが挙げられます。
ただし、現実問題1円では事業を行うことはできません。資本金とは事業を行う元手の資金なので、ある程度の金額を準備しておきましょう。
合同会社の特徴と性質
合同会社の持つ特徴や性質について4つに分けて解説していきます。
合同会社の特徴①所有者と経営が一致している
合同会社の特徴として、出資した人(社員)が会社の所有者(経営者)となるため、会社の所有と経営が一致しているということがあります。
そのため、何か問題が起きたり、社会情勢や世間のニーズに合わせて素早く会社の経営について修正できる性質を持っています。「自由度の高い経営がしたい」と考えている人には合同会社が向いているかもしれません。
また、合同会社を含む持分会社では、負債や倒産などの責任が生じた場合、社員(出資者)が責任を負わなければなりません。社員には「有限責任」が生じ、出資範囲の分だけ責任を負うことになります。
合同会社の特徴②利益配分や経営方針は社員の総同意で決定
合同会社の社員(出資者)は、基本的には出資額に関わらず平等に決定権をもっています。そのため直接経営に関わることができ、利益の配分割合や経営方針などを決定できるのです。
ただし、それぞれが決定権をもっていると対外的な混乱を招いたり、会社の意思決定に時間がかかったりする場合があります。そのため合同会社では、社員の中から代表権を行使できる「代表社員」を定款で定めておくことが可能です。また、定款によって業務執行社員と社員を分けている場合には、業務執行社員の中から代表社員の選出を行ないます。
合同会社の意思決定ルールの原則として、定款の内容変更、社員の追加、持分譲渡(合同会社の経営権)の承諾などの会社全体に関わることには「全ての社員の同意」が必要になります。また、どこに支店を出すか、どこから商品を仕入れるのか、いくらで売るかなどの業務上の意思決定には「社員の過半数の同意」が必要です。
合同会社の特徴③任期が決まっていない
合同会社では役職の任期に関する規定がありません。そのため同じ人が10年以上役員を続けることも可能です。役員の氏名や役職に変更がない限り、登記の変更は必要ありません。
合同会社の特徴④初期費用や運営費が抑えられる
合同会社の場合、かかる費用は約10万円で、株式会社の半額ほどで設立できます。
また、株式会社の場合は決算公告義務があり、毎年決算期ごとに最低約8万円ほどの官報公告掲載費がかかりますが、合同会社には決算公告義務がないためこれらの費用も発生しません。※しかし、多くの株式会社が決算公告をしていないのが実態です。
引用:株式会社東京商工リサーチ「官報で決算公告、株式会社のわずか1.8%」
他にも株式会社では法律上、役員の任期が原則2年、最長10年と決まっているため、そのたびに登記費用が掛かりますが、合同会社では任期が決まっていないため、登記の再登録などにかかる費用も、役員の氏名や役職が変わらない限り手続きは不要です。
合同会社の代表社員が2名の場合メリットとデメリット
先でも述べたように代表社員は2名(複数)でも可能ですが、その場合に生じるメリット・デメリットがあります。会社内部の社員同士の関係性や業務内容、取引先との関係性、人柄などを十分に考慮して選択する必要があります。
メリット
代表社員が2名であれば、出資額に関わらず2名ともに対等な代表権をもつことになり、それぞれ単独で代表権を行使できます。そのため意思決定から行動までのプロセスが非常に速くなり、機動的で自由な会社経営が可能です。
また、何らかの理由で一方が長期不在の場合でも、他の代表社員が契約できます。
他にも本社は日本、支社は海外というような場合はそれぞれに代表社員を置くことも可能です。
デメリット
代表社員が2名の場合に気を付けなければいけないのは、混乱を招いてしまう可能性がある点です。それぞれが代表社員を名乗ることで取引相手に誰が代表者なのかわからないとビジネスとは関係ない部分で不信感を与えてしまい、取引がうまく進まないことも考えられます。また代表社員ごとに会社の実印を持っているため、勝手に契約される可能性もあります。他の社員の同意を得ることなく第三者と結んだ契約でも有効なため、注意が必要です。
合同会社を設立する手続きと流れ
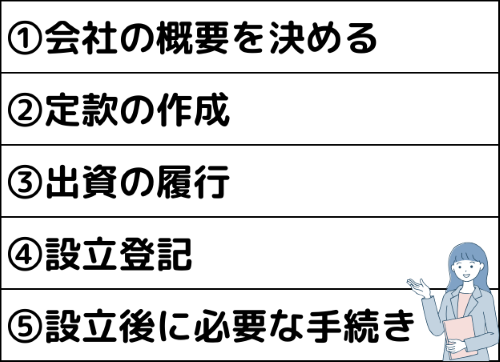
合同会社設立①会社の概要を決める
まずは定款を作るために、社名・業務内容・所在地・資本金額・決算期・設立日・事業内容・社員構成などの基本事項を決定します。
・社名(商号)
社名(商号)とは会社の顔となる大切なものです。さまざまな決め方がありますが、個人事業者から法人化する場合は、屋号を引き継いでも構いません。ただし、銀行や学校などの特定の団体を連想させる名称を使ったり、有名企業の名前を連想させる名前を使用したりすると、不正競争防止法によって賠償責任を求められる可能性があります。社名を考える時には類似する名前がないか、本店所在地を管轄する法務局で、商号調査を行い確認しておきましょう。
なお、社名の前後には、必ず合同会社という法人格を入れます。
・本店の所在地
所在地は法律上の住所のため、実際の事業活動地と異なっていてもかまいません。自宅やレンタルオフィスでも可能ですが、後で事務所を移転すると、登記の変更手続きと登録免許税がかかります。そのため、長期で業務を行える場所を選びましょう。
・資本金
合同会社は、資本金が1円でも会社設立が可能です。
ただし、当然、資本金が1円では会社の経営や運営は成り立ちません。金融機関の融資も、売上などのほかに、資本金も確認されます。特に、会社設立直後は決算書がないため、資本金の額は信用度に直結すると言えるでしょう。資本金が極端に少ない=会社の資本力がないと判断され、融資が受けにくくなる可能性があります。
・決算期
法律で会社は一定期間の収支を整理し、決算書を作成することを義務付けられています。会計年度(事業年度)は決算書を作成するために区切る年度のことです。
定めるには決算期を一にするのかを決める必要があり、1年を超えなければ自由に決めることができます。
・設立日
会社の設立日とは、法務局に設立を登記申請した日のことです。設立日は自由に決められるので、設立日にしたい希望日が決まっているのなら、逆算して準備をする必要があります。もし、郵送で書類を法務局に送る場合、日付指定をしても業務外の日や、書類に不備があると受理されないため、指定した日が設立日にならないことがあるので気を付けましょう。
・事業目的
事業目的では、会社の事業内容、どんな事業を行うかを明示します。この後で作成する定款で、事業目的は取引先や金融機関が会社を判断するときの目安となるので、できるだけ明確で過不足のない内容を考えましょう。将来を見据えていろいろ事業を書くことも大切ですが、「一貫性がなく不自然で信用性にかける」と判断される可能性もあるため書き方に注意が必要です。
後から事業目的を変更する場合には、定款と登記の変更手続きが必要で、登録免許税として3万円がかかります。
・社員構成
合同会社では、誰が代表社員なのか、何人なのかといった社員構成を決めます。株式会社の代表取締役と、合同会社の代表社員は同じ役割で、ともに1名から設立が可能です。ここまで決まったら、出資者(社員)全員の印鑑証明書を準備しておきましょう。
合同会社設立②定款の作成
①が決まったら定款を制作します。定款は会社の規則になるので、設立する会社の実状に合わせて検討しましょう。合同会社は会社内部の自由度が高いため、定款の作成作業は非常に重要です。定款には必ず記載しなければならない絶対記載事項があり、1つでも記載がないと定款そのものが無効となります。
絶対記載事項は次の通りです。
- 目的
- 商号(社名)
- 本店の所在地
- 社員の氏名または名称、及び住所
- 社員全員が有限責任社員であること
- 社員の出資の目的、価格、評価の基準
上記以外でも定款に定めておけば効力が発生するため、会社独自の事柄や必要なことがあれば、後のトラブルを防ぐためにも記載しておきましょう。
例えば
- 社員の中で業務執行する社員、代表社員を定める場合
- 損益配分の比率
- 事業年度
- 社員総会の開催に関する事項
- 社員を除名する方法
定款を作成したら、会社保管用と登記申請用の2部用意します。会社保管用には4万円の収入印紙を貼って会社で保管し、登記申請用は法務居へ登記申請書と合わせて提出するためです。一方、電子定款で作成する場合、紙媒体ではないため収入印紙代の4万円は不要となります。
合同会社設立③出資(金銭・現物出資)の履行
合同会社の場合、定款の認証は必要ありません。定款の作成後は資本金の払い込みを行い、現物出資の場合は、その財産の全部、または一部の給付の履行を行います。
出資金は、誰がいくら振り込んだのかがわかるように、出資者の預金口座に振り込まなければなりません。もし出資者が複数名いる場合は、代表者1名の口座に、出資者が1名ずつ出資金を振込む必要があります。この時、まとめて振り込まないように注意しましょう。
全ての出資金の振り込みが完了したら、払込証明書を作成します。また、払い込みのあった通帳の表紙、支店名の記載があるページ、払い込みがあった明細のページのコピーも必要です。払込明細書の後ろに付けて留め、全てのページの境目に法人実印で割印します。
合同会社設立④設立登記
定款と払込証明書が用意できたら、合同会社設立登記申請書を作成します。登記申請に必要な書類一式と収入印紙6万円(登録免許税は資本金の0.7%の金額で、最低金額が6万円)を揃えて法務局に提出することが必要です。
法務局に登記申請をした日が合同会社の設立日となるため、希望日がある場合は平日かどうか確認しておきましょう。法務局は土日祝日と年末年始は閉庁しているため、必然的に平日しか申請することができません。
また、郵送で書類を法務局に送る場合、日付指定をしても業務外の日や、書類に不備があると受理されないため、指定した日が設立日にならないことがあるので気を付けましょう。
合同会社設立⑤設立後に必要な手続き
法務局での登記が完了したら法人の設立に際して各種届出が必要です。税務署、都道府県税事務所、市区町村役場、年金事務所、ハローワーク、労働基準監督署などへの届出を行いましょう。税務署、都道府県税事務所、市区町村役場には、法人が設立したことを届ける法人設立届を提出する必要があります。特に税務署では、青色申告の承認申請書や、給与支払い事務所などの開設届出書など、届け出ることによってメリットがある書類もあるため、手続きを忘れないよう注意しましょう。
年金事務所では社会保険の加入手続きが必要です。全ての法人会社は、設立と同時に健康保険と厚生年金保険の新規適用事業者となります。たとえ1人であっても社会保険に加入しなければなりません。必要な書類は、新規適用届、登記簿謄本などがあり、この届出には役員報酬や従業員の給与額も記載します。
ハローワークや労働基準監督署は従業員を雇用するときに必要です。役員のみで構成されている場合には労働保険へ加入はできませんが、従業員を雇い入れる場合には労働保険に加入しなければなりません。労働保険は労働災害補償保険(労災)と雇用保険の2つからなり、事業主が一部を負担します。
代表社員を2名(複数)にする場合の注意点
合同会社の代表社員を2名(複数)にする場合、気を付けておきたいことがあります。2人の関係がこじれてしまったり、一方と連絡が取れなくなったりすると、会社の経営自体が危ぶまれるため、信用できる相手との設立が必須です。そうは言っても、問題が起こる可能性は否定できないため、リスク回避の行動は必要になります。
定款を作成する際
定款は会社の根本規則です。必要な記載事項以外にも、会社の形態や現状に必要なことを記載することで、後から起きる問題への対処が可能となります。
例えば「合同会社の業務は、社員の過半数をもって決定すること」「定款の変更や解散には社員の総同意が必要」などを記載しておいたり、あらかじめ考えられるリスクに対しての対処方法などを盛り込むことも一つの方法です。
法人の実印を登録するとき
法人実印は合同会社を設立する際に、代表社員が法務局へ登録する印鑑です。
代表社員が2名(複数)いる場合、法人実印はそれぞれ別に用意する必要があります。1つの印鑑に代表社員1名と定められており、1本の印鑑を複数で共有することはできません。代表社員が2名(複数)いる場合はどちらか1人が登録するか、どちらも登録するか選ぶことができます。どちらも登録する場合は、それぞれの名前で印鑑登録を行うため別々の印鑑を準備しましょう。
合同会社を株式会社にすることは可能?
合同会社から株式会社への移行はできますが、手数料や提出書類や手続きの増加といった業務が増えます。会社を設立するにあたって、将来的にどうなりたいかを見据えたうえで、合同会社と株式会社のどちらを選ぶか選択しなければなりません。
合同会社から株式会社へと組織変更するには5つのステップがあります。
②株式会社として人事の決定
③全ての社員から「組織変更計画書」への総同意を得る
④官報公告による債権者保護手続きを行なう
⑤合同会社の解散と株式会社の登記申請を行なう
上記の通り合同会社から株式会社への変更にはさまざまな手続きが必要になり、それぞれに費用が発生し、目安は約20万円ほどです。
④では合同会社の解散に必要な手続きとして、官報公告への掲載があります。オンライン申し込みか、官報公告販売所への申し込みで行うことができ、掲載料は文字数によって異なりますが、3万5千円程度です。
⑤では合同会社の解散に3万円、株式会社の設立に3万円の登記免許税が発生するため、合計6万円の費用がかかります。
また、法的な手続きを正確に行うため、税理士などの専門家に依頼する場合もあります。専門家への報酬は、依頼内容の複雑さによって異なりますが、数万円〜10万円程度かかることを想定しておくとよいでしょう。
関連記事:合同会社から株式会社に変更するメリットは?変更の流れや費用を解説
共同経営|設立直後のトラブルを避けよう
近年、共同経営をされている方が増えてきました。しかし、設立後に揉める等トラブルが多いのも事実です。だからこそ、お互いに話し合い、自分たちに合った会社形態を選ぶことはとても重要なことです。
本記事でご紹介した合同会社は、株式会社に次いで2番目に多い会社形態です。メリットデメリットを理解したうえで決断してください。
専門的な内容や個別に分からないことがあれば一人で考えず、信頼できる専門家に相談しましょう。
当事務所では、毎月3社限定で会社設立を0円(無料)で対応しております!会社形態でお悩みの方、会社設立をご検討の方は下記お問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。
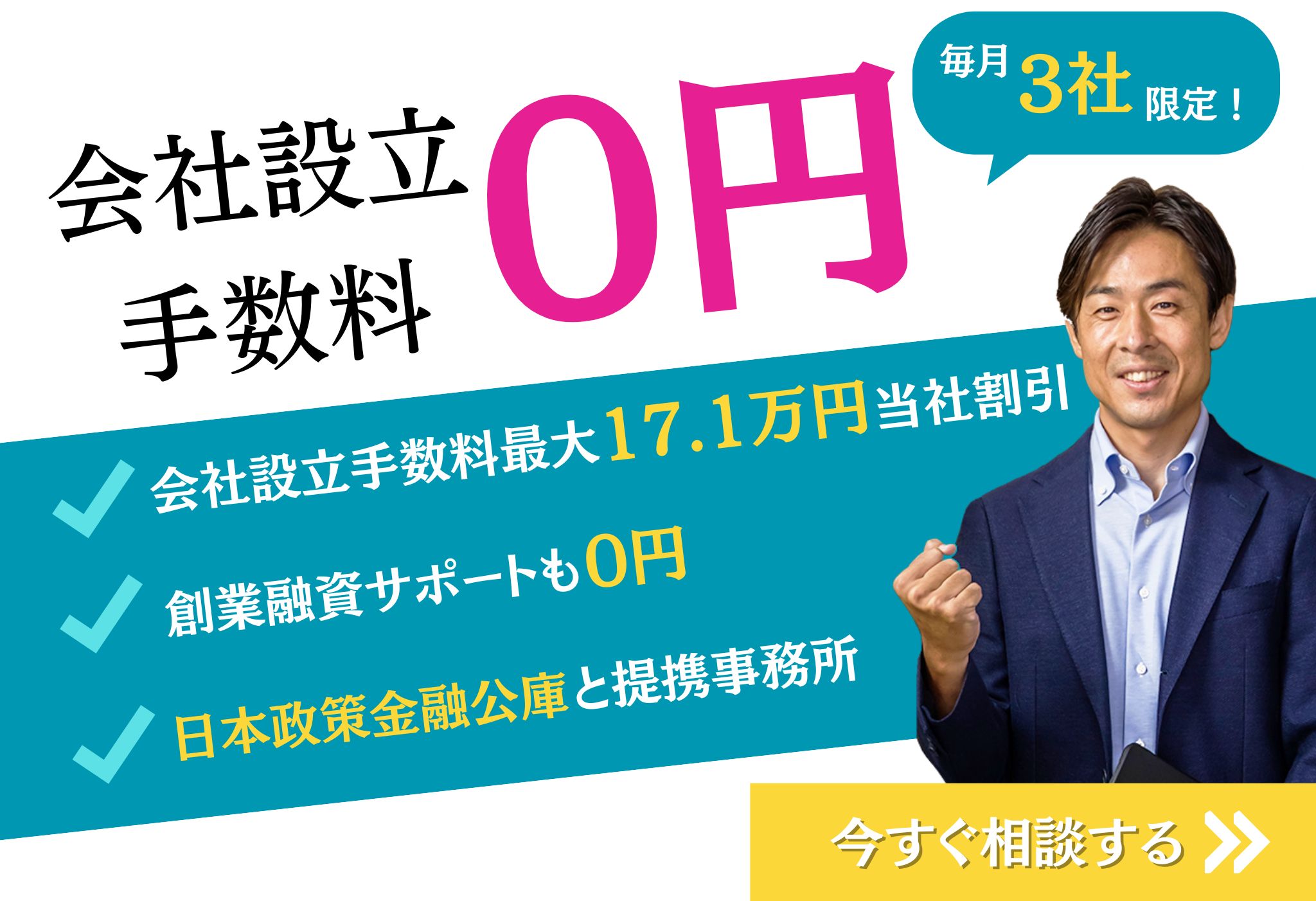
関連記事:会社設立に税理士は必要か?流れや費用についても解説‼︎
関連記事:【まとめ】会社設立に必要なことリスト
関連記事:会社設立手続きは自分でする?依頼する?時間と手間を徹底比較!
関連記事:【横浜で会社設立】流れや方法とは?メリットや必要書類について
関連記事:会社設立のメリットは?個人事業主と法人どちらがいいの?
関連記事:会社設立のための資本金はいくら必要?平均額や決め方について解説



