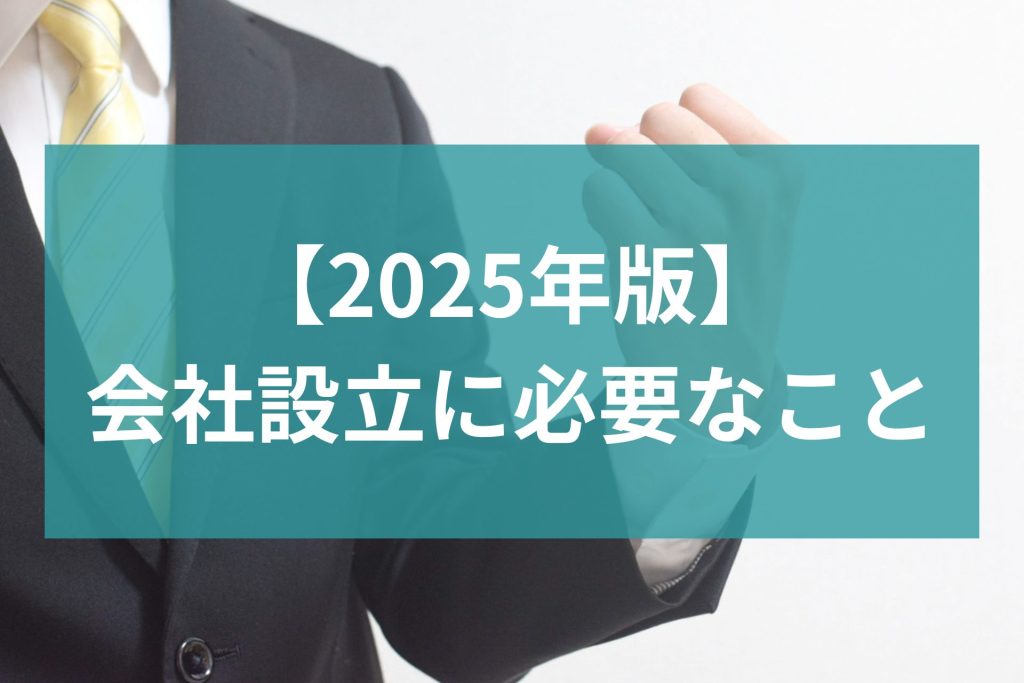
会社を設立する際、何から始めたら良いのか悩む方は実は少なくありません。
会社設立したいけど、まずは何をすべきなのか知りたい!
やるべきことを一目で知りたい!
会社設立に必要な書類を前もって準備しておきたい!
今回の記事ではこんな方々のために、会社設立のためにすべきことを分かりやすく解説していきます。

会社を設立するメリットとは?
事業を運営するには、個人事業主として開業するか、法人なりをして会社を経営するかのどちらかになります。個人事業主の場合は、管轄の税務署へ開業届を提出すれば事業を始めることができます。一方で、会社を設立するには税務署以外にも手続きが必要になるので、個人事業主よりも手間がかかります。時間はかかりますが、個人事業主では得られないメリットが法人にはあるので、メリットを理解したうえで会社を設立したほうが良いでしょう。
ここでは、会社を設立するメリットについて紹介するので、会社設立をするべきか悩んでいる方は参考にしてください。
 節税効果が高くなる
節税効果が高くなる
法人として事業を展開すると、個人事業主よりも節税効果が高くなります。個人事業主と法人とでは、課される税金が異なり、個人事業主は所得税、法人は法人税が課せられます。所得税は、所得が増えると比例して税金も高くなる仕組みの累進課税が定められており、最大税率が45%です。
法人の場合は、最大税率が23.20%なので、所得が増えるほど節税効果が高くなります。また、個人事業主は事業とプライベートの境目があいまいになるため、家事按分などの考え方から経費として扱える項目が少ないです。法人となると、事業とプライベートがはっきりと区別できるので、経費計上できる項目が増え、このような点でも節税効果があります。
 社会的信用の向上
社会的信用の向上
会社を設立すると、会社名や本店所在地、事業目的、資本金などを法務局に登記しなければなりません。登記した情報は登記簿謄本(全部事項証明書)として、誰でも見ることが可能なので、取引を検討している方や金融機関は情報をもとに取引の可否を判断します。会社の情報を開示して誰でも確認できる状況が、社会的信用を得ることにつながります。
企業によっては、法人でなければ契約しないという考えを持っているケースもあるので、取引先の拡大を検討している場合は、法人成りを強くおすすめします。
 資金調達の選択肢が増える
資金調達の選択肢が増える
社会的信用の向上に伴い、資金調達の選択肢が増えます。資金調達の方法は、補助金・助成金制度の活用や金融機関からの借入、株式の発行があります。
補助金・助成金制度の場合は、さまざまな施策を講じているので個人事業主・法人のどちらも申込むことはできますが、法人のほうが対象となる制度が多く、内容が充実しています。また、金融機関からの借入は、信用情報に基づいて審査が行われるため、法人よりも個人事業主の審査のほうが厳しい傾向にあります。もし審査を通ったとしても、借入上限金額が法人よりも少なく設定されます。
そして、法人ならではの資金調達方法が株式の発行です。株式を発行することで出資を受けることができ、なおかつ出資で得た資金は返済する必要はありません。
会社を設立することで、資金調達方法の選択肢が増え、事業拡大や設備を購入する際にもまとまった資金を得ることができます。
 有限責任になる
有限責任になる
個人事業主の場合は、事業に関するすべての責任を自分自身で負わなければなりません。取引先への不手際があったときや金融機関との借入金の交渉、税金の滞納などはすべて個人の責任であり、負担になります。このような状況を「無限責任」といいます。
一方で会社を設立し、組織として事業を行うと、限られた範囲の「有限責任」となり、代表者1人がすべての責任を負うことはありません。個人保証を除き、出資金以上の支払義務は発生しないため、自己破産などのリスクを避けることができます。
会社設立の前にすべきこと
早速ですが、会社を設立する前に事前にすべきことをお伝えします。
それは「会社の基本的なことを決める」ことです。
定款を作成する際、会社名や会社の住所、事業目的などを記載することが必須となります。
書類の作成など、手続きをスムーズに進めていく為にもあらかじめ考えておくと良いでしょう。
では、具体的にどのようなことを決めていくべきなのかそれぞれ見ていきましょう。
 会社名を決める
会社名を決める
当たり前ですが、会社設立を行うには会社の名前を決める必要があります。
基本的に事業者が決めて良いのですが、以下の一定の条件があります。
・株式会社の場合は「株式会社」、合同会社の場合は「合同会社」と入れる
・特殊な記号は使用しない
・「部門」「支店」などの誤解を招くような言葉を使用しない
以上のようなことに注意しましょう。
ごく当たり前のことですので、基本的には大丈夫かと思います。
この他にも、インターネット上で同じ会社名がないかなどを事前に検索してみても良いでしょう。
 会社の設立日(希望日)を決める
会社の設立日(希望日)を決める
基本的には登記の申請を行った日が会社の設立日となります。
もし、この日にしたい!という希望がある場合には、その日に向けて逆算して準備を進める必要があります。
 会社の所在地(登記場所)を決める
会社の所在地(登記場所)を決める
会社の住所も決めておきます。自分の自宅にしたり、最近ではバーチャルオフィスやコワーキングスペースを会社の所在地にする場合などもあります。
注意すべきポイントは、賃貸のオフィスなどを所在地にしようと考える場合に、その物件自体が「法人可」かどうかという点です。これも事前に確認しておくようにしましょう。
関連記事:賃貸契約で法人登記はできるのか?無断で法人登記をするリスク
 事業年度(決算期)を決める
事業年度(決算期)を決める
会社の決算を行うタイミングである事業年度も自由に決めることができます。4月から始まり、3月末で締めるという会社が多くはありますが、繁忙期を避けることなどもできるので自分の事業内容に沿って決めることをおすすめします。
 事業目的を決める
事業目的を決める
会社の事業に関しての目的は、設立の手続きの際に必須で記載しなければなりません。この事業内容に記載していることが今後の融資の際などにチェックされることとなりますので不明確な内容にならないように、しっかりと明確に記載するようにしましょう。
また、今後、事業の拡大を考えている場合などは、設立直後には予定がないにしても、初めの段階で事業内容に記載しておくようにしましょう。定款の事業目的の部分に記載されていない事業は行うことができないので、今後やろうと考えている事業内容は記載しておきましょう。
 資本金の額を決める
資本金の額を決める
資本金は、実は1円からでも会社を設立することは可能です。ただし、この資本金は会社の運転資金となります。設備の準備や人材確保など創業時は特に、ある程度まとまったお金が必要になる場合が多いです。
理想としては、もし仮に利益がなかったとしても3ヶ月間は事業を行うことのできる金額は必要経費として準備しておくのが望ましいでしょう。具体的な金額はその事業の内容によって異なりますので、事前に確認しておくか、専門家などに相談してください。
また、多ければ多いだけ良いというわけでもなく、基本的には創業後2年間は消費税の納税が免除されるのですが、もし資本金が1,000万円を超える場合には設立1年目から消費税を納める必要がありますので、その点からいうと資本金は多くても1,000万円は超えないようにすることが良いでしょう。
 発行可能株式総数を決める
発行可能株式総数を決める
株式会社の設立を検討している場合は、発行可能株式総数も定款に記載しなければなりません。公開会社の場合には発行済株式総数の4倍まで、非公開会社の場合には上限は決まっていません。株式が会社設立後の資金調達に大きく関わってきますので、出来るだけ高い上限で設定しておくことが望ましいと言えるでしょう。
関連記事:会社設立時の持ち株比率と権利について解説
 発起人を決める
発起人を決める
発起人とは、つまり会社を設立した人を指します。発起人は会社の設立を考えて具体的な手続きを行う人、役員は設立された会社の運営や管理を行う人のことです。よく聞く「取締役」なども役員の中の一つの役職です。取締役とはつまり会社の経営者のことです。もちろん発起人がそのまま取締役になることも可能です。
発起人は会社を設立するにあたって、定款を作成したり、出資や設立時の取締役の選任を行ったりと一定の役割があります。
発起人の数に上限はなく、1人でも可能です。1人の場合は定款の内容を自由に決められるというメリットもありますが、逆に複数人いる場合には、出資者が多いので会社設立後の運転資金なども豊富にあるため設備投資や設立間もないうちからの事業拡大などを視野に入れやすくなりというメリットもあります。
 出資財産を用意
出資財産を用意
出資金は基本的には現金で準備をするのが一般的です。ただ、不動産などの有価証券、車やパソコンなどの財産としての価値があるものである現物、知的財産権などの無形固定資産も可能です。
注意点として、客観的にみて評価することが難しい物の場合は厳格な規制もありますので頭に入れておきましょう。
 役員構成を決める
役員構成を決める
先程の「発起人」のところでも軽く触れましたが、会社を設立する際に役員の構成も決めておく必要があります。
代表取締役:取締役の中から選任
取締役:株式会社に置いては少なくとも1人は選任
監査役:取締役の職務と会計を監査する役割。設立する会社によって設置する場合としない場合があります。
決める段階で取締役や監査役の任期も考えておきましょう。
会社法によると、取締役は2年、監査役は4年が任期となります。もし任期を延ばしたいといった場合には任期に関して定めとなるものを定款に記載しなければなりません。
 取締役会設置の有無
取締役会設置の有無
取締役会とは、会社の業務を行う上での意思決定を行う機関のことです。意思決定という意味では株主総会と似ていますが、取締役会では株主の意思を伺うことはありません。そのため、株主の権限を抑えながら、重要事項の決定を行うことも可能となるのです。
上場企業の場合は義務
上場企業の場合には、取締役会の設置は義務となっていますが、ほとんどの中小企業は取締役会を設置する義務はありません。実際に、開催にあたっては準備が手間になるといった理由からほとんどの中小企業は取締役会を設けてはいません。
もし、取締役会を設置する場合には原則として、3人以上の取締役と1人以上の監査役の選任が必要となりますので、理解しておきましょう。
以上が会社を設立する前に決めておくべき各事柄です。
とても膨大に思えるかもしれませんが、手続きの際には決めなければならずこれらが決まらないと先へは進めません。
前もってじっくり考え、決定していきましょう。
会社設立の流れ|それぞれ解説
会社設立前にすべきことを終えたら、会社設立の流れを確認しておきましょう。会社設立と聞くと「なんか複雑でめんどくさそう」「やること多すぎてなんか忘れてそう…」と感じる方が多いですが、要点を抑えておくと手続きがスムーズになるので、大まかなステップを把握しておくことが大切です。
会社の基本情報の決定
まずは事前に決めておいた会社名(商号)や事業内容、事業年度(決算期)などを正式に決定します。会社の基盤となる情報なので、内容についてしっかりと突き詰めて検討を重ねたほうがいいでしょう。特に会社名は、今後の事業展開に大きな影響を及ぼす可能性があります。そのため、既存の会社と会社名が重複・類似していないかといった確認はしっかりとしておく必要があります。会社名を決める際のルールなどもあり、違反してしまうと登記がおこなえず、会社設立まで時間がかかってしまいます。ルールと照らし合わせながら、会社名を検討するようにしましょう。
会社の印鑑(実印)の作成
本格的に事業が始まる前に会社の印鑑を作成します。銀行口座を開設するときや取引先との契約を締結するときなどさまざまな場面で印鑑が必要になります。印鑑といっても1つだけでなく、使用する目的や書面に応じて必要な印鑑が異なります。準備するべき印鑑は大きく分けて4種類です。
| 会社の実印 | 会社の登記申請手続きの際に必要 |
| 会社の銀行印 | 法人口座の開設や小切手・手形の振り出しに必要 |
| 角印 | 請求書や領収書などの代表印でなくても問題ない書類の押印に必要 |
| ゴム印 | 契約書など自筆のサインではなく、押印で済ませる際に必要 |
一気に準備する必要はありませんが、どの印鑑もいずれは必要になるので、事前にまとめて作成しておくと、事業が始まった後も契約書や領収書、請求書のやり取りがスムーズに行えます。
定款の作成
会社設立の際に重要なのが、定款の作成です。定款とは会社の土台となるルールのようなものであり、会社を設立するにあたって作成が義務付けられています。定款は、絶対的記載事項、相対的記載事、任意的記載事項の3つの事項を記載しなければなりません。詳しい内容はこちらの記事をご覧ください。
定款の作成が終わったら、公証役場で「定款の認証」を受けます。現在はオンラインでも受付をしているため、電子定款で認証を行うことも可能です。電子定款を利用すると、印紙代4万円が不要なので、会社設立の費用負担を軽減できます。
資本金の払込
定款の認証が終わった後に資本金の払込を行います。この時点では、法人口座の開設はできないため、発起人の個人口座へ振り込むことになります。資本金は1円からでも申請が可能ですが、資本金額が会社の信用につながるケースもあるので、専門家に相談しながら金額を決めたほうが良いでしょう。
登記の申請書類に資本金の払込証明書類が必要なので、表紙と見開きページ、振り込みが記載されたページをコピーします。ネット銀行の場合は、該当箇所のスクリーンショットをコピーします。コピーした書類はまとめて大切に保管しておきましょう。
設立の登記申請
登記申請に必要な書類がそろったら、法務局へ提出して問題がなければ、会社設立が完了します。提出方法は、法務局の窓口へ直接提出するか、郵送、オンラインでも可能です。
設立登記に必要な書類は以下の一覧の通りなので、不足している書類がないか確認しましょう。
- 設立登記申請書
- 定款
- 登録免許税の収入印紙を貼付した台紙
- 発起人の決定書
- 設立時取締役の就任承諾書
- 設立時代表取締役の就任承諾書
- 設立時取締役の印鑑証明書
- 資本金の払込証明書
- 印鑑届出書
- 登記すべき事項を記載した書面または保存したCD-R
必要に応じて、監査役の就任承諾書などが必要になる場合もあるので、不安に感じたら税理士や司法書士等の専門家に相談すると適切なアドバイスがもらえます。
手数料0円で設立サポートいたします
今回は、主に会社を設立するにあたっての準備、決定すべきことの詳細をまとめました。
細かいことで、印鑑や備品の準備も必要になります。
よく分からない手続きで面倒そうと思う方も多いはずです。
設立後の経営に注力するためにも、事前に決められるところから検討していくようにしましょう!
当事務所では、毎月3社限定で手数料0円にて会社設立のご支援を行っております!
不明点やご不安な点があれば、まずはお気軽にご相談くださいね。
ご連絡お待ちしております!
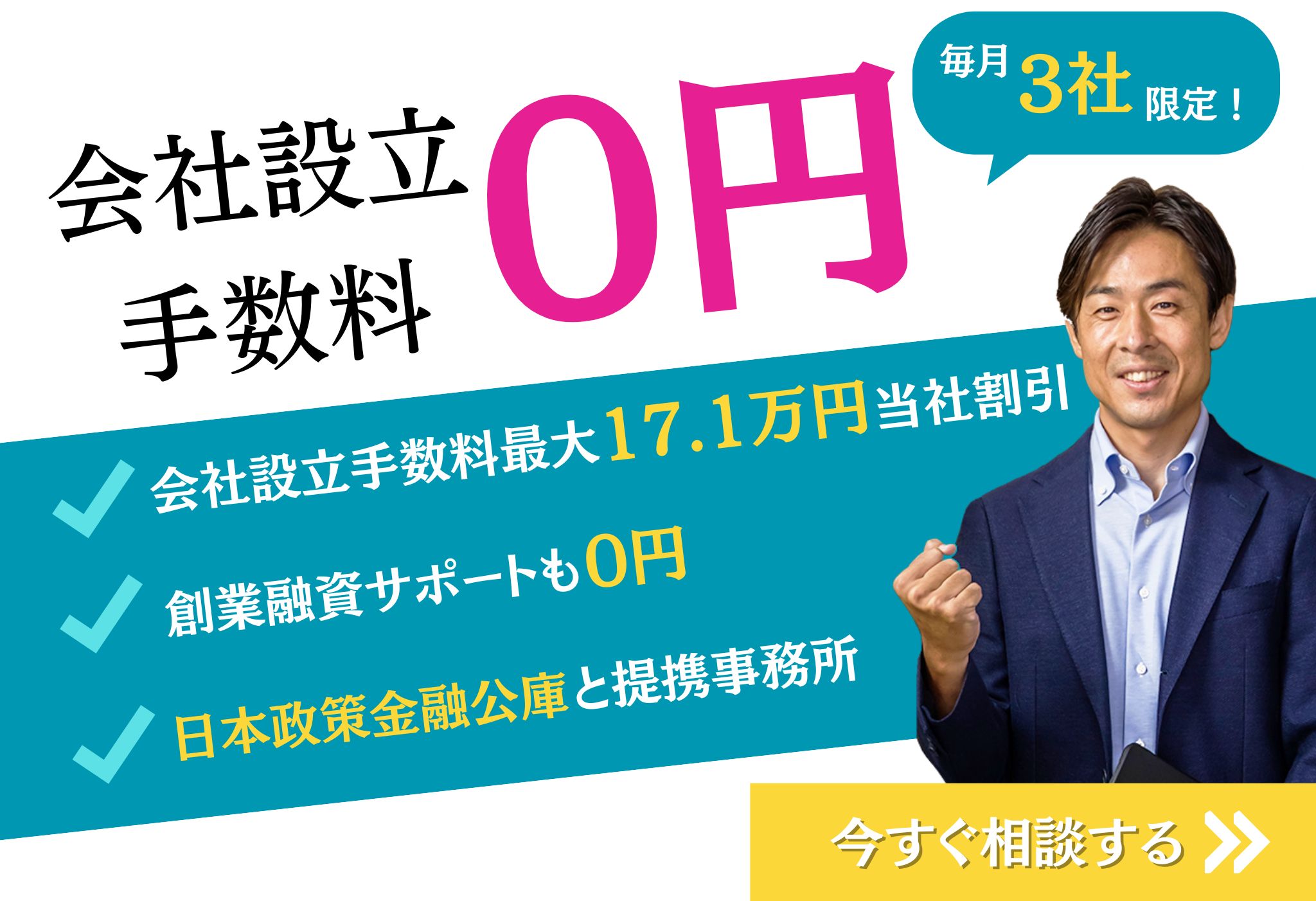
関連記事:【横浜で会社設立】流れや方法とは?メリットや必要書類について



