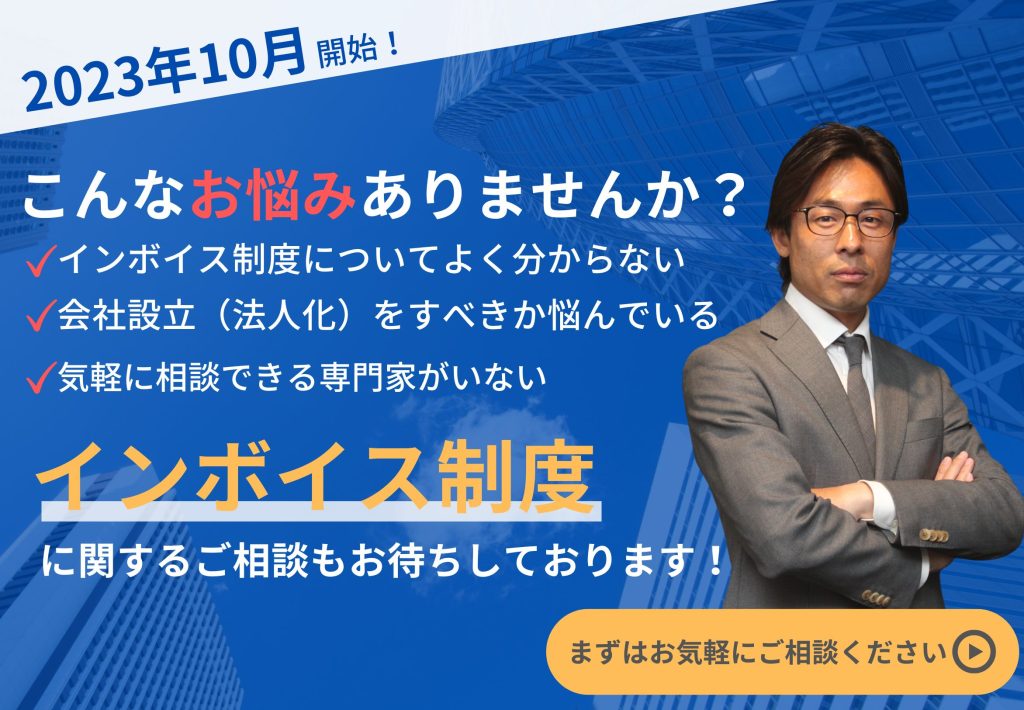2023年の10月1日から開始されたインボイス制度。
「一体どのような制度なのだろうか」
「具体的にどんな申告の手続きをすればよいのだろう」
「登録の方法がわからない」
「制度が開始されることで何の影響があるのか」
こういった疑問を抱えている人も少なくないのではないのでしょうか?
本記事では、事業主の方に向けて、インボイス制度についての概要、具体的な手続きの流れ(申請の手順)を解説していきます!
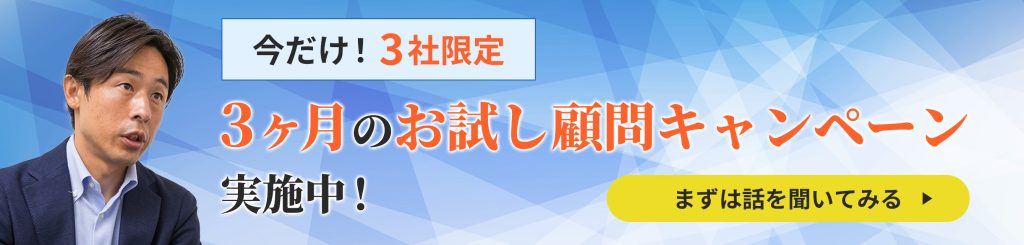
Contents
インボイス制度での影響とは?
インボイス制度を導入することでどのような影響があるのかは、体験してみないとわかりません。ここでは、インボイス制度を導入した背景やどのような影響があるのかという点について、詳しく説明します。
インボイス制度とは~導入の背景~
インボイス制度とは、「インボイス(適格請求書)」を用いて仕入額控除を受けるために設けられる制度です。
インボイス(適格請求書)とは売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額などを伝えるためのものです。この制度の導入の背景には2019年10月からの消費税の引き上げが挙げられます。今現在の請求書の中には、10%の消費税率と8%の軽減税率の2種類が存在し、それぞれの商品の税率と税額を正確に把握することがなかなか難しい現状です。その解消とともに税額を明確に区分した上で記録に残すことによって、仕入れや販売における不正やミスを防止するという効果が期待されて導入されることとなりました。
具体的には、現在の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」および「消費税額等」の記載が追加されることになります。
関連記事:【2023年10月開始】インボイス制度とは?すべき対応を分かりやすく解説
インボイス制度によって仕事が減少する?
インボイス制度が開始されると、事前に税務署より承認された適格請求書発行事業者のみが発行できる「適格請求書」による取引でなければ仕入税額控除の適用を受けることが出来なくなります。
仕入税額控除がない場合、事業者と取引をした際に預かった消費税をそのまま国に納付しなければならず、そうなるとビジネスとして大きな損害となってしまいます。そのため、インボイス制度に対応していない事業者は、取引先からの信用面の不安により取引を少なくされたり、仕事自体の減少につながる可能性も考えられます。
インボイス制度の対象者は、現在消費税を納税している「課税事業者」はもちろんのこと、多大なる影響を加味して、現在は消費税を納付する義務のない「免税事業者」も課税事業者になるケースも増えてくることが予想されます。申請する段階になってバタバタすることのないようにこれから説明する手順などもしっかり頭に入れておきましょう!
インボイス制度の登録申請手順
適格請求書発行事業者になるためには、登録申請手続きが必要です。登録申請は、書面を郵送するほか、パソコンやスマートフォンで行うことができるので、自分に合った方法で手続きを行いましょう。
ここからは実際に行うべき手順を説明していきます。
 インボイス制度の申請手順(郵送)
インボイス制度の申請手順(郵送)
①国税庁のサイトから「適格請求書発行事業者の登録申請用紙」をダウンロード
この際に国内事業者用と海外事業者用とがありますので、間違いのないようにしましょう。
出典:国税庁HP 適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用)
出典:国税庁HP 適格請求書発行事業者の登録申請書(国外事業者用)
②申請用紙の必要事項に記入
記入項目は以下の通りです。
- 住所
- 納税地の住所
- 氏名または名称
- 法人番号
- 事業者区分(課税事業者か免税事業者か)
- 登録要件の確認(課税事業者であるかどうかや消費税法の違反歴の有無など)
もし、現在免税事業者が課税事業者になる場合には、これらの項目に追加で「個人番号」「設立年月日」「事業内容」「資本金」などを記入、さらに所定のチェック項目にチェックすることが必要になってきます。
③申請書作成後、本人確認書類の写しを添えて、郵送にて納税地を管轄するインボイス登録センターへ送付
詳しい宛先はこちらの国税庁のHPをご確認ください。
本人確認書類はマイナンバーカードが望ましいですが、難しい場合は、マイナンバーが確認できる通知カードの書類と運転免許証など身元確認書類が2種類必要になります。書類に不足や不備があると再度提出する手間が増えてしまうので、事前に必要書類を準備しておきましょう。
インボイス登録センターに申請用紙が到着すると、審査が行われ、無事審査が通ると登録番号が記載された登録通知書が送付されます。
上記でご紹介した紙(郵送)による申請以外では、国税庁のオンラインシステム(e-Tax)を利用することも可能ですが、こちらを始めて利用する場合には、事前に利用者識別番号や暗証番号、電子証明書を取得する必要があります。
申請して登録が完了するまでの日数は、紙(郵送)の場合は約1ヶ月半程度、オンラインシステム(e-Tax)の場合には1か月程度となっています。余裕をもった申請を心がけることが大切ですね。
 インボイス制度の申請手順(パソコン)
インボイス制度の申請手順(パソコン)
①専用のソフトと電子証明書の準備
パソコンで手続きを行うには、e-Taxソフトもしくは、eーTaxソフト(Web版)のソフトが必要となります。eーTaxソフトを利用する場合は、ソフトをダウンロードする必要があるため、まだソフトをダウンロードしていない方は、新しくダウンロードをしましょう。すでにソフトを利用されている方は、ソフトが最新のものになっているか確認して最新の状態へアップロードしておきましょう。
②利用者識別番号の登録
PCやスマホで手続きを行うと利用者識別番号が必要になりますが、この番号は手続きの途中で即時発行が可能なので心配することはありません。また、手続きを行う際にインターネット状況が安定していることが重要なので、確認しておくことをおすすめします。
③登録申請データの作成と送信
電子証明書や利用者識別番号を取得した後は、登録申請データを作成します。使用するソフトによって作成方法が異なります。eーTaxソフトの場合は、帳簿形式になるため、登録申請書に必要事項の入力を行います。eーTaxソフト(Web版)の場合は、問答形式となり、表示された質問に答えて登録申請書を作成します。
登録申請データの作成が完了したら、送信をすると受け取り通知が届き、通知データも併せて届くので内容を確認しましょう。
 インボイス制度の申請手順(スマホ)
インボイス制度の申請手順(スマホ)
①eーTaxソフト(SP版)にログインする
国税庁のインボイス制度の申請手続きを行うサイトからeーTaxソフト(SP版)を開いて、マイナンバーカードを用いてログインをします。ログインをする時には、マイナンバーカードをスマホで読み取りますが、読み取るにはマイナポータルのダウンロードが必要です。スマホで手続きを行う予定の方は、事前にマイナポータルをダウンロードしておくとスムーズに手続きが行えます。
②利用者識別番号の登録
ログイン後に、必要項目を入力して利用者識別番号の取得と登録を行います。事前にマイナンバーカードに登録している方は、この作業を行う必要はありません。
③登録申請データの作成と送信
eーTaxソフト(SP版)はeーTaxソフト(Web版)と同じように問答形式で行うため、必要事項などの記入・入力漏れの起こる可能性が低くなります。回答が終了して申請データの作成が完了すると、電子署名の付与画面へ移ります。電子署名は他人が手続きを行うことや名前の改ざんなどの不正を未然に防ぐために、本人であることの証明として署名します。
インボイス制度の申請期間や必要なもの
手続きの手順や申請方法の種類については把握できたので、実際に手続き開始から完了までの期間がどのくらいなのか、手続きに必要なものはあるのかといった点を確認します。
インボイス制度の申請期間
インボイス制度の登録申請は2021年の10月1日からすでに始まっています。インボイス制度への加入義務はありませんが、加入することで仕入税額控除などが適用されるメリットがあります。インボイス制度へ加入した際のメリット・デメリットについては以下の記事で解説しているので、加入しようか検討している方は是非参考にしてください!
関連記事:【インボイス制度】やらないとどうなる?状況に応じて解説!
また、インボイス制度へ加入するための登録申請ですが、申請方法によって登録申請から登録番号通知までの期間が異なります。前述したように、申請方法は大きく分けて書面を郵送する方法とeーTaxソフトで行う方法の2通りあります。書面で郵送する方法だと、約1.5ヶ月、eーTaxソフトの場合は約1か月程度で登録番号通知が届きます。
制度自体はすでに始まっているため、これから手続きをしようとしている方は手順を考えながら効率的に申請をしましょう。登録申請データや書類に記載漏れや不備があるとさらに時間がかかってしまうため、書類やデータをしっかり確認してから送付・送信を行いましょう。
登録申請に必要なもの
申請手続きをスムーズに行うには、事前に必要なものを準備しておく必要があります。申請方法によって必要なものが異なるため、手続きを行う前に必要なものを確認しましょう。具体的に必要なものは以下の一覧の通りです。

・利用者識別番号
・マイナンバーカード
・適格請求書発行事業者の登録申請書(書面で申請する場合)
パソコンやスマホのeーTaxソフトで登録申請を行う場合は、電子証明書が必ず必要になります。また、デジタル署名として利用できるため、事前に取得しておきましょう。利用者識別番号はeーTaxで新規取得ができるので、もし取得していなくても心配不要です。
マイナンバーカードは本人確認書類として必須です。マイナンバーカードを発行していない場合は、個人番号通知カードなどの個人番号がわかる書類と運転免許証などの本人確認書類の準備が必要です。
書面での手続きで検討している方は、「インボイス制度の申請手順(郵送)」に記載しているように登録申請書をダウンロードして必要事項を記入します。この書類は国内事業者用と国外事業者用に分かれているため、該当する方を国税庁のサイトからダウンロードしましょう。
登録申請以外でやっておくべきこと
上記で説明した国税庁への申請以外にも自分たちでインボイス制度開始に備えてすべきことはどんなことでしょうか。
・インボイス制度対応のレジの導入
現在使われているレジではインボイス制度に対応するためには記載項目が不十分となってしまいます。そのため、対応するためには事前にインボイス制度対応のレジの導入の必要が出てきます。もちろんそのためにはある程度のコストもかかってきますので、計画的に準備をしましょう。
・インボイス制度対応のシステムの導入
例えば、受発注システムや請求書などを管理するシステムがインボイスに対応していない可能性も十分に考えられます。その場合もシステムの改修などが必要になってきます。
また、これらのこと以外に現在取引を行っている取引先が適格請求書発行事業者登録を行っているかを事前に確認することも大切でしょう。何度も言うように、もし登録が行われていない場合は、適格請求書が発行されず仕入税額控除が受けられなくなり、事業に大きな損害をもたらすことになりかねないからです。万が一、適格請求書を発行することのできない免税事業者と取引を行う場合には、これまでとは経理処理が変わるため区別して管理する必要も出てきます。
インボイス制度開始後のワークフロー
実際にインボイス制度が開始されると売り手側と買い手側でどのようなやりとりがなされるのか解説します。
売り手の場合
大原則として、取引前に適格請求書発行事業者登録をしておく必要があります。そして取引先から適格請求書の発行を求められた場合は、適格請求書を交付する必要があり、その交付した適格請求書は控えを7年間保存する義務があります。保存するのは、適格請求書の写しもしくは、買い手に送付した電子データのどちらかになります。電子データの場合は、電子データのまま保存することが定められているため、印刷して保存するという方法は出来ません。
発行する適格請求書には6つの項目を記載する必要があります。

・取引を行った年月日
・取引内容
・税率ごとに区分して合計した金額と適用税率
・税率ごとに区分した消費税額等
・書面を受け取る事業者名または名称
また、買い手との間に値引きや返品などが生じて、支払金額の一部または全額を返金する対応が必要な場合は、適格返還請求書の発行が必要になります。
適格返還請求書に記載が必要な項目は6つあります。

・返金を行う年月日
・返金する取引内容
・元の取引をした年月日
・税率ごとに区分して合計した返還金額
・返還する金額の消費税額・適用税率
適格請求書のときとあまり変わりませんが、返還が必要なものに関する金額や取引を行った年月日など後から見ても分かりやすいように、上記のような項目の記載が必要です。もし返金額が税込1万円未満の場合は、適格返還請求書の交付義務が免除されます。適格返還請求書を作成する際は、返金額に気を付けて、適格返還請求書の発行義務の有無について判断できるようにしましょう。
買い手の場合
仕入税額控除が適用されるには、売り手である取引先から交付された適格請求書を保存する必要があります。さらに、適格請求書の要件項目が正確に記入された仕入明細書などを作成して、売り手が確認の上保存することが必要です。
インボイス制度もご相談ください
今回は、インボイス制度について、具体的な申請手順やメリットをご紹介してまいりました。
当事務所では、申請などのサポートから今後の方向性のご相談などインボイス制度にまつわるサポートを幅広くさせていただいております!
まずはお気軽にご相談ください!税理士の資格を持った担当が対応いたします。