
小規模企業共済は、個人事業主や中小企業の役員の退職金制度として利用されていますが、掛金の仕訳に頭を悩ませている方もいるかもしれません。仕訳について理解できていないと、税務上の問題が発生したり、確定申告の数字が合わなくなったりと経営に支障が出る可能性があります。
そこで本記事では、小規模企業共済掛金の仕訳について、個人事業主と法人の違いを解説します。小規模企業共済への加入を検討している方や今まさに仕訳に悩んでいる方は是非参考にしてください。
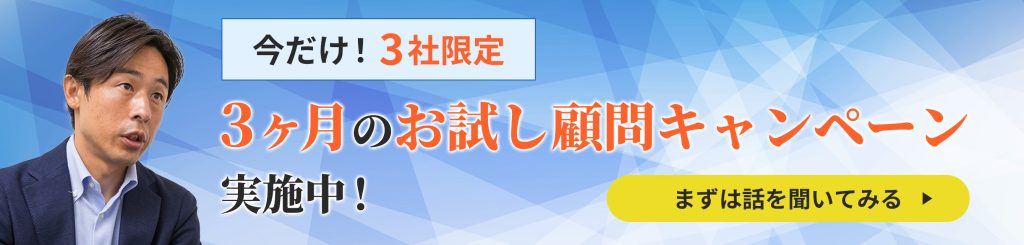
Contents
小規模企業共済とは
小規模企業共済とは、先述したように個人事業主や中小企業の役員を対象とした退職金制度です。
会社員とは違い、個人事業主などには退職金制度がないため、廃業した後や退職後の生活を不安視する声が多くあり、1965(昭和40)年に小規模企業共済の制度が発足しました。運営は「独立行政法人 中小企業基盤整備機構」が行っており、在籍している人数は、2013(平成25)年以降増加傾向にあります。(経済産業省調べ)
加入資格
小規模企業共済に加入できるのは、以下のいずれかに該当する方です。
2.商業(卸業・小売業)、サービス業(宿泊業、娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社の役員
3.事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員か常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
4.常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
5.常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人などの士業法人の社員
6.上記1、2に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
小規模企業共済掛金の仕訳方法
小規模企業共済掛金を仕分けする際の勘定科目は、個人事業主と法人役員によって税務上の扱い方が異なります。この違いをしっかりと認識しておくことで、正しい仕訳をすることができます。
特に、個人事業主を経て、会社を設立した方は間違えないように注意しましょう。
 個人事業主の場合
個人事業主の場合
個人事業主の場合は、個人事業主が本人のために積立を行い、本人が支払をしているため、勘定科目は「事業主貸」を使います。
「事業主貸」とは、個人事業主が事業用の資金をプライベートの支出で使用したときに使う勘定科目のことです。個人事業主は、事業とプライベートとの区別がつけづらいため、支出が事業用とプライベート用のどちらに分けられるのかが経理処理において重要です。
小規模企業共済掛金は、事業の支払いではなく、個人へ還元されるものになるので、プライベートの支出として「事業主貸」という勘定科目で仕訳を行います。「事業用の資金を個人へ貸す」ことから「事業主貸」となっているので「事業主借」と混同しないように注意しましょう。
[仕訳例]
| 借方 | 貸方 | 摘要 |
| 事業主貸 10,000円 | 普通預金 10,000円 | 小規模企業共済掛金 |
「事業主貸」の勘定科目を使用することで、税務署に対して「経費ではないものを経費計上していない」ということを示すだけでなく、事業とプライベートの区別をつけることが可能になります。
 法人役員の場合
法人役員の場合
法人役員の場合は、掛金の実質的な負担者などによって勘定科目や税務上の扱いが変化するため、専門家に相談しながら仕訳を行いましょう。
まず、大前提として小規模企業共済は法人が契約することはできません。契約できるのは、あくまでも個人事業主や法人の役員といった個人のみになるので、この認識を間違わないようにしましょう。
ここで大切なのは、誰がどのようにして掛金を支払っているかという点なので、ケースごとに整理します。
①法人が役員の掛金を負担しているケース
法人が福利厚生として、役員個人の掛け金を負担しているケースは、「福利厚生費」または「役員報酬」の勘定科目が使用されます。会社に所属している役員のために支払うため、「福利厚生費」として仕訳をすることも可能ですが、場合によっては税務署から認められないこともあります。
一方で、掛金分を「役員報酬」として上乗せすることで、実質会社の損金として算入することが可能です。掛金は全額所得控除になるため、役員報酬に上乗せしても掛金分は所得税の対象外となるので、上乗せ前と課税対象金額は変わりません。
②法人が掛金を立て替えるケース
会社が一時的に掛金を支払って、あとで役員が会社に返金するケースは、「立替金」として帳簿に記載をします。このケースは、会社に実質的な負担はないため、損金算入はできません。
小規模企業共済掛金控除の申告方法
小規模企業共済は、全額所得控除として適用できるため、忘れずに申告することが大切です。年間で総額84万円(月7万円)が所得控除の対象となるので、節税効果がとても高く、節税対策に悩んでいる方におすすめです。
申告する流れは、確定申告の際に「小規模企業共済掛金控除」という項目があるので、その年に支払った掛金の総額を記載します。もし翌年分の掛金を前納していた場合は、前納期間が1年以内であれば、合わせて全額控除が可能になります。本年分と翌年分を合わせて、総額168万円が所得控除の対象になるので、節税対策の中でも大きい金額といえます。
また、確定申告書類を提出する際には、控除証明書の提出が必要です。中小機構(中小企業基盤整備機構)から送付される「小規模企業共済掛金払込証明書」か掛金を支払ったことがわかる通帳のコピーなどを添付しましょう。
小規模企業共済に似た制度
小規模企業共済と合わせて検討してほしい制度が2つあります。資産形成という点では似ていますが、特徴がそれぞれ異なるので、資産形成で悩んでいる方は参考にしてください。
iDeCo(個人型確定拠出年金)
iDeCoは、自分で投資信託や保険、定期預金などを選んで運用し、老後に備える私的年金制度です。この制度も掛金全額が所得控除の対象になることや運用益を非課税で再投資できる点、受け取り時に控除が適用される点はメリットといえます。
小規模企業共済と異なる点は、運用する金融商品によって受け取る金額が変動したり、元本割れをする可能性があります。また、原則として60歳まで引き出すことはできないので、その点を踏まえて加入を検討しましょう。
国民年金
国民年金は、日本に住んでいる20歳以上60歳未満の方を対象とした公的年金制度です。厚生年金もある会社員よりも受給額は少ないですが、老後の生活のために欠かせない資金です。
支払った保険料は社会保険料として控除が適用されるので、税制上のメリットがあります。iDeCoと違って、元本が保証されているため、元本割れのリスクを避けたいという方にも安心です。
仕訳は適切な勘定科目で行いましょう
小規模企業共済は個人事業主や法人役員のための退職金制度として利用できます。その掛金は全額所得控除にできるため、節税効果が高いため、廃業後や退職後の資金積立を検討している方にぴったりの制度です。
加入後に掛金を仕訳する際は、適切な勘定科目で経理処理ができるように事前準備を行いましょう。会計ソフトなどで処理の負担が軽減されてきていますが、誤った勘定科目で処理をしてしまうと決算などに影響が出て、税務署から再提出を促されたり、ペナルティが発生する可能性があったりします。
そのようなリスクを減らすためには、日々の仕訳や適切な勘定科目を使用することが重要です。
そうは言っても、「自分で会計業務を行うのは不安…」「税務が複雑すぎて訳わからない」と頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか?少しでも不安に感じている方は、是非当事務所へご相談ください。
会計関連だけでなく、税務や社会保険のプロがみなさまの悩みを解消します!
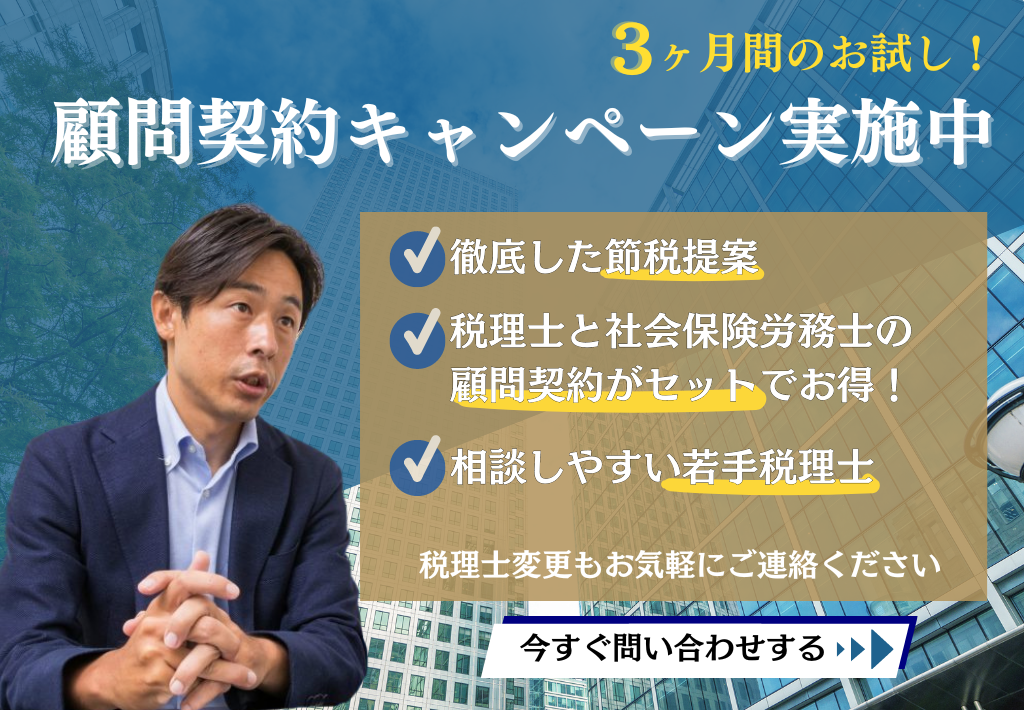
関連記事:【2025年最新版】小規模企業共済とはどのような制度?メリットとデメリットを解説



