
近年では、年金制度の根幹が揺らぎ始め、若年層だけでなく幅広い世代において、将来の資金について漠然とした不安を抱える方が多いでしょう。大企業に長年勤めた結果として受け取れるのが退職金です。その退職金のために、定年まで頑張り続けるというモチベーションを保っている方もいるかもしれません。
その一方で、働き方が多様化し、フリーランスとして働く方や起業して中小企業の経営者として働く方も増加しており、退職金は無縁と思っている方も多いでしょう。
しかし、社会的保障の弱さや廃業・引退後の生活に対する不安を解消するために施行されたのが、個人事業主や中小企業の経営者向けの退職金制度である「小規模企業共済」です。
ネット上ではネガティブな意見が散見されますが、制度の内容を理解し、自分に合った使い方を身につければ、リスクは回避できます。
本記事では、小規模企業共済のメリットとデメリット、加入手続きの流れや注意点について解説します。
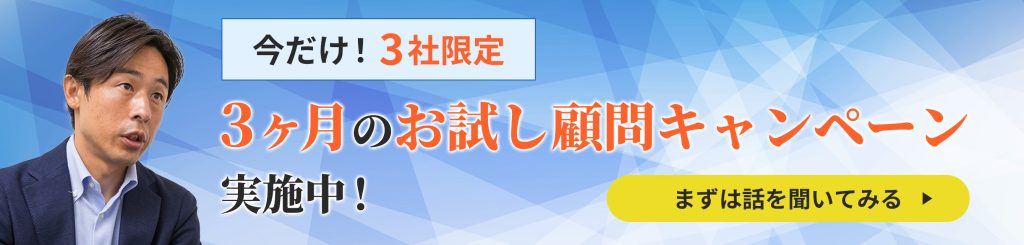
小規模企業共済とはどんな制度?
小規模企業共済とは、中小企業基盤整備機構が運営しており、個人事業主や中小企業の経営者の廃業や退職後の生活資金を準備するための共済制度です。
経営者自身の努力だけでは、老後資金の積み立てが難しかったり、セーフティネットが整えられなかったりするため、国の施策として1965年(昭和40年)に発足しました。そのため、経営者のための退職金制度という位置づけになっています。
加入資格のある対象者
小規模企業共済に加入できるのは、以下のいずれかに該当する方です。
2.商業(卸業・小売業)、サービス業(宿泊業、娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社の役員
3.事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員か常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
4.常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
5.常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人などの士業法人の社員
6.上記1、2に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
掛金について
小規模企業共済の掛金は、月々1,000円〜70,000円の範囲でいくらにするか設定することができます。500円単位で金額を変更できるので、会社の経済状況に応じて減額・増額が可能です。
納付方法は、月払い、半年払い、年払いのいずれかから選択して預金口座振替で引き落とされます。また、前納することで前納減額金という形で、還付されるので実質的な割引となります。前納減額金は、毎月の掛金と前納する月数によって金額が変わります。気になる方は実際に計算してみると分かりやすいので、掛金を決めるときや前納を検討する際の参考にしてください。
小規模企業共済のメリット
小規模共済が個人事業主や中小企業の役員向けの制度であることが理解できたところで、実際にどんなメリットがあるのか理解したうえで、加入を検討しましょう。
小規模企業共済のメリットは以下の5つがあるので、詳しく解説します。

・個人事業主や中小企業経営者の退職金の代わりになる
・共済金の受け取り時に税制優遇を受けられる
・毎月の掛金額を自由に設定できる
・7つの貸付制度が利用できる
掛金の全額が所得控除の対象になる
小規模企業共済の積み立てた掛金は、「小規模企業共済等掛金控除」として全額所得控除の対象になります。退職金の準備をしながら、節税対策ができるのは大きなメリットになり得るでしょう。
毎月の掛け金の上限が7万円となるので、1年間で最大84万円分の控除が適用可能です。掛金が大きくなるほど控除額が大きくなるので、経営状況によっては掛金の増額も検討するとよいでしょう。
個人事業主や中小企業経営者の退職金の代わりになる
個人事業主や中小企業経営者は、廃業・退職をしても会社員のように退職金が受け取れるわけではないため、小規模企業共済に加入していれば、共済金が退職金代わりとなります。小規模企業共済は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しており、受け取りの際は退職金の扱いとあまり変わりないです。
会社員の退職金と異なる点は、「共済金の積み立て自体は経営者自身で行わなければならない」「共済金を受け取るには事由が必要」などがあります。「共済金を受け取るには事由が必要」に関しては、最後の「共済金を受け取る事由とは」で詳しく解説するので、気になる方はご覧ください。
個人事業主や中小企業の経営者は、廃業・退職後の生活が不透明で不安になる方も多いですが、小規模企業共済を活用することで退職金を受け取れる環境を作ることができます。
共済金の受け取り時に税制優遇を受けられる
前述したように、共済金は退職金と同様の扱いになるため、共済金を受け取った際に退職所得控除が適用可能です。また、共済金を一括ではなく、年金のように分割で受け取る選択をすると、公的年金等の雑所得扱いとなるので、税負担が軽減します。
そのため退職金や公的年金と同様、それぞれの所得控除が適用され、事業所得よりも税金の負担が軽減されるので、節税効果が高いといえます。
毎月の掛金額を自由に設定できる
毎月の掛金額を自由に設定できるのもメリットの1つです。ライフステージの変化や事業の収益状況に応じて掛金を増減することができます。
そのため、収益が見込めるときは増額をして、所得控除の対象になる金額を増やすことで、節税対策をすることができ、収益が落ち込んでいるときは減額して資金をほかの補填に充てることが可能となります。
7つの貸付制度が利用できる
小規模企業共済に加入している方は、掛金の範囲内ではありますが7つの貸付制度が利用できます。銀行よりも低金利で年利0.9〜1.5%と設定されており、担保や保証人は不要という好条件で貸付が可能です。
貸付制度には以下の7つがあるので、貸付を希望する理由に応じた制度を利用しましょう。
- 一般貸付制度
- 緊急経営安定貸付
- 傷病災害時貸付
- 福祉対応貸付
- 創業転業時・新規事業展開等貸付
- 事業承継貸付
- 廃業準備貸付
金融機関と比較して金利が低いだけでなく、場合によっては即日貸付が可能になるので、有利な条件で融資を受けることができます。
小規模企業共済のデメリット
小規模企業共済に加入するデメリットは次の通りです。

・元本割れのリスクがある
・共済金の受け取り時に課税される
それぞれのデメリットについて詳しく説明します。
加入期間が12か月未満で解約すると、掛け捨てになる
小規模企業共済の掛金納付月数が12か月未満のときに解約をしてしまうと、共済金を受け取れず、掛け捨てになるリスクがあります。共済金の種類によって、掛け捨てになってしまう納付月数が異なるので、把握しておく必要があります。
- 共済金A・共済金B:掛金の納付月数が6か月未満
- 準共済金・解約手当金:掛金の納付月数が12か月未満
しかし、掛金は1,000円〜70,000円の範囲で、無理のない範囲で掛金を支払うことができるため、掛け捨てを回避することができます。掛金を決めるときは、経営状況に左右されることなく、継続して支払えることを前提とした金額設定をしましょう。
元本割れのリスクがある
納付期間が20年未満で任意解約してしまうと、元本割れのリスクがあります。解約手当金の支給率は納付期間によって変わるので、以下の表を前もって確認しましょう。
| 掛金納付月数 | 支給率 | 備考 |
| 1~11月 | 0% | |
| 12~83月 | 80.00% | |
| 84~89月 | 80.50% | 6か月ごとに0.75ポイントずつ支給率が上がる |
| 120~125月 | 85.00% | |
| 180~185月 | 92.5% | |
| 240~245月 | 100.00% | |
| 246~251月 | 100.25% | 6か月ごとに0.25ポイントずつ支給率が上がる |
| 474~479月 | 109.75% | |
| 480月 | 110.00% | |
| 720月以上 | 120.00% |
また、納付月数が20年以上であっても、加入期間中に掛金を変更していると共済金の条件を満たすことができずに元本割れする可能性もあります。起業したときに20年先のことを見通すことはできないため、加入する際はこのリスクも理解したうえで手続きしたほうが良いでしょう。
ただし、20年未満の解約であっても「任意解約」ではなく、「廃業」などの事由である場合はその限りではないので、安心してください。
共済金の受け取り時に課税される
メリットとして「掛金の全額が所得控除の対象になる」という点を説明しましたが、その一方で共済金を受け取るときは、課税される点がデメリットです。受け取り方に応じて、退職所得や公的年金等の雑所得として所得税が課せられます。
ただメリットでも説明したように、事業所得として課税されるよりは税負担が軽減されるので、そこまで深刻なデメリットとしてとらえる必要はありません。
将来的に課税されること、課税が先送りになっている状態であることをしっかりと認識しておきましょう。
加入手続きの流れや必要書類
小規模企業共済への加入を検討している方は、加入手続きの流れや必要書類を把握しておくと事前の準備がスムーズになります。もちろん、すべてを覚える必要はないので大まかな流れを知っておくだけで、準備のしやすさが変わるので、是非ご覧ください。
 加入に必要な書類を準備する
加入に必要な書類を準備する
加入する方が、個人事業主・法人の役員・共同経営者によって必要な書類が変わるので、その点には注意が必要です。
それぞれの立場で必要な書類は以下の表にまとめたので、ご覧ください。
| 共通の必要書類 | ・契約申込書 ・預金口座振替申出書 |
| 個人事業主の必要書類 | ・確定申告書の控えもしくは開業届の控え (電子申告の場合は、受付確認のページを添付) |
| 法人役員の必要書類 | ・履歴事項全部証明書(3か月以内に発行したもの) |
| 共同経営者の必要書類 | ・確定申告書の控えもしくは開業届の控え ・共同経営契約書の写し ・報酬の支払いが確認できる書類 |
共同経営者の必要書類である「報酬の支払いが確認できる書類」とは、社会保険の標準報酬月額通知書や青色申告決算書、賃金台帳などがあります。
 書類に必要事項を記入する
書類に必要事項を記入する
中小機構のホームページから、契約申込書と預金口座振替申出書を取得して必要事項を記入します。書面でもオンラインでも手続きが可能なので、手続きしやすい方で行いましょう。
 窓口へ書類を提出する
窓口へ書類を提出する
オンラインで提出するか、中小機構と契約している団体または金融機関窓口へ必要書類を提出します。受付をしている団体・金融機関は以下の通りです。
| 中小機構が委託している団体 | ・商工会 ・商工会議所 ・中小企業団体中央会 ・事業協同組合 ・青色申告会 ・損害保険ジャパン株式会社 ・アクサ生命保険株式会社 |
| 中小機構が委託している金融機関 | ・都市銀行 ・信託銀行 ・地方銀行 ・第二地方銀行 ・商工組合中央金庫 ・信用金庫 ・信用組合 ・農業協同組合 ・その他の金融機関 (ゆうちょ銀行、インターネット専業銀行) |
郵送などでは受付してもらえないので、上記の窓口へ持参するかオンラインで提出するかのどちらかになります。
 書類の受け取り
書類の受け取り
申込をしてから約40日後に中小機構から「小規模企業共済手帳」と「小規模企業共済制度加入者のしおりおよび約款」が届きます。
もし審査の結果で加入できないときは、中小機構から約2か月後に加入できない旨を知らせる書類が送られます。
共済金を受け取る事由とは
共済金は4種類あり、それぞれ支給される事由は異なるので、どのような事由で共済金を受け取れるのか確認しておきましょう。
共済金A・共済金B・準共済金・解約手当金の支給理由や支給方法は以下の通りです。
| 共済金A | 共済金B | 準共済金 | 解約手当金 | |
| 支給対象年齢 | 年齢不問 (廃業・解散等) |
原則65歳以上 | 年齢不問 | 年齢不問 |
| 支給事由 | ・廃業 ・会社の解散 ・共済契約者の死亡 |
・老齢給付 ・65歳以上で役員を退任した場合 ・疾病や負傷により役員を退任した場合 |
・個人事業から法人成りして加入資格を失った場合 ・配偶者または子へ事業をすべて譲渡した場合 |
・任意解約 |
| 支給方法 | 一括/分割/併用可 | 一括/分割/併用可 | 一括のみ | 一括のみ |
| 課税区分 | 退職所得/公的年金等の雑所得 | 退職所得/公的年金等の雑所得 | 退職所得 | 一時所得 |
小規模企業共済を活用しよう
小規模企業共済は、廃業や退任後生活に不安を抱えている個人事業主や法人の役員を支えるための積立による退職金制度です。積み立てた金額に応じて、将来まとまった金額の共済金を受け取ることができます。
退職金の代わりになったり、掛金の全額が所得控除の対象になって節税効果がある一方で、納付月数によっては掛け捨てになる可能性があったり、元本割れのリスクがあったりとデメリットもあります。メリットとデメリットのどちらも理解したうえで、加入を検討しましょう。
小規模企業共済への加入は、退職金の準備や節税対策として適していますが、「この制度以外の節税対策もしたい」という方は専門家に相談してみることも1つの手です。
起業したばかりで、節税や融資に関して何もわからなくて困っているという方は、是非1度、当事務所へご相談ください!
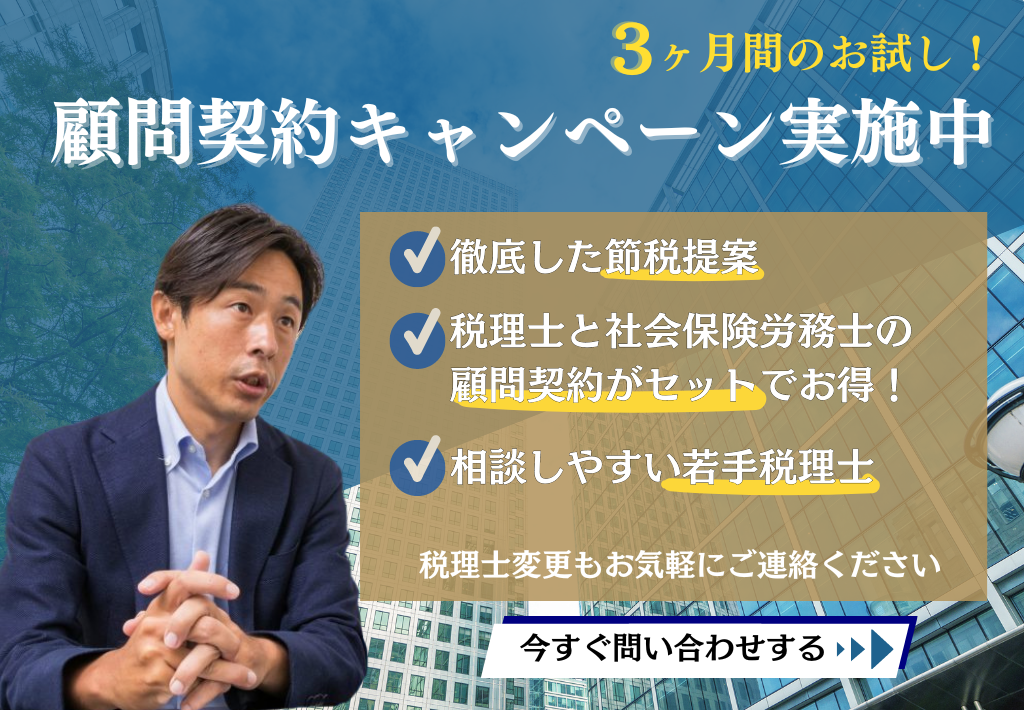
関連記事:【最新】中小企業倒産防止共済とは?メリットやデメリットについて解説



